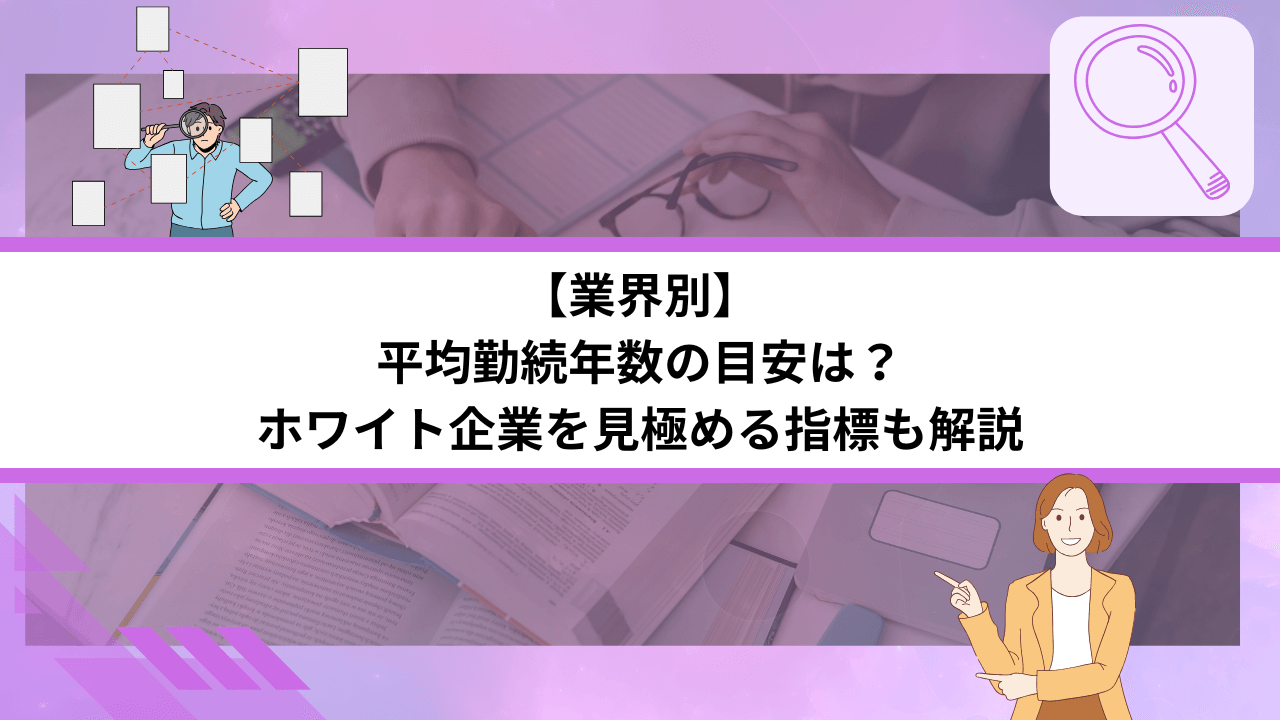平均勤続年数って何年くらいが目安なの?
長い会社はホワイト企業って言えるの?
業界によって違いはあるの?
こういった疑問に答える記事です。
この記事でわかること
- 平均勤続年数の計算方法と調べ方
- 業界別の平均勤続年数の目安
- 平均勤続年数が長い・短い企業の特徴
- ホワイト企業を見極めるための他の指標
平均勤続年数は企業選びの際に役立つ指標ですが、数字だけでホワイト・ブラック企業を判断するのは危険です。
この記事では、業界別の平均勤続年数の目安や、企業研究で確認すべき他の指標も併せて紹介しています。
企業選びで後悔しないために、平均勤続年数の正しい見方を理解しておきましょう。
平均勤続年数を調べられるおすすめアプリ
私たちが提供する「HELLOBOSS」というアプリは、無料ですぐに平均勤続年数がわかります。
550万社以上の企業情報が収録されているため、あなたが応募する企業のことも調べられる可能性があります。
他にも「従業員の平均年齢」「月の残業時間」「離職者数」などもわかるため、企業研究に活用してみてください。
Contents
平均勤続年数とは
平均勤続年数は、企業で働く社員たちの在籍期間を数値化した指標です。
高い数値は定着率が良い企業と考えられますが、業界特性や社内制度の違いで変化が大きくなります。
以下で計算方法や調べ方、全体の推移を順番に見ていきましょう。
平均勤続年数の計算方法
平均勤続年数の計算方法は以下のとおりです。
平均勤続年数の計算方法
在籍社員の勤続年数合計÷社員数=平均勤続年数
例えば、社員Aが5年、Bが10年、Cが15年在籍している職場なら(5+10+15)÷3=10年です。
大人数が働く大企業では数値が比較的安定します。
一方、中小規模の組織では一部の勤続が長い社員や非常に短い社員がいる際に全体の結果へ大きく影響するでしょう。
注意点
端数の扱いは資料によって切り捨てや四捨五入などの違いがあります。
統計を扱う場合は基準を確認しましょう。
企業研究の段階で平均勤続年数を見るときは、どのような社員層が中心なのかを考察すると実態のイメージが鮮明になります。
平均勤続年数の調べ方
平均勤続年数は就職情報サイトや就職四季報などの資料で確認できます。
主な調査方法は以下のとおりです。
| 調べ方 | 詳細 |
|---|---|
| 就職情報サイト | 大手求人プラットフォームの企業概要欄に平均勤続年数が載っているケースあり。非公開企業もあるため複数サイトを確認。 |
| 就職四季報 | 資本金や業績と併せて平均勤続年数を掲載する場合あり。比較的規模が大きい企業が中心。 |
| 有価証券報告書 | 上場企業が提出する公式資料。情報量が多い。 |
| OB・OG訪問 | 現場の声を直接聞く方法。担当者によって伝わる内容に差が生じる可能性があるので、複数人から話を得ると客観性が増す。 |
いずれの方法でも確認が難しい場合は、企業説明会や公式SNSで質問するのも効果的です。

OB・OG訪問は、Webサイトや資料だけでは得られない「生の声」を聞ける貴重な機会です。
特に社風や人間関係といった情報は、実際に働いている方の話が参考になります。
ただし、個人の意見に偏る可能性もあるため、複数の社員の方から話を聞けると、より客観的な判断ができるでしょう。
無料ですぐ平均勤続年数を確認できるアプリ
ちなみに、私たちが提供する「HELLOBOSS」は、無料ですぐに企業の平均勤続年数がわかります。
550万社以上のデータを収録しているため、あなたが検討中の企業も調べられる可能性があります。
さらに
「平均年齢」「月間残業時間」「離職者数」「男女比率」など、企業研究に必要な情報も一目でわかります。
採用担当者に直接チャットで質問できるので、企業研究を効率的に進めたい方は無料で活用してみてください。
平均勤続年数の全産業平均は約12年が目安
厚生労働省の賃金構造基本統計調査によると、全産業の平均勤続年数は「12年前後」が一般的な目安です。
男女差や学歴差、業界別の違いで差がありますが、製造業や金融・保険では比較的長く、宿泊・飲食やサービス業はやや短めな傾向が見られます。
ポイント
12年を上回る企業は安定感があると捉えられる場合もありますが、それだけで社内環境を断定するのは早計です。
労働条件や福利厚生、離職率などを総合的に捉えると、職場の実態が見えてきます。
日本全体の平均勤続年数の推移
日本の平均勤続年数は長期雇用慣行や労働者の高齢化に伴い、緩やかに伸びる傾向があります。
2014〜2019年はほぼ12年強で推移し、2018〜2019年には12.4年と高い水準に達しました。
それ以降もおおよそ12年で推移しています。
近年は人手不足で企業が人材定着を図っていることや、雇用延長により高年齢層が増加していることで、平均勤続年数は緩やかに上昇しつつあります。
【業界別】平均勤続年数の目安

業界によって勤続年数は違います。
厚生労働省の「令和4年賃金構造基本統計調査の概況」第5表には産業別の平均値が示されており、参考にすると業界ごとの特徴が見えてきます。
| 業界 | 平均勤続年数 |
|---|---|
| サービス業 | 約9年 |
| 建設業 | 約13年 |
| 製造業 | 約15年 |
| 情報通信業 | 約12年 |
| 金融・保険業 | 約14年 |
| 不動産業 | 約10年 |
| 宿泊・飲食業 | 約10年 |
| 教育・学習支援業 | 約11年 |
| 医療・福祉 | 約9年 |
以下で主な業界の平均勤続年数と、その背景を確認しましょう。
サービス業|約9年
サービス業の平均勤続年数は約9年と全産業平均を下回っています。
長時間労働と賃金水準のミスマッチが定着を妨げる要因です。
人手不足による過剰な業務負担や、休日取得の難しさも関係しています。
出典:厚生労働省|第2-(2)-9図 男女別・産業別平均勤続年数の推移
また、昇給・昇進の展望がもちにくい環境も長期勤続の障壁となっているのが現状です。
長く勤続しやすいサービス業の特徴は以下のとおりです。
長く勤続しやすいサービス業の特徴
- 従業員の育成に注力し、OJTや資格取得支援を行っている
- 評価制度が明確でキャリアパスが見える企業
- IT導入など業務効率化で長時間労働を是正している
- 正社員登用や処遇改善に積極的に取り組んでいる
大手企業や「隠れホワイト企業」では平均勤続年数が長い傾向があります。
福利厚生が整った職場に勤めることが長期勤続のカギとなるでしょう。
詳しくは、平均勤続年数が長い企業の5つの特徴から解説していきます。
建設業|約13年
建設業の平均勤続年数は約13年と平均並みの水準です。
労働環境の厳しさが勤続年数を伸ばす障壁となっています。
出典:国土交通省|建設業における雇用管理現状把握実態調査報告書
ただし、週休2日制導入や残業時間上限規制への対応が進み、ワークライフバランスが改善した企業では平均勤続年数が延びる傾向が見られます。
大手ゼネコンでは給与水準が高く将来の昇進機会もあるため、長期的に働く社員も多いです。
製造業|約15年
製造業の平均勤続年数は約15年と全産業の中でも長めであり、安定した雇用環境が整っています。
一方で肉体的・精神的負担とキャリア展望の乏しさが勤続年数の伸び悩みに影響することもあります。
出典:厚生労働省|第2-(2)-9図 男女別・産業別平均勤続年数の推移
長く働きやすい製造業の特徴は以下のとおりです。
長く働きやすい製造業の特徴
- 安定した経営基盤を持つ大手メーカー
- 給与水準が高く昇格機会が用意されている
- 労働組合がしっかり機能し労使関係が安定している
- 現場の負担軽減策(自動化や人員増強)を講じている
- 技能検定や社内資格制度でキャリアを見える化している
特に自動車・電機など大手メーカーでは終身雇用の文化が根強く、平均勤続年数が20年以上に及ぶ企業も珍しくありません。

私も製造業での勤務経験がありますが、安定性は魅力の1つです。
ただ、企業によっては部署や職種で働きがいや負担感が大きく異なることも。
特に工場勤務の場合は、体力的な側面やキャリアパスの具体例を確認しておくと、入社後のミスマッチを防ぎやすくなりますよ。
情報通信業|約12年
情報通信業の平均勤続年数は約12年と全国平均に近い水準ですが、企業間の差が大きいのが特徴です。
大手通信企業では勤続年数が長い一方、ベンチャー企業では短くなる傾向があります。
ポイント
キャリア形成や最新技術への関心から企業間を移動する人材も多く、技術環境の変化が勤続年数に影響します。
情報通信業で勤続年数が伸びる企業は、労働環境の整備を重視しているのが特徴です。
残業削減やリモートワーク・フレックスタイム導入でワークライフバランスを確保し、社員のスキルアップ支援やキャリアパスを提示することで定着率を高めています。
金融・保険業|約14年
金融・保険業界の平均勤続年数は約14年と全産業平均より長く、安定志向が強い人材が多いのが特徴です。
メガバンクや大手保険会社では新卒入社者が長く勤める傾向があり、業界全体として長期勤続の文化が根付いています。
金融・保険業は離職率も低いことがわかります。
長く働きやすい金融・保険業の特徴は以下のとおりです。
長く働きやすい金融・保険業の特徴
- 雇用が安定しており景気変動による人員削減が少ない
- 給与水準が高く生活基盤が守られている
- 充実した福利厚生による帰属意識の高さ
- 階層別研修や資格取得支援など人材育成プログラムの充実
- 社内で培った専門知識が評価される環境
都市銀行や大手生保の平均勤続年数は20年前後にも及び、働きやすい企業風土や専門性の高さが長期勤続につながっています。
不動産業|約10年
不動産業界の平均勤続年数は約10年と全国平均をやや下回る水準です。
労働時間の長さと休暇の取りづらさが勤続年数の伸び悩みにつながっており、特に営業職では歩合給への依存が強いため、転職する方もいます。
ポイント
不動産業界で平均勤続年数が長い企業は、労働環境と評価制度の改善に取り組んでいる傾向です。
営業時間の工夫やITツール導入による業務効率化を進め、適切な休息と休日を確保できる会社も増えています。
また、基本給を手厚くし、過度な歩合依存を避けている企業では、社員が安心して長く働く傾向が強まっています。
宿泊・飲食業|約10年
宿泊・飲食サービス業の平均勤続年数は約10年と全産業平均よりも短く、業界全体として定着率の課題を抱えています。
長時間労働やシフトの不規則さによる体力的な負担、休日不足によるプライベート時間の欠如などが勤続年数を伸ばしにくくしています。
宿泊・飲食業で長く働きやすい企業の特徴は以下のとおりです。
長く働きやすい宿泊・飲食業の特徴
- 残業時間削減や週休2日制の徹底に取り組む企業
- 研修制度や昇格制度が整い成長実感を得られる環境
- 頑張りを還元するインセンティブや店長手当の充実
- 安定した雇用と福利厚生の提供
- 働きやすさを重視する経営方針
大手ホテルチェーンや外食チェーンでは働き方改革が進み、長く働く従業員も増えています。
老舗の高級旅館や一流レストランでは10年以上勤務するベテラン従業員もいます。
教育・学習支援業|約11年
教育・学習支援業の平均勤続年数は、約11年と全国平均に近い水準です。
公立学校教員では長期勤続者が多い一方、学習塾や予備校では比較的短いなど、業態によって差があります。
長時間労働や業務過多、職場環境の厳しさは勤続年数を伸ばす上での障壁となっています。
ポイント
教育業界で勤続年数が長い職場は、安定した雇用環境と働き方改革を重視しているのが特徴です。
公立学校教員は公務員として雇用が保障され経済的に安定しているため、平均勤続年数が長くなる傾向にあります。
出典:独立行政法人労働制作研究・研修機構|1日あたりの勤務時間数は減少するも、平均在校時間は依然として10時間以上
部活動指導の外部委託や事務作業のサポートスタッフ配置など、教員の業務負担軽減策を導入している学校では定着率が向上しています。
医療・福祉|約9年
医療・福祉業界の平均勤続年数は約9年と全国平均を下回り、特に若手の定着が課題となっています。
看護・介護職は体力的な負担や夜勤・不規則勤務の影響で長期勤続が難しく、職種や施設規模によって勤続年数に差があるのが特徴です。
出典:厚生労働省|図表1-2-61 職種別の平均勤続年数(職種別、年齢別)
長く働きやすい医療職の特徴は以下のとおりです。
長く働きやすい医療職の特徴
- 十分な人員配置による一人当たり業務量の削減
- 夜勤回数調整や連続夜勤制限など働き方の柔軟化
- 計画的な有給取得推進によるワークライフバランス確保
- 処遇改善手当や経験加算などの給与面での評価
- 研修制度やキャリアアップ支援の充実
看護職の配置基準を手厚くしている大病院では平均勤続年数が長い傾向にあり、職場環境と支援体制の充実が長期勤続につながっています。
公的病院や大手法人施設では、平均勤続年数が業界平均より長い例も見られます。
無料ですぐ平均勤続年数を確認できるアプリ
前述のとおり、HELLOBOSSは無料ですぐに企業の平均勤続年数がわかります。
550万社以上のデータを収録しているため、あなたが検討中の企業も調べられる可能性があります。
さらに
「平均年齢」「月間残業時間」「離職者数」など、企業研究に必要な情報も一目でわかります。
採用担当者に直接チャットで質問も可能なので、企業研究を効率的に進めたい方は無料で活用してみましょう。
平均勤続年数が長い企業の5つの特徴

平均勤続年数が長い会社は、社員が長く働きやすい環境を整えている例が多いです。
具体的には以下のような特徴があります。
平均勤続年数が長い企業の特徴
- 業績や経営が安定している
- 福利厚生が充実している
- 勤務時間や休日などの労働条件が良い
- 年功序列や終身雇用の文化が根強い
- 社内の研修・キャリアパス制度が整備されている
それぞれのポイントを詳しく見ていきましょう。
業績や経営が安定している
業績や経営が安定している企業は、不況期でも解雇が起こりにくく雇用が確保されやすいです。
公共インフラを担う組織は生活基盤を支えるため、景気変動の影響を受けにくい特徴があります。
ポイント
業績が落ち込みづらい企業では、人材育成への投資が進みます。
その結果、社員は長期的な視点でキャリアを築きやすく、安心感をもって働けるでしょう。
具体例として、電力やガス会社などの公共サービス企業では、需要が安定しているため、長期的な視点で人材を育成する仕組みが整っています。
こうした環境が社員の安心感を高め、勤続年数の長さにつながる傾向があります。
福利厚生が充実している
福利厚生が行き届いた企業では、社員の職場への愛着が深まります。
育児や介護などライフイベントに合わせた柔軟な働き方ができると、家庭と仕事の両立が可能になるでしょう。
例えば育休や介護休暇の制度が整った組織では、一時的な休職後も復帰しやすい環境があります。
こうした制度があれば退職を選ばずに済むため、結果的に平均勤続年数が上昇する傾向が見られます。
主な福利厚生の例
- 住宅手当や社宅制度
- 資格取得支援や受講料の補助
- 産休や育休に加え、時短勤務制度
- フィットネスクラブや保養施設の優待
自分のライフプランと企業の制度を照らし合わせると、長く働く上での不安を減らせます。
勤務時間や休日などの労働条件が良い
労働条件が良い会社では、過度な残業や休日出勤が少なく、社員の生活リズムが整います。
毎日遅くまで働く環境は心身に負担がかかり、中途での転職を考える人が増えがちです。
ポイント
一方、ノー残業デーの導入や完全週休2日制を整備している組織では、仕事とプライベートの切り替えがスムーズです。
疲労が軽減されるため、長く働き続ける社員が増える傾向にあります。
社員の健康を大切にする企業ほど離職率が下がり、結果として平均勤続年数が伸びるケースが多いでしょう。
年功序列や終身雇用の文化が根強い
年功序列や終身雇用の文化がある企業では、入社後に少しずつ役職や給与が上がり、将来への期待をもちやすいです。
急なリストラが少ない環境もあり、結婚や子育てなど人生の転機でも働き続ける人が多くなります。
例
大手メーカーや銀行では、長い年月をかけて職能を身につける前提の制度をもち、若手からベテランまで段階的に処遇が改善される仕組みがあるでしょう。
ただし、実力主義を求める人には物足りなく感じられることもあります。
自分の価値観に合うかどうかを見極めることが大切です。

私が新卒で入った大手企業も、まさに年功序列の文化が根強い会社でした。
安定性はありましたが、正直、人間関係で苦労しました…
どんなに平均勤続年数が長くても、自分に合わない環境だと続けるのは難しいです。
会社の文化が自分の価値観と合うかどうかも、しっかり見極めてくださいね。
社内の研修・キャリアパス制度が整備されている
研修やキャリアパス制度が整った企業では、入社後のスキル育成やキャリアアップを見据えて長く働く社員が増えます。
社内で段階的に専門知識やリーダーシップを磨ける環境があると、職務への不安が減り、離職率の低下につながるケースが多いでしょう。
多くの組織で導入されている研修とキャリアパス制度の例は以下のとおりです。
組織として社員の成長を促す姿勢が明確な職場ほど、早期離職が減り、平均勤続年数が上がる傾向が見られます。
平均勤続年数が短い企業の5つの特徴

平均勤続年数が短い企業って、ブラック企業なの?
なぜ社員がすぐに辞めてしまうんだろう?
平均勤続年数が短い会社は悪いイメージが先行しがちですが、創立年数や業界の慣習、若手社員の割合など多面的な要素が絡んでいます。
以下の5つの特徴をチェックすると、平均勤続年数の背景にあるポイントを理解しやすくなります。
平均勤続年数が短い企業の特徴
- 創立して間もない、または急成長中のベンチャー企業
- 若い社員が多い
- 給与や労働環境に不満があるケースが多い
- 業界特性として転職が多い
- 評価制度やキャリアパスが明確でない
それぞれ詳しく見ていきましょう。
創立して間もない、または急成長中のベンチャー企業
創立して間もないベンチャー企業は、必然的に在籍期間が短くなります。
設立から数年しか経っていない状態では、勤続が5年を超える社員が存在しない場合もあるでしょう。
ポイント
急成長を続けて人手不足に陥っている企業は、新卒や中途を大量に採用するため、全体の勤続年数が下がりがちです。
例えば、創業5年以内のIT系企業が事業拡大のために若手を一度に採用すれば、在籍期間の平均が一気に下がります。
このような場合は、企業の成長ステージを考慮する必要があります。
若い社員が多い
若い社員が多い会社では、採用数や退職率の影響から勤続期間が短くなるケースが目立ちます。
新卒を大量に迎え入れれば全体の平均が下がり、早期離職や転職によってさらに在籍年数が短縮されることがあります。
若手社員が増えると平均勤続年数が短くなる主な理由は以下のとおりです。
平均勤続年数が短くなる理由
- 若い人材はさらなる成長を目指して転職を検討する傾向がある
- 社歴の浅い社員が増加して全体の在籍年数が下がりやすい
- 20代や30代を優先採用する方針によりベテラン層が減少する
若手中心の組織は柔軟でエネルギッシュな反面、長く落ち着いて働きたい人には合わない場合もあります。
事前に社風をよく確認しましょう。
給与や労働環境に不満があるケースが多い
給与水準や労働条件が見合わない企業では、負担が大きくなり退職を選ぶ人が増えます。
例えば残業時間が多いわりに賃金へ反映されない状態や、有給休暇を取得しづらい社風が続くと在籍が長続きしません。
注意点
手当が少なく給与アップが見込みにくい職場だと、将来への不安が増し、離職につながります。
内部で処遇改善や制度を定期的に見直す仕組みがなければ、結果的に平均勤続年数は短くなります。
労働環境を調べたい場合は、口コミサイトやOB・OG訪問で実際の声を確認し、入社前に社員の満足度を探ると参考になるでしょう。
業界特性として転職が多い
業界によっては転職が当たり前で、勤続年数が短くなるケースがあります。
コンサルティングやIT、外資系企業などは数年単位でキャリアを変える例が多く、結果として社内の在籍期間が平均的に短くなります。
転職者が多い主な業界
- コンサル業界
- IT業界(SE、プログラマーなど)
- 外資系金融、外資系メーカー
- 広告代理店やメディア関連
こうした分野は実力主義が進みやすく、若手でも早く活躍できる魅力があります。
一方で安定志向の人には向かない可能性があるため、業界選びの際は将来の方向性を見極めることが大切です。
評価制度やキャリアパスが明確でない
評価制度やキャリアパスが整っていない組織は、昇給や昇進の基準があいまいになりがちで、やる気を保ちづらいです。
例えば、誰にどのような基準で昇進が与えられるか不透明な環境だと、より好条件の職場を求めて外へ移る社員が増えます。
注意
キャリアビジョンが提示されていないと長期的な目標を描きにくく、教育制度への意欲も下がるため、定着率が下がる一因となります。
こうした状況では若手が腰を据えて働かず、最終的に平均勤続年数の低下につながりやすいでしょう。
求人票や現場の声を手がかりに、評価基準がどれだけはっきりしているかを確認することをおすすめします。
平均勤続年数だけでホワイト・ブラックは決まらない3つの理由

平均勤続年数は企業を判断する際に目立つ数値ですが、実は社内環境や将来性を正しく映し出すとは限りません。
以下の3つの理由を押さえると、勤続年数だけでホワイト・ブラックを結論づけない方が良い理由がわかりやすくなります。
平均勤続年数だけで判断できない理由
- 事業フェーズや企業規模による影響を受けるから
- 労働市場・業界特性の影響を受けるから
- 企業ごとの事情が反映されにくいから
それぞれ詳しく解説します。

平均勤続年数はあくまで1つのデータに過ぎません。
特に新卒や若手の転職では、この数字に惑わされがちですが、企業の成長段階、業界特性、そして何より「自分がその環境で成長できるか、やりがいを持てるか」という視点が大切です。
事業フェーズや企業規模による影響を受けるから
事業拡大期のベンチャーや新設組織は、新人が一度に増えて平均勤続年数が短くなる場面が多いです。
反対に、古参社員が多い大手グループ企業は在籍期間が長くなる例が見られます。
古参社員が多い企業では新しい考え方が取り入れられにくく、変化への対応が遅いかもしれません。
事業フェーズや規模の変化によって数値が左右されるため、長短だけでホワイト・ブラックを決めるのは考えものです。
労働市場・業界特性の影響を受けるから
産業の構造や転職のしやすさは、勤続年数にも影響します。
専門職が多いITやコンサル分野は流動性が高く、入れ替わりが頻繁です。
一方、インフラや公務など安定性の高い領域は、社員が長期で在籍する傾向があります。
労働市場や業界特性で生じる差異
- 他社へ移る動きが増える分野は勤続期間が短くなる
- 終身雇用の慣行が残る業界では、勤続年数が上昇しがち
- 景気に左右される業種は退職者が集中する時期がある
業種によって社員の移動パターンが大きく異なるため、平均勤続年数だけではホワイト・ブラックを断定しにくいでしょう。
企業ごとの事情が反映されにくいから
平均勤続年数は全社員を1つの数字にまとめる方式のため、部門や職種ごとの実態が見えにくくなります。
ある部署は社員が定着していても、別の部門で離職が続けば数字のバランスが崩れる場合があります。
具体例
総合職と技術職をまとめて計算すると、転勤やプロジェクトの終了で退職するパターンが混在し、結果的に平均勤続年数が変動することが多いです。
また、年齢層や制度が部署によって違うケースも珍しくありません。
このように1つの数値だけでホワイト・ブラックを判断するのはリスクがあります。
平均勤続年数が長いからといって良いとは限らない事例
「平均勤続年数が長い=良い」「平均勤続年数が短い=悪い」と捉えられがちですが、反対の事例を紹介します。

私が実際に体験した例です。
平均勤続年数が長い企業が働きにくく、1年半で辞めてしまった事例。
そして、平均勤続年数が短いのにもかかわらず、キャリア形成できて独立できた事例です。
平均勤続年数が長い企業でも働きにくかった体験談

私が新卒で就職した会社は、誰もが知る超大手企業です。
当時は定年まで勤め上げる方が多かった印象です。
ところが、相性が悪い先輩に当たってしまい、精神的にすごく病んだのを覚えています。
質問するたびにため息をつかれて、陰口を言われているのも知っていました。
土日休みだったのですが、日曜日の午後くらいから憂鬱になっていたのです。
当時のこと
平日は毎日22時くらいに就寝しないと、体力もメンタルも保たない状態でした。
「これはとても続けられない…」と思い、1年半で退職しました。

平均勤続年数が長いといっても、自分に合わない環境だと長く働けないケースもあります。
くれぐれも平均勤続年数だけに執着せず、自分に合う仕事かどうかを判断してほしいです。
平均勤続年数が短い企業でもキャリア形成できた体験談
一方、社員が2人しかいないスタートアップ企業で働いた経験もあります。
創業まもない企業だったため、平均勤続年数は「3年」くらいです。
当時のこと
人材が少ないので、ほとんどすべての業務を一人で回していました。
Webマーケティングの企業だったのですが、営業・リサーチ・制作・アフターフォローなどを一人で担当したのです。

結果的に「一人でこれだけできるなら独立できるのでは…?」と思うようになりました。
意を決して独立したところ、現在も無事に生活できています。
このように、平均勤続年数が短いからといって、キャリアを築けないわけではありません。
【結論】自分のやりたいことや理想のキャリアがすべて
これらの経験を通して、結局のところ「自分のやりたいことや理想のキャリア」を追い求めるのが良いと感じています。
平均勤続年数が長い会社でも合わなければ続けられないし、平均勤続年数が短くてもスキルが身につけば次のキャリアが広がります。

漠然とでも良いので「自分のやりたいこと」を考えてみて、それを実現するためにどんなキャリアを歩めばいいか考えると、後悔が少ないと思います。
まずはあなたの理想の未来を考えて、そこから逆算してみてください。
企業研究で平均勤続年数の他に見るべき6つの指標


平均勤続年数以外にも、企業選びで確認すべきポイントがあるの?
どんな指標を見ればいいんだろう?
平均勤続年数だけでなく、複数の指標を合わせて調べると企業の働きやすさや今後の見通しをより正確に捉えられます。
以下の項目に目を向けると、将来も安心して勤務できるか見えやすくなるでしょう。
企業研究で見るべき6つの指標
- 離職率・新卒3年以内の定着率
- 労働時間や残業時間、休日・休暇制度
- 業績・財務状況の推移
- 福利厚生・研修制度・資格支援制度
- 社員の平均年齢・年齢構成
- 企業の採用方針・育成方針
こちらも詳しく解説していきます。
離職率・新卒3年以内の定着率
離職率が高い会社は人が頻繁に入れ替わるため、社内ノウハウが定着しにくく混乱が生じるケースがあります。
新卒3年以内の定着率は、若手社員が働き続けられる環境を整えているかどうかの目安です。
研修制度や人間関係の良し悪しを推し量るうえで有効です。
計算例
従業員規模1,000名の企業で1年間に離職した人が50名なら、離職率は5%です。
新卒向けの就職情報サイトや就職四季報で3年以内の離職率を確認すると、若手へのサポート体制があるかどうかを見定めやすいでしょう。
数字だけでなく、面接や説明会の場でも定着率向上の取り組みを質問してみると実態を把握しやすくなります。
労働時間や残業時間、休日・休暇制度
平均の残業時間が長いと心身への負荷がかかり、結果的に離職を検討する人が増えがちです。
一方、ノー残業デーや定時退社を実施している会社は、ワークライフバランスを重視する姿勢がうかがえます。
年間休日が120日を超えると、余裕をもってリフレッシュできるとの見方もあるでしょう。
チェックポイント
- 完全週休2日制の有無
- 祝日休みか営業日か
- 長期休暇制度の有無
- 有給休暇の取得率
- 残業時間の上限管理
求人票や企業HPをチェックすると、記載されている可能性があります。
面接時に「直近の月平均残業時間はどれくらいか」「休日取得率はどの程度か」と尋ねてみると詳しい情報を得られるでしょう。
業績・財務状況の推移
業績や財務の安定性は、長期的な雇用の可能性を左右します。
チェックすべきポイント
- 売上高や営業利益の増減
- 自己資本比率や負債額の推移
- 主力商品・サービスの成長性
- 決算説明資料やIR情報の内容
数字が伸びている企業は事業拡大の余地があり、キャリアアップの機会が増える可能性が高いです。
一方、赤字が続く会社や負債が増え続ける会社は、経営が不安定といえます。
福利厚生・研修制度・資格支援制度
福利厚生や研修制度、資格取得サポートの充実度は働きやすさに直結します。
住宅手当や育児休暇制度がある職場は、出産後も継続して働く社員が増える傾向があります。
社員の平均年齢・年齢構成
社員の平均年齢は、組織の雰囲気やキャリア形成のしやすさに影響を与えます。
例えば、営業職が多い職場で若い社員が中心なら元気さがメリットでしょう。
一方、技術系の部門が多い企業で年齢が高い人が多いと、深い専門知識を集約しやすい特徴があります。
自分の年齢や希望するキャリアに合うかどうかを検討するのがおすすめです。
企業の採用方針・育成方針
企業研究では、採用や育成の考え方もチェックしてみてください。
平均勤続年数が長い企業の採用・育成方針例
- 中長期前提で人材を育てる計画をもつ
- 新卒採用後の育成プログラムを数年間実施
- 社員のキャリアチェンジや部署異動に柔軟な制度を用意
- 定期的な研修・面談でキャリアアップを支援
育成に力を注ぐ会社は社員を長く働かせたい意識が強く、離職率の抑制や勤続年数の維持につながります。
説明会や面接で「社内研修の期間はどれくらいか」「部署間の移動はあるか」などを確かめると、企業がどのように人材を伸ばすかを把握できるでしょう。
無料ですぐに企業研究できるアプリ
前述のとおり、HELLOBOSSは無料ですぐに企業情報がわかります。
具体的には、以下のような情報が収録されています。
HELLOBOSSでリサーチできる情報例
- 定着率
- 中途採用の実績
- 中途採用比率
- 平均勤続年数
- 従業員の平均年齢
- 月の平均残業時間
- 有給休暇の取得日数
- 育児休暇取得率など
さらに、不明点は企業の採用担当者にチャットで気軽に質問できるため、疑問点を解消しやすいです。
550万社以上のデータを収録しているため、あなたが検討中の企業も調べられる可能性があります。
無料で企業研究を効率的に進めたい方は利用してみましょう。
平均勤続年数の目安についてよくあるQ&A
ここでは、平均勤続年数の目安についてよくある質問に回答していきます。
平均勤続年数は何年から「長い」といえる?
平均勤続年数は12〜13年前後が全体の基準とされるため、それを上回れば長いとみなす考え方があります。
例えば、設立から50年以上続く老舗のメーカーで平均勤続年数が15年を超えていれば、安定した就業環境を維持していると捉える人が多いでしょう。
逆に設立年数が浅い会社は在籍期間が伸びようがなくても短く見えるため、数字のみで良否を決めるのは早計といえます。
平均勤続年数が3年・4年・5年など短い企業はやはりブラック?
平均勤続年数が3年や4年だと人の入れ替わりが激しい印象を受けますが、ブラックと決めつけるのは早いです。
新興企業やベンチャーでは設立年数が浅く、結果として数字が短く映るケースがあります。
注意点
プロジェクト単位で転職しやすい業界もあり、一概に判断しにくいです。
一方で、給与や労働条件に難があり早期退職が頻発する組織もあるため、離職率や業界特性を調べるとリスクを減らせます。
平均勤続年数と離職率の関係は?
平均勤続年数と離職率は似たような指標に思えますが、必ずしも一致しない場面があります。
大量採用を実施すると、離職率が低くても勤続年数が短くなることがあります。
ベテランが中心の職場だと離職率がやや高くても、平均勤続年数が長くなる場合もあるでしょう。
会社説明会やOB・OG訪問で具体的な人材の流れを聞くと、勤続年数と離職率の背景を理解できます。
最初に入る会社で平均勤続年数をどの程度重視するべき?
最初に就職する段階では平均勤続年数が気になりますが、数字だけで企業の良否を決めると他の重要な部分を見落とす恐れがあります。
仕事内容や社風、キャリア支援の仕組みなど総合的に検討すると、自分に合った選択をしやすいでしょう。
チェックすべき観点
- 学びたいスキルや経験と業務内容が合致しているか
- 自分の価値観に合った社風や組織体制を築いているか
- 新卒向けの研修やキャリア支援制度が整っているか
- 福利厚生や評価制度を長期的な視点で検討できるか
平均勤続年数は参考指標の1つにすぎません。
会社説明会やOB訪問で働く人の声を聞きながら、自分が今後のキャリアを積み重ねられる場なのかしっかり見極めると良いでしょう。

初めての就職では特に安定性を求めて平均勤続年数を気にする方が多いですが、最も重要なのは「その会社で何を得たいか」「どんなキャリアを築きたいか」です。
平均勤続年数は参考程度にとどめ、仕事内容、社風、成長環境などを総合的に見て、ご自身に合うか判断してください。
まとめ|多角的な視点で企業を見極めよう
平均勤続年数は企業選びの参考になる指標ですが、それだけで「ホワイト企業」「ブラック企業」と判断するのは早計です。
企業の実態をより深く理解するためには、以下の指標も合わせて確認してみてください。
平均勤続年数以外に見るべき6つの指標
- 離職率・新卒3年以内の定着率
- 労働時間や残業時間、休日・休暇制度
- 業績・財務状況の推移
- 福利厚生・研修制度・資格支援制度
- 社員の平均年齢・年齢構成
- 企業の採用方針・育成方針
これらの情報を多角的に収集・分析し、あなた自身の価値観やキャリアプランに合った企業を見つけ出すことが、後悔しない企業選びにつながります。

平均勤続年数だけじゃなく、離職率や残業時間、福利厚生とか、他のデータも効率よく知りたい…
という方は、くりかえしですが、スマホアプリ「HELLOBOSS」がおすすめです。
企業の平均勤続年数だけでなく、離職率、平均残業時間、有給取得日数などの詳細なデータも無料でチェックできます。
さらに、企業の採用担当者に直接チャットで質問できるので、求人情報だけではわからないリアルな情報を得ることも可能です。
無料なので、さっそくインストールして、効率的な企業研究に役立ててみてください。
あなたの企業選びが成功し、納得のいくキャリアをスタートできることを応援しています!