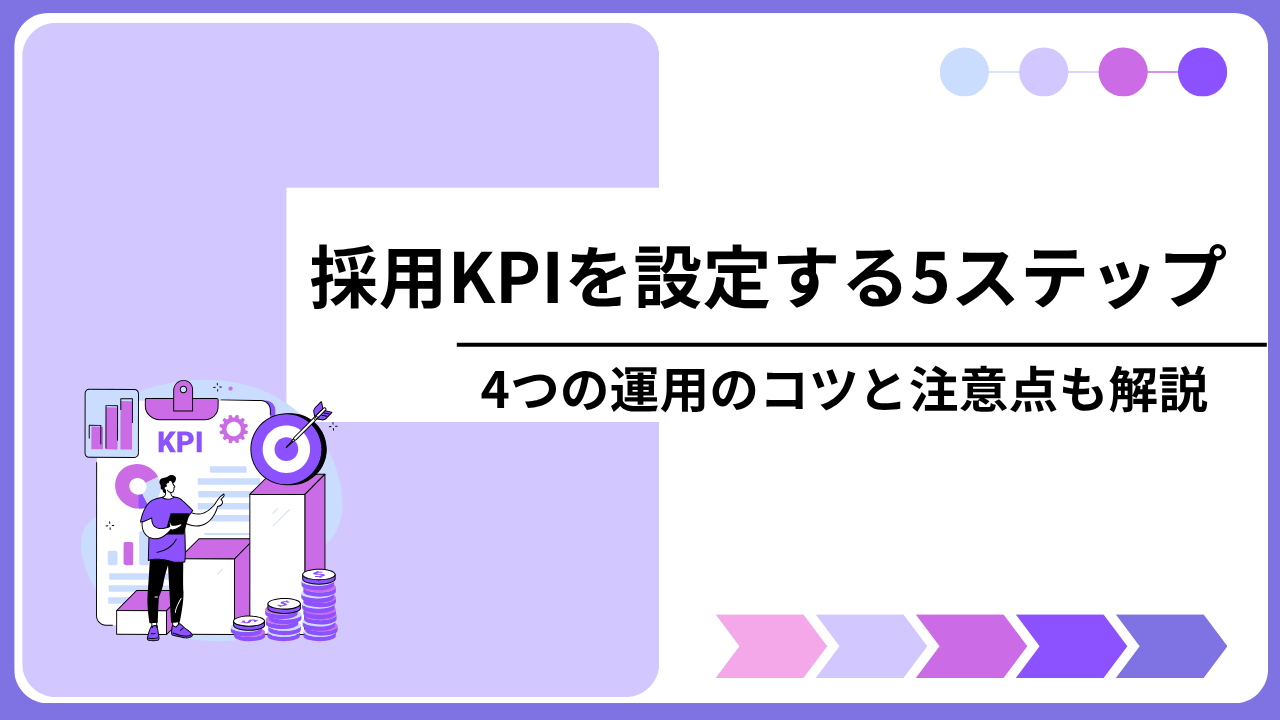「応募者数が目標に届かない」「内定辞退率が高い」など、採用活動の課題に直面している人事担当者は少なくありません。
採用目標を達成するためには、採用KPIを導入するのがおすすめです。
この記事では、採用KPIの基本的な考え方から、5ステップの設定手順、運用のコツまで、網羅的に解説しています。採用目標の達成を目指す人事担当者の方は、最後まで読んでみてください。
無料で求人を掲載できます
Contents
採用KPIとは
KPIとはKey Performance Indicator(キー パフォーマンス インジケーター)の頭文字をとったもので「重要業績評価指標」を意味しています。
採用KPIは、企業の採用目標を達成するために管理する指標です。各プロセスの成果を数値化することで、採用戦略の立案や改善に活用できます。
代表的な採用KPIには、以下のような項目があります。
採用KPIの主な項目
- 応募者の人数
- 採用面接の通過率
- 内定率
- 内定辞退率・内定承諾率 など
KPIとKGIの違い
KGIは企業が達成すべき最終的なゴールを数値化した指標で、Key Goal Indicatorの略称として「最終目標達成指標」を表します。
例えば、採用分野では「年間で20名を採用する」といった具体的な数値目標がKGIにあたります。
それに対してKPIは、この最終目標を実現するために設定される途中経過の指標です。
採用活動の場合「応募者数を200名確保する」「50%以上の面接通過率を目指す」などの進捗管理指標として活用されます。
組織が掲げる採用目標を着実に達成していくには、KGIを明確に定め、それと整合性のあるKPIを設定した上で、採用活動を展開することが求められます。
採用KPIを実践する4つのメリット
採用KPIを実践すると、以下のようなメリットがあります。
採用KPIを実践するメリット
- 採用活動を見える化できて改善点がわかる
- 採用プロセスと目標を明確化できる
- 採用活動の費用対効果が上がる
- 関係者の目標が明確になる
1つずつ解説していくので、採用KPIを導入してみてください。
採用活動を見える化できて改善点がわかる
書類選考の通過率、面接の実施回数、内定承諾率など、各段階でのパフォーマンスを数値化することで、採用活動の全体像を可視化できます。
人事チームは数値化された情報をもとに、採用活動の各工程における課題を素早く発見できるでしょう。
代表的な課題と、考えられる理由は以下のとおりです。
| 課題 | 考えられる理由 |
|---|---|
| 書類選考の通過率が悪い | 求人情報の内容が不明瞭 |
| 面接通過率が低い | 面接の内容が厳しすぎる |
| 内定承諾率が低い | 企業の魅力が伝わっていない |
数値データはチーム内での情報共有も促進します。特に新卒採用では1年近くの長期的なスケジュールで活動するため、途中経過を正確に把握することが必要不可欠です。
採用KPIを活用すれば、定期的なミーティングで現状の課題や今後の施策を具体的に議論できて、チーム全体で同じ方向を向いて行動しやすくなります。
採用プロセスと目標を明確化できる
採用KPIの導入は、最終目標達成までの道筋を具体的な数値で示します。
「新卒10名採用」などの漠然とした目標だけでは、いつまでに何をすべきか判断に迷ってしまうでしょう。必要な施策とスケジュールを明確にするには、段階的な数値目標の設定が必須です。
採用KPIがあれば、期限をつけた数値目標の設定・管理に役立ちます。
具体例
- 6月まで:説明会参加者100名を達成する
- 8月まで:一次面接実施50名を達成する
- 10月まで:内定承諾15名を達成する
最終目標までのプロセスを数値で管理することで、採用活動全体の生産性が向上します。
採用活動の費用対効果が上がる
採用活動における費用対効果の最適化にも、採用KPIが役立ちます。採用チャネルごとの応募者数、面接設定率、内定承諾率などを数値化することで、投資対効果を正確に把握できます。
例えば、求人サイトAは掲載料が高額でも応募者の質が高く、内定承諾率も80%を超えています。
一方、安価な求人サイトBは書類選考通過率が20%と低調です。
募集開始から入社までの採用コストを総合的に比較すると、一見コストの高いサイトAの方が効率的に採用できるとわかるでしょう。
成果の高い採用チャネルへの予算配分を増やし、効果の低い施策は見直すなど、限られた予算で最大限の採用効果を引き出せます。
関係者の目標が明確になる
採用KPIを設定することで、採用活動に関わるすべての担当者の役割と責任を明確にできます。人事部門、面接官、外部の求人代理店など、多岐にわたる関係者が目標数値を共有することで、各自の役割を認識し、主体的な行動につながるでしょう。
具体例
- 採用代理店:候補者の質や量に対して目標設定
- 人事部門:応募者数や面接設定率に目標設定
- 面接官:面接通過率に目標設定
各担当者がKPIを意識することで、重複業務を避けながら効率的な採用活動が実現できます。
また、数値目標の達成度に基づいて公平な評価が可能になり、担当者のモチベーション向上にもつながります。普段は見えにくい業務の価値も数字で示せるため、チーム全体の信頼関係も深まり、組織全体の採用力が向上するでしょう。
採用KPIを設定する5ステップ
次に、採用KPIを設定する具体的な手順を解説していきます。
採用KPIを設定する5ステップ
- KGIを設定する
- 採用チャネルの選考フローを決める
- 歩留まり率を調べる
- KGIから逆算してKPIを設定する
- KPIをまとめて共有する
1ステップずつ解説していくので、さっそく実践していきましょう。
ステップ1.KGIを設定する
KPIを設定する前に、KGIを設定しましょう。ゴールであるKGIから逆算してKPIを設定していくためです。
具体的な数字を入れてKGIを設定していきます。
KGIの具体例
- 3ヶ月以内にエンジニア5名を採用する
- 半年で営業職10名を採用する など
予想される退職者数も加味して、実質的な人員充足数を算出すると良いでしょう。
目標設定の優先順位は企業の状況により異なります。新規事業で即戦力が必要な場合は「人材の質」を重視し、事業拡大で広く人材を募る場合は「採用人数」を重視します。
目標の期限や採用予算も明確にしておくことで、その後のKPI設定がスムーズになるでしょう。
ステップ2.採用チャネルの選考フローを決める
企業が活用する採用チャネルには、以下のように複数の種類があり、それぞれで採用フローを設定する必要があります。
企業が活用する採用チャネルの例
- 求人媒体
- 合同説明会
- 人材紹介会社
- リファラル採用など
採用チャネルごとに応募者の特性や特徴が異なるため、それぞれに適した選考フローとKPIを設定します。以下は、採用チャネルごとの選考フローの一例です。
各チャネルの特性を活かした選考フローを設計すると、効率的な採用活動が実現できます。
採用フローの設計はKPI設定の基盤となり、採用活動全体の生産性向上につながります。
ステップ3.歩留まり率を調べる
歩留まり率は、採用プロセスの各段階における候補者の通過率を示す指標です。
「選考通過数÷選考対象数×100」で、選考段階ごとの効率性を計算できます。
採用チャネルによって適切な歩留まり率は大きく異なります。
歩留まり率の設定には、自社の過去データや業界標準を参考にしましょう。データが不足する場合は、採用コンサルタントに相談するのも有効です。
ステップ4.KGIから逆算してKPIを設定する
続いて、KGIから逆算してKPIを設定していきます。
例えば、全体の採用目標が20名の場合、まず採用チャネルごとの人数を割り当てます。
具体例
- 求人媒体:6名
- 人材紹介会社:4名
- 合同説明会:10名
設定した歩留まり率を基に、各選考段階で必要な人数を算出していきます。
例えば、求人媒体経由で6名採用するケースで、内定承諾率が50%なら内定者数は12名必要です。
採用チャネルごとの数値目標を明確にすることで、限られた採用予算を効果的に配分し、戦略的な採用活動が実現できます。
ステップ5.KPIをまとめて共有する
設定した採用KPIは、部門内のメンバー全員に共有しましょう。採用活動の目標値や進捗状況をメンバー間で認識することで、採用業務の効率化や質の向上につながるためです。
共有の際には、各指標の意図や計測方法についても明確に説明してください。
その後、実際の採用活動を通じて得られた気づきや課題をメンバーで話し合い、KPIの内容を見直していきます。
メンバーの経験や視点から意見を出し合うことで、より実践的で効果的な指標へと磨き上げましょう。
【参考】採用KPIに組み込むデータ
採用KPIに組み込むデータは企業によって違いますが、代表的なものは以下のとおりです。
採用KPIに組み込むデータ例
- 応募者数
- 適性検査の合格率
- 説明会参加率
- 書類選考通過率
- 面接設定率
- 内定率
- 内定承諾率
- 採用単価 など
自社で作成するKPIの参考にしてみてください。
採用KPIの運用のコツ4選
続いて、採用KPIの具体的な運用方法を解説していきます。
採用KPIの運用方法
- SMARTの法則に沿った採用KPIにする
- 直近の採用状況を把握・共有する
- 状況を見ながらKPIを見直す
- PDCAサイクルを回してKPIを改善する
これら4つの運用方法を実践することで、目標を達成できる確率が上がるので、確認してみてください。
SMARTの法則に沿った採用KPIにする
採用KPIの設定では「SMARTの法則」を活用した検証が効果的です。SMARTの法則を用いることで、目標達成を実現しやすくなります。
例えば「6月末までに求人媒体経由の応募者を月間20名獲得する」など、達成できそうな目標で、成果を測定できる具体的な数値目標を立てましょう。
もちろんKGIと関連性があり、期限も明示されていることが必要です。
SMARTの法則は定期的なKPIの見直しにも役立ちます。市場環境の変化や採用状況に応じて目標を修正する際にも、SMARTの5つの観点から妥当性を検証してみてください。
直近の採用状況を把握・共有する
採用KPIは日々の状況変化に応じて、柔軟に管理する必要があります。応募者数、選考通過率、内定承諾率など、各指標をリアルタイムで把握し、目標値との差異を確認しましょう。
例えば、応募者数が目標を下回る傾向にある場合、早期に採用チャネルの追加や広報施策の強化を検討できます。
採用チーム内での情報共有も重要です。週次ミーティングで進捗状況を確認し、リアルタイムの課題への対策を議論してみましょう。
状況を見ながらKPIを見直す
実際に採用活動をスタートすると、当初設定したKPIと現実の数値に大きな乖離が生じることがあります。その場合は、KPI自体の見直しも検討してみてください。
具体例は以下のとおりです。
KPIの見直しには現場の意見を反映させてください。採用担当者や面接官の声に耳を傾け、実態に即した目標設定に修正するのがコツです。
一方的な数値調整は現場のモチベーション低下を招く恐れもあるため、丁寧なコミュニケーションを通じて合意形成を図りましょう。
PDCAサイクルを回してKPIを改善する
採用KPIの運用では、PDCAサイクルを高速で回して、早期に解決策を見つけていくのがコツです。
PDCAサイクル
- Plan:計画
- Do:行動
- Check:評価
- Action:改善
活動終了後の事後分析だけでは、現在進行中の採用活動の改善につながりません。
例えば、内定辞退率が上昇傾向なら、面接での企業説明の充実や内定者フォローの強化など、具体的な対策を講じてみましょう。
週次で進捗を確認し、課題への対策を迅速に実行する体制が必要です。
特に中途採用では、市場環境の変化も激しく、素早い対応が求められます。KPIに基づく高速なPDCAサイクルで、採用活動の質を継続的に向上させましょう。
目的別|KPIの運用例
自社の採用目標によって、重視すべきKPIは異なります。人材の量と質、どちらを優先するかで適切な指標を選択しましょう。
多くの人材を採用したい場合
採用人数の目標達成を重視するケースでは、応募者数と選考効率の向上に重点を置きます。
書類選考通過率を50%程度、面接設定率も70%以上を目指し、できるだけ多くの応募者と対面しましょう。
一方で、選考基準を緩和しすぎると、自社への理解不足による選考途中での辞退や、入社後のミスマッチも増えかねません。面接では企業理念や業務内容を丁寧に説明し、応募者の入社意欲を高めるのがコツです。
内定承諾率60%以上を目標に、内定者フォローも強化する必要があります。
人材の質を重視したい場合
優秀な人材を厳選する採用では、各選考段階の通過率を重要指標とします。
書類選考では職務経験やスキルを精査し、通過率30%程度に抑えます。面接では求める人物像との適合度を慎重に判断し、通過率は40%程度を目安にすると良いでしょう。
選考担当者間で評価基準を統一し、高い選考精度を維持する必要があります。
また、内定辞退を防ぐため、面接での会社説明を充実させ、職場見学や配属後の育成計画も提示します。
採用KPIの運用における2つの注意点
目標を達成するために有効なKPIですが、2つの注意点があります。
運用方法を間違えると効果を最大化できないため、知っておきましょう。
KPIの項目は多くしすぎない
必要以上に採用KPIの指標を設けないように注意してください。
過剰なKPI設定は、データ収集や分析の負担を増大させ、採用チームの疲弊を招きます。また、指標が多すぎると優先順位が曖昧になり、採用活動の方向性が定まらなくなる恐れもあるでしょう。
応募者数、面接通過率、内定承諾率など、採用プロセスの重要な指標に絞って設定することで、採用担当者は本質的な業務に集中できます。
採用目標の達成に直結する3〜5個程度の核となる指標に絞り込むのがおすすめです。
KPIの数値に固執しない
採用KPIは目標達成のための手段であり、KPIの数値を達成すること自体が目的ではありません。応募者数のKPI達成を優先するあまり、採用基準を緩和して質の低下を招くケースや、内定承諾率にこだわって条件面で無理に譲歩するケースは避けなければなりません。
本質的な採用目標を見失わず、柔軟な運用を心がけましょう。市場環境の変化や自社の採用ニーズに応じて、KPIの見直しや調整も必要です。
数値目標は達成の指標として活用しながら、採用活動全体の質を高めることを意識してください。
まとめ|さっそく採用KPIを実践してみましょう
効果的な採用活動の実現には、採用KPIの設定と運用が必要不可欠です。
KGIから逆算してKPIを設定し、採用チャネルごとの選考フローや歩留まり率を適切に管理することで、採用目標の達成が視野に入ります。
運用にあたっては、SMARTの法則を活用した目標設定や、リアルタイムでの状況把握、PDCAサイクルを回すことを意識してください。
一方で、KPIの数を必要以上に増やさず、数値にこだわりすぎないよう注意も必要です。
採用KPIにより、採用活動の可視化や費用対効果の向上、関係者の役割明確化など、多くのメリットが生まれます。
自社の採用目標に合わせて適切なKPIを設定し、戦略的な採用活動を実践していきましょう。