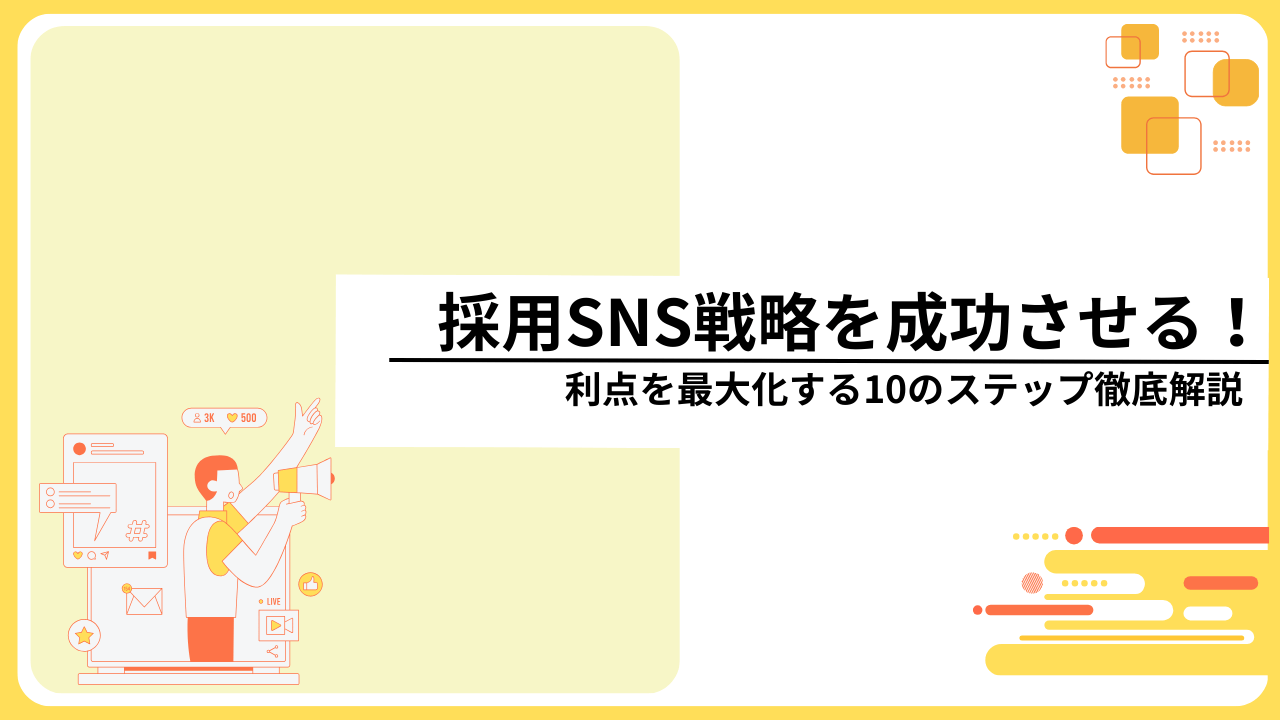「採用にSNSを活用したいけど、どうSNSを使えばいいかわからない…」
「具体的に何から始めればいいの?」
こういった疑問をお持ちの人事担当者様向けの記事です。
この記事でわかること
- SNS採用のメリットとデメリット
- SNS採用と相性が良い企業や業界
- 人材を採用するSNS戦略10ステップ
採用活動にSNSを取り入れる企業が増えています。
求人サイトやエージェントに比べてコストが安く、採用の成果に繋がりやすいためです。
「でも、SNSで人材を採用できるイメージができない…」と思いますよね?
この記事では、SNS採用を始めるステップや、貴社と相性が良いSNSも解説しています。
社内稟議を通すコツもわかるので、人材採用の目標を達成したい人事担当者様は最後まで読んでみてください。
SNS採用が難しそうなら…
「うちの会社ではSNSはムリかなぁ…」という場合は、ダイレクトリクルーティングを検討してみてください。
低コストで貴社に必要な人材に直接アプローチできます。
ダイレクトリクルーティングは、私たちが提供する「HELLOBOSS」がおすすめです。
無料から始められて、有料でも月額4,000円から利用できます。
コストを抑えて人材を採用したい場合は、まずは無料で試してみてください。
Contents
そもそもSNS採用とは
SNS採用はInstagramやXなどを活かして人材獲得を進める仕組みです。従来の求人媒体に頼らず、企業が主体的に情報発信して母集団を増やせます。
例
職場の雰囲気を動画で届けるとイメージしやすいです。また、採用したいターゲットに役立つノウハウを配信すると興味を持ってもらえます。
直接メッセージのやり取りもできるため求職者の疑問を素早く解消できます。結果としてコミュニケーションが深まり、新卒や若年層への認知が高まりやすいでしょう。
SNS採用は双方向のつながりを重視するため、企業と候補者が近い距離で情報を交換しやすいです。コストを抑えながらスピード感を保てる点がメリットです。
SNS採用が注目されている理由
SNS採用が勢いを増している背景には、若年層の利用率の高さがあります。総務省の令和3年の「情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」によれば、若年層のSNS利用時間が多いとわかります。
出典:総務省|令和3年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書
例えば、新卒生が企業の評判を調べる際にInstagramやXを活用し、リアルな内容を把握して応募を検討するケースが多いです。企業側としても広告費を抑えつつ、ターゲットとなるユーザーへダイレクトに発信しやすい点が評価されています。
こうした背景から、SNSを活かす採用手法が注目されています。
求人サイトやエージェントとの違い
求人サイトやエージェントは幅広い応募を集めやすいですが、基本的に受け身の手段です。
一方、SNS採用は企業が能動的に情報を発信し、ターゲットへ直接アプローチしやすい点が特徴です。さらに候補者とのやり取りで雰囲気を伝えやすく、信頼関係も築きやすいでしょう。
求人サイト・エージェント・SNS採用のメリットとデメリットは、以下のとおりです。
SNS採用では候補者との距離が縮まりやすく、職場の実情を身近に感じてもらいやすいです。求人サイトやエージェントと併用すると、応募の質と量を同時に高められるでしょう。
SNS採用のメリット9選
さらに詳しくSNS採用のメリットを解説していきます。
SNS採用のメリット
- 無料で始められる
- 簡単に情報発信できる
- 情報の拡散性が高い
- 転職潜在層と繋がれる
- 企業イメージを向上できる
- タレントプールを形成できる
- 候補者とコミュニケーションできる
- 特定の属性に向けてアプローチできる
- 採用時のミスマッチを減らせる
1つずつメリットを解説していくので、導入を検討してみてください。
無料で始められる
SNS採用は初期費用がかかりません。
例
X(旧Twitter)やInstagramでアカウントを運用するだけなら出費はゼロです。さらに広告を出稿する場合も少額から始められます。
以下は代表的なSNSに広告を出稿する場合の最低金額です。
| プラットフォーム | 最低出稿費用 |
|---|---|
| X(旧Twitter) | 1円〜 ※X Blue(月額8ドル)への加入や、認証済み組織(Verified Organizations、月額1000ドル)への登録が必要 |
| 100円〜 | |
| 約100円〜 |
費用を抑えながら広告を出せるため、短期間のテストで様子を見ながら調整しやすいでしょう。自社がターゲットとしている層へターゲティングを細かく設定すれば、無駄なコストを減らせます。
簡単に情報発信できる
SNSは短文や写真で気軽に投稿できるのが強みです。難しいシステムを使わなくても、スマートフォンやパソコンで手軽に文章や画像をアップできます。
メリット
余計なデザイン費用が不要なため、スピーディーに応募者へ届くでしょう。投稿内容が固くなる必要もないので、職場の雰囲気や日常の出来事をリアルに伝えやすいです。
以下はX・Instagram・Facebookの作業時間の目安です。
| プラットフォーム | 投稿作成の目安時間 |
|---|---|
| X(旧Twitter) | 3〜30分 |
| 10〜60分 | |
| 5〜30分 |
上表はあくまでも目安ですが、テキストや写真でシンプルな情報を発信するだけなら数分で済みます。突発的なニュースや新プロジェクトの告知も短時間で終わるため、運用のハードルが低いでしょう。
情報の拡散性が高い
SNSにはリポストやシェア機能があり、興味を持ったユーザーが企業の投稿を広げてくれる場合があります。多くの人の目に触れれば母集団を増やしやすく、予期しない層にも企業の存在を認知してもらえるでしょう。
例
採用したいターゲット層に役立つ仕事のノウハウを投稿すると、思わぬ形でバズが起きる可能性もあります。
個人のつながりを軸に拡散が進むため、信頼度や親近感が高まりやすい点もメリットです。特にTwitter(X)やFacebookでインパクトのある投稿が注目されると、1日で何万人ものユーザーにリーチするケースもあります。
一度話題になれば公式サイトや採用ページへの流入が増え、応募の機会を一気に広げられるでしょう。
転職潜在層と繋がれる
SNS採用には「今すぐ転職するわけではないが、面白い会社があれば考えたい」という層へもアプローチしやすいです。求人サイトは明確な転職希望者が集まりやすい一方、SNSは普段から使っている人が多いため、関心が薄い状態の人にも情報が届きます。
例
YouTubeでターゲット層に役立つ知識や社内の様子を伝えると、転職を考えていなかった人が「この会社に興味がある…」と意識を変えるきっかけになります。
気軽にフォローしてもらい、そのままコミュニケーションを続けられるのもSNSのメリットでしょう。時期を問わず接点を持ち続ければ、いざ転職を考える段階で有力な候補者になってもらうチャンスが高まります。
企業イメージを向上できる
SNSを通じて、会社の魅力や独自の活動を定期的に発信すると、対外的な印象が良くなります。リクルート目的だけでなく、ブランド全般の向上につながる点が特徴です。
普段の社内風景や社員の実体験を写真付きで紹介したり、達成したプロジェクトをライブ配信で報告したりするのも有効です。
| 発信内容の例 | 取り入れるポイント |
|---|---|
| ターゲット層に役立つノウハウ | ハック術などを視覚的に伝える |
| 社員の1日ルーティン | 具体的なスケジュールと感想を記載 |
| オフィス紹介動画 | 社内設備や働く雰囲気を分かりやすく見せる |
| 成功事例インタビュー | チームが苦労した点や成長した部分を話す |
| 新プロダクトの舞台裏 | 開発や改善プロセスを共有し、親しみを感じさせる |
こうしたコンテンツを発信すると、外部からは「独自のノウハウがある」「社員が活き活きとしている」という印象を持たれやすいです。ポジティブな評価が積み重なると、応募者だけでなく取引先や顧客に対するイメージアップにもつながります。
企業の透明感を高め、信頼を得ながら採用活動を進められるでしょう。
タレントプールを形成できる
SNSを活かせば、長期的に有望人材と繋がり続けられます。
例
ITエンジニア向けに「最新の言語やスキルを学ぶ無料セミナー」をライブ配信すると、多くのエンジニアが興味を持つでしょう。解説だけでなく、リアルタイムで質問を受け付ければ、視聴者との交流が深まります。
さらに「もっと詳しい情報をLINE登録で案内します」という案内を挟み、簡単なQRコードを提示すれば、関心を持った人が気軽に登録しやすいです。LINEから継続的に企業情報や研修イベントの案内を送り、理解を深めてもらうと良いでしょう。
さらに
親和性が高まった段階で、オフラインの勉強会やワークショップに招待すると、双方向のコミュニケーションが生まれます。実際に顔を合わせると、配信だけではわからなかった雰囲気や企業文化を感じ取ってもらえるでしょう。
こうした場が増えれば、候補者は「一緒に働いてみたい」と思いやすくなります。SNSで情報発信を続けて、LINE登録やオフラインでの交流へ繋げる流れはタレントプールづくりに役立ちます。
いざ人材を採用したい段階になった際、こうした候補者群に直接声をかければ、ネット越しのやり取りより深い関係値を築いた状態で採用を進められるでしょう。
候補者とコミュニケーションできる
SNSを通じて有益な情報を発信すると、ターゲットから自然に声がかかりやすいです。特に営業人材を探しているなら、営業ノウハウをわかりやすくまとめた投稿を続けてみましょう。反応が集まれば、そこからコミュニケーションがスタートします。
以下はSNSから応募に繋がる流れの例です。
①ターゲットに有益な投稿
- 営業職向けのノウハウを連載形式で紹介
- 商談の質を上げるコツ・顧客に響くトーク例など具体的な内容
- 参考になりました・勉強になりましたなどのコメントがつく
②コメントからDMへ発展
- コメント欄に「詳しく知りたい」と書かれたらDMで詳細を伝える
- やり取りを続けるうちに相手の志向や希望が見えてくる
- 相手が警戒心を抱かないために、最初は丁寧に情報を返す
③企業への関心が高まる
- ノウハウを提供した企業として好意を持ってもらいやすい
- 「どんな職場?」「働くイメージは?」など相談に繋がる
- マッチしそうと感じれば、カジュアル面談を提案する
このように、まずは有益な投稿でターゲットを惹きつけ、その後、自然な流れでDMや個別相談に進むのがコツです。すぐに採用へ直結しなくても、関係性を築いておけば将来的に面接へ進む可能性も高まります。
特定の属性に向けてアプローチできる
SNSを通じて採用を検討する際は、狙いたいターゲット層に対する発信や広告配信を工夫しやすいです。
上の表のような施策を組み合わせると、自社がほしい人材に対して無駄なく誘導しやすいでしょう。年齢や居住地域、興味分野を細かく設定して広告を流し、興味を示したユーザーへダイレクトメールで声をかける流れも有効です。
特定属性にフォーカスした情報発信や広告配信に取り組むと、採用効率が上がります。
採用時のミスマッチを減らせる
SNSは企業も候補者も双方が普段の様子を発信するため、求人票や履歴書だけでは見えにくい面を補い合いやすいです。
例
候補者がイベント参加レポートを投稿しているなら、行動力や人との関わり方が読み取れます。
企業側もオフィス紹介や社員の実体験を載せておけば、応募者は職場の実像をイメージしやすいでしょう。
面接だけでは伝わらない互いの価値観を日常レベルで知ることで、ミスマッチを防ぎやすくなります。SNS発信を通じて相互理解を深めたうえで接触すれば、入社後の定着率も高まるでしょう。
SNS採用のデメリット4選
一方、SNS採用には以下のようなデメリットもあります。
SNS採用のデメリット
- 採用まで時間がかかる
- 運用の手間がかかる
- 高品質なコンテンツを継続的に発信する必要がある
- 炎上リスクがある
デメリットも理解した上で、SNS採用を検討してみてください。こちらも1つずつ解説していきます。
採用まで時間がかかる
採用SNSの成果が形になるまでには、6〜12ヶ月ほどかかるケースが多いです。拡散性がある一方、フォロワー数や認知度の向上には積み重ねが必要になるため、すぐに応募が増えるわけではありません。
例
新卒向けであれば学年初期から情報を投げかけておき、興味を持つ層をゆっくり育てるイメージです。
スタート時はフォロワーが少なく、反応も薄く感じるかもしれませんが、焦って手を引くと成果にはつながりにくいです。長期目線でコツコツ継続し、必要に応じて広告活用やオフラインのイベントなどを併せて実施する姿勢が求められます。
運用の手間がかかる
採用向けにSNSを活用する際は、投稿作成から応対まで幅広い作業が発生します。タイムリーな更新を怠るとフォロワーの興味が下がりやすいため、ある程度まとまった運用工数が必要です。
以下はX(旧Twitter)・Instagram・YouTubeで投稿する際の工程と、時間の目安です。
SNSごとに求められるタスクや作業量が異なります。もちろん、上記より時間がかかるケースもあるでしょう。
企業規模や採用ニーズに合わせて担当を複数人に振り分けたり、投稿スケジュールを管理ツールで可視化したりするなど工夫が必要です。
高品質なコンテンツを継続的に発信する必要がある
定期更新を意識するあまり「とにかく投稿数を増やす」という方向に偏ると、投稿の品質が低下して候補者が離れてしまいます。
悪い例
社員が立ち寄ったカフェや社内ランチの紹介ばかりを続けると、仕事の実態を知りたいユーザーに飽きられやすいです。
特に、専門人材を集めたいなら、候補者に役立つ情報や具体的な事例を入れないとフォロワーが興味を失います。「単なる社内日記」に終わらないよう、投稿カレンダーや企画会議を設けて内容を検討しましょう。
質を保ちつつ更新し続けるには手間がかかりますが、ターゲットが求める話題と企業の魅力を両立させる工夫が必要です。
炎上リスクがある
SNSは拡散力が高いため、一度炎上すると企業イメージに大きく響きます。文章や画像の中に誤解を招く表現が含まれた場合、不特定多数のユーザーから批判が集まりやすいです。
例
意図せず差別的な発言や、関係者の個人情報が映り込んだ写真を投稿すると炎上する可能性があります。
万が一の騒動に備えて、ダブルチェックの体制や投稿ガイドラインを設けましょう。また、ネガティブなコメントがついた際の対応スピードや、誠実な姿勢も必要です。反響を狙うあまり過激な発信に走ると逆効果のため、常にネットリテラシーを考えながら運用しなければなりません。
SNS採用が難しそうならダイレクトリクルーティングがおすすめ
「うちの会社ではSNSは難しいかも…」という場合は、ダイレクトリクルーティングを検討してみてください。
低コストで貴社に必要な人材に直接アプローチできます。
おすすめツール
ダイレクトリクルーティングは、私たちが提供する「HELLOBOSS」がおすすめです。
10万人を超えるユーザーの中から、貴社が必要とする人材を探せます。
AIによるマッチングも可能なので、人事担当者様の負担も軽減できます。
候補者と直接チャットできるため、返信率も高く、信頼関係を築きやすいのもメリットです。
月額4,000円〜スカウトメールを送り放題なので、貴社に積極的にアプローチしてみましょう。
無料版から始められるので、テストとして使ってみてください。
わずか3ステップで始められるため、さっそくHELLOBOSSを試してみましょう。
SNS採用と相性が良い企業や業界
SNS採用のメリットとデメリットを紹介してきましたが、それを踏まえて「SNS採用と相性が良い企業や業界」を解説します。
SNS採用と相性が良い企業や業界
- 中小企業やベンチャー企業
- IT企業
- クリエイティブ
- サービス業
当てはまっている場合は、SNSを使った採用戦略を検討してみてください。
中小企業やベンチャー企業
中小企業やベンチャー企業はSNS採用がおすすめです。知名度が低くても、採用したい人材に情報が届く可能性があるためです。
例
代表や社員が登壇したイベントの話を写真付きで共有したり、製品開発の裏話をまとめる投稿を作ると効果が期待できます。オフィスツアー動画を載せて「少人数だからこそ意見が通りやすい」雰囲気を伝える手段もおすすめです。
当然ながら、候補者に役立つ仕事のノウハウも投稿しましょう。
気軽にコメントをもらえるようにすれば、興味をもつユーザーと直接やりとりを進められます。候補者と信頼関係を作っていくことで、応募に繋がる可能性が高まります。
IT企業
IT業界はSNS利用率が高く、最新技術や開発事例の共有を好む層が多いです。エンジニアが挑戦中のプロジェクト進捗を説明したり、新しいプログラミング言語を導入してみた感想を発信する流れが向いています。
ポイント
社内勉強会の内容をハッシュタグを活用してシェアしておくと、同じ興味をもつユーザーと繋がりやすいです。
IT企業と相性が良いSNSは以下のとおりです。
| SNS | 特徴 |
|---|---|
| X(旧Twitter) | 短文で技術情報を流しやすい。開発者コミュニティと手軽に接点をもてる。 |
| 経歴やスキルを確認しながら、ピンポイントでスカウトしやすい。 | |
| YouTube | エンジニアの作業画面やコードレビューの様子を動画で見せると興味を持たれやすい。 |
クリエイティブ
以下のような職種を採用したい場合は、作品や制作過程を見てもらうSNS投稿が有効です。
SNSと相性が良いクリエイティブ職
- Webデザイナー
- グラフィックデザイナー
- イラストレーター
- UI/UXデザイナー
- 映像クリエイター
写真や動画を活かして実際の制作フローや作品のビフォー・アフターを投稿すると、クリエイター志望のユーザーが興味を抱きやすいです。作りかけの段階や完成までの工夫を具体的に記録し、他の人が学びを得られる形でシェアする流れが良いでしょう。
クリエイティブ採用では、以下のSNSがおすすめです。
| SNS | 特徴 |
|---|---|
| ビジュアル重視で作品のテイストをダイレクトに伝えやすい。 | |
| YouTube | 制作工程の動画をアップし、工程の解説を含めて発信しやすい。 |
| 作品のアイデア集やムードボードを作り、関連するユーザーと繋がる機会が広がる。 |
サービス業
以下のようなサービス業の職種は、SNS採用と相性が良いです。
SNS採用と相性が良いサービス業
- 飲食店スタッフ
- ホテルや旅館スタッフ
- 小売・接客スタッフ
- ウェディングプランナー
- カスタマーサポート
例えば、明るい接客の様子を写真や動画にまとめると、働く場所の楽しさが伝わります。飲食店なら新メニュー試作の裏側やスタッフの研修風景を発信すると良いでしょう。ホテルスタッフなら館内ツアー動画や季節イベントの案内を載せると効果的です。
サービス業と相性が良いSNSは以下のとおりです。
| SNS | 特徴 |
|---|---|
| 写真重視で店舗や料理の魅力を視覚的に紹介しやすい。 | |
| TikTok | 短尺動画で接客の一場面や面白い日常を、ライブ感をもって共有できる。 |
| 地域イベントやキャンペーン情報を落ち着いた雰囲気で届けやすい。 |
SNS採用が合わなそうならダイレクトリクルーティングがおすすめ
「うちの会社はSNS採用が合わなそう…」という場合は、ダイレクトリクルーティングも検討してみてください。低コストで貴社に必要な人材に直接アプローチできます。
おすすめツール
くりかえしですが、ダイレクトリクルーティングは、私たちが提供する「HELLOBOSS」がおすすめです。
10万人を超えるユーザーの中から、貴社が必要とする人材を探せます。
無料から始められるので、テストとして使ってみてください。
わずか3ステップで始められるため、さっそくHELLOBOSSを試してみましょう。
人材を採用するSNS戦略10ステップ
ここからは、実際にSNS採用を進めていく手順を解説していきます。
SNS採用の10ステップ
- 採用コンセプトを決める
- SNS採用がうまくいっている競合他社を分析する
- 採用ペルソナを設定する
- SNSを選定する
- 人材採用までのフローを設計する
- KGIとKPIを決める
- コンテンツ作成のマニュアルを整備する
- アカウントを設計する
- コンテンツを作成して投稿する
- PDCAサイクルを回す
ステップに沿って準備を始めてみてください。
採用コンセプトを決める
最初に決めたいのは、どのような方向性で人材を迎え入れたいかを示す採用コンセプトです。
例
自社のビジョンと絡めて「グローバル視点で新市場に挑戦する組織づくり」や「地域に根差した商品開発で共感を得たい」などのコンセプトを考えてみましょう。
この指針があると、投稿内容に一貫性を持たせやすいです。以下のようにコンセプトに合わせた投稿の具体例をイメージしてみてください。この段階では、ざっくりとしたイメージでもOKです。
| 採用コンセプトの例 | SNSで発信する内容の具体例 |
|---|---|
| 世界に通じる製品を作る組織に | ・海外展示会のレポート ・英語コミュニケーションの取り組み |
| 地域特化の優しいサービスを提供 | ・地元イベントの様子 ・利用者の声とコラボした企画 |
| 社員が楽しみながら成長する | ・勉強会やワークショップの写真 ・社内挑戦制度の実例とインタビュー |
| スキルの高いエンジニアを採用 | ・プログラミングノウハウ ・AIを使ったシステム開発の方法 |
それぞれの投稿がバラバラな印象にならないよう、最初にコンセプトを定めてから運用に入る流れが望ましいです。
SNS採用がうまくいっている競合他社を分析する
SNSで成果を出している競合他社が、どんな投稿をしているかリサーチしましょう。オリジナルの発信を手探りで始めると伸びないリスクがあるためです。
例
競合のIT企業が最新技術のレポートを発信して伸びているなら、自社の領域で最新技術のレポートを発信していきましょう。
伸びている投稿を参考にして、独自のコンテンツを作っていくと伸びやすいです。競合他社の投稿で数字が良いものをスプレッドシートにまとめておき、アレンジするのがコツです。
採用ペルソナを設定する
採用したい具体的な人材像を「採用ペルソナ」といいます。採用ペルソナを決め、その人物像に刺さりやすい投稿を考えると、配信内容がぶれにくく数字も伸びやすいです。
採用ペルソナは以下の流れで設定すればOKです。
採用ペルソナを設定する流れ
- 採用したい人材像を社長や現場に聞く
- 人材を採用する目的を定義する
- 採用したい人材像を書き出す
- 採用市場に合わせたペルソナにする
- ペルソナを経営層や現場のメンバーに確認してもらう
詳細な採用ペルソナの設定方法は、採用ペルソナの作り方完全ガイド|テンプレートと7ステップのフレームワークにまとめています。
SNSを選定する
SNSは多く存在します。目的やペルソナに合ったSNSを選ぶには、それぞれの特徴を見比べながら判断しましょう。以下は代表的な8つのSNSと、どんな企業に向いているかをまとめた例です。
| SNS | 向いている企業の特徴 |
|---|---|
| X(旧Twitter) | ・学習意欲の高い人材を採用したい企業 ・ITエンジニアや若年層を採用したい企業 ・短文でこまめに情報発信したい企業 |
| ・魅力的な有形商品がある企業 ・社内環境を紹介したい企業 ・若い人材を採用したい企業 | |
| ・30代以上のビジネス層を狙う企業 ・コミュニティ重視で顧客やOBを巻き込みたい企業 ・海外にも発信したい企業 | |
| LINE | ・直接的な通知やリマインドが必要な企業 ・内定者フォローを強化したい企業 ・閉じた環境でコミュニティを育てたい企業 |
| YouTube | ・動画で仕事現場を紹介したい企業 ・社員インタビューや技術解説を視覚的に伝えたい企業 ・長尺コンテンツを発信できる体制がある企業 |
| TikTok | ・若いユーザー層にアピールしたい企業 ・カジュアルな雰囲気を打ち出したい企業 ・短尺動画を定期的に作れる企業 |
| ・専門人材や中途採用をターゲットにする企業 ・海外展開を見据えている企業 ・職歴重視の採用戦略を考えている企業 | |
| Wantedly | ・スタートアップやベンチャー企業 ・共感やカルチャーフィット重視で採用したい企業 ・ブログやストーリー形式で魅力を伝えたい企業 |
それぞれのSNSにはユーザー層や表現方法に特徴があり、発信方法を変えるだけで反応が変わります。まず1〜2つに絞り、ターゲットに合わせた情報を集中的にアップしていくと成果につながりやすいです。
人材採用までのフローを設計する
SNSで広く投稿するだけでは応募に繋がらないこともあります。フォロワーに興味を深めてもらうため、一連の採用フローを具体的にイメージしておきましょう。
具体例は以下のとおりです。
段階ごとにどう情報を渡すか、どのような反応を期待するかを整理し、SNSだけに限らない接点をデザインすると応募率が高まります。特設ページや説明会の告知を兼ねた投稿を混ぜると候補者をスムーズに誘導できます。
KGIとKPIを決める
ゴールを明確にして成果を評価しやすくするために、KGI(Key Goal Indicator)とKPI(Key Performance Indicator)を設定します。KGIは最終的に目指す大きな目標、KPIはそれを達成するための中間指標です。
KPIを設定する手順は以下のとおりです。
KPIを設定する手順
- KGIを設定する
- 採用チャネルの選考フローを決める
- 歩留まり率を調べる
- KGIから逆算してKPIを設定する
- KPIをまとめて共有する
これらを踏まえると、SNS運用がブレずに進み、必要なタイミングで改善を図りやすいです。採用KPIの設定方法は、採用KPIを設定する5ステップ|4つの運用のコツと注意点も解説にまとめています。
コンテンツ作成のマニュアルを整備する
社内で誰が投稿してもある程度の品質を保てるように、統一されたマニュアルを用意しましょう。トーン&マナーや投稿頻度がばらばらだと、フォロワー側は混乱する場合があります。
ポイント
社内リソースの割り当てを明確にして、炎上した場合のガイドラインも記載すると安心です。
日々の運用担当者が簡単に参照できる形にしておくと、スムーズな更新が可能です。
| 項目 | 内容の例 |
|---|---|
| 投稿頻度 | 週3回更新を目標 火・木・土の朝10時に予約投稿 |
| テーマ | 技術研修レポート、求人説明、社員のインタビューなど、複数パターンをローテーション |
| 炎上対策ガイドライン | 投稿チェック担当を2名設定 誹謗中傷コメントの確認と素早い対応策 謝罪文テンプレートなど |
| 社内リソース割り当て | 採用担当:企画とコメント返信 広報担当:デザインや画像作成 エンジニア:技術面ネタの原稿 |
| 運用担当者 | 媒体ごとのリーダーを1名設定 週1回の進捗ミーティングでステータス共有 |
運用初期からルールを固めるとトラブルを防ぎやすくなり、投稿内容の質も維持できます。
アカウントを設計する
SNSアカウントの印象は、候補者が最初に目にする入り口です。競合他社でSNS採用がうまくいっているアカウントを参考にしながら、自社の強みを打ち出す設計が望ましいです。
ヘッダー画像で企業のキャッチフレーズを大きく表示すると、候補者が流し見した際にも興味を持ちやすいです。デザイナーに依頼して、ブランドイメージと統一感を持たせるとクオリティが上がります。
プロフィール文には、ヘッダー画像からさらに詳細に踏み込んだ情報を書き足す形をとると「この企業は何が得意か」を即座に理解してもらえるでしょう。
| 要素 | ポイント |
|---|---|
| 競合他社の参考例 | フォロワー数やエンゲージメントが多いアカウントを見て、投稿頻度や画像の使い方を調査する。 |
| 自社の強み | 「AI開発ノウハウ」「多言語サービス」など、企業が誇れる要素を見極め、大きな文字で発信する。 |
| ヘッダー画像 | 魅力を短いフレーズで訴求。フォントや色合いをデザイナーに任せて、読みやすく引きつけるデザインに。 |
| プロフィール文 | ヘッダー画像を見て興味を持った候補者が、次に知りたい追加情報を書く。社風や実績を端的に伝える。 |
参考までに、X(旧Twitter)のヘッダー画像とプロフィール文の例を掲載するので、参考にしてみてください。
X(旧Twitter)のプロフィール文の例文
AIで社会を変えるITベンチャー!自社開発100%!週3リモートOK。育成重視のエンジニア文化。創造力と挑戦意欲ある仲間募集中です!
コンテンツを作成して投稿する
運用を始める際は、コンテンツをゼロから考えるより、採用SNSで成功している競合他社の伸びている投稿をスプレッドシートにまとめるのが有効です。すでに伸びている型を発見し、自社の内容にアレンジして発信すると最初からある程度の反応を期待しやすいです。
ポイント
ネタが尽きたらAIにサポートしてもらう方法もあります。例えば「こんなテーマで、面白い投稿案を考えてほしい」と投げると、想定外のアイデアが得られるでしょう。
コンテンツ制作のコツをまとめると以下のとおりです。
| 方法 | 内容の例 |
|---|---|
| 競合他社で伸びている型をスプレッドシートにまとめる | 技術系、社員インタビュー、Q&A形式など |
| 自社内容にアレンジする | 同じ型を自社のカラーで再構築する |
| AIでネタを出す | ChatGPTなどで「ITエンジニアが興味を持つネタを考えてほしい」などのプロンプトを入力 |
AIプロンプトの例文
あなたはSNS採用とITの専門家です。ITエンジニア志望向けのSNS投稿アイデアを30個教えてください。そして、そのアイデアを140文字のX投稿用の文章にしてください。
企画した内容を定期的に投稿して候補者の反応を計測すると、響くテーマが絞れます。
PDCAサイクルを回す
SNS採用を始めたら、PDCAサイクルを回してブラッシュアップしていきます。1度投稿したら反応を見ながら修正し、次に活かす形を模索します。
具体的には、以下のような項目でPDCAサイクルを回すと良いでしょう。
| 項目 | チェック例 |
|---|---|
| 投稿のエンゲージメント | インプレッション、いいね、コメント数、クリック数、シェアなどが増えているか |
| ターゲット属性 | 想定していた年齢や職種のユーザーに届いているか フォロワーの属性とマッチしているか |
| KPIとの比較 | 「毎月の応募数」「面接参加率」など設定していた数値に近づいているか |
| タイミングの調整 | 投稿時間帯や曜日を変えたときの反応の差 |
| フィードバック | フォロワーや候補者からの意見 質問や要望のコメントが増えていないか |
企画した内容を定期的に投稿して候補者の反応を計測すると、響くテーマが絞れます。
このようにチェックする要素を明確にしておくと、改良点を見失いにくくなります。良い結果が出たら続け、反応が低い内容は変えると、SNS運用が洗練されていき、採用もスムーズに進むでしょう。
人材採用に活かせる8つのSNS|メリット・デメリットも紹介
SNSを選ぶ際は、狙いたい層や企業のイメージに合っているかが重要です。代表的な8つのSNSのメリットとデメリットは以下のとおりです。
さらに、それぞれのSNSの特徴を詳しく解説していくので、どのSNSを始めるか参考にしてみてください。
X(旧Twitter)|拡散性が高い
| 特徴 | 短文中心で拡散性が高いリアルタイムSNS。ハッシュタグやリポストで情報が広がりやすい。 |
| メリット | 素早く注目を集められ、若年層へのリーチがしやすい。話題化する投稿でフォロワーが急増する可能性がある。 |
| デメリット | 投稿が流れやすく、炎上リスクが高い。こまめな更新が必要。 |
| 相性が良い業種 | IT系やエンタメ関連、ベンチャー企業。若年層をターゲットに広い認知度を狙いたい場合に最適。 |
| 伸ばすコツ | 候補者に有益なノウハウを発信する。短く興味を引く文章に画像や短動画を添える。 |
| 1投稿にかかる時間の目安 | 3〜30分(テーマ決めやハッシュタグ選定を含む。短文なので作成しやすい) |
Xはリアルタイム性が魅力ですが、投稿の寿命が短いため定期的な投稿が求められます。候補者に有益なコンテンツ作成と、コメント対応が活発にできる体制を作るとフォロワーとの距離が縮まり、採用ページや募集情報への誘導に繋がりやすいです。
Instagram|ビジュアル向け
| 特徴 | 写真や短動画を活用するビジュアル中心のSNS。世界観を演出したり若年層をひきつけやすい。 |
| メリット | オフィスや社員の雰囲気を直感的に伝えられ、商品やサービスをビジュアルでPRしやすい。 |
| デメリット | 写真や動画の撮影・編集に手間がかかりがち。拡散力はXほど高くない。 |
| 相性が良い業種 | 飲食、アパレル、デザインやクリエイティブ関連など見た目が重要な職種やブランディング重視の企業。 |
| 伸ばすコツ | フィード全体の統一感を意識。リールやストーリーズで動きのある投稿を増やし、ハッシュタグを丁寧に選ぶ。 |
| 1投稿にかかる時間の目安 | 10〜60分(写真の選定や簡単な加工、キャプション作成、ハッシュタグ付けを含む) |
Instagramは自社のビジュアル面を発信したい場合に効果的です。例えばオフィス紹介や社員の一日を写真や動画でまとめると、働く現場をイメージしやすいでしょう。
統一感のある色使いやレイアウトに注意しつつ、見栄えを意識した投稿が効果的です。また、候補者の職種に役立つノウハウをスライド形式で投稿するとフォローされやすいです。
Facebook|ビジネスマン向け
| 特徴 | 実名登録制でビジネス利用者が多いSNS。長文投稿やイベントページなど多機能。 |
| メリット | 30代以上を中心に実名で利用している層が多く、信頼度や落ち着いた雰囲気をアピールしやすい。 |
| デメリット | 若年層への浸透度が低く、拡散性もXに劣る。フォロワーを増やすのに時間がかかりやすい。 |
| 相性が良い業種 | BtoB企業、地方企業、中途採用メインの会社。実名制で誠実さを大切にする企業とも相性が良い。 |
| 伸ばすコツ | イベントページを使い企業説明会を告知、コミュニティ機能でファンを育成。広告ターゲティングも活用。 |
| 1投稿にかかる時間の目安 | 5〜30分(文章量が多めになりがちだが、急ぎで写真添付なら短時間で済む) |
Facebookは落ち着いた企業アピールが可能です。中途採用やスキル重視の人材に向けて、長文で業務内容や働くやりがいを具体的に伝えると効果的でしょう。
また、ターゲットに有益な仕事のノウハウを発信するのもおすすめです。
LINE|フォロー向け
| 特徴 | 多くの人が日常的に使うメッセージアプリ型SNS。1対1や公式アカウント発信向き。 |
| メリット | 閲覧率が高く、友だち追加してもらえれば確実に情報を届けられる。内定者フォローや案内に有効。 |
| デメリット | 友だち登録が必須で、初期誘導が必要。拡散力は低くブロックされることがある。 |
| 相性が良い業種 | 幅広い業種、特に内定者フォローや継続コミュニケーションが重要な企業 |
| 伸ばすコツ | プレゼントや説明会で友だち追加を促す。メッセージの送り過ぎに注意し、必要な情報を短く届ける。 |
| 1投稿にかかる時間の目安 | 数分(テキスト中心だが、配信タイミングを考慮し慎重に作成したほうが好印象を得やすい) |
LINEは日程調整や内定者フォローに優れている反面、最初に登録してもらわないと情報を届けられません。SNSやイベントなどで接触した候補者に登録してもらい、フォローアップのチャネルとして使いましょう。
他のSNSで集客した候補者に役立つ有料級のコンテンツをプレゼントする代わりに、LINEに登録してもらう流れを作ると効果的でしょう。
YouTube|非言語のイメージが伝わる
| 特徴 | 動画共有プラットフォームで、長短さまざまな映像を配信。大容量かつ高いブランディング効果。 |
| メリット | 文章だけでは伝えにくい雰囲気を映像で伝える。動的なプロモーションや技術解説に向く。 |
| デメリット | 動画撮影・編集に時間とコストがかかる。更新頻度が低いと視聴者が定着しづらい。 |
| 相性が良い業種 | IT・製造・クリエイティブ・ベンチャーなど、実演や説明動画で魅力的に見せたい企業。 |
| 伸ばすコツ | ノウハウ解説や職場ツアーを撮影。ある程度の台本を作ってから撮影する。 |
| 1投稿にかかる時間の目安 | 数時間〜数日(撮影と編集に時間が必要。企画段階も含めるとさらに長くなる) |
YouTubeは企業の世界観やこだわりを見せられるため、候補者に「入社後のイメージ」をつかんでもらいやすいです。撮影体制と編集スキルを確保できるなら、社員ストーリーや仕事の1日密着動画などを定期的に上げると企業ファンが増えやすいでしょう。
また、候補者の職種に役立つノウハウを解説する動画を投稿すると、チャンネル登録されやすいです。
TikTok|若年層向け
| 特徴 | 15~60秒程度の短尺動画が中心。若年層の利用者が多く、カジュアルでエンタメ色が強い。 |
| メリット | 拡散力が高く、バズれば一気に数万~数十万再生が期待できる。動画を通して企業カルチャーを軽快にアピールできる。 |
| デメリット | 動画撮影・編集の手間が大きい。短尺では内容を伝えきれない場合がある。 |
| 相性が良い業種 | エンタメ色のあるベンチャー、飲食やサービス業などユニークな職場が多い企業、クリエイティブな発想で採用したい会社など。 |
| 伸ばすコツ | 流行の音源やハッシュタグを活用。踊りや寸劇など社員が楽しんでいる様子を出すと拡散されやすい。企画段階から面白さを狙う。 |
| 1投稿にかかる時間の目安 | 数時間(短い動画でも撮影と編集に手間がかかる) |
TikTokを活用する際は「いかに短い時間で視聴者の興味を引くか」が重要です。職場の雰囲気や先輩社員の一日をコメディ調にまとめるなど、Z世代が好むストーリー性や軽快さを打ち出すと拡散が期待しやすくなります。
TikTokで集客して他のSNSやLINE登録に誘導する流れを作ると、候補者リストが増えていくでしょう。
LinkedIn|ビジネス色が強い
| 特徴 | ビジネス特化SNS。職歴や保有スキルを詳細に記載でき、中途人材のプロフィール検索とスカウト機能が充実。 |
| メリット | 実名登録で経歴が明確。専門人材とのマッチング精度が高く、グローバル採用にも対応しやすい。 |
| デメリット | ビジネス色が強いため短期的な拡散は弱め。 |
| 相性が良い業種 | IT・コンサル・エンジニアリング・外資など専門スキル人材の採用に注力したい企業。 |
| 伸ばすコツ | 社長や役員も積極的に投稿し、企業ページでもブログやニュースを充実させる。 |
| 1投稿にかかる時間の目安 | 30~60分(職歴や専門性を絡めた内容をじっくり書けば興味を持たれやすい) |
LinkedInは即戦力を探す中途採用向けの色合いが強く、専門性の高い人材を求めるなら効果が大きいです。企業ページを育成し、コンテンツを定期的に投下すると「どんな実績を持つ会社か」をアピールしながら候補者を引き寄せられます。
このようにチェックする要素を明確にしておくと、改良点を見失いにくくなります。良い結果が出たら続け、反応が低い内容は変えると、SNS運用が洗練されていき、採用もスムーズに進むでしょう。
Wantedly|特徴を書く
| 特徴 | 企業と求職者を「共感」でつなぐ採用プラットフォーム。給与や待遇ではなく企業のカルチャーを重視。 |
| メリット | 求職者のモチベーションが高く、カルチャーフィット重視の採用でマッチング率が高い。求人作成やスカウト機能が充実。 |
| デメリット | 利用者が20~30代のベンチャー志向寄り。 |
| 相性が良い業種 | スタートアップや急成長ベンチャー、中小企業でカルチャー重視の採用を行いたい会社。 |
| 伸ばすコツ | ストーリー投稿や社員インタビューで企業理念を深掘りして伝える。社内イベントや挑戦文化を具体的に示す。 |
| 1投稿にかかる時間の目安 | 30~60分 (写真やストーリー執筆に凝るとさらに時間が延びる) |
Wantedlyは、待遇面では大企業と競合しにくい中小・ベンチャーが自社の魅力を発信し、共感度の高い人材を引きつけるのに有効です。ブログ感覚で企業ストーリーを発信し続けると、候補者が「ここで働きたい」と自然に感じるコミュニティづくりができます。
SNS採用を成功させる8つのコツ
SNS採用を成功させるコツを、さらに詳しく解説していきます。
SNS採用を成功させるコツ
- 主軸を「価値提供」にする
- 社内を巻き込んでコンテンツを作成する
- 継続的に情報を発信する
- 自社の魅力を投稿する
- 初期はSNS広告も併用する
- インプレッションが伸びやすい方を実践する
- 認知拡大と問い合わせ目的でコンテンツを分ける
- SNSで繋がった候補者とオフラインで会える場を設定する
こちらも1つずつ解説していくので、SNS運用の参考にしてみてください。
主軸を「価値提供」にする
自社のPRに終始すると、フォロワーは「宣伝ばかりだ」と感じて離れやすいです。それよりも「候補者に役立つノウハウ」を発信すると、自然に支持されやすくなります。
例
ITエンジニア向けに「最新フレームワークの使いこなし方」をまとめたり、営業職向けに「提案資料づくりのヒント」を公開するとフォロワーが増えやすいです。
転職を考えていない潜在層も「学びになるからフォローしておこう」と思わせる効果が生まれます。会社の強みを直接打ち出すより、まずは価値ある情報をシェアして「信用できる発信源」だと認識してもらいましょう。
社内を巻き込んでコンテンツを作成する
投稿を人事担当者だけで頑張り過ぎるとマンネリ化しやすいです。社内各部署の協力を得ると、現場ならではの取り組みが見えてきて幅広いネタを増やせます。
例
エンジニアからは新技術の研究話、デザイナーからは制作裏話、営業からはトークの実例を集める流れを作ると、多角的に社内のリアルを伝えられます。
インタビュー形式で共通フォーマットを用意し「チームの強みや学んだことは?」といった質問を一定周期で回していくと、定期更新がスムーズです。社内の人たちにSNSの意義を伝え、取材される方にもメリットを感じてもらえれば協力体制が整います。
継続的に情報を発信する
SNSは新着投稿が優先表示されるため、更新頻度が低いと目立ちにくいです。こまめな発信を続ける姿勢がフォロワーとの距離感を縮めます。
コツ
伸びた投稿は、同じ内容で形式を変えて複数回投稿しても問題ありません。過去に反応が良かったネタは需要がある証拠なので、ストックしておき再利用しましょう。
短期集中で一気に投稿して放置するより、月や週ごとの投稿数を決めて定期的に更新した方が、フォロワーと応募数の両面で効果を期待できます。
自社の魅力を投稿する
自社ならではの強みや社風を発信すれば、興味を持ったフォロワーが「この会社で働いてみたい」と考えるきっかけになります。
| 自社の魅力の例 | 詳細 |
|---|---|
| 社員の声 | 社員インタビューやチームで立ち上げたプロジェクトのストーリー |
| 社内行事 | 社内イベント、懇親会、勉強会などの写真やエピソード |
| 日常業務 | 業務風景や実際の仕事の手順、工夫しているポイント |
| オフィス紹介 | 職場のレイアウトや設備、休憩スペースなど雰囲気が伝わる写真 |
| 成果や実績 | サービスローンチや受賞歴など、具体的な成功エピソード |
こうした投稿は、どのような会社かイメージしてもらいやすくなります。活き活きと働く社員の姿や達成感に満ちた表情を見せることで「ここなら楽しめそう」と感じる候補者との距離が縮まります。
初期はSNS広告も併用する
アカウント開設直後はフォロワーが少なく、反応も少ないです。認知を広げるために広告を併用すると、ターゲット層に効率的にリーチできます。
ポイント
X(旧Twitter)やInstagramでは数百円単位でも広告を出稿できるため、小規模でもテストしながら反応を測定しやすいです。
投稿に対するリアクションを見ながら、相性の良いコンテンツを絞り込むのがコツです。母集団形成がある程度進んだ段階で広告予算を下げ、オーガニック投稿の拡散力にシフトしていくと効果的です。
インプレッションが伸びやすい型を実践する
各SNSには伸びやすい型があります。SNS運用を進めながら「伸びた投稿の共通点」を探すと、伸びやすい型が見えてきます。
ちなみに、X(旧Twitter)の「インプレッションが伸びやすい型」の一例は以下のとおりです。
| 型 | 概要 |
|---|---|
| 箇条書きまとめ型 | 「◯◯する方法5選」など数字を入れ、箇条書きで情報を羅列 |
| 疑問提起→回答型 | 「なぜ◯◯が必要?→実は××だから」など、疑問形で興味を引き、次に回答を提示 |
| 共感ストーリー型 | 失敗談や成功談を短い物語調で紹介し、学びを最後にまとめる構成 |
| ランキング紹介型 | 「人気◯◯ベスト3」など、簡潔に順位をつけて賛否を巻き込み拡散を狙う |
インプレッションを伸ばしたいときは、フォロワーの興味を誘うタイトルと、短く区切りやすい情報提供がコツです。相手がパッと理解しやすく、リポストしたくなる要素を意識すると広がりやすいです。
認知拡大と問い合わせ増加でコンテンツを分ける
SNSを運用する際は「認知拡大を狙う投稿」と「問い合わせ増加を狙う投稿」のバランスが重要です。「問い合わせ増加を狙う投稿」が多いとセールス色が強くなってしまい、フォロワーが離脱しやすいです。そのため「認知拡大を狙う投稿」を多くするのがコツです。
割合の例
- 認知拡大を狙う投稿:8~9割
- 問い合わせ増加を狙う投稿:1~2割
例えば、認知拡大向けの投稿としてノウハウ解説を主軸にして、たまに「オンライン説明会はこちら」「中途採用枠を増やしました」などの告知を入れると良いでしょう。「ただの宣伝アカウントではない」と認識され、フォロワー数と募集への興味が両立しやすくなります。
SNSで繋がった候補者とオフラインで会える場を設定する
SNSで興味を持ってくれた候補者とさらに関係性を深めるには、顔を合わせる場を用意すると効果的です。
| オフラインイベントの例 | 概要 |
|---|---|
| 交流会 | 軽い飲食を交えて社員と自由に話せるイベント |
| 勉強会 | エンジニア向けの勉強会 マーケ職向けに分析ワークショップなど |
| 職場見学 | 実際にデスク周りや社内設備を見てもらい、業務風景を想像しやすくする |
上記のようにカジュアルな機会を定期開催すると、候補者と会えるチャンスが広がります。オンライン上だけでは伝わりにくい温度感や社員の雰囲気をオフラインで体験してもらえるため、そのまま応募検討に進むケースもあるでしょう。
SNS採用のリスクヘッジで他の採用チャネルも組み合わせる
「SNS採用がうまくいかなかったらどうしよう…」と不安になる人事担当者様もいると思います。たしかに、SNS運用が100%成功するとは限りません。
そこで、他の採用チャネルを組み合わせて、リスクヘッジしておきましょう。
SNS採用と組み合わせた方が良い採用チャネルを紹介していきます。
ダイレクトリクルーティング
ダイレクトリクルーティングは、企業が求めるスキルや経験を持つ候補者をデータベースで検索し、直接アプローチする手法です。採用担当者が「この人に来てほしい」と思った相手へダイレクトメッセージを送るため、早期に内定まで進む可能性が高いです。
ポイント
SNSを活用して企業の文化を先に伝えたり、候補者の投稿内容から興味関心を事前にリサーチしたりすると、メッセージの精度が上がります。
例えば、X(旧Twitter)上で発信しているエンジニアがいたら、その人が熱中している技術やポートフォリオを確認しながらスカウト文を作成する流れです。応募ハードルを下げるためにSNSアカウントを提示し、企業への親近感を持ってもらえると面談につながりやすくなります。
ダイレクトリクルーティングについては、【徹底比較】ダイレクトリクルーティングのメリット5選|他の手法と何が違う?で詳しく解説しています。
ダイレクトリクルーティングはHELLOBOSSがおすすめ
くりかえしですが、ダイレクトリクルーティングでは私たちが提供する「HELLOBOSS」がおすすめです。
10万人を超えるユーザーの中から、貴社が必要とする人材を探せます。
候補者と直接チャットできるため、返信率も高く、信頼関係を築きやすいのもメリットです。
月額4,000円〜スカウトメールを送り放題なので、貴社に積極的にアプローチしてみましょう。
無料版から始められるので、テストとして使ってみてください。
求人サイト
大手求人サイトに広告を掲載して、母集団を広げる手法です。認知度の高いサービスなら幅広い層からの応募が見込めるので、SNSでは届きにくい年代や地方の候補者にもアピールできます。
SNSとの組み合わせ方
求人サイトで応募を集めつつ、SNSで会社のリアルな様子や社員インタビューを発信し、補足情報を伝えると効果的です。
例えば、求人票からX(旧Twitter)やInstagramのアカウントURLを案内すると、興味をもった人が詳しい情報をSNS経由で知れる流れができます。求人サイトで幅広く集客し、SNSで働くイメージを強化する二段構えがおすすめです。
エージェント
人材エージェント(人材紹介会社)を利用する方法です。人材コンサルタントが候補者を紹介してくれるため、専門人材やハイクラス層の採用でもミスマッチを抑えやすいです。
SNSと併用するメリット
エージェントから紹介された候補者が「どんな会社かイメージしたい」と思ったとき、SNSでオフィスの雰囲気や社員の日常をすぐに確認できます。
面接前にInstagramの社内写真やX(旧Twitter)の投稿を見れば、企業文化がわかりやすいでしょう。エージェント経由で真剣度の高い候補者を得ながら、SNSで「この会社なら働きがいがある」と感じてもらえるよう仕掛けると内定辞退を減らせます。
両者の強みを掛け合わせるとスピード感と認知度向上が同時に狙えます。
リファラル採用
社員が知人や友人を紹介する手法です。現場社員が「この人なら合いそう」と見込んで紹介するため、社風との相性や意欲の高さが期待できます。
SNSの活用方法
友人が転職や就活を考えたときにLINEやX(旧Twitter)で求人情報を手軽に共有できると良いでしょう。
例えば、社内でリファラル採用キャンペーンを始める際、Xの固定ツイートに募集要項を載せておき、社員に拡散してもらうと外部ユーザーの目に留まりやすいです。SNSとセットでリファラル採用を進める環境を整えると、社員が紹介しやすくなるでしょう。
企業の採用活動にSNSを使う際の注意点
SNS採用を実施するときは、2つの注意点があります。
SNS採用の注意点
- 炎上リスクに備えておく
- 応募者のSNSチェックなどコンプライアンス対策を実施する
後でトラブルにならないためにも、事前に注意点を知っておきましょう。
炎上リスクに備えておく
SNSの投稿は拡散が早く、炎上してしまうと企業イメージが損なわれるリスクがあります。社内で「投稿ガイドライン」や「コメント対応ルール」を定め、運用担当者以外が事前にチェックする仕組みを用意しておく流れが望ましいです。
ポイント
特に、不適切表現や誤解を生む文面を回避するために、複数人で最終承認する方法も検討してください。また、ネガティブコメントが付いた際の対応マニュアルを用意し、初動で誠実に返す姿勢を見せると炎上しにくいです。
以下のような項目をテーブル化すると整理が進みます。
| 項目 | 内容の例 |
|---|---|
| 投稿ガイドライン | ・不快に感じそうな表現の禁止、写真に映る個人情報の排除 ・業務上知り得た非公開情報や顧客・取引先の情報、従業員や応募者の個人情報をSNSに投稿しない ・他人の著作物や写真、企業ロゴ等を無断使用しない ・特定の個人・集団や、人種・民族・思想・信条・宗教・政治などに関する蔑視・差別的表現は禁止 |
| コメント対応ルール | 不満や批判の投稿を見つけたら◯時間以内に返信。対応が困難な場合は上司へ相談 |
| 初動対応マニュアル | ネガティブコメントに対してまず感謝や謝罪を述べ、事実関係を確認してから次のアクションへ |
このように事前準備を徹底すれば、万が一炎上しかけても適切な対処が可能です。
応募者のSNSチェックなどコンプライアンス対策を実施する
候補者の裏アカウント(本人が普段使っている非公開アカウント)まで無断で調査する行為は、プライバシーの侵害や差別的扱いのリスクがあります。社内規定として「表向きに公開された投稿のみを対象とし、私生活の批判や宗教・思想差別につながる確認は避ける」と決めておきます。
採用選考でSNSを確認する際は、法的・倫理的な問題が生じないように注意を払い、むやみに裏アカウントを深追いしないようにしましょう。無断で私生活を探り過ぎると、社内外で「社内コンプライアンスが甘い」と見られる恐れもあります。
| 観点 | 留意すべき点 |
|---|---|
| プライバシー保護 | 候補者の人格権や私生活を尊重し、裏アカウントの強制的調査は避ける |
| 企業イメージへの影響 | 応募者のSNSを過度にチェックしている事実が外部に広がると、情報管理意識が低いと見られやすい |
| 法的・倫理的リスク | ・差別につながる発言や思想に基づいた不当な不採用は法令違反の可能性がある ・人事担当者が応募者のSNS投稿をスクリーンショットやメモに残すと、その時点で個人データを収集したことになり、事前に応募者へ「公開情報も含め選考目的で利用する」旨を知らせておく必要あり ・自社の採用プライバシーポリシーにその旨を明記し、応募者から包括的にでも同意を得ておくのが望ましい ・思想信条に関する情報は初めから収集しない |
こうしたコンプライアンス対策を明文化することで、安心して候補者を評価できる体制ができます。
SNS採用の社内稟議を通す9つのコツ
「企業でSNSをやってみたいけど、稟議が通るか不安…」という人事担当者様もいるでしょう。そこで、SNS採用の社内稟議を通すコツも解説していきます。
SNS採用の社内稟議を通すコツ
- 具体的な目的・効果を明確にする
- 経営層が感じるメリットを強調する
- 競合他社の成功事例を提示する
- リスク管理・コスト面の対策を具体化する
- リソースと運用体制を明確にする
- 費用対効果をシミュレーションする
- 導入スケジュール・ロードマップを作成する
- 小規模成功や具体的イメージを提示する
- 社内他部署の協力や巻き込み計画を説明する
こちらも1つずつ解説していくので、稟議を通してSNS運用を始めていきましょう。
具体的な目的・効果を明確にする
SNS採用を始める理由を曖昧にしたままだと、担当者の熱意だけが先行して経営層に響きにくいです。どんな成果を得たいのかを明示して「どのSNSを使って、どんな候補者を集めたいのか」「既存の採用手法との違いは何か」などを伝えると説得力が増します。
さらに具体的な目標があれば社内で協力してもらいやすいです。以下の表を参考に目的と効果を整理し、社内で共有するだけでも話が通じやすくなるでしょう。
このように最初から「何をどこまで目指すのか」を数字や行動レベルで設定しておけば、効果測定もしやすくなります。
経営層が感じるメリットを強調する
稟議を通すには、経営者や上層部が「投資する価値がある」と判断する後押しが必要です。単なる宣伝費ではなく、企業の成長にどう貢献するかを明確にするのがコツです。
以下に経営層が関心を持ちそうなメリット例を挙げます。
このように経営視点での費用対効果やブランディング効果を強調すれば、予算確保やリソース獲得への協力を得やすくなります。
競合他社の成功事例を提示する
競合他社がSNS採用に成功している例を挙げれば「弊社もやるべきだ」という説得力が増します。以下の表のように具体例を示すとわかりやすいです。
事例を見せると、上層部は「自社でも似た方法が可能」とイメージしやすいです。特に数字で示される成果は説得力を高めます。
リスク管理・コスト面の対策を具体化する
SNSは炎上や予算の無駄遣いなどのリスクが伴います。そこで「どんなリスクがあるか」「どう費用を抑えるか」をまとめると、安心してもらえるでしょう。
初期は広告予算の上限を決めておき、定期的なレビューで投資対効果を確認する流れを伝えると納得してもらいやすいです。
リソースと運用体制を明確にする
SNS運用は社内の工数がかかります。誰がどんな役割を担うかをきちんと示すと、社内への負荷を減らせるイメージがつきやすいです。
以下のように分担を可視化するのがコツです。
役割を固めておけば、投稿やコメント対応が属人化せず、休暇時も別メンバーがカバーできる体制になります。継続性を心配する経営層もいるため、こうした見せ方ができると納得してもらいやすいです。
費用対効果をシミュレーションする
経営層は「どのくらいの期間で投資を回収できるのか」を気にします。SNS採用への投資回収の流れを時系列で簡潔に示すと、イメージしやすいです。
「1年後に広告費を一部削減しながらも月5名の内定を狙う」など目標を設定すると、上層部の理解を得やすいです。
導入スケジュール・ロードマップを作成する
経営層が判断しやすいように、SNS導入のロードマップも作りましょう。
具体的には、以下のような資料がおすすめです。
このように段階的に取り組めば、最初から過大な期待を背負わずにPDCAを回すイメージが伝わります。
小規模成功や具体的イメージを提示する
いきなり大予算を投下するのではなく、まずは数ヶ月のテスト運用で「小さな成功」を狙う形を提示すると、上層部の不安が少なくなります。
例
「X(旧Twitter)で月◯本投稿・広告費◯万円から始めて反応を確認する」と明確に決めれば、稟議の段階で具体性を示せます。
以下のように表にまとめると、上層部も投資を渋りにくいでしょう。
段階的に投資して結果を測定し、効果が見えてきたら本格展開へ移行する流れだと納得してもらいやすいです。特に中小企業やベンチャー企業であれば、このようなスモールスタートで検証を重ねながら拡大を狙うと良いでしょう。
社内他部署の協力や巻き込み計画を説明する
SNS採用は人事部単独では情報発信が偏りがちです。技術ネタはエンジニア、広報向け記事はマーケティングなど、他部署で協力するとコンテンツが豊かになります。
どの部署に何を依頼するのかを表にまとめるとわかりやすいでしょう。
このように部署ごとのメリットも提示すれば「協力する意義がある」と理解してもらえます。全社で取り組む空気を醸成することが、SNS採用を成功させるコツです。
採用SNSでよくある質問
最後に、SNSを使った人材採用でよくある質問に答えていきます。
SNS採用は運用代行に外注した方が良い?
運用を代行会社に依頼すれば、専門家がノウハウを持って運用するため短期的に成果へ近づける可能性があります。担当者が足りない場合やSNSに不慣れな場合には頼もしいでしょう。
注意点
内製せずにすべてを任せると、社内でスキルが蓄積しにくいです。今後も継続する施策として考えるなら、少額のコンサル契約から始めてノウハウを学びながら、徐々に自社でも運用を回す形がおすすめです。
特に企業らしさを発信したい場合は、社内メンバーが主体的にアイデアを出す方が良いコンテンツができる可能性があります。外部と協力しつつも、最終的には自社で運用できる体制を作るのが良いでしょう。
SNSを運用できる担当者が1人しかいない場合の注意点は?
担当者が1人だけだと、更新頻度が下がったり不在時の対応ができなかったりするリスクがあります。以下のような点に留意すると、運用が安定しやすいです。
| 対策 | 概要 |
|---|---|
| 運用ルールを明文化 | 投稿の承認フローやコメント対応手順をガイドライン化 |
| コンテンツのネタを社内で集める | 本人の負担を軽減して多彩な情報を発信 |
| 予約投稿を使う | 担当者が休暇でもSNS更新が途絶えない |
| 定期的に社内報告会 | 運用成果を周囲へ共有して協力を得る |
このように担当者が1人で業務を抱え込まない仕組みを整えれば、運用を続けやすくなります。
SNS広告をかけなくても成果は出る?
広告を出さなくても、地道な発信によって一定数の候補者へ情報を届けることは可能です。
ただし、競合が多い領域や早期に成果を得たい場合、広告運用を並行すると認知度を高められます。
ポイント
広告は費用がかかりますが、ターゲット層に確実にリーチできる点が強みです。予算に余裕があれば少額から広告テストを始めて反応をチェックし、成果を出せる流れが望ましいでしょう。
地方企業でもSNSをやるべき?
地方企業にもSNS運用がおすすめです。SNSは地域の発信も有効で「こんな会社が近くにあるのか」と、近隣の候補者の目にとまることもあります。
ポイント
SNS広告は地域を絞って配信できるため、地方の企業でも効果があるでしょう。
また、地元の若者やIターン・Uターンを狙う層に対しては、地元密着のイベント情報や地域の魅力を絡めた発信が好印象です。
採用だけでなく顧客獲得も並行して狙っていい?
1つのSNSアカウントを多目的で使うと、投稿内容がバラバラになりがちです。採用のためにフォローした候補者が急に製品の宣伝を見せられれば「セールス色が強い」と感じて離れる恐れがあります。
ポイント
SNSではターゲットを明確にするほど、フォロワーが定着しやすくなります。顧客も獲得したいなら専用アカウントを作成し、採用アカウントとは分けて運用しましょう。
新卒採用にはどんなSNSとコンテンツが有効?
新卒生をターゲットにするなら、若年層の利用が多いSNSが良いです。以下を参考にしてください。
| 新卒向けのSNS | 具体的なコンテンツ例 |
|---|---|
| X(旧Twitter) | 短文での最新告知、インターン情報、就活ノウハウの投稿 |
| 社内の写真やリール動画 内定者の学校生活と会社見学ストーリー | |
| TikTok | 短尺の自己紹介動画や職場ルーティン 社員の1日をコミカルに編集 |
学生が興味を持ちやすいコンテンツや、キャッチーな投稿を意識すると反応が良いです。
中途採用にはどんなSNSとコンテンツが有効?
経験者や専門職を狙う場合、ビジネス志向の強いSNSが向いています。キャリアアップを視野に入れた層に響く情報を発信すると効果的です。
| 中途採用向けのSNS | 具体的なコンテンツ例 |
|---|---|
| 経営者や社員が書く業界トレンド記事 最新プロジェクトの成果報告 | |
| YouTube | ビジネスノウハウのプレゼン動画 社員インタビューの長尺映像を詳細に紹介 |
| 落ち着いた雰囲気で長文投稿 イベント開催情報や企業の歴史を語る |
このようなSNSでは業務内容の深掘りや、技術的・ビジネス的な成果を丁寧に説明すると応募者の関心が高まりやすいです。また、候補者の仕事に役立つノウハウの発信も効果的です。
中途採用者は即戦力や条件面を重視しがちなので、専門性や職場環境を伝える投稿も良いでしょう。
社員や社長の個人アカウントは運用すべき?
個人アカウントを活用すると、企業公式アカウントとは違う親近感が生まれます。トップや現場社員が普段の仕事ぶりを発信すれば「経営者の考え方」や「生の職場の空気」を感じてもらいやすいでしょう。
注意
ただし、個人アカウントと企業アカウントが意図せず内容を重複させたり、投稿が私的領域と混ざるリスクもあります。
社員がSNSに慣れていない場合は最初にガイドラインを共有し、投稿するテーマを社内で決めておくのがおすすめです。経営者なら会社のビジョンや将来像を発信するだけでも求職者の興味を引きやすく、応募への後押しになります。
まとめ|SNSを使って採用マーケティングを実践しましょう
最後にもう一度、SNS採用のメリットとデメリットをまとめておきます。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 無料で始められる 簡単に情報発信できる 情報の拡散性が高い 転職潜在層と繋がれる 企業イメージを向上できる タレントプールを形成できる 候補者とコミュニケーションできる 特定の属性に向けてアプローチできる 採用時のミスマッチを減らせる | 採用まで時間がかかる 運用の手間がかかる 高品質なコンテンツを継続的に発信する必要がある 炎上リスクがある |
メリットとデメリットを理解した上で、SNS運用を始めていきましょう。
もしSNSの活用が難しい場合は、ダイレクトリクルーティングを検討してみてください。
低コストで貴社に必要な人材に直接アプローチできます。
おすすめツール
ダイレクトリクルーティングは、私たちが提供する「HELLOBOSS」がおすすめです。
10万人を超えるユーザーの中から、貴社が必要とする人材を探せます。
候補者と直接チャットできるため、返信率も高く、信頼関係を築きやすいのもメリットです。
月額4,000円〜スカウトメールを送り放題なので、貴社に積極的にアプローチしてみましょう。
無料版から始められるので、テストとして使ってみてください。
わずか3ステップで始められるため、さっそくHELLOBOSSを試してみましょう。
貴社の採用戦略の参考になれば幸いです。