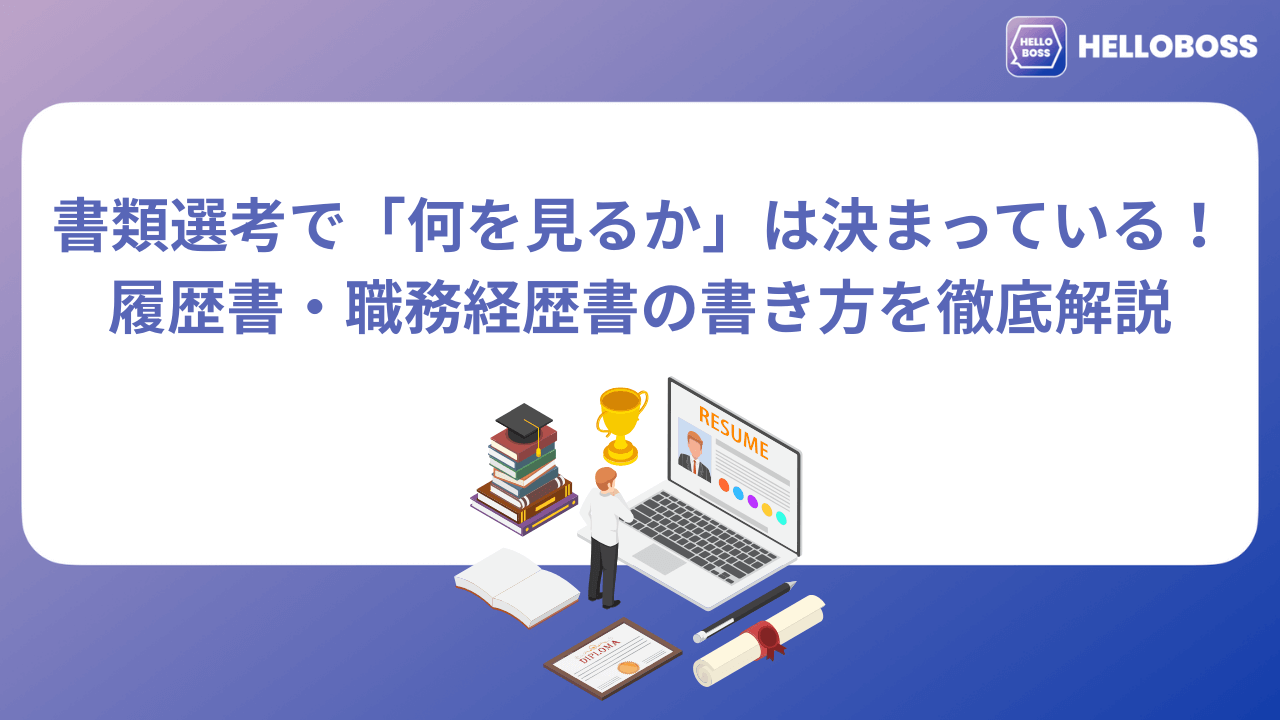「企業は書類選考で何を見るのか知りたい」
「自分の経歴で評価されるポイントが分からない」
「どう書けば熱意が伝わるんだろう…」
こういった疑問に答える記事です。
この記事でわかること
- 書類選考で企業が評価する5つの項目
- 書類選考で落ちる人の特徴と避けるべきNGワード
- 書類選考の通過率を上げるための具体的な5ステップ
書類選考で企業が見るポイントは決まっており、事前に対策すれば通過率を上げることは可能です。
採用担当者は応募者のスキルや経験だけでなく、基本的なビジネスマナーや企業への貢献意欲などを、定められた評価項目に沿ってチェックしています。
この記事では、書類選考で見られるポイント、通過率を上げるための具体的な書き方などについて解説します。
さっそく対策を始めて、次の面接ステップへ進みましょう。
書類だけで判断されない新しい転職活動
「HELLOBOSS」は、従来の書類選考とは異なり、応募前に企業の採用担当者と直接チャットで話せる新しい転職プラットフォームです。
AIがあなたに合った企業を推薦し、書類だけでは伝わらないあなたの熱意や人柄を直接アピールできます。
書類選考に不安を感じている方は、新しい転職の形を体験してみてください。
Contents
書類選考の目的と採用担当が最初に見るポイント
採用担当者は、毎日数多くの応募書類に目を通します。
そのため、書類選考は効率的に、かつ企業の求める人物像と合致するかどうかを見極める目的でおこなわれます。
応募者の基本的な情報を確認し、次のステップに進んでもらうべきかを判断する重要な工程です。
まずは、書類選考がどのような位置づけなのかを正しく把握し、最初の関門を突破する準備を整えましょう。
そもそも書類選考はふるい分けの工程
書類選考は、採用候補者を一定の基準で絞り込むための「ふるい分け」の工程です。
多数の応募者の中から、企業の採用基準に満たない候補者を見極め、面接に進むべき人材を効率よく選別する目的があります。
ポイント
限られた時間の中で判断するため、書類の第一印象が合否を左右します。
この段階では、個々の能力を深く掘り下げるというよりは、基本的な条件を満たしているかを確認します。
例えば、募集職種に必要な資格の有無や、勤務地への適応性などが該当します。
応募者は「選ばれる」だけでなく「落とされない」ための書類作成を意識する必要があります。
採用担当が最初にチェックする3要素
採用担当者が書類選考で最初に確認するのは、以下の3つの要素です。
採用担当者が最初にチェックする3要素
- 応募条件を満たしているか
- 企業への志望度は高いか
- 誤字脱字や明らかな不備はないか
これらの要素は、応募者の基本的なビジネススキルや仕事への姿勢を示す指標です。
基本的な項目で不備があると、内容を読まれずに不採用となる可能性があります。
特に、誤字脱字は注意力が散漫である、あるいは志望度が低いという印象を与えかねません。
提出前には必ず複数回読み返し、完璧な状態で提出するように心がけましょう。
新卒でも転職でも共通する必須項目とは
新卒採用と転職採用では評価の重点が異なりますが、共通して見られる必須項目があります。
それは、社会人としての基礎的な能力やポテンシャルです。
具体的には以下のような項目が挙げられます。
| 項目 | 見られるポイント |
|---|---|
| 基本的なビジネスマナー | 正しい敬語の使い方、丁寧な文字 |
| 論理的な文章構成力 | 結論から先に書く、分かりやすい文章 |
| 基本的なPCスキル | ワードやエクセルなどの基本操作 |
| 自己管理能力 | 提出期限の遵守、書類の丁寧な扱い |
企業は、組織の一員として円滑に業務を遂行できる人材を求めています。
基礎的な部分で評価を落とさないよう、細心の注意を払って書類を作成しましょう。
書類選考では何を見る?企業が評価する5大項目
書類選考において、採用担当者は単に経歴を眺めているわけではありません。
自社で活躍できる人材か、長く貢献してくれる人材かを見極めるため、複数の評価項目を設けてチェックしています。
書類選考で企業が評価する5つの項目
- 求める経験・スキルの一致度
- 自己PRと志望動機の一貫性
- 社歴・学歴・資格の整合性
- 入社可能時期の現実性
- 加点要素の扱い
企業が特に注目する項目について、それぞれ解説します。
求める経験・スキルの一致度
企業がまず確認するのは、募集しているポジションに必要な経験やスキルを応募者がもっているかです。
これが最も基本的な評価項目であり、前提条件となります。
求人票に記載されている「必須スキル」や「歓迎スキル」と、自身の経歴を照らし合わせ、合致する点を具体的にアピールする必要があります。
ポイント
- 職務経歴書では、関連する業務内容を冒頭に記載する
- 専門用語を使いすぎず、誰が読んでも分かる言葉で実績を説明する
- 具体的な数字を用いて客観的な成果を示す
これらの点を意識すると、採用担当者はあなたのスキルレベルを正確に把握できます。
自己PRと志望動機の一貫性
自己PRで伝える「自身の強み」と、志望動機で語る「企業で成し遂げたいこと」に一貫性があるかは、論理的思考力や志望度の高さを測る上で見られます。
この2つに矛盾があると、自己分析が不十分、あるいは手当たり次第に応募しているという印象を与えかねません。
一貫性を持たせるポイント
- 強みを発揮して、企業のどのような課題を解決したいかを明確にする
- 企業の事業内容や文化を理解し、自身の価値観との接点を見つける
- 「なぜこの企業でなければならないのか」を具体的に説明する
具体例を見てみましょう。
一貫性のある自己PRの例文
私の強みは、相手の懐に入り込み、潜在的なニーズを引き出す「傾聴力と関係構築力」です。
前職のIT機器販売の法人営業では、顧客との定例会議以外に週1回の雑談ベースの訪問を続け、担当者との信頼関係を築くことに注力しました。
その中で、顧客が「業務の属人化」という潜在的な課題を抱えていることを発見。
課題解決のために自社のタスク管理ツールを提案し、導入いただいた結果、チーム内の業務平準化に成功し、部署全体の残業時間を月平均15%削減できました。
上記の自己PRに続く志望動機の例文
貴社の「徹底した顧客志向」という理念と、単なる製品販売にとどまらず、導入後のサポートまで一気通貫で支援するビジネスモデルに強く惹かれ、志望いたしました。
前職で培った「傾聴力と関係構築力」を活かし、お客様がまだ気づいていない課題まで引き出し、貴社の多様なソリューションを組み合わせることで、事業成長に貢献できると確信しております。
お客様と長期的な信頼関係を築き、共に成長していくという貴社のスタイルの中で、自身の強みを最大限に発揮したいです。
強み(関係構築力)、やりたいこと(顧客の課題解決)、そして企業の方向性(顧客志向)が、このように一つの線で繋がるストーリーを構築しましょう。
社歴・学歴・資格の整合性
応募書類に記載された社歴、学歴、各種資格の情報に矛盾がないか、整合性のチェックがおこなわれます。
例えば、卒業年月と入社年月がずれている、資格の正式名称が間違っているなどの不備は、信頼性を損なう原因となります。
| チェックされる項目 | 具体的なポイント |
|---|---|
| 時系列の整合性 | 学歴・職歴の開始年月と終了年月に矛盾がないか |
| 内容の正確性 | 企業名、学部・学科名、資格の正式名称は正しいか |
| 空白期間の説明 | 離職期間がある場合、その理由が納得できるものか |
提出前には、全ての項目で情報が正確か、時系列に矛盾がないかを慎重に確認してください。
入社可能時期の現実性
採用活動にはスケジュールがあり、企業が希望する入社時期と、応募者が希望する入社可能時期が大きくずれていると、選考から外れる場合があります。
ポイント
特に、急募のポジションやプロジェクトが決まっている求人では、入社可能時期が合否を分ける要因になるケースも少なくありません。
正直に「相談可能」と記載するのも1つの方法です。
内定から入社までの期間は、一般的に1ヶ月〜3ヶ月程度が目安とされています。
現在の職場の退職交渉に必要な期間を考慮し、現実的な時期を記載してください。
加点要素の扱い
必須スキルではないものの、もっていると評価が上がる「加点要素」も、他の応募者との差別化につながります。
特に、グローバル展開を進める企業では、英語力が大きなアドバンテージになります。
| 加点要素の例 | アピール方法 |
|---|---|
| 語学力 | TOEICやTOEFLのスコア、海外での実務経験を具体的に記載 |
| 専門資格 | 募集職種に関連する高度な専門資格を明記 |
| リーダーシップ経験 | プロジェクトやチームでのリーダー経験を職務経歴書で説明 |
| ITスキル | プログラミング言語や高度な分析ツールの使用経験をアピール |
これらのスキルは、入社後の活躍の幅広さやポテンシャルを示す材料となります。
関連するスキルや経験がある場合は、忘れずに応募書類に盛り込みましょう。
書類だけで判断されにくいHELLOBOSSを使ってみよう
という方は、書類選考なしで企業と直接話せる「HELLOBOSS」を使ってみてください。
「HELLOBOSS」なら、AIがあなたに合った企業を推薦し、応募前に採用担当者とチャットでカジュアルに話せます。
ポイント
求人票だけではわからないリアルな情報を聞いたり、あなたの熱意を直接伝えたりできるので、入社後のミスマッチを防げます。
無料で利用できるので、まずはインストールしてどんな企業があるか覗いてみましょう。
書類選考で落ちる人の特徴と履歴書NGワード一覧
多くの応募書類を見ている採用担当者は、良い点だけでなく「評価を下げやすい書類」のパターンも把握しています。
意図せず評価を落としてしまう事態を避けるため、書類選考で落ちる人の共通点を知っておきましょう。
この章で解説する内容
- 「成長したい」だけでは弱い理由
- 一発でNGになりうる形式的なミス
- 過去の経験に一貫性がないケース
- 避けるべきNGワードのチェックリスト
不採用につながりやすい書類の特徴と、履歴書で使うべきではないNGワードについて具体的に解説します。
「成長したい」「御社第一志望です」だけでは弱い
「成長したい」という意欲や「第一志望」という熱意は、それ自体が悪いわけではありません。
しかし、その言葉だけでは採用担当者に響きません。
なぜなら、企業は「応募者がどう成長したいか」よりも「自社にどう貢献してくれるか」を知りたいからです。
貢献度を伝えるポイント
- 「成長」を「貢献」の言葉に置き換える
- どのように成長し、その結果どう企業に貢献できるのかをセットで伝える
- 「第一志望」の根拠として、企業のどの部分に魅力を感じたのかを具体的に示す
「貴社の〇〇という事業で、私の△△というスキルを活かして貢献し、将来的には□□の分野で成長していきたい」のように、具体的な貢献意欲を示すことが重要です。
誤字脱字・空欄・写真ミスは即NG
書類の基本的な不備は、仕事への姿勢や志望度を疑われる直接的な原因となります。
採用担当者は、細かい部分まで注意を払える人材を求めています。
特に注意すべき形式的なミス
- 誤字や脱字
- 入力漏れによる空欄
- 不適切な証明写真(サイズ違い、不鮮明、スナップ写真など)
- 古い情報のまま提出
これらのミスは、内容を読まれる前に不採用となる可能性が高い項目です。
自分では気づきにくい間違いもあるため、提出前には声に出して読んだり、第三者にチェックを依頼したりすることをおすすめします。
参考:履歴書を間違えた場合の対処法|書き間違いを防ぐ9つの方法も解説
過去の経験が点在し一貫性がないケース
職務経歴に一貫性が見られないと、採用担当者は「キャリアプランが不明確」「すぐに辞めてしまうかもしれない」という懸念を抱きます。
たとえ異業種への転職であっても、これまでの経験から得たスキルや知識が、応募先企業でどのように活かせるのかを示す必要があります。
ポイント
- 課題解決能力
- コミュニケーション能力
- マネジメント経験
これまでのキャリアを振り返り、応募職種で活かせる共通のスキルや経験を抽出し、一貫したストーリーとして伝えましょう。
【チェックリスト】絶対避けたいNGワード15選
意欲を伝えようとして使った言葉が、かえってマイナスの印象を与えてしまう場合があります。
以下の表にあるような言葉は、具体的でなかったり、受け身な姿勢に見えたりする可能性があるため、使用を避けるか、より具体的な表現に言い換えましょう。
| 避けるべきNGワード | 言い換え・改善案の例 |
|---|---|
| コミュニケーション能力 | 相手の意見を傾聴し、論点を整理して提案する力 |
| 頑張ります | 〇〇という目標に対し、△△の施策を実行し達成します |
| 勉強させていただきます | 〇〇の知識を習得し、貴社の△△という業務に活かします |
| 色々なことに挑戦したい | 特に〇〇の分野に挑戦し、△△という形で貢献したいです |
| チームワークを大切に | チーム内で〇〇という役割を担い、目標達成に貢献します |
| 〜だと思います | 〜と考えます、〜と確信しています |
| 〜のようです | 〜と認識しています |
| 社会貢献したい | 貴社の〇〇という事業を通じて、△△という社会課題を解決したい |
| 御社の将来性に惹かれた | 貴社の〇〇という事業の将来性に対し、私の△△の経験を活かせる |
| いずれは〜したい | まずは〇〇で成果を出し、将来的には△△の業務に携わりたい |
| 〜に興味があります | 〇〇に興味があり、△△の知識を活かせると考えたため |
| 何でもやります | まずは〇〇の業務で貢献したいです |
| 前職(前社)では〜 | 前職で培った〇〇の経験を活かし〜 |
| (ネガティブな)退職理由 | ポジティブなキャリアプランに繋がる理由に変換する |
| 御社 | 御社は話し言葉のため書き言葉である「貴社」に統一 |
書類全体を完成させた後、これらのNGワードが含まれていないか、最終チェックを必ずしてください。
書類選考の通過率と不採用連絡が来るまでの期間
書類選考の結果を待つ期間は、応募者にとって不安な時間です。
選考の通過率や、連絡が来るまでの期間の目安を知っておくと、落ち着いて次の準備を進められます。
一般的な数値を把握し、冷静に状況を判断しましょう。
この章で解説する内容
- 書類選考の平均通過率とその根拠
- 連絡期間から読み解く企業の意図
- 不採用通知後のリカバリー策
ここでは、書類選考の通過率や結果連絡の目安、そして万が一不採用だった場合に次に繋げるための行動について解説します。
転職市場平均通過率は30~40%と言われる根拠
一般的に、書類選考の通過率は30%〜40%前後とされています。
これは、採用コンサルティング会社や転職エージェントが公表しているデータに基づくものです。
10社に応募した場合、3社か4社で次の面接に進める計算となります。
ポイント
この数値はあくまで全体の平均値です。
人気企業や大手企業では通過率が10%以下になることもあります。
専門性の高い職種や、応募者が少ない求人では通過率が高くなる傾向があります。
通過率の数字に一喜一憂するのではなく、応募書類の質を高め続けることが何よりも重要です。
1つの結果に固執せず、継続的に活動を進めましょう。
「3日以内お祈り」「1週間沈黙」の意味を読み解く
企業からの連絡期間は、選考状況を推測する1つの材料になります。
応募から連絡が来るまでの期間によって、企業の意図がある程度読み取れる場合があります。
| 連絡期間の目安 | 考えられる企業の状況や意図 |
|---|---|
| 応募後〜3日 | ・募集要件と著しく異なり、早期に不採用と判断された ・非常に評価が高く、すぐにでも会いたいと思われている |
| 4日〜1週間 | ・標準的な選考期間 ・他の応募者と比較検討している段階 |
| 1週間〜2週間 | ・応募者が多数で選考に時間がかかっている ・合格ライン上で、通過させるか迷っている(キープされている) |
| 2週間以上 | ・選考が難航している、または別の候補者で選考が進んでいる ・サイレントお祈り(不採用通知を送らない)の可能性も |
上記の期間はあくまで目安です。
企業の規模や応募状況によって選考スピードは異なります。
2週間を過ぎても連絡がない場合は、一度問い合わせてみてもよいでしょう。
早すぎる不採用通知でも諦めないリカバリー策
応募してすぐに不採用通知が届くと、気持ちが落ち込むかもしれません。
しかし、それは単に今回の募集要件と合わなかっただけで、あなた自身の価値が否定されたわけではありません。
気持ちを切り替え、次の行動に移しましょう。
不採用通知後にすぐできること
- 応募書類の見直し(誤字脱字、分かりにくい表現がないか)
- 企業の求める人物像と自分のアピールポイントのずれを確認
- キャリアアドバイザーなど第三者に客観的な意見を求める
- 条件を見直し、応募先の範囲を広げてみる
1社の結果を引きずらず、PDCAサイクルを回すように書類を改善し続ける姿勢が、最終的な内定獲得につながります。
失敗を次に活かすための貴重なデータと捉え、前向きに行動を続けましょう。
書類だけで判断されにくいHELLOBOSSも活用してみる
という方は、繰り返しですが「HELLOBOSS」の活用も検討してみましょう。
書類だけで評価される従来の選考方法では、あなたの本当の魅力が伝わりきらないこともあります。
書類選考に疲れてしまった方は、新しい形の転職活動で、あなたに合う企業を見つけてみてください。
新卒と転職で異なる書類選考のチェックポイント
書類選考における評価基準は、応募者が「新卒」か「転職」かによって大きく異なります。
企業がそれぞれの候補者に何を期待しているのかを理解すると、より的確なアピールができます。
自身の立場に合わせた書類作成を心がけましょう。
この章で解説する内容
- 新卒採用で見られるポテンシャル
- 転職採用で求められる即戦力性
- キャリアチェンジの際の注意点
新卒と転職、それぞれの立場で採用担当者がどこに注目しているのか、そのチェックポイントの違いを解説します。
新卒はポテンシャル・将来性が8割
新卒採用では、実務経験がないことが前提のため、現時点でのスキルよりも将来的な成長の可能性、いわゆる「ポテンシャル」が重視されます。
企業文化への適応力や、学習意欲の高さが評価の対象です。
ポテンシャルを示す要素
- 学生時代の経験(学業、部活動、アルバイトなど)から何を学んだか
- 困難な課題にどう向き合い、乗り越えたかというプロセス
- 企業の事業内容への深い理解と、そこで挑戦したいこと
自己PRやガクチカ(学生時代に力を入れたこと)を通じて、自身の学びや人柄、熱意を伝えることが重要です。
スキル面をアピールするよりも、入社後の成長意欲や貢献したいという姿勢を前面に出しましょう。
参考
転職は即戦力スキル+一貫したキャリア軸
転職採用では、企業は即戦力となる人材を求めています。
これまでの職務経験で培った専門知識やスキルが、募集ポジションで直接的に活かせるかが最も重要な評価ポイントです。
職務経歴書では、具体的な業務内容とそこで挙げた実績を定量的に示す必要があります。
例
- 売上を〇%向上させた
- 〇人のチームをマネジメントした
- 〇〇の導入によりコストを△%削減した
また、これまでのキャリアに一貫性があるかも見られます。

20代の転職では、短い職歴でも『なぜ転職するのか』『どう成長したいか』を明確にすることが重要です。
一貫性のあるキャリアストーリーを作りましょう。
キャリアチェンジ希望者が意識すべき職務経歴書の構造
未経験の職種や業種へ挑戦するキャリアチェンジでは、アピールの仕方に工夫が必要です。
即戦力採用が基本の転職市場において、なぜ未経験の自分を採用すべきなのか、その理由を説得力をもって伝えなくてはなりません。
職務経歴書では、これまでの経験と希望職種の共通点を見つけ出し、「ポータブルスキル」を軸に構成します。
| 意識すべき項目 | 具体的な書き方 |
|---|---|
| キャリアの棚卸し | これまでの経験で得たスキルを全て書き出し、希望職種で活かせるものを整理する |
| ポータブルスキルの強調 | マネジメント能力や課題解決能力など、業種を問わず通用するスキルを具体例と共にアピールする |
| 熱意と学習意欲 | なぜその職種に挑戦したいのか、そのために現在どのような学習をしているのかを具体的に示す |
単に「やる気があります」と伝えるだけでは不十分です。
これまでの経験を新しい分野でどう活かせるのか、その再現性を具体的にアピールすることが、採用を勝ち取るための鍵となります。
書類選考を突破する履歴書・職務経歴書の書き方
書類選考は、内容だけでなく「書き方」そのものも評価されています。
採用担当者が読みやすいと感じる書類は、それだけで好印象を与えます。
戦略的な書き方を身につけ、通過率を高めましょう。
この章で解説する内容
- 履歴書で印象を決定づけるポイント
- 職務経歴書の基本的なフレームワーク
- 実績を効果的に見せる数字の使い方
ライバルに差をつけるための具体的な書類作成テクニックについて、履歴書と職務経歴書に分けて解説します。
履歴書は「一覧性」と「余白の使い方」で印象が決まる
履歴書は、応募者の基本情報を一覧で確認するための書類です。
採用担当者は短時間で必要な情報を探すため、パッと見て分かりやすい「一覧性」が重要になります。
レイアウトが整っており、適度な余白があると、丁寧で知的な印象を与えます。
見やすい履歴書のポイント
- 文字の大きさを統一し、詰め込みすぎない
- 手書きの場合は、楷書で丁寧に書く
- Webで作成する場合は、基本的なビジネスフォントを使用する
- アピールしたい項目以外は、箇条書きで簡潔にまとめる
履歴書は、あなたという商品をプレゼンテーションする最初の資料です。
細部まで気を配り、情報が整理された美しいレイアウトを心がけるだけで、他の応募者と差がつきます。
職務経歴書は”結論→成果→再現性”のPREP+STAR法
職務経歴書では、PREP法とSTAR法を組み合わせたフレームワークを意識すると、論理的で説得力のあるアピールができます。
これは、自身の経験やスキルが、入社後にどう貢献できるかを明確に示すための有効な手法です。
PREP法とSTAR法とは
- PREP法: Point(結論)、Reason(理由)、Example(具体例)、Point(結論)の順で説明する手法。
- STAR法: Situation(状況)、Task(課題)、Action(行動)、Result(結果)の頭文字を取ったもので、実績を具体的に示す際に有効なフレームワーク。
まずPREP法の「結論」としてアピールしたいスキルを提示し、その後の具体例(Example)の部分でSTAR法を用いて実績を説明します。
この流れで書くことで、採用担当者はあなたの能力と再現性をスムーズに理解できます。
具体例を見てみましょう。
PREP+STAR法を活用した例文(営業職)
P(結論): 私の強みは、顧客の課題を分析し、的確なソリューションを提案する課題解決能力です。
R(理由): 前職の法人営業において、常にお客様の潜在的なニーズを引き出し、最適な製品を組み合わせることで、顧客満足度の向上と売上拡大に貢献してきた経験があるからです。
E(具体例):※ここからSTAR法で説明。
S(状況): 担当していたIT業界のクライアントは、既存システムの運用コストの高さと、業務効率の低下に悩んでいました。
T(課題): クライアントの年間運用コストを15%削減し、業務効率を20%向上させるという目標を設定しました。
A(行動): まず、クライアントの業務フローをヒアリングし、コストと時間のボトルネックを特定しました。その上で、自社の新製品Aと既存製品Bを組み合わせた独自のシステム構成を提案。導入効果を具体的な数値でシミュレーションし、費用対効果を分かりやすく提示しました。
R(結果): 結果、クライアントの年間運用コストを目標を上回る20%削減、業務効率は30%の向上を実現しました。この取り組みが評価され、新たに5年間の大型契約を獲得し、社内の四半期MVPを受賞しました。
P(結論): この課題解決能力を活かし、貴社のソリューション営業として、クライアントの事業成長に直接的に貢献できると確信しております。
このようにフレームワークに沿って記述すると、あなたの強みと実績が論理的に伝わります。
具体数字を盛り込む3つのコツ
職務経歴書で実績を示す際は、具体的な数字を用いると客観性と信頼性が増します。
しかし、ただ数字を並べるだけでは効果がありません。
効果的にアピールするための3つのコツを紹介します。
| 数字を盛り込むコツ | 具体的な記載例 |
|---|---|
| パーセンテージ(%)で示す | 担当地域の売上を前年比120%に向上させました |
| 具体的な件数・人数で示す | 新規顧客を毎月平均15件開拓しました |
| 期間を明確にする | 6ヶ月のプロジェクトで、納期を2週間短縮しました |
数字を使う際は、誰が見てもそのすごさが分かるように、比較対象(前年比、目標比など)を明確にすることが重要です。
これにより、あなたの実績が具体的かつ客観的な事実として採用担当者に伝わります。
書類選考通過率を上げるための5ステップ
やみくもに応募書類を送り続けても、通過率が上がることはありません。
書類選考の通過率を高めるには、戦略的な準備が必要です。
正しい手順を踏むことで、書類の完成度は飛躍的に向上します。
書類選考通過率を上げるための5ステップ
- 求める人物像を求人票・IRから抽出
- 自己分析で接点ワードを洗い出す
- スキル/実績を数字で可視化
- 第三者に添削依頼し客観性を担保
- 送付前に応募書類チェックリストで最終確認
それぞれくわしく解説していきます。
STEP1|求める人物像を求人票・IRから抽出
最初のステップは、応募先企業がどのような人材を求めているかを正確に把握することです。
企業の「採用したい人」の解像度を上げ、その人物像に自身を近づけていくことが、選考突破の鍵となります。
情報収集の主な情報源
- 求人票の「仕事内容」「必須・歓迎スキル」の欄
- 企業の採用サイトにある「求める人物像」や「社員インタビュー」
- 企業の公式サイトにあるIR情報(投資家向け情報)や中期経営計画
- 代表メッセージやプレスリリース
特に、中期経営計画や代表メッセージからは、企業が今後どの方向に進もうとしているのかが読み取れます。
そこから逆算して、どのようなスキルや経験をもつ人材が必要とされるのかを予測しましょう。

求人票を読み解く力は転職成功の鍵です。
「必須スキル」だけでなく「歓迎スキル」や企業の方向性を読み取り、自分の経験とどうマッチするかを分析することが大切です。
STEP2|自己分析で接点ワードを洗い出す
次に、抽出した「求める人物像」と、あなた自身の経験・スキルとの接点を見つけ出します。
これまでのキャリアを棚卸しし、企業が求めるキーワードと合致するエピソードや実績を洗い出す作業です。
この段階では「こんな経験はアピールにならない」と決めつけず、些細なことでも全て書き出してみましょう。
例
- 過去の業務内容
- プロジェクトでの役割
- 仕事で工夫した点
- 成果や社内での評価 など
洗い出した経験の中から、STEP1で見つけた「求める人物像」に最も響くであろう「接点ワード」を選び出します。
この接点ワードが、応募書類全体の軸となります。
STEP3|スキル/実績を数字で可視化
自己PRや職務経歴に説得力をもたせるため、スキルや実績を具体的な数字に落とし込みます。
これは、あなたの貢献度を客観的な事実として示すための不可欠な作業です。
「頑張りました」といった定性的な表現ではなく、定量的なデータで示しましょう。
例
- マネジメント経験 → 5人のチームを率い、目標達成率を前年比110%に向上させた
- 業務改善スキル → 新しいツールを導入し、月間20時間の業務時間削減に成功した
全ての業務を数字で示すのは難しいかもしれませんが、売上、コスト、時間、件数、人数など、何らかの形で数値化できないか検討する癖をつけることが重要です。
STEP4|第三者に添削依頼し客観性を担保
応募書類が完成したら、必ず自分以外の第三者に添削を依頼しましょう。
自分では完璧だと思っていても、他人から見ると分かりにくい表現や、誤字脱字が見つかるものです。
添削を依頼する相手の候補
- 転職エージェントのキャリアアドバイザー
- 応募する業界・職種に詳しい知人や先輩
- 大学のキャリアセンターの職員
特に、転職エージェントは数多くの書類を見ているプロなので、採用担当者の視点から具体的な改善点を指摘してくれます。
客観的なフィードバックを取り入れることで、書類の完成度は格段に上がります。
STEP5|送付前に応募書類チェックリストで最終確認
最後のステップとして、送付直前に最終チェックを行ないます。
基本的なミスが、選考結果に致命的な影響を与える可能性があるため、慎重に確認しましょう。
以下のチェックリストをぜひ活用してください。
| チェック項目 | 確認内容 |
|---|---|
| 基本情報 | 氏名、住所、連絡先に誤りはないか |
| 誤字脱字 | 全ての文章を音読して、誤字脱字がないか確認したか |
| 日付 | 提出日または前日の日付になっているか |
| 写真 | 規定のサイズで、3ヶ月以内に撮影したものか。剥がれていないか |
| 企業名 | 企業名は正式名称で、株式会社の位置も正確か(「(株)」はNG) |
| 一貫性 | 履歴書、職務経歴書、志望動機の内容に矛盾はないか |
| ファイルの形式 | 企業からの指定(PDFなど)を守っているか |
| ファイル名 | 「履歴書_氏名_日付」のように、分かりやすいファイル名になっているか |
これらの最終チェックをクリアして初めて、応募の準備が整ったといえます。
書類選考なしで企業とチャットできる「HELLOBOSS」とは?
「HELLOBOSS」は、従来の就職・転職活動の形を変える新しいプラットフォームです。
最大の特徴は、応募前に企業の採用担当者と直接チャットでコミュニケーションが取れる点にあります。
書類選考というハードルを越えずに、あなたの意欲や人柄を直接伝えられます。
HELLOBOSSがどのようにあなたの転職活動をサポートするのか、その具体的な仕組みと利点について解説します。
AIが求職者と企業を無料マッチングする仕組み
HELLOBOSSでは、登録されたあなたのプロフィールや希望条件をAIが分析します。
そして、数多くの求人の中から、あなたに最適な企業を自動で探し出し、マッチングさせます。
これにより、自分で求人を探す手間が省け、これまで出会えなかった優良企業と巡り会う可能性が広がります。
ポイント
AIは、単にスキルや経験だけで判断するわけではありません。
あなたの価値観やキャリアプランといった、プロフィールの深い部分まで読み取り、企業文化との相性も考慮してマッチングを行ないます。
このAIマッチング機能は、求職者と企業のミスマッチを減らし、より満足度の高い転職を実現するための仕組みです。
応募前に採用担当者とチャットできるメリット
マッチングした企業の採用担当者とは、応募前にチャットで気軽に話せます。
これにより、従来の選考フローでは得られなかった多くのメリットが生まれます。
チャットで得られる主なメリット
- 企業の雰囲気や文化を直接感じられる
- 求人票だけでは分からない具体的な業務内容を確認できる
- 自分のスキルや経験が本当に活かせるか質問できる
- 面接では聞きにくい条件面(残業や休日など)を事前に把握できる
- 人柄や熱意を直接アピールできる
堅苦しい面接の場とは異なり、リラックスした状態で相互理解を深められます。
入社後の「こんなはずではなかった」というギャップを防ぎ、納得感のある転職活動を進める上で非常に有効な機能です。
書類選考についてよくある質問(FAQ)
最後に、書類選考に関して多くの求職者が抱く疑問について、Q&A形式で回答します。
不安や疑問を解消し、自信をもって選考に臨みましょう。
学歴フィルターは本当に存在しますか?
存在しないとは言い切れませんが、その影響は限定的になってきています。
新卒採用の一部では、応募者が殺到する人気企業が効率的に選考を進めるために、一定の基準として用いるケースがあります。
ポイント
中途採用(転職)においては、学歴よりも実務経験やスキルが重視されるため、学歴フィルターを気にする必要はほとんどありません。
学歴に自信がない場合でも、それを補って余りあるスキルや実績を職務経歴書でアピールすることが重要です。
企業が本当に求めているのは、学歴そのものではなく「自社で活躍できる人材」です。
経歴全体で自身の価値を示しましょう。
履歴書の自己PRにアルバイト経験は書くべき?
書くべきかどうかは、あなたの状況とアルバイトの内容によります。
特に、アピールすべき実務経験が少ない新卒や第二新卒の場合は、有力な自己PRの材料となります。
アルバイト経験を書くべきケース
- 応募職種と関連性の高い業務経験(例:飲食店のアルバイト→外食産業に応募)
- リーダーシップや課題解決能力を発揮した経験
- 長期的に継続し、責任ある仕事を任されていた経験
一方で、豊富な実務経験がある転職者の場合、アルバイト経験まで記載するとアピールポイントがぼやける可能性があります。
職務経歴を中心に、アピールしたい内容を絞って記載しましょう。
職務経歴書の理想ページ数は?
職務経歴書の理想的なページ数は、応募者の経験年数によって異なりますが、採用担当者が短時間で内容を把握できるよう、簡潔にまとめるのが基本です。
| 経験年数の目安 | 推奨ページ数 | ポイント |
|---|---|---|
| 第二新卒〜5年未満 | 1〜2枚 | ポテンシャルと基本的な実務能力をアピール |
| 5年〜10年程度 | 2枚 | 即戦力となる専門スキルと実績を具体的に示す |
| 10年以上 | 2〜3枚 | マネジメント経験や専門性の高さを中心にまとめる |
経験が豊富な方でも、アピールしたい内容を絞り込み、3枚以内に収めるのが一般的です。
職務要約を冒頭に設け、詳細な経歴は必要に応じて記載するなど、読みやすさを意識した工夫が求められます。
書類選考に落ちた企業へ再応募してもいい?
再応募すること自体は、多くの企業で禁止されていません。
しかし、ただ同じ書類を送り直すだけでは、結果も同じになる可能性が高いです。
再応募する際の注意点
- 前回の応募から一定期間(最低でも半年〜1年)を空ける
- その期間に、応募職種で求められるスキルや経験を新たに身につけている
- 不採用の理由を自己分析し、応募書類を大幅に改善している
再応募する際は、前回応募時から自分がどう成長したのかを具体的に示せる場合に限り、挑戦する価値があります。
「どうしてもこの企業で働きたい」という強い熱意と、それを裏付ける客観的な成長を示しましょう。
まとめ | さっそく書類選考の通過率を上げるステップを実践しよう
書類選考のポイントを理解したら、さっそく通過率を上げるための行動を始めましょう。
書類選考通過率を上げるための5ステップ
- 求める人物像を求人票・IRから抽出する
- 自己分析で企業との接点ワードを洗い出す
- スキルや実績を具体的な数字で可視化する
- 第三者に添削を依頼して客観性を担保する
- 送付前に応募書類のチェックリストで最終確認する

やるべきことは分かったけど、やっぱり一人で完璧な書類を作るのは難しい…
という方は、くりかえしですが「HELLOBOSS」を使ってみてください。
おすすめアプリ
無料で始められるので、まずはインストールして、あなたに合う企業からの連絡を待ってみましょう。
この記事が、あなたの書類選考突破の助けになれば嬉しいです!