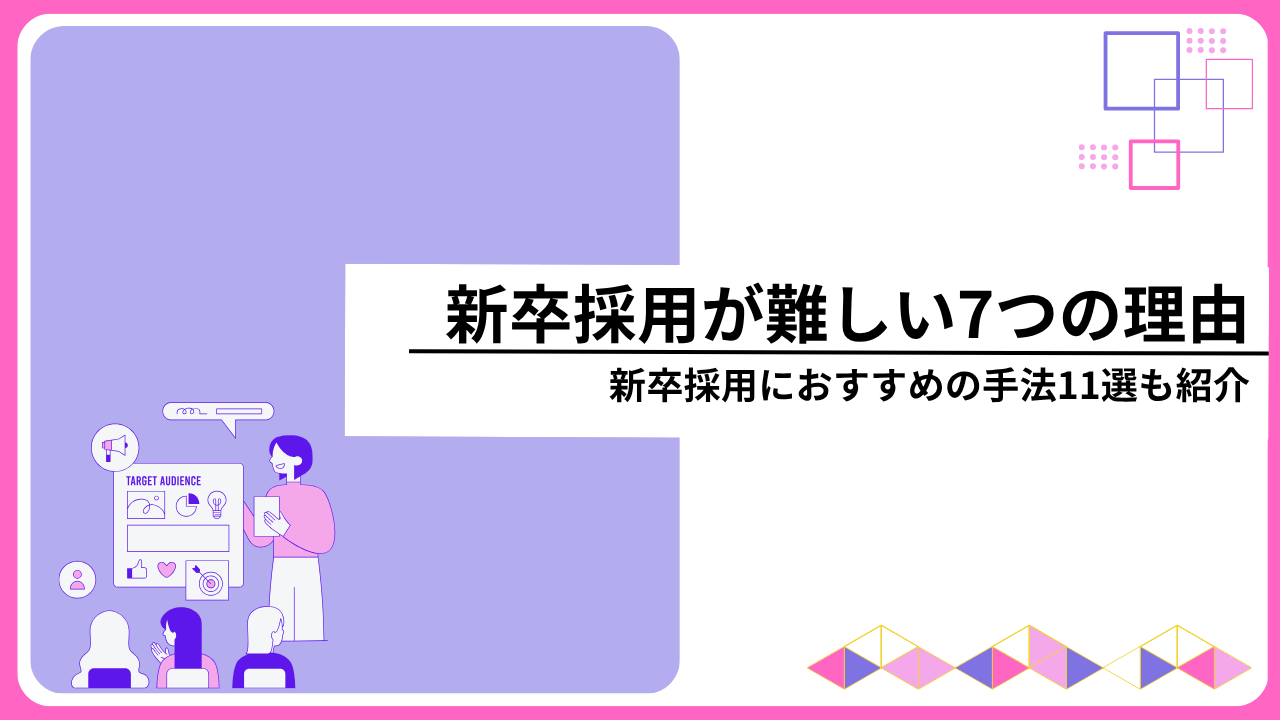「新卒採用が難しい…」
「どうすれば新卒人材を採用できる?」
とお悩みの人事担当者様に向けた記事です。
この記事でわかること
- 新卒採用が難しい7つの理由
- 新卒採用を成功させる7つのコツ
- 新卒採用におすすめの手法11選
人材不足や売り手市場が続いていることから、新卒採用の難易度が上がっています。
「会社説明会に人がこない…」といった経験をした人事担当者様もいるかもしれません。
この記事では、新卒採用のノウハウを網羅的に解説しています。
人材採用の目標を達成したい人事担当者様は、最後まで読んでみてください。
新卒人材にダイレクトアプローチできます
「前置きはいいから、早く新卒を採用するコツを知りたい!」という方は、新卒採用を成功させる7つのコツへジャンプしてみて下さい。
Contents
新卒採用が難しい7つの理由
まずは新卒採用が難しい理由を解説していきます。
新卒採用が難しい理由
- 就活市場で人材が不足しているから
- 社内の採用担当者が不足しているから
- 採用ノウハウが不足しているから
- 採用予算が不足しているから
- 企業の知名度が低いから
- 採用スケジュールが早期化しているから
- 内定辞退者が多いから
新卒の市場を知っておかないと、効果的な対策を打てません。まずは新卒採用が難しい理由を把握していきましょう。
就活市場で人材が不足しているから
厚生労働省の発表によると、令和6年11月の有効求人倍率は1.25倍となっており、新卒を含む広範な人材不足が続いています。
参考:厚生労働省|一般職業紹介状況(令和6年11月分)について
買い手優位だった時代とは違い、企業側が学生に応募を促す売り手市場です。
さらに、大手企業や人気業界へ学生が集中し、母集団を確保しづらい企業もあります。こうした背景の中、思うように応募が集まらず、新卒採用が滞ってしまう企業も少なくありません。
社内の採用担当者が不足しているから
社内に採用専門の担当者がいない場合、新卒採用の計画立案や学生対応に遅れが生じやすいです。他の業務と兼任すると、応募確認や面接調整が後回しになり、機会を逃す恐れがあります。
具体的には、以下のような問題が起こりやすいです。
社内の採用担当者が不足すると起きる問題
- 学生への連絡が遅れ、印象を悪くする
- 説明会の回数を減らさざるを得ない
- 内定を出してからのフォローが不足する
こうした状況を解決するためには、採用業務を分担したり外部サービスを利用したりする取り組みが必要です。
採用ノウハウが不足しているから
就職イベントやオンライン面接など、対応が必要な手段が増えていますが、ノウハウを積み重ねていないと成果が出にくいです。特に、創業から間もない企業は採用ノウハウが蓄積されていないでしょう。
説明会でどのように学生と関係を築くか、オンライン時に伝わりにくい企業文化を補うかなど、工夫が必要です。
注意
面接官の質問内容や進め方が定まっていない場合、学生の意欲や適性を正確に見きわめるのが難しいでしょう。
経験豊富な社員から学んだり、外部セミナーへ参加したりして、最新の事例を取り入れる努力が求められます。
採用予算が不足しているから
求人広告や就職イベントなどへ支出する金額が限られると、学生への露出機会を増やしづらいです。大手企業はブランド力を背景に効率よく応募を集める場合が多く、中小企業が対抗するには予算面の工夫が必要です。
ちなみに、採用費の目安は以下のとおりです。
| 費目 | おおよその金額 | 特徴 |
|---|---|---|
| 求人広告 | 数万円~数十万円 | 期間や掲載枠で変動が大きい |
| 説明会 | 数万円〜数百万円 | オンライン化で節約も検討しやすい |
| 採用ツール | 数千円~数万円 | 学生管理システム、採用アプリなど |
経費を十分に確保できないほど、魅力の発信や採用活動が制約され、質の高い採用に繋がりにくくなります。最終的に人材不足が起き、長期的な成長戦略にも影響が及ぶ懸念があるでしょう。
企業の知名度が低いから
学生は時間の限られた就職活動で、聞いたことがある企業や広告などで知る機会が多い企業を優先的に調べる傾向があります。名前を知らない企業だと「本当に安心できる就職先なのか」という疑念が生まれ、候補から外されやすいです。
ポイント
就職サイトに掲載しても認識されず、説明会でもブースに人が集まらないケースが起こりやすいです。
知名度が低いと就活生の目に留まりにくく、選考までたどり着かないまま採用活動が終了するリスクが高まります。
採用スケジュールが早期化しているから
採用スケジュールが早期化していることも、新卒採用が難しい要因です。学生が早い段階で就職活動を始める動きが加速し、企業が後れを取ると応募数が減りやすいです。
ポイント
多くの学生は大企業が先手を打って内定を出す流れに乗りやすく、中小企業は求人情報を公開する時期が遅い場合、学生との接触が少なくなります。
さらに、早期の時期に複数の内定を得た学生は、より条件が合う就職先を後から選ぶ傾向があり、初期に出した内定が辞退される場合があります。
また、採用スケジュールが短期間に集中すると、企業は限られた期間で広報や選考を進めないと、応募を確保しにくいです。
内定辞退者が多いから
新卒者の多くは複数の企業で選考を進めるため、条件が良いと感じた企業を後出しで優先することも珍しくありません。
例えば、他社の入社時期や仕事内容を詳しく知った後に「こちらの企業の方が自分に合っている」と判断し、すでに取得していた内定を断るケースがあります。
ポイント
学生は周囲の情報収集を通じて会社の将来性を見極め、最初の決心を覆すこともあるでしょう。
結果として複数名に内定を出しても承諾数が伸びず、新卒採用が難航しがちです。
新卒採用を成功させる7つのコツ
難易度が高くなっている新卒採用を成功させるには、以下のコツを実践していきましょう。
新卒採用を成功させる7つのコツ
- 採用スケジュールを早める
- 採用ペルソナを明確にする
- 選考プロセスの最適化
- 現場社員や経営者が採用活動に参加する
- 企業情報を魅力的に伝える
- 内定者フォローを徹底する
- 既卒や第二新卒を採用する
1つずつ解説していくので、できることから始めてみてください。
採用スケジュールを早める
採用スケジュールを早めると、意欲の高い就活生との接点が増えます。募集開始を先行すれば、積極的に企業研究する就活生が注目しやすくなるでしょう。
ポイント
興味を持った学生に詳しく説明する場を設けると、人が集まりやすい可能性があります。
余裕を持ったスケジュールによって、面談や面接の設定もしやすいです。競合より早めに募集を開始すると、注目を集めるチャンスが広がります。
ただし
採用スケジュールを早めると、学生にとっては「学業に支障が出る」などのデメリットが発生します。ターゲットとなる学生に配慮したスケジュールが望ましいです。
採用ペルソナを明確にする
採用ペルソナは「企業が求める人材像」を具体化した仮の人物像のことです。自社が採用したい人物像を明確化しておくことで、採用条件や面接での質問も決まりやすくなります。
注意
ペルソナを決めないまま募集をかけると、選考基準が不明瞭になり、ミスマッチや早期離職のリスクが高まります。
採用ペルソナは、以下の手順で設定していきましょう。
採用ペルソナを設計する手順
- 採用したい人材像を社長や現場に聞く
- 人材を採用する目的を定義する
- 採用したい人材像を書き出す
- 採用市場に合わせたペルソナにする
- ペルソナを経営層や現場のメンバーに確認してもらう
詳しい設定方法は、採用ペルソナの作り方完全ガイド|テンプレートと7ステップのフレームワークにまとめています。
ペルソナを定義すると、新卒採用の成功率を高められるでしょう。
選考プロセスの最適化
採用活動が長期化すると、学生は他社に流れる恐れがあります。そこで短期間かつ納得感を保つ流れを検討しましょう。以下はよくある課題と改善例です。
| 課題 | 改善例 |
|---|---|
| 面接回数が多すぎる | 一次と最終を中心に回数を減らす |
| 日程調整に時間がかかる | オンライン面接を併用して候補日を増やす |
| 社内で評価がばらばらになる | 面接官向けの共通マニュアルを用いて基準を合わせる |
このとき、採用KPIも計測すると、選考プロセスの最適化に役立ちます。選考の妨げになっている箇所を調整してみましょう。
※採用KPIの詳細は、採用KPIを設定する5ステップ|4つの運用のコツと注意点も解説にまとめています。
シンプルな選考ステップを心がけるほど、学生が途中で離脱しにくくなり、採用担当者の負担も軽減されます。
現場社員や経営者が採用活動に参加する
実務を担う社員が企業説明会や面接に参加すると、就活生は具体的な仕事の進め方や職場の雰囲気を理解して、興味を持ってくれやすいです。プロジェクト事例を話せば、入社後の実務を想像できて、会社との相性も把握しやすいでしょう。
ポイント
社員自身も就活生の疑問に答えられるため、企業文化の共有が進み、意欲の高い学生を後押しできます。
また、経営トップが会社の将来像や経営理念を伝えると、組織がどの方向へ進もうとしているかが伝わり、新卒者は中長期的なキャリアパスを描きやすいです。トップと直接話す機会があれば、入社後の期待や目指す姿も明確になり、内定承諾への動機づけが強まります。
社員と経営者にも協力してもらうことで、学生の理解度と納得感が高まるでしょう。
スケジュールの調整やプレゼンの練習など手間は発生しますが、新卒を採用する場合には有効な手段です。
企業情報を魅力的に伝える
学生は待遇だけでなく、職場の雰囲気や成長の機会に興味を持つケースが多いです。そこで画像や動画を使った発信を強化して、働くイメージを提供すると良いでしょう。
具体例
- 社員インタビューをSNSで公開する
- 各部署の取り組みをブログや社内報で紹介する
- 研修やスキルアップの流れをビジュアル化する
数字では伝わりにくい業務内容や学習環境などを具体的に示すほど、就活生が社内で活躍する姿を思い描きやすくなります。
また、求人情報の書き方も工夫すると、興味を持ってもらえる確率が高まります。
応募が集まりやすい求人情報の書き方
- 求めるペルソナを明確にする
- ペルソナが興味を持つ自社の強みをまとめる
- 求人内容を具体的に記載する
- 写真や動画を入れる
- 社内で求人票の内容をチェックする
魅力的な求人情報の書き方は、求人票の書き方のコツを徹底解説|求人票の作り方5ステップで詳しく解説しています。
内定者フォローを徹底する
複数社から内定を得た学生は、入社先を最後まで迷う場合が多いです。そこで、内定後も見学会や懇談を開いて企業とのつながりを継続し、辞退を抑えましょう。
ポイント
早い段階で先輩社員とコミュニケーションをとる機会を用意すれば、疑問をすぐ解消でき、安心感が高まる可能性があります。
候補者を放置すると、他の企業と条件を比較されて離脱につながりかねません。継続的に接点を設けるほど、学生は「ここで働きたい」という気持ちを強めやすいです。
既卒や第二新卒を採用する
新卒枠に限らず、卒業後しばらく経った既卒や、一度就職して転職を考える第二新卒を対象に含めると、母集団が広がります。既卒や第二新卒には以下の表のような特徴があります。
| 対象 | 特徴 |
|---|---|
| 既卒 | 学生時代の就職活動で合わず、改めて企業を探すケースが多い |
| 第二新卒 | 社会人経験があり、基本的な業務習慣を身につけている |
すぐに実務対応が期待できる人材も含まれ、研修負担を下げられるなどのメリットが見込めます。
新卒採用におすすめの手法11選|費用相場も解説
では、新卒採用を進める上で、おすすめの媒体や手法を解説していきます。
新卒採用におすすめの手法
- 就職サイト
- ダイレクトリクルーティング
- 就職エージェント
- インターンシップ
- SNSリクルーティング
- リファラル採用
- 採用動画の作成
- 自社サイトの強化
- 合同説明会
- 大学との連携
- カジュアル面談
各手法のメリットやデメリット、費用相場、成果が出やすい企業の特徴もまとめています。
複数の手法を組み合わせることで成果が出やすいため、採用手法を選ぶ参考にしてみてください。
就職サイト
| メリット | ・多くの就活生にアプローチしやすい ・知名度が低い企業でも目に触れやすい |
| デメリット | ・競合と比較されやすい ・掲載が終了すると効果が薄れやすい |
| 費用相場 | 数十万〜数百万円 ※掲載枠や期間によって変動 |
| 成果が出やすい企業の特徴 | 条件面や魅力を明確に打ち出せる企業 |
多くの就活生は就職サイトを利用するため、掲載すると認知度を補う効果があります。
ポイント
応募数を増やしやすい反面、競合も多いため、求人票の記載内容が曖昧だと埋もれやすいです。
学生は就職サイトで条件面や社内の雰囲気を見比べるため、企業文化や働く魅力をわかりやすく示す工夫が必要です。求人票のキャッチコピーにも工夫して、就活生の目を引きましょう。
関連記事:求人キャッチコピーの例文集50選一覧|6つの面白い心理効果も紹介
掲載費はプランによって変動し、費用対効果を高めるにはアクセス解析や、応募者との連絡を適切に行う姿勢が必要です。
ダイレクトリクルーティング
| メリット | ・ターゲットの学生に直接連絡できる ・潜在層に接触できる |
| デメリット | ・採用担当者の手間が増える ・大量採用には不向き |
| 費用相場 | 数万円〜数十万円 ※サービスや採用する人数によって変動 |
| 成果が出やすい企業の特徴 | ・個別対応に注力できる企業 ・技術系など専門性の高い人材を求める企業 |
ダイレクトリクルーティングは、企業から就活生へ直接アプローチして、スキルや適性が合う人材を見つけやすい方法です。応募を待つ就職サイトと違い、潜在的な就職意欲を持つ学生にも声を届けられます。
例
自社が求めるペルソナに近い人材にアプローチが可能で、ミスマッチを減らしやすいでしょう。やり取りを重ねるほど、選考段階での相互理解が深まりやすいです。
就活生と丁寧にやり取りする工数はかかりますが、その分だけ興味を抱いた学生を逃しにくいです。
配信するメッセージや紹介文を細かく調整して、相手が興味を持つ内容にするほど返信率が上がります。短期間で内定者を増やしたい場合にもおすすめの手法です。
ダイレクトリクルーティングはHELLOBOSSがおすすめ
新卒のダイレクトリクルーティングでは、私たちが提供する「HELLOBOSS」がおすすめです。10万人を超えるユーザーの中から、自社にマッチした人材に直接アプローチできます。
チャットを通じたコミュニケーションで就活生との距離が縮まり、新卒ならではの不安や疑問を解決しながら魅力をしっかり伝えられます。
さらに、管理画面で候補者の進捗を確認しやすいので、内定までの流れを見失いません。
月4,000円から利用できるため、コストを抑えたダイレクトリクルーティングを実現しています。
無料版から始めることも可能です。テストとして使ってみてください。
わずか3ステップで始められるため、さっそくHELLOBOSSを試してみましょう。
就職エージェント
| メリット | ・自社に合う就活生を紹介してもらえる ・採用管理の一部を任せられる |
| デメリット | ・成功報酬が高額になる傾向がある ・採用業務を任せすぎると、就活生の企業理解が浅くなる可能性がある |
| 費用相場 | 採用1名につき80〜100万円程度 |
| 成果が出やすい企業の特徴 | 人材採用にコストをかけられる企業 |
エージェントが企業の希望に合った就活生を紹介してくれるサービスです。人材確保に時間を割きにくい現場では、候補者とのマッチングをサポートしてもらえるため負担が減ります。
ポイント
エージェントは就活生に対して、企業の魅力や業務内容を事前に共有するため、書類選考や面接の通過率が高まりやすいです。
一方、採用人数が多いとコスト費用がかさむ場合があります。少人数の採用や厳選採用を目指す企業であれば、成果を得やすいでしょう。
インターンシップ
| メリット | ・企業と学生双方がリアルな働き方を知れる ・ミスマッチを減らせる |
| デメリット | ・準備や研修に手間がかかる ・報酬など労務管理が必要 |
| 費用相場 | 数万円〜数十万円 ※期間や規模により変動 |
| 成果が出やすい企業の特徴 | 業務フォローできる企業 |
インターンシップは就業体験を通して、学生に実務や社風を体験してもらう方法です。業務内容や社内の雰囲気をリアルに知ることで、入社後のミスマッチや早期離職を減らしやすいです。
ポイント
企業側も学生の働きぶりを観察しやすく、採用面接だけではわからない適性を見いだせるメリットがあります。
インターンからそのまま内定につながる事例も多く、志望度を高められます。ただし、プログラムの設計や受け入れ体制を整える手間がかかるため、実施期間や参加人数を決める際は準備が必要です。
SNSリクルーティング
| メリット | ・広告費を抑えられる ・リアルな雰囲気が伝わり親近感を持ってもらえる |
| デメリット | ・継続的な更新が必要 ・炎上リスクがある |
| 費用相場 | 無料〜数万円程度 ※広告を出稿すると費用がかかる |
| 成果が出やすい企業の特徴 | 社員と協力して情報発信できる企業 |
就活生の多くはSNSで情報を収集し、企業探しや就業イメージづくりに活用しています。企業アカウントから発信される社内の取り組みやメンバーの様子は、就活生にとって親近感を抱きやすい素材です。
ポイント
XやInstagramなどでこまめに投稿することで、検索やタイムライン経由で接点が生まれ、企業の知名度を上げられます。
ただし、投稿を続けないと効果が薄れてしまいます。また、炎上に繋がるケースもあるため、リスクを回避するためのルールづくりも必要です。
低コストで導入しやすい分、社内の連携体制や継続発信の仕組みが成否を左右します。
リファラル採用
| メリット | ・社員の価値観と似たタイプの人材を採用しやすい ・定着率が高い傾向がある |
| デメリット | ・紹介者との人間関係が壊れないように注意が必要 ・紹介される人数が安定しない |
| 費用相場 | 無料〜50万円程度 ※給与への上乗せで支払うのが一般的 |
| 成果が出やすい企業の特徴 | ・社員数が多い企業 ・社員が採用活動に協力的な企業 |
社員や新卒内定者、OBなどの人脈を通じて人材を紹介してもらう手法です。紹介する側が自社の雰囲気をよく知っているため、紹介される就活生が企業と合う確率も高いです。
ポイント
応募者の母集団を補うメリットもある一方、社員と似ている人材が集まりやすく、新しいタイプの人材を探せないことがあります。
自社が望む人物像を社員に共有しておくと、希望の人材が見つかる可能性が上がります。
採用動画の作成
| メリット | ・企業の雰囲気が伝わりやすい ・就活生の印象に残りやすい |
| デメリット | ・動画制作のコストがかかる ・動画を更新していく必要がある |
| 費用相場 | ・数万円〜数十万円 ※委託する業者や動画の内容により変動 |
| 成果が出やすい企業の特徴 | 社内のストーリーやビジョンを映像で明確に打ち出せる企業 |
動画コンテンツは、文字だけではつかみにくい職場の空気感や社員の想いを、映像を通じて訴求できるメリットがあります。SNSや企業HPに掲載すれば、就活生に見てもらいやすいでしょう。
ポイント
応募前に仕事風景をイメージしてもらえるため、興味を深めるきっかけづくりにも役立ちます。
一方で、撮影や編集などの工数を要するため、内容を明確に詰めておかないと効果が薄い映像になる恐れがあります。
自社サイトの強化
| メリット | ・詳細な情報をアピールできる ・本格的に入社を検討している学生にアピールできる |
| デメリット | ・更新や運用に手間がかかる ・デザインが悪いとネガティブな印象を与える |
| 費用相場 | 数万円〜数十万円 |
| 成果が出やすい企業の特徴 | 充実したコンテンツを掲載できる企業 |
就職サイトから企業ホームページへ移動した就活生は、より詳しい情報を求めています。仕事内容や募集要項だけでなく、事業戦略や社員の声を掲載して、入社後のイメージを具体化できるページを構築すると注目度が増します。
注意
更新が途絶えたり、採用情報が見当たらなかったりすると、機会を逃しやすいです。
こまめにメンテナンスして、学生が読みやすく情報を収集しやすいサイトを目指しましょう。先ほど紹介した採用動画も掲載すれば、文章では伝わりにくい雰囲気を伝えられます。
合同説明会
| メリット | ・たくさんの学生にアプローチできる ・その場で質問に答えられる |
| デメリット | ・場所代などのコストがかかる ・他社と比較される |
| 費用相場 | 数万円〜数百万円 |
| 成果が出やすい企業の特徴 | 短時間で魅力を伝えられる企業 |
複数の企業が参加する合同イベントで、応募前の学生と対面でコミュニケーションできる手法です。一度に多くの学生と会えるため、認知度や母集団を拡大しやすいです。
ポイント
短くてインパクトのある訴求ができれば、会場内を生き行く学生に興味を持ってもらえるでしょう。
近年はオンライン形式の合同説明会も増えています。多くの学生とコミュニケーションを取りながら、アピールしてみてください。
大学との連携
| メリット | 学生とスムーズに会える |
| デメリット | 学部や学科をまたいだ連携は、やや調整が難しい |
| 費用相場 | 少額(交通費や資料代など) |
| 成果が出やすい企業の特徴 | 大学と密接な協力関係がある企業 |
学内セミナーや研究室を訪問し、大学と共同で学生との接点をつくる方法です。大学が協力的だとゼミ単位や教授からの紹介も得やすく、目的を持った学生と話しやすくなります。
ポイント
企業説明会やインターンシップを学内で周知してもらえれば、初期接触の障壁が下がり、短期間で多くの学生と交流できる可能性があります。
ただし、大学ごとに求人を扱う体制や優先する学科が違うため、相手の事情に合わせてアプローチしないと成果は限定的になるかもしれません。
カジュアル面談
| メリット | ・潜在層と接触しやすい ・就活生の応募ハードルが下がる |
| デメリット | 採用担当者の負担が増える |
| 費用相場 | ほとんどかからない |
| 成果が出やすい企業の特徴 | ・柔軟に面談のスケジュールを組める企業 ・面談の工数をかけられる企業 |
正式な面接に移る前に、就活生と軽い雑談や意見交換する手法です。「厳しい選考」という印象を与えないため、就活生が気軽に応募の第一歩を踏み出しやすくなります。
ポイント
会社の業務や職場の雰囲気をフランクに伝えられる利点もあり、応募者の本音や価値観を見極める場にもなります。
ただし、面談の準備や日程調整に時間を要するので、担当者が複数の学生に対応する場合は負担が増えやすいです。企業側の姿勢やコミュニケーション力が合否を左右する場合もある点に留意してください。
AIのダイレクトリクルーティングで新卒採用に成功した事例

ここでは、AI採用ツール「HELLOBOSS」を活用し、新卒採用や採用難易度の高い職種で成功した企業の事例を紹介します。
新卒採用が難しい状況を打破した成功事例
新卒採用が難しいと感じている企業様も、AIを活用したダイレクトリクルーティングで打開策が見つかるはずです。
26卒で100名のエントリーを獲得した自動車ディーラーの事例
ある自動車ディーラーでは、26卒採用に向けて説明会やインターンの集客が課題となっていました。
ナビサイト経由だけでは、優秀な学生の確保が困難だったのです。
そこでHELLOBOSSを活用し、ナビサイト未登録のユーザーに対して早期にアプローチを実施。
その結果、これまで獲得できていなかったハイクラス層を含め、100名のエントリー獲得に成功しました。
新卒採用が難しい層へは、早期の直接的なアプローチが有効です。
毎月40名以上の応募を獲得した飲食サービス業の事例

飲食サービス業の「串カツ田中」では、他媒体で苦戦していた中途採用における母集団形成が課題でした。
同社はSocial+プランを導入し、AI学習による精緻なターゲティングを実施して求職者にアプローチを行いました。
導入後はコンスタントに毎月40名以上の応募を獲得し、有効応募率も高い水準を維持しています。
採用が難しい業界でも、AIを活用すればターゲット人材を効率的に集められます。
地方で500名以上の応募を獲得した宿泊業の事例

宿泊業の「星野リゾート」では、地方エリアでの採用難易度が高く、従来の求人媒体ではターゲット層との接点を持てずにいました。
そこでSocial+プランを活用し、SNSを通じた地域特化型プロモーションを展開して潜在層にもアプローチを実施。
結果として、これまでリーチできていなかった層を含め、500名を超える応募を獲得することに成功しました。
立地条件で採用が難しい場合でも、手法を変えれば母集団は形成可能です。
新卒採用でよくある質問
最後に、新卒採用でよくある質問に答えていきます。
就活の売り手市場はいつまで続きそう?
未来のことなので断定はできませんが、近年の新卒採用の状況を見ると、売り手市場はまだ続くと考えられます。主な理由は以下のとおりです。
売り手市場が続く可能性がある理由
- 少子化
- 団塊世代の大量退職による若手獲得の競争激化
- ITなど成長産業での人材不足
売り手市場はまだ数年は続く可能性があります。
もちろん大規模な経済危機や海外情勢の急変など、予測不能な外的要因で変動するリスクはあるでしょう。しかし、人口構造と企業側の採用ニーズを考えると、当面の間は「就活生優位の売り手市場」が続くと見込まれます。
新卒採用と中途採用はどっちが難しい?
企業規模や業界、採用ターゲットによって「新卒採用」と「中途採用」のどちらが難しいかは変わります。
ポイント
全体的な傾向として、新卒採用は「母集団形成」と「内定後の辞退対策」が難しくなりがちです。一方、中途採用は「即戦力の確保」と「採用ターゲットに合う人材との出会い」が難しいと言われています。
また、どちらも人材の見極めが難しいのは共通しています。新卒採用ではポテンシャルを見ますが、面接だけでは把握しにくいケースもあるでしょう。中途採用では、能力のある人材でも、新しい環境に適応できず辞めてしまう人もいます。
人材不足の背景もあるため、広義でいえば、新卒採用も中途採用も難しい状況です。
企業説明会に1人しかいない…
企業説明会を開催したのに、一人しか来ないと落ち込みますよね。次回のためにしっかり原因を見直し、対策を再検討すれば、次は良い結果になる可能性があります。
先ほど紹介した方法で、まだ実践できていないものがあれば検討してみてください。
新卒採用を成功させる7つのコツ
- 採用スケジュールを早める
- 採用ペルソナを明確にする
- 選考プロセスの最適化
- 現場社員や経営者が採用活動に参加する
- 企業情報を魅力的に伝える
- 内定者フォローを徹底する
- 既卒や第二新卒を採用する
できるところから対策していきましょう。
新卒で採用した人材の育成はどうすればいい?
新卒で採用した人材が早期離職せず、現場で力を発揮できるようにするには、計画的な育成とフォロー体制が必要です。以下のポイントを押さえておくと、新入社員が自社の文化や仕事にスムーズに適応し、モチベーションを保ちやすくなります。
| 取り組むこと | 概要 |
|---|---|
| オンボーディングの整備 | ・入社初期のサポート体制を強化する ・業務フローやマニュアルを整備する |
| ベーシック研修の実施 | ビジネスマナーやコミュニケーションなどの基礎研修と、業務に特化した研修を実施 |
| OJTの活用 | ・メンターをつけてフォローする ・定期的なフィードバックを実施 |
| 社内コミュニケーションの強化 | ・新入社員が孤立しないように、チームのイベントで交流を促す ・不明点や不安点をすぐ相談できる環境を作る |
新人育成の参考にしてみてください。
まとめ|新卒採用のコツを実践して採用難を乗り越えましょう
新卒採用が難しい状況が続いていますが、以下の手法を組み合わせながら対策してみてください。
新卒採用におすすめの手法
- 就職サイト
- ダイレクトリクルーティング
- 就職エージェント
- インターンシップ
- SNSリクルーティング
- リファラル採用
- 採用動画の作成
- 自社サイトの強化
- 合同説明会
- 大学との連携
- カジュアル面談
くりかえしですが、新卒のダイレクトリクルーティングでは、私たちが提供する「HELLOBOSS」がおすすめです。10万人を超えるユーザーの中から、自社にマッチした新卒人材に直接アプローチできます。
月4,000円から利用できるため、コストを抑えたダイレクトリクルーティングを実現しています。
無料版から始めることも可能です。テストとして使ってみてください。
わずか3ステップで始められるため、さっそくHELLOBOSSを試してみましょう。
貴社の新卒採用の参考になれば幸いです。