「採用活動にAIって使えるの?」
「採用にAIを導入するメリットとデメリットは?」
こういった疑問をお持ちの採用担当者様向けの記事です。
この記事でわかること
- 採用活動にAIを導入するメリットとデメリット
- AI採用の成功事例
- AIで効率化できる6つの採用業務
結論、採用活動にAIを導入することで、採用業務が効率化したり、採用の目標を達成しやすくなります。
AIが業務をサポートすることで、人はクリエイティブな採用業務に集中できるからです。
「でも、AIってよくわからない…」と不安に思いますよね?
この記事では、採用活動においてAIの活用方法を詳しく解説します。
業務ごとにおすすめのAIツールも紹介するので、最後まで読んでみてください。
おすすめのAI採用ツール
AIを活用して採用の成果を最大化するには、私たちが提供するAI採用ツールの「HELLOBOSS」がおすすめです。
10万人以上のユーザーの中から、貴社が求める人材をAIが自動で推薦します。
また、候補者とチャットでやり取りできるので、返信率も高いです。
無料から利用できるため、コストを抑えつつ、AIを使って目標を達成したい人事担当者様は、今すぐ「HELLOBOSS」を見てみてください。

Contents
AI採用とは?
履歴書や面接評価など、採用プロセスの一部をAIで自動化・効率化する手法のことです。人間だけでは相当な時間を費やす書類選考や応募者分析を、学習データをもとに高速かつ客観的に処理できます。
ポイント
最近は録画面接の表情解析や適性推定などでも、AIの導入が進んでいます。
今後はAI技術の発達に合わせて、採用活動の幅がさらに広がるでしょう。
AI採用が注目されている背景
AIを使った採用手法は人手不足や競争が激しい現状に対応する手段として、多くの企業が導入を検討しています。採用担当者の負担が軽減され、採用の質も高まりやすい点も注目されています。
AI採用が注目されている主な理由
- 選考段階でのデータ分析が早い
- 採用担当者の主観を減らして客観的な評価が可能
- 面接予約や質疑応答を自動化できる
- 優秀な人材を早めに確保しやすい
AI技術の発達やサービス料金の低下も追い風になっています。
AI採用のメリット5選
それでは、AI採用の具体的なメリットを解説していきます。
AI採用のメリット
- 採用業務が効率化され工数が減る
- 採用コストを削減できる
- 公平な選考につながる
- 多くの応募者を選考できる
- データを活用した採用戦略の構築が可能
AIを活用した採用を検討している企業の方は、以下のメリットを参考にしてみてください。
採用業務が効率化され工数が減る
AI導入で人力に頼る部分を減らし、大量の書類選考や面接スケジュール調整が短時間で済むようになります。
例
応募者の履歴書を自動解析して必要な要素を抽出したり、チャットボットで問い合わせに対応したりと、担当者が対応しなくても回る仕組みを構築しやすいです。
忙しい季節でも作業負担が抑えられるため、全体の進行がスムーズに進みやすいです。以下は業務効率化の例です。
人間だけで回すと大変な作業でも、一部をAIに任せれば効率的にこなせます。採用担当者は候補者との対話や社内調整など、本来注力したい業務に集中しやすくなります。
採用コストを削減できる
AI導入は時間や人件費の面でもコストカットが可能です。面接日程の調整や合否連絡などを自動化すれば、担当者の残業を減らしたり、求人広告への過度な出稿を抑えたりできます。
以下は採用コスト削減につながりやすい項目です。
削減できる採用コスト
- エージェント手数料
- 求人広告の掲載費
- 採用担当者の残業代
- 遠方面接時の交通費
- 書類印刷代
採用予算を最適化しながら、多くの候補者にアプローチできます。
公平な選考につながる
人間だけで人材を評価すると、無意識の偏見や先入観が混ざりやすいです。AIを活用して合否を判定すると、公平性が高まる可能性があります。
例
外見や学歴の印象に左右されにくく、候補者が自身のスキルや適性を客観的に見てもらいやすいです。
あらかじめ統一した指標を設定してスコアリングすれば、ヒューマンエラーを減らせます。最終的には面接官の感覚と組み合わせることで、より精度の高い選考が可能です。
多くの応募者を選考できる
AIを活用することで大量のエントリーがあっても、担当者がパンクしにくくなります。例えばPR動画を複数本まとめて受け付ける場合でも、自動タグ付けと要点抽出で比較が容易です。
こうした仕組みがあれば、活躍しそうな人材を逃すリスクを下げやすいでしょう。以下では大人数の応募者に対応しやすいAIの具体例です。
上記のように映像解析や自動メッセージ送信を組み合わせれば、多人数が一度に応募しても対応の抜け漏れが起きにくいです。採用担当者が把握しきれない規模でも、AIの力を借りながら網羅性を高めやすいでしょう。
結果的に優秀な人材を取りこぼすリスクが減り、質と量の双方で採用活動を進められます。
データを活用した採用戦略の構築が可能
AIを導入した場合、選考過程や内定者の情報がデジタルデータとして蓄積されます。大量の履歴書や面接情報を数値化すれば、どんなタイプの応募者が内定に至りやすいか分析しやすいです。
AIによるデータ活用の例は以下のとおりです。
データを活用すれば、属人的な判断に依存しすぎず客観性を保った戦略を組み立てられます。
継続的に分析すれば、採用成功率の向上だけでなく離職対策にも役立つため、組織全体の人事施策が洗練されやすいです。
AI採用のデメリット4選
AIを活用した採用はメリットが多いですが、一方でデメリットも存在します。
AI採用のデメリット
- AIの判断は絶対ではない
- 応募者が不安や抵抗を感じる場合がある
- データ量が十分にないと精度の高い判断が難しい
- データだけではわからない情報を見落とす可能性がある
デメリットを理解した上でAIを導入していきましょう。
AIの判断は絶対ではない
AIは膨大なデータを基に統計的手法で推定しますが、想定外の誤情報を提示するリスクが高いです。この現象は「ハルシネーション」と呼ばれ、実在しない内容や矛盾を含む回答を正しい事実のように示すことがあります。
注意
例えば、候補者の経歴にない実績を生成し、まるで本物のように説明してしまうこともあります。
こうした誤りを防ぐには、AIに正確な情報を入力することや、採用担当者が目を通して整合性を確認することが求められます。また、最終的な評価を安易にAIに任せないことも重要です。
応募者が不安や抵抗を感じる場合がある
応募者の中には、AIによる評価に対して不安や抵抗を感じる方もいます。特に面接での表情解析や音声分析などは、プライバシーに関する懸念を抱かれやすいです。
企業側は事前に選考プロセスを透明化し、AIをどのように活用するかを説明することが大切です。候補者の理解を得られれば、より良い関係性を築けるでしょう。
データ量が十分にないと精度の高い判断が難しい
AIの判断精度は、学習に使用するデータの質と量に大きく依存します。過去の採用データが少ない企業や新しい職種では、AIが適切な判断を下すのが困難な場合があります。
また、偏ったデータで学習したAIは、偏見を助長する可能性もあるため注意が必要です。
データだけではわからない情報を見落とす可能性がある
AIは履歴書やテスト結果を重視しますが、人柄や空気感など数値化しにくい要素を正確に評価しきれない場合があります。例えば以下のようなポイントは面接官や現場メンバーが直接確認しないと見逃しやすいです。
AIで判定しにくい要素
- 面接時の温かい表情や笑顔
- 会話の端々から感じられる仕事への興味
- 転職理由を話すときのトーンや誠実さ
- チームと合いそうな雰囲気
対話しないと把握できない魅力や気遣いは、AIだけでは見えにくいです。面接の場で応募者の個性を立体的にチェックし、人間とAIを組み合わせた選考が良いでしょう。
AI採用を始める際の注意点
実際にAI採用を始める場合は、以下の3つに注意しましょう。
AI採用の注意点
- データの透明性を確保し、バイアスを排除する
- 人間の判断と併用する
- プライバシーとデータ管理に注意する
こうした取り組みで、AIの真価を発揮できて効果的な採用活動を実現できます。
データの透明性を確保し、バイアスを排除する
採用では、性別や年齢などに基づく差別的な判断を避けなければなりません。しかし、AIに偏ったデータを学習させると、公平な評価ができない恐れがあります。
例
過去の採用で男性が多いなら、男性優位の判定になるケースが考えられます。
これまでの採用履歴が偏っている場合は、AIに「今後はこんな採用をしたい」という希望を入力すると良いでしょう。例えば、ChatGPTに学習させる際は以下のように指示してみてください。
ChatGPTへの指示文の例
自社の採用基準を学習してほしいです。
その際、過去の採用履歴のデータと「今後はこんな人を採用したい」という理想の未来像のデータを渡すので、これらを元に採用基準のデータにしてください。
#過去の採用履歴のデータ
〜〜〜〜〜〜〜〜〜#「今後はこんな人を採用したい」という理想の未来像のデータ
〜〜〜〜〜〜〜〜〜
こうした対策でAIによるバイアスを減らしやすくなります。
人間の判断と併用する
AIはデータ処理に優れており、大量の応募を短時間で評価する段階では効率的です。一方で、現場の温度感や本人の意欲は人間の対話がないと把握しにくいです。
両者が協力する仕組みを整えると、スキル評価と人柄の見極めを進めやすくなるでしょう。
AIだけに頼らず、採用担当者が対話し、企業文化や応募者の考え方を共有する姿勢が欠かせません。面接や入社後の研修で人間がフォローすれば、ミスマッチを抑えられます。
プライバシーとデータ管理に注意する
採用活動にAIを使う際は、プライバシーやデータ管理に注意してください。AIに個人情報を入力すると、サーバーに記録される関係で、設定ミスやハッキングなどをきっかけに第三者へ流出してしまう危険があります。
具体的には以下のようなケースで情報が漏洩する可能性があります。
AIで情報漏洩するケース
- 入力したデータを別の利用者画面に誤表示するバグが発生
- クラウドサービスでセキュリティ不備がありデータが無防備になる
こうしたリスクを防ぐためには、以下のような対策が必要です。
AIから情報漏洩を防ぐ対策
- そもそもAIに個人情報を入力しない
- セキュリティが強い専門ツールを使う
- 社内でガイドラインを定めて機密事項を扱わない
- 保存データの暗号化と通信の暗号化を徹底する
これらを組み合わせて実践すれば、AIの利便性を保ちながら個人情報の保護を高めやすくなります。
AIで効率化できる主な採用業務|おすすめAIツールも紹介
AIを活用できる主な採用業務を詳しく解説していきます。
AIを活用できる主な採用業務
- 書類選考・スクリーニング
- マッチング
- スケジューリング・チャットボット
- スカウトメール文のクオリティ向上
- AI面接
- 採用活動のコンサルティング
これらの領域でAIを活用する方法について、具体的に見ていきましょう。おすすめのAIツールも具体的に紹介します。
書類選考・スクリーニング
多くのエントリーシートを人の目で確認すると時間がかかり、見落としも増えがちです。自然言語処理技術を使ったAIなら、履歴書の文章から必要なスキルや経歴を素早く抽出し、基準に合う候補者を優先表示しやすくなります。
おすすめのAIツール
- ChatGPT
- Claude
- Gemini
これらは対話型AIです。個人情報以外の応募者の履歴書テキストをAIに送り、求人要件とのマッチ度合いを評価できます。ChatGPTは履歴書・職務経歴書から特定のキーワードやスキルを自動抽出し分析できるため、大量の応募書類を人手でチェックする手間を減らせるでしょう。
採用活動に使うと、以下のようなメリットがあります。
導入するメリット
- 応募数が膨大でも短時間で完了まで進めやすい
- 担当者の読み疲れが減り、見逃しリスクを抑えられる
- データが増えるほどスクリーニングの精度を向上させやすい
担当者が最終判断すれば、単調作業を減らしつつ精度を高めやすくなるでしょう。
マッチング
膨大な応募者の中から適任者を探すときは、AIにスキルや経歴の類似度を数値化してもらって、候補者を推薦してもらうと便利です。
おすすめのAIツール
「HELLOBOSS」を使えば、10万人以上のデータベースから自社が求める人材をAIが推薦してくれます。
候補者とチャットもできるため、返信率が高く、ダイレクトリクルーティングに向いています。
こうしたマッチング系のAIツールを導入するメリットは以下のとおりです。
導入するメリット
- 要件に合う候補者を一括抽出でき、見逃しを減らせる
- 採用担当者が候補者を探す時間を削減できる
- 採用データを蓄積すれば、マッチングの精度が上がりやすい
同じ条件でも異なる視点で候補者を発掘できる可能性もあるため、多様な人材確保につながるでしょう。
スケジューリング・チャットボット
候補者と連絡を取り合う工程は、案内メールや日程調整で担当者の負荷が大きいです。AIチャットボットを導入すれば、よくある質問への自動応答や面接日程の自動候補提示ができます。
スケジューリングやチャットボットにおすすめのAIツールは、以下がおすすめです。
こうしたAIツールを導入するメリットは以下のとおりです。
導入するメリット
- 24時間365日対応で、問い合わせを放置せずに済む
- 日程の再調整やリマインドを自動化し、人為的ミスを軽減しやすい
- 候補者の満足度を上げながら、担当者の事務作業を圧縮できる
大量応募でも対応品質を保ちやすく、コミュニケーションロスを抑えやすくなります。
スカウトメール文のクオリティ向上
転職潜在層へ送るスカウトメールは、文面次第で開封率が大きく変わります。AIがターゲットの職歴や興味分野を分析した上で、最適な件名や言葉を提案すれば、反応率を高めやすいです。
例
候補者がネット上に公開している情報をChatGPTに学習させると、その候補者が興味を引くスカウトメールの文面を作成してくれます。
採用担当者がメール文を作る手間を省きつつ、反応率が上がります。
ちなみに、スカウトメールのコツは、【徹底比較】ダイレクトリクルーティングのメリット5選|他の手法と何が違う?も参考にしてみてください。
AI面接
対面形式で膨大な候補者に対応するのは負担が大きいですが、AI面接を活用すると時間と手間を節約しやすいです。ビデオ通話や録画形式でAIが質問を提示し、候補者の表情や回答内容を分析します。
AI面接におすすめのツールは以下のとおりです。
こうしたAIツールをAI面接に使うと、以下のメリットがあります。
導入するメリット
- 24時間対応が可能
- 表情や声の変化を解析し、評価のブレを減らしやすい
- 一次選考をAIに任せれば、担当者は深い面談に専念しやすい
現場と組み合わせれば、公平性とコミュニケーションの両立を図りやすくなります。
採用活動のコンサルティング
採用活動をしていると、思うように成果が出ず悩むことがあります。しかし「社内に相談できる人がいない」という採用担当者も多いでしょう。
おすすめのAIツール
例えば「ChatGPT o1 pro」を使えば、高精度のコンサルティング結果を返してくれます。仕事の悩みを相談すると、具体的な解決策がわかります。
自社の状況を細かく伝えるほど、実践的なアイデアを出力してくれるでしょう。有料のコンサルタントより安価にコンサルティングを受けられるメリットがあります。
AI採用で効果が出やすい企業の特徴
「AIに興味はあるけど、実際に導入するか迷う…」という方もいるでしょう。以下に該当する場合は、AI採用と相性が良いので導入を検討してみてください。
AI採用で効果が出やすい企業の特徴
- 応募が多くて選考業務が忙しい企業
- 属人的な採用でミスマッチが多い企業
- 採用担当者のスキルやリソースが不足している企業
- スピーディーな採用で他社と差別化したい企業
1つでも該当していれば、AIで採用活動を効率化できる可能性があります。詳しく解説していきます。
応募が多くて選考業務が忙しい企業
大量の応募者を処理する必要がある企業は、AI採用による効率化の恩恵を大きく受けられます。
効果が出やすい企業の例
- 全国規模で採用活動を行う大手・中堅企業
- 知名度が高く応募者が集中する人気企業
- 新卒一括採用で数千件の応募を扱う企業
AIによる自動スクリーニングやチャットボットでよくある質問を処理すれば、読み込みや問い合わせ対応に割く時間が減りやすいです。
以下のようなツールを活用して、応募者全員に的確なアプローチを続けながら担当者の作業量を抑えると効率的です。
書類レビューや問合せ対応をAIに任せると、担当者は最終判断や面接での深いやりとりにリソースを回せます。応募者全員に対して均等にフォローできるため、採用ブランディング向上にもつながりやすいです。
属人的な採用でミスマッチが多い企業
経験に頼った選考が続くと、面接官によって評価基準がばらばらになりやすいです。 AIが候補者の経歴や適性を数値化して提示すれば、人による見落としを軽減しやすくなります。
ポイント
個性がある人材の採用を逃さず、かつ不必要な再募集を減らしやすいです。
AIの支援によって客観的な視点を導入すれば、事業の方向性に合った人材を合理的に選べます。特に配属後の早期離職を防ぎたい場合は、応募者の意欲やカルチャーフィットを数値的に把握できるAI適性診断なども効果的です。
採用担当者のスキルやリソースが不足している企業
人材・時間・予算などの採用リソースに制約がある企業では、AI導入の費用対効果が高いです。
効果が出やすい企業の例
- 専任の採用担当者がいない中小企業
- 採用経験の浅い担当者が中心の企業
- 採用予算が限られているスタートアップ企業
AIを活用することで、初期選考や面接調整といった定型業務を自動化し、限られた人的リソースをコアな採用活動に集中できます。採用ノウハウが蓄積されていない企業では、AIが標準化された質問や評価基準を提供することで、経験の浅い担当者でも質の高い選考が可能です。
スピーディーな採用で他社と差別化したい企業
求職者との接触から内定までのスパンを短縮すれば、優秀な人材を他社に奪われにくくなります。AIを使って日程調整や候補者の合否判定を効率化すれば、面接や内定通知までの速度が上がりやすいです。
以下のようなAIを取り入れることで、募集開始から内定出しまでの流れを加速できます。
候補者を長く待たせずに進めると、内定辞退や他社への流出が減ります。担当者の都合だけでなく、応募者の希望にも合わせやすいため、企業イメージ向上にもつながるでしょう。
採用活動にAIを導入して成功した企業の事例

ここでは、実際に採用活動でAIを取り入れて成果を上げた企業の事例を紹介します。
AIを活用して採用に成功した企業の事例
具体的な成果と活用ポイントを1つずつ見ていきましょう。
毎月40名以上の応募を獲得した飲食業のAI活用事例
飲食サービス業の「串カツ田中」では、他媒体で苦戦していた中途採用の母集団形成に悩んでいました。
解決策として、AI学習による精緻なターゲティングができるHELLOBOSSのSocial+プランを導入。
結果、属性の整った人材から毎月40名以上の応募をコンスタントに獲得することに成功しています。
AIが学習することで、質の高い応募者を効率的に集めることが可能です。
地方で500名超の応募を獲得|宿泊業のAI活用事例

宿泊業の「星野リゾート」では、地方エリアでの採用難易度が高く、既存媒体ではリーチできない層へのアプローチが課題でした。
そこで、HELLOBOSSでSNSを活用した地域特化型プロモーションを展開し、潜在層・顕在層の双方にアプローチ。
その結果、これまで接点を持てなかった層も含め、500名を超える応募の獲得に成功しました。
立地のハンデがあっても、AIとSNSを駆使すれば大規模な母集団形成が可能です。
獲得単価を下げて応募数増|教育業のAI活用事例
教育業の「個別教室のトライ」では、塾講師のアルバイト採用において、獲得単価(CPA)の高騰が課題となっていました。
HELLOBOSSのAI生成の動画広告を導入してPDCAを回した結果、応募数が純増。
過去平均よりも安価なCPAで応募を獲得することに成功しています。
AIによるクリエイティブ作成と運用最適化は、採用コストの削減に大きく貢献します。
履歴書提出率がアップ|小売業のAI活用事例
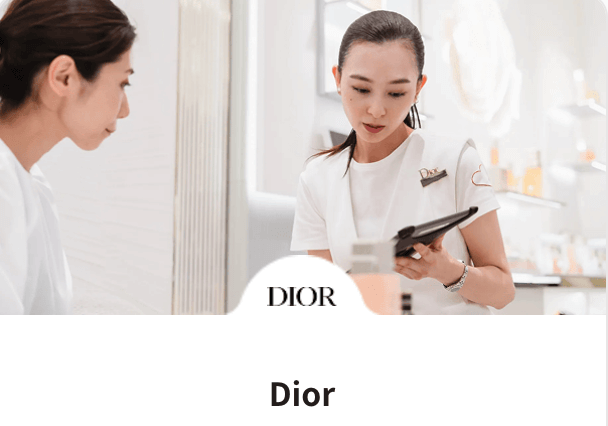
卸売・小売業の「Dior」では、採用コストと工数の削減、および応募時の履歴書提出率の向上が課題でした。
そこでHELLOBOSSを導入して、求職者側の「AI履歴書作成機能」を活用しつつ、Social+で激戦区のエステティシャン採用を実施。
結果、履歴書提出率がアップし、難易度の高いエリアでの採用にも成功しました。
AI支援機能で応募ハードルを下げることは、選考の歩留まり改善に直結します。
3名推薦で3名採用決定|情報通信業のAI活用事例
情報通信業の株式会社Yoiiでは、難易度の高い「審査」や「経理・財務ポジション」の採用が課題でした。
そこでHELLOBOSSのデータベースとAIマッチングを活用し、候補者へピンポイントにアプローチ。
その結果、半年間で3名の推薦に対し3名の採用決定という、非常に高精度な実績を創出しました。
専門性が高い職種こそ、AIによる精緻なマッチングが効果を発揮します。
地方のドライバー採用に成功した運輸業のAI活用事例
ある地方の運輸業では、ドライバー採用の母集団形成に苦戦していました。
そこでHELLOBOSSを活用し、ターゲットに対して的確なアプローチを実施。
有効応募率は90%を超え、既存媒体と比較して一人当たりの採用単価を30%削減することに成功しました。
採用活動にAIを活用すると、採用難易度が高いエリアや職種における解決策となり得ます。
わずか2週間で2名採用|サービス業のAI活用事例
サービス業のフィナンシャルフィールパートナーズでは、経理経験者のアルバイト採用において、母集団形成とコストが課題でした。
AIマッチングとスカウト機能を活用できるHELLOBOSSのProプランを導入し、効率的に候補者へアプローチ。
その結果、導入からわずか2週間で2名の採用成功というスピード内定を実現しています。 AIが最適な人材を推薦することで、採用期間を劇的に短縮できた好例です。
採用活動にAIを導入する4ステップ
それでは、採用活動にAIを導入する具体的な手順を解説していきます。
採用活動にAIを導入する4ステップ
- 導入準備【目的・要件の明確化】
- システム・ベンダーの選定
- 導入・運用フェーズ
- 成果検証と改善
ステップに沿って、さっそくAIを導入していきましょう。
①導入準備【目的・要件の明確化】
どんな成果を求めるかを考えて、必要機能を言語化するとAI導入がブレにくくなります。以下の表を参考に準備を進めていきましょう。
大まかなゴールが決まれば、社内で使うデータや評価観点を整理して具体的な要件へと落とし込みやすくなります。また、事前の準備がしっかりしているほど、導入後のトラブルや修正を減らせる可能性が高まります。
②システム・ベンダーの選定
要件を固めたら、条件に合うシステムと導入をサポートする企業(ベンダー)を比較検討します。以下の表は選定時に着目したいポイントです。
選定の段階でベンダーから成功事例や失敗例を聞くと具体的なイメージが持ちやすいです。また、無理のない導入計画を一緒に作る姿勢を確認しましょう。
③導入と運用
システムを決めたら、自社の採用フローに合わせた連携や初期設定を進めます。
導入後は、担当者がAIの出力を検証して、誤判定があれば早めに調整しましょう。カスタマイズが可能な場合は、運用しながら微調整を繰り返して精度を高めるのがおすすめです。
ポイント
困ったときはベンダーと連絡を取り、設定やアルゴリズムを見直すとスムーズに改善できます。
日常的に面接官や採用担当がログを見返す文化をつくると、運用ノウハウが蓄積されやすいです。
④成果検証と改善
一定期間運用したら、採用成果や工数削減効果を検証します。以下のようにPDCAサイクルを回せば、AIの効果を最大化しやすくなります。
AIから得た数値や傾向を基に、次の採用シーズンに向けた改善策を立案するとスムーズです。また、導入後もAI関連の勉強会や最新事例をチェックすれば、社内の知見が深まり、精度向上と安定運用を実現しやすくなります。
AI採用でよくある質問
最後に、AI採用についてよくある質問に答えていきます。
AIの誤判定による採用ミスは起きない?
AIも学習データや設定次第で誤判定する可能性があります。以下のようなケースで誤りが生じやすいです。
AIが誤判定する可能性
- 学習データが偏っていて、特定スキルや属性に過剰反応する
- 表面的なキーワードだけで判断し、人柄や潜在力を見逃す
- バージョン更新や運用ルールの変更で選考基準がずれる
念頭に置いておきたいのは、AIが出す評価をあくまで参考情報として扱う姿勢です。最終判断を担当者がチェックするフローを整えておけば、見当はずれな合否決定を抑えられます。
導入コスト・ROIはどのくらい?
初期投資はシステム規模やカスタマイズ範囲で差があります。月額料金制の場合は1ユーザーあたり数千円のAIツールもあります。
費用対効果を検証するにはROI(投資利益率)を計算します。
ROIの計算式
ROI=(AI導入によって生まれる利益-導入費用)÷導入費用×100(%)
例えば書類選考をAIに任せて、人事担当者の年間人件費を100万円分削減できたとします。導入と運用で年間50万円のコストがかかった場合、ROIは以下のとおりです。
ROIの計算例
(100万円-50万円)÷50万円×100=100%
導入当初に費用が発生しても、長期で見れば工数削減や迅速な採用による機会損失の防止が期待できます。
AI導入で人事担当や面接官の仕事は消える?
書類スクリーニングや問い合わせ回答を任せれば、人間の作業が減る面はあります。
しかし人事担当や面接官の業務がすべてAIに置きかわるわけではありません。AIはデータ分析や定型対応に強みがありますが、応募者との信頼関係づくりやチームへのカルチャーフィット判断などは「人ならではの視点」が欠かせないです。
ポイント
スクリーニング作業から解放された採用担当が、面接や社内フォローに集中する流れが生まれやすくなります。
役割の比重が変わる結果として、人が担う部分は高度でクリエイティブなタスクにシフトしていくでしょう。
まとめ|さっそくAI採用を実施してみましょう
最後にもう一度、AI採用のメリットをまとめておきます。
AI採用のメリット
- 採用業務が効率化され工数が減る
- 採用コストを削減できる
- 公平な選考につながる
- 多くの応募者を選考できる
- データを活用した採用戦略の構築が可能
さっそく採用活動にAIを導入して、採用の成果を最大化していきましょう。
おすすめのAI採用ツール
AIを活用して採用の成果を最大化するには、私たちが提供するAI採用ツールの「HELLOBOSS」がおすすめです。
10万人以上のユーザーの中から、貴社が求める人材をAIが自動で推薦します。
無料から利用できるため、コストを抑えつつ、AIを使って目標を達成したい人事担当者様は、今すぐ「HELLOBOSS」を見てみてください。











