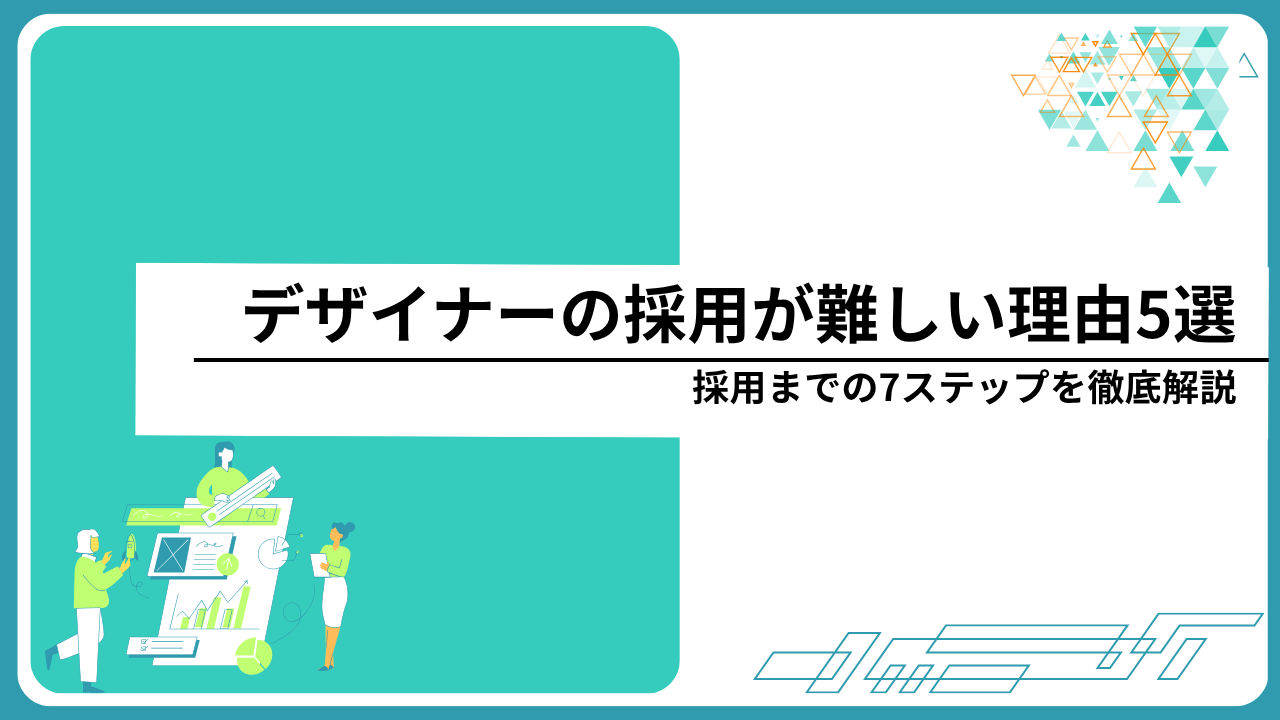「デザイナーの採用が難しい…」
「デザイナーを採用するコツを知りたい」
とお悩みの人事担当者様に向けた記事です。
この記事でわかること
- デザイナーの採用が難しい理由5選
- デザイナーを採用するための7ステップ
- デザイナー採用におすすめの手法8選
デザイン需要が高まっているにも関わらず、デザイナーの数が足りておらず、採用が難しい状況が続いています。
「そうは言っても、何とか良いデザイナーを採用したい…」と思いますよね?
この記事では、デザイナーを採用し、長く活躍してもらうコツがわかります。
デザイナーを採用するノウハウを確立したい人事担当者様は、最後まで読んでみてください。
デザイナーにダイレクトアプローチできます
「前置きはいいから、早くデザイナーを採用するコツを知りたい!」という方は、デザイナーを採用するための7ステップへジャンプしてみて下さい。
Contents
デザイナーの採用が難しい理由5選
「デザイナーの採用が難しい」と言われる主な理由は、以下の5つです。
デザイナーの採用が難しい理由
- デザイナーの人数が少ないから
- デザインの需要が拡大しているから
- 採用手法が多様化しているから
- フリーランスのデザイナーが増えているから
- デザイナーを採用していいか判断が難しいから
まずは採用においてどんな問題があるか知ってから、この後に具体的な対策を立てていきましょう。
1つずつ解説していきます。
デザイナーの人数が少ないから
そもそもデザイナーの数が少ないため、採用活動が難しくなっています。
2015年の経済産業省のデータによると、デザイナー数は約19万人です。
同時期の日本の就労人口は6376万人であり、デザイナーの人口比率はわずか0.29%しかないとわかります。
出典:総務省統計局|労働力調査(基本集計)平成27年(2015年)平均(速報)結果の要約
ちなみに、同時期の建設業と介護業界の就労人口と比較すると、以下のようになります。
| 業界 | 人口 |
|---|---|
| デザイン | 約19万人 |
| 建設 | 約500万人 |
| 介護 | 約184万人 |
出典:国土交通省|建設業を巡る現状と課題/厚生労働省|介護職員数の推移
いかにデザイナーが少ないかわかるはずです。転職市場に出てくるデザイナーはさらに限定されるため、採用競争は必然的に激化します。
デザインの需要が拡大しているから
デザイナーの需要は年々急速に拡大しています。従来のグラフィックデザインや印刷物のデザインに加え、WebデザインやUI/UXデザインなど、デジタル領域での需要が増加しました。
特にDX(デジタルトランスフォーメーション)の進展により、多くの企業がデジタルサービスを展開しはじめ、顧客体験を重視したデザインの必要性が高まっています。
例えば、デザインが求められる動画配信やゲーム・アプリといった分野で、需要が伸びています。
出典:総務省|第1部 5Gが促すデジタル変革と新たな日常の構築
デザイナーの需要拡大と役割の多様化が進む一方で、これらの領域で十分な経験を積んだデザイナーが足りていない状態です。需給バランスが崩れ、優秀なデザイナーの採用が困難になっています。
採用手法が多様化しているから
デザイナーの採用市場では、従来型の採用手法の効果が低下しています。求人広告の掲載や人材紹介会社の活用だけでは、優秀なデザイナーの獲得が難しくなってきました。
特にスキルの高いデザイナーは、求人サイトやエージェントを介さずに直接企業へ応募するケースが増加しています。デザイナーの市場価値が上昇し、自身のキャリアプランに沿った転職先を明確にもつ人材が多いです。
最近では以下のような採用手法が活発です。
デザイナー向けの採用手法
- リファラル採用
- ダイレクトリクルーティング
- デザイナー同士のコミュニティや人脈の活用
デザイナー同士のコミュニティや人脈は独特で、リファラル採用との親和性も高く、転職市場に現れない優秀な人材との接点を生み出せます。
採用手法の多様化に対応するには、企業側も従来の受け身な採用スタイルから、より能動的なアプローチへと転換する必要があるでしょう。積極的な情報発信や企業ブランディング、魅力的な職場環境づくりなど、総合的な採用戦略が求められています。
フリーランスのデザイナーが増えているから
フリーランスとして活動するデザイナーが増えていることから、正社員のデザイナーの採用が困難になっています。経済産業省の「デザイン政策ハンドブック2020」によると、2015年時点でデザイナー全体の23.7%がフリーランスとして活動しています。
デザイナー職は時間や場所に縛られにくく、クラウドソーシングやSNSを通じた仕事を獲得しやすい職種です。給与面でも、フリーランスとして複数のクライアントを抱えることで、正社員以上の収入を得られる可能性があります。働き方改革やリモートワークの普及も追い風となり、フリーランスデザイナーの増加に拍車をかけました。
ポイント
また、副業・兼業の解禁により、正社員デザイナーも副業で外部案件を請け負うケースが増えています。デザイナーは他の職種と比べて副業との親和性が高く、一社に依存しない働き方が可能です。
優秀なデザイナーほど働き方の自由度を重視し、フリーランスや副業を選択するケースが多くなっています。企業は正社員採用にこだわらず、業務委託や副業としての起用も検討する必要があります。
デザイナーを採用していいか判断が難しいから
デザイナーの評価は高度な専門性を要し、採用担当者による適切な判断が難しい状況です。グラフィック・Web・UI/UX・プロダクトなど、デザインの専門分野は多岐にわたり、それぞれに必要なスキルセットも異なります。
ポイント
デザイナーがいない企業では、ポートフォリオやスキルの評価が困難です。デザインの品質やセンスだけでなく、チームとのコミュニケーション力、クライアントへの提案力など、数値化しづらい要素も評価しなければなりません。
デザインの専門知識まで把握しきれない人事担当者様も多いでしょう。採用面接で良い印象を受けた人材が、実際の現場では期待通りのパフォーマンスを発揮できないケースもあります。
採用のミスマッチを防ぐには、社内デザイナーの意見を取り入れたり、業務内容や達成目標を明確に定義したりする必要があります。特に初めてデザイナーを採用する企業は、外部の専門家に評価を依頼することも検討しましょう。
デザイナーを採用するための7ステップ
それでは、デザイナーを採用するための流れを解説していきます。
デザイナーを採用するための7ステップ
- 採用戦略を策定する
- 採用ペルソナを設定する
- デザイナーが重視していることを把握する
- 募集手法の選定
- 魅力的な募集情報を作る
- カジュアル面談を実施する
- 入社後のフォロー体制を整える
1ステップずつ解説していくので、採用活動の参考にしてみてください。
①採用戦略を策定する
まずは採用戦略から考えていきましょう。経営計画や事業戦略に基づき、以下の要素を決めていきます。
採用戦略で決めること
- 採用の目的
- 必要人数
- 採用予算
- 採用期間 など
具体的な採用要件も検討してください。例えば、少数精鋭の即戦力人材か、育成を前提とした若手かによって、求めるスキルセットや報酬水準は変わります。現場のニーズや予算に応じた採用戦略が必要です。
ポイント
採用戦略を立てる際は、KPIの設定が不可欠です。採用までのフェーズで目標を数値化して、検証・改善していきましょう。
採用KPIを設定する手順は以下のとおりです。
採用KPIを設定する5ステップ
- KGIを設定する
- 採用チャネルの選考フローを決める
- 歩留まり率を調べる
- KGIから逆算してKPIを設定する
- KPIをまとめて共有する
詳しい方法は、採用KPIを設定する5ステップ|4つの運用のコツと注意点も解説にまとめたので、参考にしてみてください。
②採用ペルソナを設定する
次に、採用したいデザイナーのペルソナを設定します。求める人材像を具体的に言語化し、採用活動の指針を明確にしましょう。ペルソナが曖昧だと、ミスマッチや採用コストの増加を招く恐れがあります。
具体的なペルソナ設定の方法は、以下のとおりです。
採用ペルソナを設計する手順
- 採用したい人材像を社長や現場に聞く
- 人材を採用する目的を定義する
- 採用したい人材像を書き出す
- 採用市場に合わせたペルソナにする
- ペルソナを経営層や現場のメンバーに確認してもらう
詳しいペルソナの設定方法は、採用ペルソナの作り方完全ガイド|テンプレートと7ステップのフレームワークにまとめています。
デザイナーのペルソナ設定の注意点
デザイナーのペルソナ設定では、担当業務や必須スキル、使用ツールなどの技術要件を細かく定義します。
例
WebサイトのUI/UXデザインならFigmaやSketchの使用経験、グラフィックデザインならAdobe製品のスキルレベルなど、具体的な基準を設けてください。
また、必要なスキルは「Must要件」と「Want要件」に分類しておくと、採用時の優先順位を理解しやすくなります。以下は、Must要件とWant要件の具体例です。
| 要件 | 具体例 |
|---|---|
| Must要件 | ・HTML/CSSの実務経験 ・JavaScriptの基本理解 ・Adobe Photoshop、Illustrator、Figmaの使用経験 |
| Want要件 | ・WordPressやShopifyを使用したWebサイト構築経験 ・CSSアニメーション、GSAP、Lottieなどを使った動的デザインの作成経験 ・ECサイト、医療、教育、不動産など特定の業界でのデザイン経験 |
デザイン経験だけでなく、チーム内でのコミュニケーション力やプロジェクトマネジメント力なども考慮に入れましょう。
採用ペルソナは人事部門だけでなく、現場のデザイナーや事業責任者とも共有し、認識をすり合わせます。採用活動に関わる全員が、同じ基準で人材を評価できる体制を整えるのがコツです。
③デザイナーが重視していることを把握する
多くのデザイナーが「仕事をする上で重視すること」も理解しておきましょう。希望と違う求人を出してしまうと、応募が集まりにくいです。
デザイナーが主に重視していることは以下の4つです。
デザイナーが重視していること
- 年収
- 勤務体系
- 労働環境
- スキルアップ
それぞれ解説するので、チェックしてみてください。
年収
相場に合った年収を希望するデザイナーが多いです。以下は厚生労働省がまとめた、デザイナーの種類別の平均年収です。
| デザイナーの種類 | 平均年収 |
|---|---|
| Webデザイナー グラフィックデザイナー 広告デザイナー | 509.3万円 |
| UX/UIデザイナー | 557.6万円 |
参考:jobtag
こうした年収相場より極端に低い年収だと、応募が集まりにくくなります。競合他社の年収もチェックして、自社の条件を改善する工夫が必要です。
勤務体系
勤務体系に柔軟性を求めるデザイナーもいます。パソコンとインターネット環境があればどこでも仕事ができるため、リモートワークやフレックスタイム制度の有無が転職先選びの判断材料になるケースもあるでしょう。
ポイント
デザインは創造的な作業を伴うため、アイデアが浮かんだときに集中して取り組める環境が不可欠です。決まった時間に縛られるのではなく、自分のクリエイティブな感性が最も活きる時間帯に仕事ができる、柔軟な勤務制度が求められています。
また、デザイナーはワークライフバランスも重視する傾向があります。育児や介護との両立、自己啓発の時間確保など、個人のライフスタイルに合わせた働き方を実現できる企業が選ばれやすいです。時短勤務やワーケーション制度なども魅力的な制度です。
デザイナー採用を成功させるには、従来の固定的な勤務体系からの脱却も検討してみてください。働き方の自由度を高め、クリエイターとしての能力を最大限発揮できる環境づくりが、優秀な人材確保に必要です。
労働環境
デザイナーは長時間パソコンに向き合う職種のため、快適な労働環境への関心が高くなっています。例えば、以下のようなツールがあると喜ばれるでしょう。
デザイナーをサポートするツールの例
- 大画面のデュアルモニター
- 人間工学に基づいた高品質な椅子
- 高さ調整可能なスタンディングデスク
デザイン制作に必要な機材やソフトウェアも必要です。Adobe Creative CloudやFigmaなどの業界標準ツールを、企業負担で利用できる環境も魅力的です。
デザイナーの作業効率を高める機材への投資は、企業の本気度を示すバロメーターにもなります。給与や福利厚生だけでなく、快適な労働環境の整備も検討してみてください。
スキルアップ
デザイナーはスキルアップへの意欲が高く、転職先選びでも成長機会を重視します。技術革新が速いデザイン業界では、常に新しいスキルの習得が不可欠です。業務を通じて専門性を高められる環境が、優秀なデザイナーを惹きつけます。
求人情報では、担当するプロジェクトの具体的な規模や、内容を明示するのがコツです。具体的な数字を示すと「この会社でスキルアップしたい」と興味を持ってくれやすいです。
例
- Webデザイン:月間PV数
- グラフィックデザイン:制作物の種類や部数
また、研修や勉強会の実施も効果的です。デザインツールの講習会やUX改善の事例共有会など、体系的な学習機会があると魅力的です。社外セミナーへの参加支援や資格取得補助なども、デザイナーの成長意欲に応える施策といえます。
スキルアップできる環境があると、優秀なデザイナーを採用できるだけでなく、定着率も上がりやすくなります。
④募集手法の選定
続いて、デザイナーの募集手法を選定していきましょう。具体的には以下のような手法があります。
デザイナーの募集手法
- ダイレクトリクルーティング
- リファラル
- SNS
- 求人サイト
- 転職エージェント
- 採用代行
- 逆求人イベント
- オウンドメディア
それぞれのメリット・デメリットや、手法が適している企業の特徴は、デザイナー採用におすすめの手法8選から解説していくので、このまま読み進めてみてください。
⑤魅力的な募集情報を作る
求めるデザイナーの価値観や関心に沿って、魅力的な募集情報を作成しましょう。単なる職務内容や待遇面の説明だけでなく、企業理念やビジョン、デザインチームの特色など、多角的な情報を盛り込みます。
デザイナー向けの求人票に盛り込む情報例
- リモートワーク
- フレックスタイム
- デザインツールの充実度
- スキルアップ支援制度
- 経営層のデザインへの理解度 など
募集内容の作成では、社内デザイナーの意見も取り入れてください。現場の声を反映することで、デザイナーの視点に立った魅力的な求人情報を作成できます。
入社後の働き方やキャリアパスをイメージできるよう、求人票には具体的な情報を記載しましょう。
求人票を書くコツは、求人票の書き方のコツを徹底解説|求人票の作り方5ステップで詳しく解説しているので、チェックしてみてください。
⑥カジュアル面談を実施する
デザイナーの採用活動では、カジュアル面談がおすすめです。リラックスした雰囲気で話すと、お互いの価値観を理解しやすくなります。
ポイント
気軽に対話することで、普段の仕事の進め方や、デザインに対する情熱が自然と表れます。形式張った面接では見えにくい部分まで把握できるでしょう。
さらに、デザイナー自身も職場の雰囲気や文化を正確に感じとって、興味を持たれやすくなります。
まずはカジュアル面談から始めて、信頼関係を構築するのが効果的です。
⑦入社後のフォロー体制を整える
入社後の定着・活躍を見据えたフォロー体制も構築しておきましょう。内定承諾から入社、戦力化までのプロセスを設計・サポートすることで、デザイナーは安心して入社を決断できます。
ポイント
内定後も定期的に面談し、入社への不安を解消してください。社内デザイナーとの交流機会を設けたり、ポートフォリオを共有したりすることで、スムーズな入社を促進します。
入社後は専任のメンターを配置し、業務や組織への適応をサポートしましょう。OJTを通じた実践的な育成に加え、定期的な1on1面談で課題やニーズを把握します。デザイナーのスキルに応じた評価・処遇制度も、長期的な定着に有効です。
デザイナー採用におすすめの手法8選
デザイナーを募集する際に、おすすめの手法を紹介していきます。
それぞれのメリットとデメリット、成果が出やすい企業の特徴も解説します。
デザイナー採用におすすめの手法
- ダイレクトリクルーティング
- リファラル
- SNS
- 求人サイト
- 転職エージェント
- 採用代行
- 逆求人イベント
- オウンドメディア
貴社にフィットする手法を選んでみてください。
ダイレクトリクルーティング
ダイレクトリクルーティングは、企業が候補者に直接アプローチする採用手法です。スカウト型転職サービスを活用し、自社の魅力を発信します。デザイナー採用では特に効果的で、従来の求人広告では出会えない優秀な人材との接点を生み出せます。
ダイレクトリクルーティングのメリット
- 採用コストを抑えながら、デザイナーにアプローチできる
- 採用ノウハウが社内に蓄積されやすい
ダイレクトリクルーティングのデメリット
- 工数の確保が必要
- 大量採用には不向き
デザイナーの市場では、待ちの姿勢ではなく積極的なアプローチが有効なので、ダイレクトリクルーティングは成果が出やすいです。
ただし、候補者の探索やスカウトメールの作成、やり取りの管理など、採用担当者の負担は増加します。
採用リソースに余裕があり、少数精鋭のデザイナー採用を目指す企業に適した手法です。
ダイレクトリクルーティングはHELLOBOSSがおすすめ
デザイナーに対してダイレクトリクルーティングを実施する場合は、私たちが提供する「HELLOBOSS」がおすすめです。10万人を超えるユーザーの中から、AIが貴社に合うデザイナーをマッチングしてくれるため、採用担当者の負担を軽減します。
候補者と直接チャットができるため、返信率も高く、デザイナーとの関係を築きやすくなっています。
月額4,000円〜でスカウトメール送り放題なので、貴社にフィットしそうなデザイナーをAIに推薦してもらったら、積極的にアプローチしてみましょう。
無料版から始めることも可能です。テストとして使ってみてください。
わずか3ステップで始められるため、さっそくHELLOBOSSを試してみましょう。
リファラル
リファラル採用は、社員の知人や友人を紹介してもらう採用手法です。デザイナーはコミュニティのつながりが強く、表立って転職活動しない潜在層も多いため、効果が期待できます。紹介者には報奨金などのインセンティブを設定するのが一般的です。
リファラル採用のメリット
- 社員の紹介なのでミスマッチが少ない
- 事前に候補者の人柄やスキルを確認しやすい
- 採用コストを抑えられる
リファラル採用のデメリット
- 安定的に人材を採用するのが難しい
- トラブル発生時に紹介者との人間関係に影響が出る可能性がある
- 似た傾向の人材が集まりやすく、組織の同質化が進むリスクがある
リファラル採用は、社員の定着率が高く、健全な組織文化が醸成されている企業で成果が出やすい手法です。特にデザイナーの採用では、潜在的な優秀人材へのアプローチ手段として、積極的に活用しましょう。
ただし、インセンティブの支払は職業安定法に抵触する恐れがあるため、給与の上乗せとして支払うのが妥当です。インセンティブの相場は5〜50万円程度です。
SNS
SNSを活用したデザイナー採用は、低コストで効果的なアプローチが可能です。デザイナーはSNSでポートフォリオを公開したり、作品を発信したりする傾向が強く、採用活動との親和性が高いです。
特に効果的なSNS
- X(旧Twitter)
- Behance
- Dribbble
デザイナーの作品を確認し、ダイレクトメッセージでコンタクトが取れます。
SNS採用のメリット
- コストを抑えた採用活動ができる
- リアルタイムに情報を発信できる
- 拡散を期待できる
SNS採用のデメリット
- 継続的な運用が必要
- 効果が表れるまでに時間がかかる
- 自発的に投稿しないとデザイナーに興味を持たれにくい
自社のデザインプロセスやチームの雰囲気など、求人票では伝えにくい情報を発信できるのも強みです。特に若手デザイナーへのアプローチでは、SNSの活用が有効です。
SNS採用は、日頃からデザインへの取り組みを積極的に発信し、デザイナーとの関係構築に注力できる企業に適しています。
求人サイト
求人サイトはテキストだけでなく、画像や動画、社員インタビューを掲載して、自社の魅力を多角的に伝えられます。デザイナー採用には、総合求人サイトよりも、クリエイティブ職特化型の求人サイトがおすすめです。
求人サイトのメリット
- 幅広い求職者層へのアプローチできる
- 複数名から応募がくる可能性がある
求人サイトのデメリット
- 応募者の質にばらつきが出やすい
- 知名度が低い企業では応募が集まりにくい
求人サイトは、ブランド力があり、複数名の採用を予定している企業に適しています。また、応募者の選考や、管理の工数を確保できる体制が必要です。
転職エージェント
転職エージェントは、企業の要望に合わせて、厳選された候補者を紹介する採用手法です。デザイナー採用に特化したエージェントも存在し、市場動向や適切な待遇について助言も得られます。採用が成立した場合のみ費用が発生する「成功報酬型」が一般的です。
転職エージェントのメリット
- 採用担当者の工数を削減できる
- エージェントのノウハウを活用できる
転職エージェントのデメリット
- 年収の20〜30%程度の紹介手数料が発生する
- 社内に採用ノウハウが蓄積されにくい
面接日程の調整や、候補者とのコミュニケーション、入社条件の交渉をエージェントが担当します。
転職エージェントは、即戦力のデザイナーを短期間で採用したい企業や、採用ノウハウが不足している企業に適しています。採用予算には余裕が必要ですが、質の高い人材を採用したい場合の有効な手法です。
採用代行
「採用代行」とは、企業の採用活動の一部または全部を専門業者に委託できるサービスです。
採用代行のメリット
- 採用プロセスにかかる時間を短縮できる
- プロのノウハウを活用できる
採用代行のデメリット
- 社内にノウハウが蓄積しにくい
- 固定コストがかかる
採用代行はリソースが少ない企業や、人事担当者が育っていない企業に適しています。
逆求人イベント
デザイナー志望の学生がブースを設け、企業の採用担当者に直接作品をプレゼンするのが「逆求人イベント」です。主に美術大学や専門学校の学生が参加し、自身のポートフォリオを通じて企業にアピールします。企業は学生のブースを訪問し、作品や制作意図を直接確認できます。
逆求人イベントのメリット
- 学生の作品と人柄を直接確認できる
- 書類選考では伝わりにくい制作プロセスを確認できる
- 情熱や意欲が高い学生と出会える確率が高い
逆求人イベントのデメリット
- 即戦力人材を採用しにくい
- 開催時期も限られている
逆求人イベントは新卒デザイナーの採用や、デザイン文化の醸成に注力する企業に適しています。特に、若手人材の育成に注力できる体制が整っている企業でも有効です。
オウンドメディア
オウンドメディアとは、自社の採用サイトやブログを通じて、企業の魅力や価値観を発信する採用手法です。デザイナー採用ではサイトのデザイン性自体が企業のデザインへの姿勢を示すため、質の高いコンテンツ制作が不可欠です。
オウンドメディアのメリット
- 自社らしさを自由に表現できる
- 求人票では伝えきれない詳細な情報を発信できる
オウンドメディアのデメリット
- コンテンツ制作の負担が発生する
- 成果が出るまで時間がかかる
オウンドメディアでは、社員インタビュー・プロジェクト事例・デザインプロセスなど、求人票では伝えきれない詳細な情報を発信できます。継続的な情報発信により、企業のデザインカルチャーへの理解を深めてもらえるでしょう。
ただし、コンテンツ制作の負担が発生します。特にデザイナー向けのメディアでは、サイトデザインの品質が採用の成否に直結します。社内リソースだけでは高品質なコンテンツを維持できない場合は、外注も検討してください。
オウンドメディアは、デザインへの投資に積極的で、独自の価値観やカルチャーを持つ企業に適しています。
フリーランスデザイナーを採用するのもおすすめ
正社員のデザイナーの採用が難しい場合は、フリーランスデザイナーの採用も検討しましょう。フリーランスのデザイナーは特定の企業に所属せず、個人事業主として複数のプロジェクトを並行して手がけています。
ポイント
プロジェクトベースでの柔軟な起用が可能で、必要なときに必要なスキルを持つデザイナーを確保できます。正社員採用と比べて採用のハードルも低く、即戦力人材の獲得がしやすいのが特徴です。
ここからは、フリーランスデザイナーのメリットとデメリットを解説していきます。
フリーランスデザイナーを採用する4つのメリット
フリーランスデザイナーを採用するメリットは、以下の4つです。
フリーランスデザイナーを採用するメリット
- ハイスキルのデザイナーを採用できる
- 低コストで採用できる
- スピーディーに参画してもらえる
- ノウハウを共有してもらえる
1つずつ解説していきます。
ハイスキルのデザイナーを採用できる
フリーランスデザイナーは、高度な専門性と豊富な実績を備えた人材が存在します。クライアントと直接契約し、複数のプロジェクトを手がけるため、スキルや経験に自信を持つデザイナーが多いです。
ポイント
フリーランスデザイナーは、高度な専門性と豊富な実績を備えた人材が存在します。クライアントと直接契約し、複数のプロジェクトを手がけるため、スキルや経験に自信を持つデザイナーが多いです。
社内には不足している専門スキルも、フリーランスデザイナーを活用することで補完できるでしょう。
例えば、UI/UXデザインやブランディングなど、特定の分野に特化したエキスパートの確保が可能です。中途採用市場では出会えないような優秀な人材との協業も実現できます。
低コストで採用できる
フリーランスは社会保険や福利厚生の負担がないため、固定費用を抑えやすいです。契約も案件ごとに終了できるので、作業が落ち着いた段階で適切なコストに調整できます。
ポイント
社員として雇用すると仕事が少ない時期でも給与を支払う必要がありますが、フリーランスであれば無駄な支出を避けやすいでしょう。
さらに、制作会社を挟まず直接依頼する場合が多いので、仲介料が省かれて発注費も低減しやすいです。結果としてプロジェクト全体にかかる負担をコントロールしやすく、利益率を確保しやすい点が特徴といえます。
長期契約が不要なケースでは特に有効な方法です。そのため、成長段階の企業やスポット案件の多い企業に適しています。
スピーディーに参画してもらえる
フリーランスは退職交渉や引き継ぎに時間がかからないことが多く、早期に業務へ合流しやすいです。社員の内定から入社まで数ヶ月かかるケースと異なり、急ぎのデザイン案件にも迅速に対応できるでしょう。
ポイント
大規模サービスの立ち上げ時や、繁忙期に即戦力を呼ぶ際に重宝されます。
加えて、個人事業主同士がチームを組む事例もあり、プロジェクトに必要なスキルをすばやくそろえられる場合があります。社内でスケジュールが合わないときでも、フリーランスなら柔軟に日程を合わせられることが魅力です。
スピード重視の環境で成果を求める企業に向いています。
ノウハウを共有してもらえる
多くの現場で活躍しているフリーランスは、多彩な業種やツールを経験している傾向があります。自社の案件に参加する際、最新デザイン手法や効果的なツール活用を惜しまず使ってくれるでしょう。
ポイント
デザインのトレンドを吸収しやすくなるため、既存チームの視野が広がりやすいです。さらに、複数のプロジェクトで培った問題解決の手順を学べる場面もあるでしょう。
社内メンバーと積極的にディスカッションすることで、新しい提案や発想が生まれることもあります。
フリーランスデザイナーを採用する3つのデメリット
プロジェクトの品質向上や費用面で多くの恩恵を得られるフリーランスデザイナーですが、いくつかのデメリットがあります。
フリーランスデザイナーのデメリット
- 情報を管理する必要がある
- 社内ノウハウが貯まりにくい
- 長期間の人材確保が難しい場合がある
こちらも1つずつ解説していきます。
情報を管理する必要がある
社外の人に資料やデータを渡すため、機密保持に配慮しないと漏洩リスクが高まります。業務上で得た重要なデータを、自宅やカフェで扱うケースも考えられるでしょう。
注意
秘密保持契約(NDA)を結ぶことや、閲覧権限を限定した共有フォルダだけを用意するなど、ルールを明確にしなければなりません。
可能であれば社内VPNや専用ツールを活用して、アクセス制御を厳格にする方法もあります。制作物やデータの受け渡しは、パスワード付きの圧縮ファイルを使うなど、細かく対策しましょう。
社内ノウハウが貯まりにくい
フリーランスのデザイナーばかりにプロジェクトを任せると、完成した制作物は残っても、その背景や手法の共有が不十分になりがちです。現場でどのようなスキルを使い、どんな過程を踏んだのかが社内に浸透しにくいでしょう。
ポイント
さらに、オンライン中心のやり取りだと、細かなテクニックや工夫が言語化されないまま終わるかもしれません。社内スタッフが学べる場面が少なくなるので、新しい案件を内製化しにくくなります。
独自のノウハウを育てられないまま、外部依存が深まる恐れがあります。フリーランスをうまく活用しつつも、社員が得た知見を社内ドキュメントに残す仕組みや、ディスカッションの場を設けるのが望ましいです。そうすれば経験が蓄えられ、次の案件で社内力を発揮しやすくなるでしょう。
長期間の人材確保が難しい場合がある
フリーランスは複数の案件を掛け持ちしている可能性もあるため、同じ人材が継続して携わる保証は薄いです。大規模プロジェクトで長期間のコミットを期待する企業にとっては、契約満了後の人材ロスが痛手になるでしょう。
注意
フリーランスデザイナーのスケジュールの都合で、参画してもらえなくなる場合もあります。長期開発や保守案件を見据えるなら、社員として採用するか、フリーランスとの長期契約を検討するなど、運営方針に沿って判断しましょう。
定期的に同じ人へ発注する方法もありますが、合意できるかは事前の打ち合わせ次第です。
フリーランスデザイナーを採用するときの注意点
まずは、契約内容や業務範囲を明確に設定し、文書化して相互に合意しましょう。例えば、支払い条件や納品日数だけでなく、修正回数や緊急時の連絡手段を細かく決めておくと安心です。
ポイント
加えて、制作物の著作権や秘密保持に関する取り決めも欠かせません。フリーランス側のスケジュールが変わるリスクに備え、予備人員の確保や契約延長の選択肢を持っておくとトラブルを回避しやすくなります。
納品後の検収手順や修正対応なども最初から共有すると、作業が円滑に進みやすいでしょう。
社内メンバーとの連携を図りながら、フリーランスデザイナーの力を最大限に活かすのがコツです。
デザイナーを見極める7つのコツ
デザイナーを採用するとき、人材を見極めるコツも解説していきます。うまく見極められないとミスマッチが発生し、プロジェクトに影響が出てしまうでしょう。
デザイナーを見極める7つのコツ
- 職務経歴書をチェックする
- ポートフォリオを見せてもらう
- 自社のデザイナーにサポートしてもらう
- 業務委託で働いてもらう
- 社風に合っているか確かめる
- 自己研鑽しているか確認する
- コミュニケーションスキルをチェックする
こちらも1つずつ解説していきます。
職務経歴書をチェックする
職務経歴書で過去の経験や携わったジャンルを確認すると、スキルの方向性がイメージしやすいです。Webや印刷物、UI・UXなど、どの分野で実績があるか把握しましょう。
例
前職で大規模プロジェクトのディレクションまで担当していたなら、自社でもディレクターとして活躍する可能性があります。逆に小規模案件の経験が長い応募者なら、丁寧で細やかな作業が期待できるかもしれません。
さらに挫折や困難をどう乗り越えてきたかを聞いてみると、柔軟性や協調性を推し量りやすいです。
ポートフォリオを見せてもらう
過去の作品を直接見せてもらうと、文章だけでは判断しづらいセンスや技術力が見えてきます。以下の点に注目すると、より的確に評価できるでしょう。
| ポートフォリオでチェックする点 | 詳細 |
|---|---|
| デザインの完成度 | 色使い、レイアウト、印象の強さ |
| 担当範囲 | アイデア立案から実制作まで行ったのか? |
| 目的達成への工夫 | クライアントの要望や課題をどう解決したか? |
| 表現の幅 | Webデザイン、紙媒体、UIデザインなど複数の分野に携わったか? |
ポートフォリオの内容が、自社のターゲットやブランドに合っているか確認しましょう。
自社のデザイナーにサポートしてもらう
人事担当者だけで判断するより、社内で活躍しているデザイナーにも選考に参加してもらうと、精度の高い見極めが期待できます。制作物を見るときに、専門的なツールの使い方や制作工程をチェックしてもらうと、ちょっとした技術差や知識量の違いがわかりやすいです。
ポイント
面接中に同席してもらえば、候補者の考え方やコミュニケーションスタイルが現場にフィットするかを具体的にイメージできます。
現場のデザイナーの意見を聞けば、採用後のミスマッチも減らせるでしょう。
業務委託で働いてもらう
正社員のデザイナーをいきなり決めづらいなら、短期間だけ業務委託で依頼するのもおすすめです。小さめの案件や特定のデザイン作業を任せ、納品や社内とのやりとりを観察すると、面接だけでは見えにくい部分がわかります。
業務委託の例
- 数ヶ月単位の契約を設定し、スキルや成果物をチェック
- 社内メンバーとの連携や、トラブル対応を把握
- 問題なく進行できたら、正社員登用を検討
業務の進め方や期日遵守に対する姿勢も見えるので、採用後のミスマッチを抑えやすいでしょう。相性が良いと判断したら、本採用をオファーしてみてください。
社風に合っているか確かめる
いくらスキルが高くても、企業文化との相性が悪いと長続きしません。大人数でアイデアを出し合うスタイルが向いているのか、個人で集中して取り組む環境を好むのかなど、確認すると良いでしょう。
また、フラットな組織かトップダウン型かといった会社の特質に合うかも観察したいところです。面接で仕事観や挑戦意欲、コミュニケーション頻度などを質問すると、社内で活躍する姿がイメージしやすくなります。
自己研鑽しているか確認する
デザイン分野は情報の移り変わりが早いため、自主的な学習や取り組みが欠かせません。次のような話題を深掘りすると、向上心が見えやすいです。
自己研鑽しているか確認する例
- 最近参加したセミナーや勉強会はあるか
- 新しいツールやソフトをどう習得しているか
- SNSやポートフォリオサイトで作品を発信しているか
- 流行やトレンドに興味があるか
チームのレベルを引き上げてくれる存在になりうるかを見極めるためにも、確認してみましょう。
コミュニケーションスキルをチェックする
デザイナーは他部署やクライアントともやりとりが多い職種です。次のような観点を基準に評価してみましょう。
| 観点 | 確認例 |
|---|---|
| 対話のスムーズさ | 話す順番や言葉遣いに無理がないか |
| 論理的な説明力 | デザインの意図をわかりやすく伝えられるか |
| ヒアリングの姿勢 | 相手が意図するゴールや課題を正しく組み取れるか |
| 傾聴スキル | 相手の意見を否定せずに聞けるか |
会話のトーンや相槌のタイミングなど、細かな部分にも目を向けると、人柄や周囲との相性が見えやすいです。社員同士の連携がスムーズになるかを重視する場合は、この点を優先してチェックすると良いでしょう。
デザイナー採用でよくある質問
最後に、デザイナーの採用についてよくある質問に答えていきます。
新卒のデザイナーを採用するメリットとデメリットは?
新卒デザイナーは業務経験が少ない一方で、理念への共感や柔軟な吸収力が期待されます。詳しいメリットとデメリットは以下のとおりです。
| メリット | ・企業文化に染まりやすく、長期的な戦力になりやすい ・給与や初期コストが少なくて済む ・育成プログラム次第で将来のコア人材を育てやすい |
| デメリット | ・実践的なスキルや現場経験が不足している ・教育コストや研修の準備が必要 ・業務をスムーズに回せるまで時間がかかる |
入社前からインターンなどで制作に携わった経験のある学生を採用すれば、導入期の手間が軽減される可能性があります。長期的な視点で人材を確保したい企業には、新卒採用が向いています。
中途採用のデザイナーを採用するメリットとデメリットは?
メリットとデメリットは以下のとおりです。
| メリット | ・即戦力になりやすい ・育成コストが抑えられる ・前職での人脈を活かしてくれる可能性がある |
| デメリット | ・環境に合わず退職するリスクがある ・前職のやり方を引きずる場合がある ・企業理念や方針への理解が浅いまま入社する懸念がある |
中途でデザイナーを迎えると、実践的なスキルをすぐ活用しやすいです。人員が必要になったときは、熟練者を早期に求めるのに向いています。さらに即戦力だけでなく、他社でのノウハウを取り込めるため、業務の幅が広がるかもしれません。
注意
ただし、スキルが高いデザイナーほど待遇面に敏感で、好条件の募集を見つけて再転職する可能性もあります。
前職での慣習が抜けず、新たな組織に合流しにくい場合もあるので、採用面接では社風への理解度や協調性を見極めてください。早期離職を防ぐには、価値観や仕事への姿勢が自社と調和しているかを確認すると良いでしょう。
地方でデザイナーを採用するコツは?
地方でデザイナーを採用するときは、地域ならではの魅力やネットワークを活かしながら、多角的に求人を発信する姿勢が必要です。近隣の学校や企業との連携によって、独自の人材ルートを築きましょう。
地方でデザイナーを採用するコツ
- オンライン就活フェアで情報提供
- 地域の専門学校と連携
- 地方移住の支援制度をPR
- SNSで制作事例を定期発信
- 地域の企業交流会で顔を広げる
新卒やUターン志望者にアピールしやすい環境を作れば、良いデザイナーとの縁が生まれます。地域の産業を盛り上げるためには、多方面からデザイナーを迎え入れる視点が必要です。
未経験のデザイナーを採用するときの注意点は?
未経験のデザイナーを採用するときは、柔軟な発想を取り入れやすい反面、実務を教える体制が整っていないと混乱しやすいです。育成計画を整えながら、長い視点で成長を支援する姿勢が求められます。
さらに、仕事の基礎を丁寧に伝えれば、早期の段階から安定した成果を期待しやすくなります。
未経験のデザイナーを迎えるときの注意点
- 業務内容を具体的に伝える
- 学習支援の仕組みを用意する
- 社内スタッフのフォロー体制を準備する
- 成長度合いを見ながら仕事を任せる
- 進捗をこまめに確認する
時間と手間はかかっても、丁寧に指導すれば将来的に大きな戦力となるでしょう。早い段階から基礎を固めるほど、今後の成長も加速しやすくなります。
デザイナーの主な退職理由は?
デザイナーの主な退職理由を把握すれば、採用後の離職を防ぎやすくなります。主な退職理由は以下のとおりです。
デザイナーの主な退職理由
- 過度な作業負担
- 評価や給与が不透明
- 方向性が合わない
- 成長機会が乏しい
応募段階から想定される課題を認識すれば、長期的な定着が見込めます。働く意義を共有しやすい仕組みを整備し、安心して働ける場を作りましょう。
まとめ
デザイナーの採用が難しい状況が続いていますが、以下のような手法を使って、積極的に採用活動を進めていきましょう。
デザイナー採用におすすめの手法
- ダイレクトリクルーティング
- リファラル
- SNS
- 求人サイト
- 転職エージェント
- 採用代行
- 逆求人イベント
- オウンドメディア
デザイナーに対してダイレクトリクルーティングを実施する場合は、私たちが提供する「「HELLOBOSS」がおすすめです。10万人を超えるユーザーの中から、AIが貴社に合うデザイナーをマッチングしてくれるため、採用担当者の負担を軽減します。
デザイナーと直接チャットができるため、返信率も高く、関係を築きやすくなっています。
無料版から始められるため、さっそくHELLOBOSSを試してみましょう。
貴社のデザイナー採用の参考になれば幸いです。