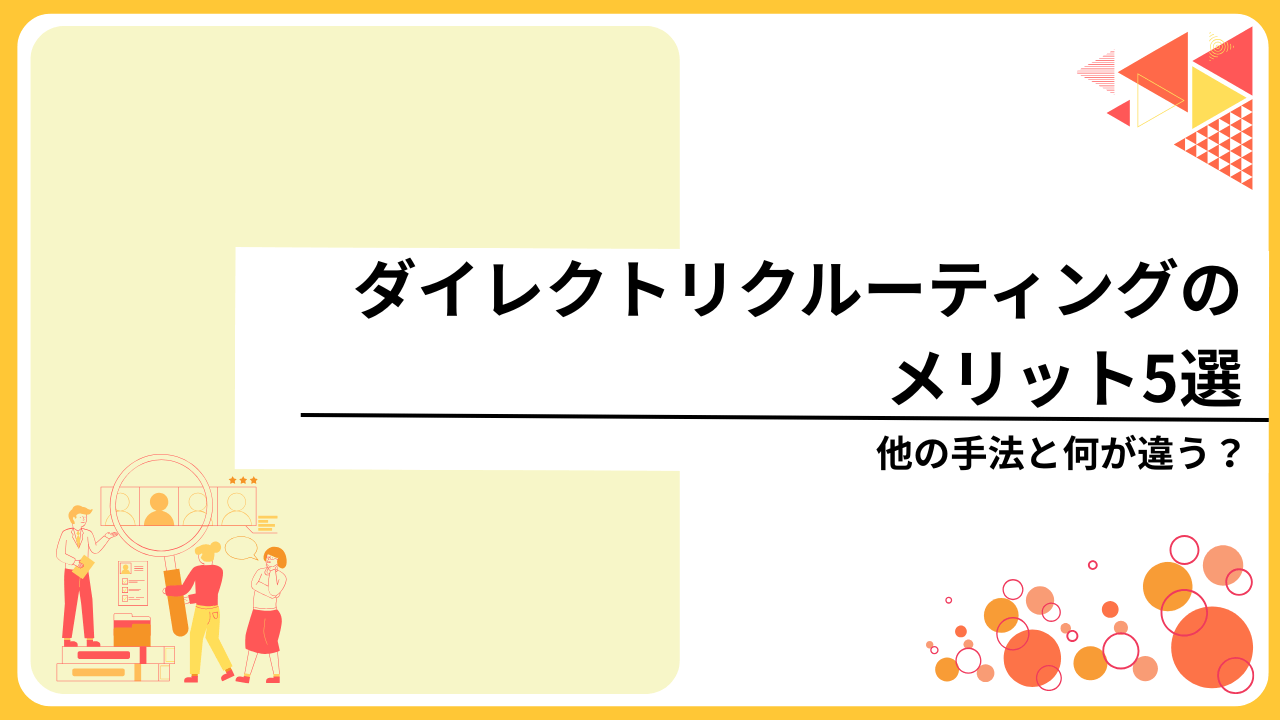「ダイレクトリクルーティングのメリットは?」
「うちの会社はダイレクトリクルーティングに向いてる?」
こういった疑問をお持ちの人事担当者様向けの記事です。
この記事でわかること
- ダイレクトリクルーティングのメリットとデメリット
- ダイレクトリクルーティングと他の採用手法の比較
- ダイレクトリクルーティングが向いている企業の特徴
結論、ダイレクトリクルーティングはメリットが多い採用手法です。候補者に直接アプローチできるため、転職を検討してもらえるチャンスが広がるからです。
しかし「運用が大変じゃないの?」「候補者に反応してもらえるの?」と不安に思う方もいるでしょう。
この記事では、ダイレクトリクルーティングの進め方や、スカウトメールの書き方まで完全解説しています。
最後まで読むことで採用の成果を上げる方法がわかるので、人材を採用したい人事担当者様はさっそくこの記事の内容を実践していきましょう。
ダイレクトリクルーティングのおすすめアプリ
私たちが提供するダイレクトリクルーティングツールの「HELLOBOSS」は、候補者とチャットでやり取りできるので、返信率が高いです。
さらに、AIが貴社にフィットする人材を見つけてくれるので、工数削減にもつながります。
月4,000円から利用できるため、コストを抑えたダイレクトリクルーティングを実現しています。
人材を採用するチャンスを広げたい人事担当者様は、今すぐ「HELLOBOSS」を見てみてください。
「前置きはいいから、早くダイレクトリクルーティングのメリットを知りたい!」という方は、ダイレクトリクルーティングのメリット5選へジャンプしてみてください。

Contents
そもそも「ダイレクトリクルーティング」とは
企業が理想とする人材へ能動的に声をかける採用手段が「ダイレクトリクルーティング」です。従来の求人広告は応募を待つスタイルですが、ダイレクトリクルーティングであれば転職潜在層にも直接アプローチが可能です。
例
人材データベースやSNSを活用し、早期に連絡を取りやすい点が特徴です。海外では「ダイレクトソーシング」と呼ばれ、企業主体で採用を進める意味合いがあります。
中小企業のように認知度が低い組織でも、自社の魅力を伝えながら優秀な人を探しやすくなるため、新しい方法として注目されています。
ダイレクトリクルーティングの需要が高い理由
転職市場は売り手優位が続き、従来の求人広告だけでは必要な人材と出会いにくい状況が生じています。専門スキルをもつ層や意欲が高い人たちは、待ちの募集では確保しにくいです。
令和6年12月時点の有効求人倍率は1.25倍となっており、求職者より求人の方が多い状況が続いています。
出典:厚生労働省|一般職業紹介状況(令和6年12月分及び令和6年分)について
こうした背景があるため、自社から直接声をかけるダイレクトリクルーティングの需要が高くなっています。
新卒・中途採用どちらでも導入可能
ダイレクトリクルーティングは、新卒採用なら企業が学生に直接話しかけ、就業観や個性を確かめながら採用活動を進められます。一方、中途採用では経歴や実績を見たうえで、気になる人へ集中的に声をかけられるので、応募が少ない悩みを軽減しやすいです。
いずれも従来の「応募が来るまで待つ方法」より広範囲に候補者を見つけやすく、中小企業が人材確保を前倒しで考えたいときにも効果があります。
以下の表は、新卒と中途採用でダイレクトリクルーティングを導入するときの特徴をまとめたものです。
ダイレクトリクルーティングのメリット5選
ここからは、ダイレクトリクルーティングの具体的なメリットを紹介していきます。
ダイレクトリクルーティングのメリット
- ほしい人材に直接アプローチできる
- 即戦力人材を採用しやすい
- 転職潜在層にコンタクトできる
- 社内の採用ノウハウを蓄積できる
- 採用コストを抑えられる
ダイレクトリクルーティングはメリットが多いので、検討してみてください。1つずつ解説していきます。
ほしい人材に直接アプローチできる
求人広告を出して応募を待つ方法では、どのような経歴や志向を持った人が応募してくるかを事前に推測しにくいです。しかし、ダイレクトリクルーティングなら理想に近い人材へ主体的に話しかけられるため、無駄打ちが少なくなります。
例
人材データベースを活用すれば、希望する経験年数や保有スキルなどで候補を絞り込みやすいです。
特に技術職や専門職で経験値の高い人と早期に話ができるメリットは大きく、競合が多い職種でも先手を打てます。
即戦力人材を採用しやすい
新しい仕事を任せたいときに、すぐ戦力になってくれる人がいると業務の進行がスピードアップしやすいです。ダイレクトリクルーティングであれば、データベースやスカウトサービスを通じて求める経験やスキルを持っている候補者と短期間で接点を作れます。
例
「マーケティング経験5年以上」「ITコンサル領域で実績を残してきた」など、具体的な条件で人材を見つけられます。すぐに詳細な役割やプロジェクト内容を伝えられるため、書類選考や面接までの流れがスムーズです。
社内に必要な人物像を明確に伝えると、興味を抱かれやすい傾向があります。中小企業でもスピード感をもって、優秀なプロフェッショナルを採用できるのが強みです。
転職潜在層にコンタクトできる
転職意欲がはっきりしていない人に対しても、ダイレクトリクルーティングなら声をかけやすいです。応募を募るだけでは出会えない層へ触れられるため、良い縁が生まれるでしょう。
ダイレクトリクルーティングで繋がれる転職潜在層
- 仕事に不満はないが、良い環境があれば転職を考える層
- 大手を視野に入れているが、中小企業の柔軟さにも関心がある層
- 将来のキャリアアップに向けて情報収集を続けている層
上記のような人々に連絡して、自社の魅力を早い段階で説明すれば、採用につながるかもしれません。自発的に転職活動を始める前の段階で自社を知ってもらうと、有望な人材を早期に囲い込めるメリットを得られます。
具体的には、以下のような方法で転職潜在層と繋がれます。
転職潜在層にコンタクトを取る方法
- SNSで直接メッセージを送る
- オフラインイベントで名刺交換をした後にスカウトを送る
- ビジネスSNSで実績を閲覧しアプローチする
社内の採用ノウハウを蓄積できる
スカウト活動や候補者との面談を自社主導で進めるため、人事担当者は自然に経験や知識を身につけていきます。例えば、どのタイミングで連絡すると返信率が上がるか、興味を引く文章の書き方はどう工夫すればよいかなど、試行錯誤で得られる学びが多いです。
ポイント
外部のエージェントに任せる方法だと細かな手応えをつかみにくいですが、ダイレクトリクルーティングでは成功や失敗の要因を把握しやすくなります。
その過程で得たスカウトメールのテンプレートや面談の進め方は蓄積され、次回以降の採用活動を円滑にする糧になります。最終的には組織全体の採用力が上昇し、長期的な人材戦略の強化につながるでしょう。
採用コストを抑えられる
人材紹介や大量広告への出稿と比較すると、ダイレクトリクルーティングは費用を抑えられるケースがあります。代表的な採用手法の費用相場をまとめた表は以下のとおりです。
ダイレクトリクルーティングは、自社担当者の時間やスキルが必要になりますが、成功すれば人材紹介より安い予算で即戦力を採用できる可能性があります。特に大規模な広告出稿やエージェントへの仲介手数料を避けたい中小企業にとって、無理のない範囲で優秀な人を探せる方法でしょう。
ダイレクトリクルーティングはHELLOBOSSがおすすめ
ダイレクトリクルーティングを実施する場合は、私たちが提供する「HELLOBOSS」がおすすめです。10万人を超えるユーザーの中から、AIが貴社に合う人材をマッチングしてくれるため、採用担当者様の負担を軽減します。
候補者と直接チャットができるため、返信率も高く、信頼関係を築きやすいのもメリットです。
月額4,000円〜でスカウトメール送り放題なので、貴社にフィットしそうな人材をAIに推薦してもらったら、積極的にアプローチしてみましょう。
無料版から始めることも可能です。テストとして使ってみてください。
わずか3ステップで始められるため、さっそくHELLOBOSSを試してみましょう。
ダイレクトリクルーティングのデメリット3選
一方、ダイレクトリクルーティングには以下のデメリットもあります。
ダイレクトリクルーティングのデメリット
- 人事担当者の業務が忙しくなる
- 採用までに時間がかかるケースがある
- 多くの人材を採用するには工数がかかる
デメリットを理解した上で、ダイレクトリクルーティングを実践してみてください。こちらも1つずつ解説していきます。
人事担当者の業務が忙しくなる
対象者の選定からスカウト文面の作成、やりとりの返信まで人事担当者の作業範囲が増加しやすいです。応募前の候補者と連絡を重ねる過程では、面談日程や質問対応など細やかな工程が続く場合もあります。
他の業務と重なると時間をさけず、全体の進捗に影響が出るかもしれません。
ダイレクトリクルーティングのタスク例
- スカウト対象のリストアップと管理
- スカウトメール文面の個別作成
- 候補者との連絡(返信作成や日程調整、Q&A対応など)
- 他部署との連携やフォロー対応
以下のように対策すると、ダイレクトリクルーティングのタスクを減らせる可能性があります。
対策案
- 採用管理システム(ATS)を導入して工数を減らす
- スカウトメールや返信文面のテンプレートを用意する
- 部署やチーム内で対応を分担してサポート体制を強化する
上記のような方法を取り入れて、全体の業務量を調整すると良いでしょう。
採用までに時間がかかるケースがある
転職潜在層へのアプローチが増えるため、採用が決まるまで時間を要する可能性があります。カジュアル面談を何度も設定して相互理解を深める場合や、候補者が他社と並行で検討を進めている際は、選考期間がさらに延びることもあるでしょう。
採用までの時間を気にする場合は、以下のような対策があります。
対策案
- ターゲットを明確にして優先度を設定し、効率的に声をかける
- 選考ステップをわかりやすく提示して、候補者の不安を軽減する
- 人材紹介やリファラル採用も併用する
ダイレクトリクルーティングは時間がかかるケースもありますが、候補者との関係を丁寧に築くことでミスマッチを減らす効果を期待できます。
多くの人材を採用するには工数がかかる
ダイレクトリクルーティングは候補者とのやりとりを1件ずつ重ねる仕組み上、大人数を迎えたいときは手間が増えやすいです。スカウト対象者リストを管理し、文面を個別調整し、進捗をすべて把握するのは手間がかかるでしょう。
| 作業内容 | 増加しやすいポイント |
|---|---|
| スカウトメールの送信 | 文面の個別作成、送信先リストの更新 |
| 候補者とのやりとり | 質問対応や面談調整で連絡の往復が重なる |
| ステータス管理 | 候補者ごとに選考進捗を把握する必要がある |
| 日程調整 | 複数候補者が同時進行するほど管理が複雑化 |
工数がかかりすぎないためには、以下のような対策が有効です。
対策案
- 送信先のターゲットを厳選し、優先順位を決めてスカウトする
- 部署を超えて協力し、メール作成や候補者リストをシェアする
- 従来の求人媒体や人材紹介なども併用する
工数増を見越して対策を打てば、効率的な運用を実現しやすくなるでしょう。
HELLOBOSSはAIで工数を削減できる
私たちが提供するダイレクトリクルーティングツールの「HELLOBOSS」は、10万人を超えるユーザーの中から、貴社にフィットする人材を推薦します。
自身で人材を探すこともできますが、時間がない採用担当者様はAIのサポートを受けながら工数を削減できます。
募集要項もAIが作成してくれるので、忙しい採用担当者様に適しているでしょう。
3ヶ月以内に人材を採用できた事例もあるため、スピーディーな採用ができる可能性があります。
無料版から始められるので、テストとして使ってみてください。
ダイレクトリクルーティングの成功事例

ここでは、AI採用ツール「HELLOBOSS」を使って、ダイレクトリクルーティングに成功した企業の事例を紹介していきます。
ダイレクトリクルーティングに成功した企業の事例
具体的な成果を見ていきましょう。
採用単価を30%削減した運輸業の活用事例
地方の運送業では、母集団形成に苦戦していたドライバー採用で、HELLOBOSSのエンタープライズプランを活用しました。
AIがターゲットへ的確にアプローチした結果、有効応募率は驚異の90%以上を達成しています。
さらに既存媒体と比較して採用単価を30%削減することにも成功。
地方の難職種であっても、ダイレクトリクルーティングならコストのメリットを最大化できます。
3名推薦で3名採用決定した情報通信業の活用事例
情報通信業の株式会社Yoii(従業員数1〜49名)では、難易度の高い「審査」と「経理・財務」の採用でHELLOBOSSを導入しました。
求職者データベースとAIマッチングによるピンポイントな採用活動を展開。
その結果、半年間で3名の推薦に対し3名の採用決定という高精度な実績を出しました。
専門性が高い職種こそ、個別にアプローチできるメリットが活きます。
2ヶ月で500名の応募を獲得した宿泊業の活用事例
あるホテル・旅館では、求人媒体だけでは人が集まらない課題に対し、HELLOBOSSのエンタープライズプランを導入しました。
AI電話機能や専属サポートを活用して候補者対応を行った結果、わずか2ヶ月で500名以上の母集団形成を実現しています。
工数を削減しながら採用数を引き上げられる点は、ダイレクトリクルーティングの大きなメリットといえるでしょう。
月40名以上の応募を獲得した飲食サービスの活用事例

飲食サービス業の「串カツ田中」では、他媒体で苦戦していた中途採用において、HELLOBOSSのSocial+プランを導入しました。
AI学習による精緻なターゲティングにより、毎月40名以上の応募をコンスタントに獲得することに成功しています。
属性が整った有効応募率の高い人材が集まり、最も効果的な採用ツールとして1年以上継続利用中。
精度の高いマッチングも大きなメリットです。
CPAを削減し応募増を実現した教育業の活用事例

教育・学習支援業の「個別教室のトライ」では、塾講師のアルバイト採用における母集団形成のために導入しました。
媒体に予算を集中させるとCPAが高騰する課題に対し、HELLOBOSSのSocial+プランを活用。
その結果、過去平均よりも安価なCPAで応募を獲得できています。
2週間で2名の採用に成功したサービス業の活用事例
サービス業のフィナンシャルフィールパートナーズ(従業員数1〜49名)では、経理経験者の採用でHELLOBOSSのProプランを導入しました。
AIマッチングとスカウト機能を活用し、わずか2週間で2名の採用に成功しています。
小規模組織でも、AIを活用してピンポイントに即戦力へアプローチできるため、短期間で採用課題を解決できるのがダイレクトリクルーティングの強みです。
ハイクラス層を獲得した自動車ディーラーの活用事例
ある自動車ディーラーでは、26卒に向けて説明会やインターンの集客として、HELLOBOSSのエンタープライズプランを活用しました。
ナビサイトにまだ登録していないユーザーに対して早期にアプローチを実施。
その結果、これまで獲得できていなかったハイクラス層を含め、100名のエントリー獲得に成功しました。
潜在層へ早期に接触できる点は、この手法ならではの利点です。
ダイレクトリクルーティングと他の採用手法の比較表
ダイレクトリクルーティングは候補者へ直接声をかける方法ですが、他にも求人サイト、人材紹介サービス、採用イベント、リファラル採用、ヘッドハンティングなど、いろいろな手段があります。
以下の表では、それぞれのメリットとデメリットをまとめています。自社の採用条件やリソースに応じて、最適な組み合わせを考えてみてください。
それでは、ダイレクトリクルーティングとそれ以外の採用手法の比較を詳しく解説していきます。
求人サイトとの比較
求人サイトは母集団形成の面で強く、大きな露出を狙いやすい反面、要件と異なる応募も集まりがちです。
一方、ダイレクトリクルーティングは候補者を厳選できるので質の面で利点があります。ただし、担当者の業務量が増えやすいので、社内リソースを見直しながら進める必要があります。
人材紹介サービスとの比較
人材紹介サービスは短期間で対象者を紹介してもらえるのがメリットです。
ダイレクトリクルーティングは自社で動く分、ノウハウを蓄積しながらコストを抑えやすいでしょう。
採用イベントとの比較
採用イベントは短期間で多くの候補者に出会えるため、ブランディング面でも活かしやすいです。
一方、ダイレクトリクルーティングはオンラインベースでじっくり候補者を探せるので、ターゲットを絞った採用を目指す場合に適しています。
リファラル採用との比較
リファラル採用は候補者と社内のメンバーにすでに信頼関係があることが多く、入社後のミスマッチを減らしやすいです。一方、ダイレクトリクルーティングは外部の人材にも幅広く声をかけたい場合に活きるでしょう。
ヘッドハンティングとの比較
ヘッドハンティングはハイレベルな人材を引き抜く手段として有効です。一方、ダイレクトリクルーティングは専門家を介さないため、コストを抑えながらターゲットの範囲を柔軟に広げたい場面で検討しやすいです。
ヘッドハンティングはハイレベルな人材を引き抜く手段として有効です。一方、ダイレクトリクルーティングは専門家を介さないため、コストを抑えながらターゲットの範囲を柔軟に広げたい場面で検討しやすいです。
ダイレクトリクルーティングはHELLOBOSSがおすすめ
くりかえしですが、ダイレクトリクルーティングでは、私たちが提供する「HELLOBOSS」がおすすめです。候補者と直接チャットができるため、返信率も高く、信頼関係を築きやすいメリットがあります。
さらに、10万人を超えるユーザーの中から、AIが貴社に合う人材をマッチングしてくれるため、採用担当者様の負担を軽減します。
月額4,000円〜でスカウトメール送り放題なので、貴社にフィットしそうな人材をAIに推薦してもらったら、積極的にアプローチしてみましょう。
無料版から始めることも可能です。テストとして使ってみてください。わずか3ステップで始められるため、さっそくHELLOBOSSを試してみましょう。
ダイレクトリクルーティングの料金形態
ダイレクトリクルーティングには、主に2つの料金形態があります。
ダイレクトリクルーティングの料金体系
- 定額制
- 成功報酬タイプ
サービスを利用する場合は、料金体系を確認しましょう。それぞれの料金体系を解説していきます。
定額制
定額制は導入時からコストが発生するものの、採用人数に上限がないため、複数人を狙う企業に向いています。
定額制の特徴
- 利用期間やスカウト可能数などを基準に、費用を前払いする
- 導入中の採用人数が増えても追加料金がかからないケースが多い
- 成果が出なかった場合でも費用が発生するリスクがある
- 利用開始前に契約期間や初期料金などを確認しておくと安全
人事担当者が「半年間でエンジニアを3人以上取りたい」という場合や、「1年間を通じて総合職を数名採用したい」という状況で採用効果が高まりやすいです。反対に、単発の採用だけで終わる見込みなら、定額制のメリットが出にくいかもしれません。
サービスによってはスカウトの通数上限が細かく決まっているため、契約前に自社の必要人数と合致するかどうかを検討すると無駄を減らせます。
成功報酬タイプ
成功報酬タイプは、採用人数に見合った支出となる点が特徴です。
| 料金発生のタイミング | 採用が確定したときに費用が生じる |
|---|---|
| 費用体系の目安 | 採用人材の年収×◯%(例:30%)などの変動制が一般的 |
| メリット | 採用が成立しない限りコストが発生しない |
| デメリット | 成功時の支払い額が大きくなりがち 複数名を採用するほど合計費用が高まる |
複数人を一度に採用すると金額が高騰するため、費用上限をあらかじめ検討しておかないと予算オーバーのリスクがあります。内定辞退や早期離職などがあった場合に部分返金を受けられるサービスもあるので、契約前に規定を確認するのが安心です。
ダイレクトリクルーティングの具体的な方法一覧
ダイレクトリクルーティングには、以下のような方法があります。データベースから人材を探す以外にも方法があるので、自社に合いそうな方法を組み合わせましょう。
ダイレクトリクルーティングの方法
- スカウトサービスの人材データベースを利用する
- SNSで情報発信しながらスカウトメールを送る
- オフラインでアプローチする
- リファラル採用と組み合わせる
- オウンドメディアから問い合わせを起こす
- インターンシップを実施する
1つずつ詳しく解説していきます。
スカウトサービスの人材データベースを利用する
人材データベースを活用すると、ピンポイントなプロフィールをもつ候補者を探しやすいです。検索フィルターが充実しているため、自社が求める経歴やスキルセットで絞り込みができます。以下は、おおまかな利用手順の例です。
| 利用手順 | 詳細 |
|---|---|
| 契約・登録 | スカウトサービスを提供する外部企業と契約し、アカウントを作成する |
| 検索条件の設定 | 職種、経験年数、勤務地など、欲しい人材の条件を具体的に入力する |
| 候補者のピックアップ | 表示された候補者情報を確認し、自社ニーズに近い相手を選ぶ |
| スカウトメール送信 | 送る文面をカスタマイズし、相手に興味を持ってもらえる内容を意識する |
| 返信対応・面談調整 | 候補者から反応がきたら日程や条件を確認して、面談・選考へと進める |
候補者を効率的に見つけるには、こまめに検索条件を見直し、進捗管理を徹底するのがコツです。競合他社も同じデータベースを利用している場合が多いため、スカウトのスピードや文面の工夫が採用成功のカギになります。
ポイント
候補者の興味を引く文面の書き方は、ダイレクトリクルーティングのスカウトメールのコツから解説しています。
人材データベース型はHELLOBOSSがおすすめ
私たちが提供する「HELLOBOSS」は、定額型のダイレクトリクルーティングツールです。10万人を超えるユーザーの中から、AIが貴社に合う人材をマッチングしてくれます。
月額4,000円〜でスカウトメールを送り放題です。
無料版から始めることもできるので、テストとして使ってみてください。
SNSで情報発信しながらスカウトメールを送る
ダイレクトリクルーティングには、SNSで自社の魅力を発信して興味をもったユーザーに直接スカウトを送る方法もあります。投稿を通じて社内の雰囲気や働き方を見せると、候補者からのアクションを得やすいです。SNSの種類ごとにユーザー層や拡散力が異なるため、狙いに合わせて使い分けましょう。
| SNS名 | 特徴 |
|---|---|
| X(旧Twitter) | 拡散されやすく、個人のフォロー文化が強い。瞬時に情報が広がりやすい。 |
| ビジネス特化型で職歴や経歴が明確。転職潜在層も多く集まる。 | |
| リアルのつながりを持つユーザーが多い。認知度は高いが若年層は減少傾向。 |
あくまで一例ですが、X(旧Twitter)なら短文中心で拡散を狙え、LinkedInはスキルや肩書を重視する中途転職層が多めです。Facebookであれば既存の人脈と連動しやすいメリットが見られます。企業アカウントの運用を担当者が継続的に行い、興味をもったユーザーに対してDMやスカウトを送るのが一般的です。
ちなみに、企業のSNS運用については、採用SNS戦略を成功させる!利点を最大化する10のステップ徹底解説に詳しくまとめています。
オフラインでアプローチする
ダイレクトリクルーティングは、オンラインに限らずオフラインでも実践できます。業界の勉強会や技術セミナー、カンファレンスなどに企業スタッフが出向き、参加者と名刺交換しながら興味のある相手に声をかける方法です。
対面で話せる場では、個性や相手のモチベーションをつかみやすいメリットがあります。
例
エンジニアが集まるイベントで「自社プロジェクトへの知見が深い人材」を見つけたり、デザイナー向けの交流会で「UI/UXスキルが高い人」を発掘したりします。実際の場だからこそのつながりが生まれやすいです。
ただし、イベント開催日程や場所が限られるため、定期的にアンテナを張っておくことが推奨されます。イベント後の連絡をスムーズにするため、採用担当がリストを整理することも必要です。
リファラル採用と組み合わせる
リファラル採用は社内の従業員が知人や友人を紹介し、ダイレクトリクルーティングと合わせて候補者を探す手段です。すでに社員との縁がある相手なので、自社カルチャーに合うかどうかを見極めやすいメリットがあります。
社内メンバーにインセンティブを設定して積極的な紹介を促す企業もあり、自然な形で候補者が集まるケースが見られます。
ポイント
紹介だけでは人数が足りない場合、スカウトサービスやSNSなど他の方法と連動して母集団を補うのが効果的です。
たとえば「5人はリファラルで集めるが、専門職はスカウトメールを活用してピンポイントで探す」という運用もあるでしょう。リファラル採用は既存メンバーが実情を伝えやすいので、お互いの理解度が深まりやすいです。
オウンドメディアから問い合わせを起こす
企業が運営するオウンドメディアに、自社の取り組みや社員の声などを掲載して候補者の関心を引き、問い合わせへつなげる方法です。読者が記事を通じて企業のカルチャーやビジョンを理解するため、転職意欲を高める効果があります。
例えば、開発ブログでプロジェクトの進行状況を定期的に紹介すれば、エンジニア層がどのような技術スタックや課題に興味を持つかを把握できるでしょう。
オウンドメディアの具体例
- 開発ブログ:技術面や制作事例を社員の目線で発信
- 採用特化サイト:募集職種や社員インタビューを集約するページ
- コンテンツ配信:候補者に役立つノウハウを発信して興味づけ
オウンドメディアで企業の魅力を伝えると、読者から「直接話を聞きたい」という問い合わせが増えやすいです。問い合わせをきっかけにして、面談へ誘導するケースもあります。
インターンシップを実施する
インターンシップを開催して、参加者と直接やりとりすることで採用につなげる手法もダイレクトリクルーティングに含まれます。新卒だけでなく、中途向けの短期インターンを実施する企業も増えました。
ポイント
リアルな職場体験を経験してもらい、相手がどのような能力を持つかを見極めつつ、入社意欲を高める狙いです。
エンジニアやデザイナーの場合、実際の業務に近い課題に取り組んでもらうことで、スキル面やチームとの相性を把握しやすいでしょう。例えば2週間のインターン期間中にプロジェクトへ参画してもらい、最終日に成果物を披露するプログラムを組むのも有効です。
本人にとっても社内の空気を直接感じられる機会になり、相性を確かめられます。
ダイレクトリクルーティングが向いている企業の特徴
ダイレクトリクルーティングの特徴を解説してきましたが、それを踏まえて「ダイレクトリクルーティングが向いている企業の特徴」を紹介します。
ダイレクトリクルーティングが向いている企業の特徴
- 少数の優秀な人材を採用したい企業
- 専門性の高い人材を採用したい企業
- 知名度が低くて応募が集まりにくい企業
- 自社の魅力をアピールできる企業
- 人材不足が深刻な職種を採用したい企業
1つでも該当しているなら、ダイレクトリクルーティングを始めてみましょう。
こちらも1つずつ解説していきます。
少数の優秀な人材を採用したい企業
少人数の精鋭を採用したいと考える企業は、ダイレクトリクルーティングを通じて条件に合う相手を探しやすいです。ターゲットを絞り込み、スキルや実績を確認しながら個別にアプローチすれば、相手が転職潜在層であっても興味を示してくれる可能性があります。
ダイレクトリクルーティングで見つけやすい人材例
- 難易度の高い技術課題をクリアしたエンジニア
- 新興市場の事業拡大を単独で成功させたマネージャー
- 海外展開のプロジェクトを率いて成果を上げたコンサルタント
このような実績を備える人材は市場に出回りにくく、ダイレクトリクルーティングで積極的に働きかける必要があります。スキルや経歴をヒアリングし、自社でどう活躍してもらいたいかを明確に伝えると入社意欲を高めやすいです。
専門性の高い人材を採用したい企業
高度な専門スキルを求める場合も、ダイレクトリクルーティングとの相性が良いです。応募型ではそもそも対象者が少なく、求人情報を見てもらえる確率が低いこともあります。
そこで、データベースやSNSなどで該当する経歴をもつ相手をリサーチし、直接オファーを送る流れならば、スピーディに話を進められます。
専門性の高い人材の具体例
- 機械学習エンジニア
- バイオテクノロジー研究員
- フィンテック領域のブロックチェーン開発者
- 宇宙衛星データ解析のデータサイエンティスト
- 自動車の自動運転アルゴリズム設計担当
このような人材は、今すぐの転職を考えていなくても、直接話を持ちかければ検討のきっかけになりやすいです。たとえば「自動運転開発に強みをもつ大企業から急成長中のベンチャーへ誘う」など、相手のキャリアを高める提案ができると良いでしょう。
知名度が低くて応募が集まりにくい企業
ブランド力が弱く、従来の求人サイトに掲載しても応募数が伸びないケースでは、ダイレクトリクルーティングがおすすめです。知名度が低い企業は候補者から「社名を聞いたことがない」と敬遠されがちですが、直接コンタクトを取れば現場の魅力や成長を伝えるチャンスが生まれます。
ポイント
ダイレクトリクルーティングでは、人材データベースやSNS検索でスキルセットに合う相手を探し「自社はこんな技術に挑んでいる」とアピールできます。
相手も興味を抱けば「知名度が低いが面白そう」とポジティブな印象に変わるかもしれません。信用を補うために、開発実績や顧客事例などをSNSやオウンドメディアで紹介するのも効果的です。
自社の魅力をアピールできる企業
ダイレクトリクルーティングは、候補者と直接やりとりするため、会社のビジョンやカルチャーをストレートに伝えやすいです。自社の社員が目指している将来像や技術力へのこだわり、組織体制の柔軟さなどを伝えれば、スキル以外の面でも相手が惹かれる可能性があります。
例
起業家精神を大切にしているベンチャー企業なら、経営メンバーと直に話をしてもらう機会を設けましょう。「社内でのキャリアアップが実践しやすい」といった魅力が具体的に伝わります。
福利厚生の詳細や仕事のやりがいを、メールだけでなく、カジュアル面談やSNS配信でも発信すると良いでしょう。
事前に企業理念や職場の特徴をまとめておくと、候補者からの興味を獲得しやすいです。面接前のやりとりで「仕事が面白そう」と印象づけられれば、入社意欲に直結します。
人材不足が深刻な職種を採用したい企業
売り手市場になりやすい分野では、応募を待つ受け身の姿勢だけでは採用が難しいです。そこで、ダイレクトリクルーティングを使って人材を探し出し、直接スカウトしてみてください。
早期にコンタクトを取り、条件や魅力を提示できる企業が採用競争をリードしやすいです。
人材不足が深刻な職種の具体例
- 保育士
- ITエンジニア
- 施工管理技士
こうした分野では、ダイレクトリクルーティングで相手の職場環境への不安や条件面の希望を直接ヒアリングし、スムーズに内定まで導けるチャンスがあります。
ダイレクトリクルーティングはHELLOBOSSがおすすめ
くりかえしですが、ダイレクトリクルーティングでは、私たちが提供する「HELLOBOSS」がおすすめです。
10万人を超えるユーザーの中から、AIが貴社に合う人材をマッチングしてくれるため、採用担当者様の負担を軽減します。
候補者と直接チャットができるため、返信率も高く、信頼関係を築きやすいメリットがあります。
月額4,000円〜でスカウトメール送り放題なので、貴社にフィットしそうな人材をAIに推薦してもらったら、積極的にアプローチしてみましょう。
3ヶ月以内に人材を採用できた成功事例もあります。
ダイレクトリクルーティングのプロセス|6ステップで解説
実際にダイレクトリクルーティングを始めていく際は、以下の6ステップで進めていけばOKです。
ダイレクトリクルーティングのプロセス
- 採用目標の設定や予算の調整
- 採用ペルソナの設定と人材の検索
- スカウトメール文の作成
- メール送信後の候補者とのやり取り
- 選考フローに沿った採用活動の実施
- 内定後フォローと入社後のサポート
1ステップずつ解説するので、さっそく始めていきましょう。
採用目標の設定や予算の調整
まず「誰を何人採用したいか」を明確にしておきます。必要なスキルや期待する成果を決めると、使うべきサービスの方向性が決まります。
以下は採用目標の具体例です。
採用目標の例
- 新卒枠で営業経験ゼロの若手を3人採用する
- デジタルマーケティング経験3年以上の即戦力を2人採用する
- 管理職候補としてマネージャーレベルの人材を1人採用する
計画を立てる段階でおおよその採用単価を想定し、合計額を算出します。
ダイレクトリクルーティングを含め、複数のチャネルを組み合わせる方針を立てるなら、どれにどのくらい配分するかも調整しましょう。事前に予算を固めておけば、適切なプランを選びやすいです。
採用ペルソナの設定と人材の検索
社内で求める人物像を言語化し、ペルソナを考案します。例えば「スタートアップの営業を2年以上経験し、目標達成率が高い」など具体的な要素を洗い出すと、人材を探すときの指標になります。
ポイント
既存社員の成功事例を参考にすると、どんな人材を採用すべきかわかりやすいです。
データベース上で年齢・職歴・持っている資格などを入力して、ペルソナに近い人材を探してみましょう。
ちなみに、採用のペルソナは以下のステップで設定すればOKです。
採用ペルソナを設計するステップ
- 採用したい人材像を社長や現場に聞く
- 人材を採用する目的を定義する
- 採用したい人材像を書き出す
- 採用市場に合わせたペルソナにする
- ペルソナを経営層や現場のメンバーに確認してもらう
詳しいペルソナの設定方法は、採用ペルソナの作り方完全ガイド|テンプレートと7ステップのフレームワークを参考にしてみてください。
スカウトメール文の作成
ダイレクトリクルーティングの成否は、最初に送るメッセージで左右されやすいです。温かみを感じる文章と、具体的なポジションの説明があると興味を引きやすいです。
ポイント
相手がどんな経歴や成果を持っているかに触れながら「なぜ声をかけたいのか」を簡潔に添えてください。単に「興味があります」だけでは相手の印象は薄いです。
相手がイメージしやすい役割や待遇を例示し、企業の強みも一文で示すと良いでしょう。忙しい人は一瞬で判断するため、最初から本題を伝えると読むモチベーションが上がります。
具体的なスカウトメールの例文は、スカウトメールの例文で紹介しているので、参考にしてみてください。
メール送信後の候補者とのやり取り
最初のメッセージを送ったあと、相手から返信が来た段階でコミュニケーションが始まります。温度感がわからないまま次の連絡を遅らせると、他社と比較検討されやすくなるため気をつけましょう。
以下は候補者とのやりとりの例です。
一度で決まらなくても粘り強くやり取りすればチャンスはあります。早めのレスポンスと誠意ある対応を心がけましょう。
選考フローに沿った採用活動の実施
候補者と対面やオンラインで話し、双方が納得できる形で選考を進めます。
ここでは候補者体験(CX)を向上させましょう。面接日時をスピーディーに調整し、当日も温かい雰囲気で迎えると、相手がストレスを抱えにくくなります。
待遇説明や質疑応答を丁寧に進め、双方が納得したうえで次のステップへ進むのが理想的です。円滑なプロセスは「この会社で働いてみたい」という気持ちを強めます。
内定後フォローと入社後のサポート
内定を出してから実際に入社するまでには時間があり、モチベーションが下がる危険があります。そこで入社の意思を強固にするための接触が必要です。
例えば以下のようなフォローが良いでしょう。
内定後フォロー
- 週1回の連絡をとり、疑問を解消する
- 内定者向けの懇親会やオンライン交流会を開催する
- 社員との座談会で職場のイメージを具体化してもらう
また、入社後のサポートは配属先や仕事内容に馴染めるように準備していきましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 初期研修 | 1〜2週間で社内規定や業務全般を学ぶプログラムを用意 |
| メンター制度 | 配属先の先輩が新入社員を定期的にフォローし、悩みを聞く |
| 中長期ゴール設定 | 半年後や1年後に目指す姿を共有し、評価指標を明確にする |
| チームビルド | オンライン含む懇親会やコミュニケーションツールを活用し、交流を深める |
こうしたサポート体制を整えると、早期離職を防ぎながら職場へスムーズに馴染む下地を作りやすいです。
ダイレクトリクルーティングのスカウトメールのコツ
ダイレクトリクルーティングで成果を出すには、スカウトメールで候補者の興味を引かなければなりません。
以下にスカウトメールのコツをまとめたので、実践していきましょう。
スカウトメールのコツ
- 候補者ごとにメール文を作成する
- メール送信の時間帯と頻度を決めておく
- スピーディーに返信する
- 自社で働くメリットを伝える
- 入社後の具体的なポジションを伝える
- カジュアル面談を提案する
こうしたコツを丁寧に実践することで、成果に繋がります。こちらも1つずつ解説していきます。
候補者ごとにメール文を作成する
まずは候補者のプロフィールを見たうえで、スキル・経歴・趣味などに触れた文面を心がけましょう。画一的なひな形のメールを送り続けると、自分が求められているかどうかを疑われます。
過去の仕事の成果を具体的に挙げながら「その経験をぜひ活かしてほしい」というニュアンスを加えると熱意が伝わりやすいです。
ポイント
候補者が運営するSNSやブログがあれば、活動内容を引用するのも効果的です。「◯◯の発信を拝見し、分析力が優れていると感じました」という一文を足すだけで、相手の人柄を把握している印象を与えられます。
こうした特別感や親近感が高まるようなアプローチが、次のやり取りへ発展するきっかけになります。
ちなみに、スカウトメールのテンプレートは以下のとおりです。
スカウトメールのテンプレート
- 相手への敬称と簡単な自己紹介
- 見つけた経緯や興味を抱いた経歴のポイント
- オファーしたいポジションと具体的役割
- 予想年収や勤務地などの条件
- 求める理由や自社の特徴
- 面談や日程調整の誘導
- 感謝の言葉と連絡先
では、スカウトメールの例文も紹介します。
スカウトメールの例文
スカウトメールの例文
件名:企画力をお持ちの◯◯様へ|プロジェクトリーダー候補としてお声がけ
本文:
◯◯様
はじめまして。◯◯株式会社で採用担当を務める△△と申します。SNSでのご実績を拝見し、斬新なアイデアに共感しました。
現在、弊社では新規プロダクトの開発を進めており、ユーザー体験を向上させるアイデアを積極的に取り入れたいと考えています。
◯◯様が主導したプロジェクトの事例を拝見したところ、非常に優れた分析力と柔軟な発想をお持ちではないかと感じました。
今回のポジションでは、少数精鋭のチームでサービス企画を進めながら、メンバーの育成や新機能の方向性を決定していただく見込みです。
年収は経験に応じて〜〜万円を想定し、週2回のリモート勤務も整えています。弊社は新しい発想を歓迎し、自由な意見交換を推奨する風土が強みです。
もし少しでも関心を持っていただけるようでしたら、オンライン面談で詳しい内容を共有できれば幸いです。30分ほどお時間をいただけないでしょうか。
日程が合わない場合は他の枠も提案いたします。ご検討、よろしくお願いします。◯◯株式会社
採用担当:△△
メール:contact@example.com
電話:00-0000-0000
上記のテンプレートは、候補者の経歴やスキルに合わせて内容を変えると効果的です。相手の実績を的確に褒める部分と、具体的なポジションを伝える部分を整理しましょう。
定型文で終わらせず、相手の個性を踏まえた訴求を加えると返信率がグッと高くなるでしょう。
メールを送ったあとのフォローや日程調整もスピーディーに進めると、候補者に好印象を与えやすいです。
メール送信の時間帯と頻度を決めておく
通勤中や休憩のすき間にスマホを確認する人が多いという理由から、朝や昼の時間帯を狙うとメールを読んでもらいやすいです。
送る回数については、しつこく連絡すると逆効果です。一定の間隔をあけて「前回のメールをご覧いただけましたか?」と尋ねる程度に抑えましょう。
ポイント
メールを送る日時と回数を事前に決めておけば、忙しさに流されてタイミングを逃すのを防ぎやすいです。
開封率や反応をテストしながら微調整すると、最適な送信パターンが見えてきます。
スピーディーに返信する
候補者から何らかのリアクションがあったら、すぐに返事しましょう。レスポンスが遅いと熱意を疑われ、他の会社に先を越される恐れがあります。
ポイント
質問への回答を早く用意したり、次の面談日程をいくつか挙げるなど、テンポよくやり取りするのがコツです。
連絡がワンテンポ早いだけで「担当者がしっかりしている」と感じてもらいやすくなります。候補者が複数のオファーを比較している場面では、その印象が結果を左右するかもしれません。
担当者が兼任業務を抱えているなら、あらかじめメール用の時間帯やツールを整えておき、候補者を待たせない仕組みを作っておきましょう。
自社で働くメリットを伝える
候補者は入社後の働き方だけでなく「先のキャリア」にも関心を持ちやすいです。そこで、最初のメールで将来像をイメージしやすい情報を示すと、返信率が上がります。
以下は職種ごとの「自社で働くメリット」の具体例です。
上記のように職種とメリットを結びつけて提示すると、相手は「入社後のキャリアパス」をより鮮明に思い描きやすくなります。また、実際の事例や先輩の成功パターンを紹介すれば、候補者が将来を想像するきっかけになり、入社への意欲が高まります。
入社後の具体的なポジションを伝える
候補者は「役割や責任範囲がどのくらいか」を気にするものです。そこで具体的なポジションをイメージしやすいように説明すると良いでしょう。
以下の例を参考にすると伝わりやすいです。
| 職種 | 具体的なポジション |
|---|---|
| 開発リーダー | 5名のチームを率いて新規アプリを立ち上げ |
| 経営企画スタッフ | 市場調査や数値管理を通じて事業計画に関わる |
| 営業マネージャー | 若手2名を指導しながら既存顧客との関係を強化 |
| 人事リーダー | 採用や教育などの全体設計に参加し、施策を推進 |
| マーケティング担当 | キャンペーン施策からSNS運用まで一貫して担当 |
こうした職務内容が明確になっていると「自分ならどんな強みを出せるか」が考えやすくなり、返信をもらう確率も上がります。
カジュアル面談を提案する
スカウトメールで興味を持ってもらったあと、いきなり面接を要求するとハードルが高いです。そこでカジュアル面談を提案すると、候補者の心理的負担が和らぎます。
カジュアル面談のコツ
雑談も交えながら、会社の雰囲気や具体的な業務内容を説明すると自然なコミュニケーションが進みやすいです。
カジュアル面談はオンラインで実施しても効果があります。質問を受け付ければ、相手の不安を早めに解消し、志望度を高められるでしょう。
最初の段階で「応募義務はない」と伝えておけば、候補者は気軽に参加しやすくなります。結果として、自社に合う人材を掘り起こす場面が増えていきます。
ダイレクトリクルーティングで継続的に成果を出すコツ
ダイレクトマーケティングのノウハウを自社で積み上げていくと、安定して採用の成果を出せるようになります。
継続的にダイレクトリクルーティングで成果を出すコツは、以下のとおりです。
ダイレクトリクルーティングで継続的に成果を出すコツ
- 社内の改善を継続していく
- 経営層や現場のメンバーに協力してもらう
- PDCAサイクルを回しながら改善していく
こちらも1つずつ解説していくので、実践していきましょう。
社内の改善を継続していく
以下のような要素を継続的に改善していきましょう。
社内で改善していくこと
- 待遇
- 研修内容
- 業務のジャンル
- 使用ツール
- 職場環境 など
これらを常に改善していくことで、求人内容が魅力的になり、人材を採用しやすくなります。もちろんこうした改善はすぐにできることではありません。しかし、徐々に改善していくことで、人材が集まりやすくなっていくでしょう。
人事担当者だけでできることではありませんが、経営層にも理解してもらいながら進めていく必要があります。
経営層や現場のメンバーに協力してもらう
人事だけでなく、経営層や現場チームが採用活動へ積極的に参加すると、候補者が安心感を持ちやすいです。
ポイント
経営層が直接面談で会社の将来像を話せば、入社後のキャリアを具体的に想像してもらいやすくなります。
現場メンバーには実務内容を説明してもらったり、普段の空気感を伝えてもらったりすると、候補者が転職後の姿をイメージしやすいでしょう。
例えば、エンジニアなら使用している言語やプロジェクトの進め方を詳しく伝えると、候補者が「自分のスキルを活かせそうか」を判断しやすくなります。転職後のイメージが良ければ、採用に繋がりやすいです。
経営層と現場が一枚岩となり、スカウトメールや面談に取り組めば、候補者の興味を引く確率が高まります。
PDCAサイクルを回しながら改善していく
ダイレクトリクルーティングでは、単純な書類選考数だけでなく、スカウト承諾率なども含めた採用KPIを設けましょう。
「採用KPI」とは、採用のフェーズごとの移行率のことです。
例えば「月内に50通スカウトを送って何件返信があったか」「内定まで進んだ割合はどうか」を定期的に振り返ります。
検証の結果、ターゲット層の条件設定を再考したり、メール文章を修正する判断ができるかもしれません。オファーが断られた場合でも、理由を把握して方針を修正すれば次の機会につながります。
こうしたPDCAサイクルを粘り強く続ければ、採用手法そのものをブラッシュアップでき、質の高い候補者とマッチングする頻度も上昇しやすくなります。
ちなみに、採用KPIを設定する流れは以下のとおりです。
採用KPIを設定する5ステップ
- KGIを設定する
- 採用チャネルの選考フローを決める
- 歩留まり率を調べる
- KGIから逆算してKPIを設定する
- KPIをまとめて共有する
採用KPIを設定する方法の詳細は、採用KPIを設定する5ステップ|4つの運用のコツと注意点も解説にまとめています。
ダイレクトリクルーティングでよくある質問
最後に、ダイレクトリクルーティングについてよくある質問に答えていきます。
ダイレクトリクルーティングの社内稟議を通すコツは?
まずは費用対効果を数字で示すと、判断材料として有益です。
例
「従来の人材紹介では年収の25%を手数料に払っていたが、ダイレクトリクルーティングなら成果によっては費用が下がる」といった形で比較します。
候補者の質やスカウト後の動向もあらかじめシミュレーションしておくと説得力が増すでしょう。さらに、他社事例を取り入れ、「月何回スカウトを送って何名が内定につながったか」を示すのも有効です。
データと事例を組み合わせて企画書を作ると、経営層も判断しやすいです。
担当者の増員やツール導入の必要性があるなら、そこも含めて整理し、トータルでどの程度のコストメリットがありそうかを伝えると理解が得られるでしょう。
採用経験が浅い担当者でもダイレクトリクルーティングできる?
経験が少ないままダイレクトリクルーティングを実施するのはハードルが高そうに思えますが、むしろ早い段階でノウハウを蓄積しておく好機ともいえます。最初はターゲット設定やスカウトメールの書き方などで戸惑うかもしれませんが、基本的なフローはシンプルです。
ダイレクトリクルーティングのプロセス
- 採用目標の設定や予算の調整
- 採用ペルソナの設定と人材の検索
- スカウトメール文の作成
- メール送信後の候補者とのやり取り
- 選考フローに沿った採用活動の実施
- 内定後フォローと入社後のサポート
初期は多くの試行錯誤が必要になりがちですが、一度送ったスカウトの返信率を検証し、少しずつ文面を変えながらコツをつかむと改善が進みます。
迷った場合は、社内の先輩や外部セミナーで手法を学ぶのも良いでしょう。問い合わせや成功事例を収集しながら取り組めば、短期間で慣れていきやすいです。
担当者が経験を深めるほど、候補者とのコミュニケーションにも余裕が生まれ、社内でも採用手段を広める中心的な役割を果たしやすくなります。
新卒採用のダイレクトリクルーティングのコツは?
就活サイトだけに頼りたくない場合、ダイレクトリクルーティングで新卒を狙うのも有効です。学生の興味関心を引き、対話の機会を早めに作るようにしましょう。
新卒のダイレクトリクルーティングのコツは以下のとおりです。
| コツ | 概要 |
|---|---|
| SNSや学校別のコミュニティをリサーチ | オープンな場で活動や研究成果を発信している学生を発見し、直接メッセージを送る。 |
| イベントやインターンとの連動 | カジュアル面談で好印象を得た学生にはインターンを案内し、職場を体験してもらう。 |
| 経営者やリーダーが学生と話す機会を設定 | 企業のビジョンや事業展望をトップから伝え、将来性を感じてもらう。 |
| 短期・長期インターンを柔軟に組む | 学業の都合に合わせて業務時間を調整し、学生が挑戦しやすい環境を用意する。 |
スカウトメールでは「大学での活動やサークル経験に興味を持った理由」を示すと親しみを感じやすいです。全体として敷居を低めに設定し、いきなり面接ではなくカジュアル面談から入ると応募意欲につながりやすくなります。
中途採用のダイレクトリクルーティングのコツは?
転職経験がある層は業務への要望や条件が明確なので、先読みしながらアプローチするのがコツです。専門知識を持っている候補者も多いため、スカウト内容のレベルを上げると本気度が伝わるでしょう。
中途採用のダイレクトリクルーティングのコツは以下のとおりです。
| コツ | 概要 |
|---|---|
| 経歴をしっかり読み取り、実績を褒める | 「◯年に渡って営業成果を伸ばしてこられた点を高く評価しています」といったコメントを添える。 |
| 待遇や役割を具体的に示す | 年収レンジやポジション名だけでなく、担当するプロジェクトやキャリアプランにも触れる。 |
| 現場メンバーや経営層も交えた面談 | 実務レベルの話と将来性の話が同時に聞ける場を作ると説得力を増やしやすい。 |
| 短いスパンでフォロー | 転職顕在層は複数社を検討しがちなので、早めに連絡や面談日程を調整する |
こうした工夫を積み重ねれば、候補者からの返信率や内定承諾率を高める効果が期待できます。
ダイレクトリクルーティングとダイレクトソーシングの違いは?
両方とも「企業が候補者へ直接アプローチする」スタイルを指す言葉ですが、使われる場面でややニュアンスが異なります。
ダイレクトソーシングとは
欧米で普及しており、人材紹介会社を経由せずに自社で採用活動を進める手法を指します。
ダイレクトリクルーティングとは
日本で定着している用語で、主に「データベースやSNSなどを活用して候補者を探し、スカウトメールを送る」という手法を指します。
企業が主導権を握って候補者を探す「攻めの採用」という点では変わりありません。
まとめ|ダイレクトリクルーティングはおすすめの採用手法
さっそく以下のステップに沿って、ダイレクトリクルーティングを始めていきましょう。
ダイレクトリクルーティングのプロセス
- 採用目標の設定や予算の調整
- 採用ペルソナの設定と人材の検索
- スカウトメール文の作成
- メール送信後の候補者とのやり取り
- 選考フローに沿った採用活動の実施
- 内定後フォローと入社後のサポート
ダイレクトリクルーティングを実施する場合は、私たちが提供する「HELLOBOSS」がおすすめです。
10万人を超えるユーザーの中から、AIが貴社に合う人材をマッチングしてくれるため、採用担当者様の負担を軽減できます。
候補者と直接チャットができるため、返信率も高く、信頼関係を築きやすいのもメリットです。
月額4,000円〜でスカウトメール送り放題なので、貴社にフィットしそうな人材をAIに推薦してもらったら、積極的にアプローチしてみましょう。
無料版から始めることも可能です。テストとして使ってみてください。
わずか3ステップで始められるため、さっそくHELLOBOSSを試してみましょう。
貴社の採用活動の参考になれば幸いです。