「整備士の採用がうまくいかない…」
「有効求人倍率が高すぎて、なかなか他社との競争に勝てない…」
このように頭を抱える採用担当者や経営者の方に向けた記事です。
この記事でわかること
- 整備士の採用が難しい5つの原因
- 整備士採用を成功させる10の対策
- 整備士採用におすすめの採用チャネル
整備士の採用難は、原因を正しく理解し、採用ターゲットの拡大や労働環境の改善といった適切な対策を組み合わせることで解決できる可能性があります。
給与や労働環境といった業界特有の課題に対し、具体的な解決策を実行することで、採用競合との差別化を図れるためです。
なかなか応募が集まらず、本当に悩みますよね?
この記事を読むことで、整備士採用の課題を克服し、自社にマッチした人材を確保するための具体的なアクションプランが明確になります。
最後まで読んで、さっそく採用活動を前に進めていきましょう。
おすすめのAI採用ツール
私たちが提供する「HELLOBOSS」は、10万人を超えるユーザーの中から、AIが貴社に合う整備士候補を推薦するダイレクトリクルーティングツールです。
資格や経験年数など、細かい条件で候補者を探せます。
無料から試せるので、AIに最適な人材を推薦してもらいながら検討してみてください。
Contents
データで見る整備士採用の厳しい現状
はじめに、整備士の採用がどれほど厳しい状況にあるのかを、国の公表するデータから見ていきましょう。
データで見る整備士採用の厳しい現状
これらのデータは、多くの企業が整備士確保に苦戦している事実を裏付けています。一つずつ詳しく解説します。
整備士の有効求人倍率の推移
整備士の有効求人倍率は全職種の平均を大幅に上回っており、採用競争が極めて激しい状況です。
実際に、厚生労働省が発表しているデータは以下のとおりです。
| 項目 | 有効求人倍率 |
|---|---|
| 自動車整備士 | 5.28倍 (令和5年度) |
| 全職種平均 | 1.31倍 (令和5年度) |
出典:厚生労働省|一般職業紹介状況(令和5年12月分及び令和5年分)について
自動車整備士の求人倍率は全職種平均の約4倍にも達しており、突出して人材が不足していることがわかります。
この数値は、整備士が「引く手あまた」の状態であることを示しており、企業は採用戦略の抜本的な見直しが求められます。
若手整備士の減少と高齢化
整備士業界では、なり手となる若者が減少する一方で、現場の高齢化が深刻な課題となっています。
まず、将来の整備士候補である専門学校の入学者数が大幅に減少しています。
| 年度 | 自動車整備専門学校 入学者数 |
|---|---|
| 平成15年 | 12,394人 |
| 令和3年 | 6,536人 (約47%減) |
この18年間で入学者数が半数近くまで落ち込んでいる事実は、採用市場に出てくる若者の絶対数が減っていることを意味します。
一方で、現場で働く整備士の高齢化も着実に進んでいます。
整備士の平均年齢の推移
- 平成23年度: 42.8歳
- 令和4年度: 46.7歳 (約10年で3.9歳上昇)
平均年齢が一貫して右肩上がりに上昇している点は、若手が入職・定着していない現状を裏付けています。
将来的な技術承継の問題にも直結するため、若手が入職し、定着できるような魅力的な職場環境の構築が急務といえるでしょう。
整備士の採用が難しい5つの原因
整備士の採用が難しい背景には、業界特有の根深い原因が存在します。表面的な問題だけでなく、これらの原因を正しく理解することが、有効な対策を立てるための第一歩です。
整備士の採用が難しい5つの原因
ここでは、主な5つの原因を掘り下げて解説します。
給与や待遇・福利厚生への不満
整備士の給与水準は、その専門性や業務の負担に対して、必ずしも十分でないことが採用の障壁になっています。
| 項目 | 自動車整備士 | 全職種平均 |
|---|---|---|
| 年間所得額 (2022年度) | 469万円 | 497万円 |
| 年間労働時間 (2022年度) | 2,184時間 | 2,124時間 |
上記のデータは、全職種より年間60時間長く働いているにもかかわらず、得られる所得が約28万円低いという実態を示しています。
このような待遇面での不満が、人材獲得を難しくする要因の一つです。
ただし、同調査では整備士の所得額は増加傾向にあり、全職種との差も少しずつ縮小しています。
この改善の動きを求職者に伝えつつ、給与テーブルや評価制度の透明化を図り、さらなる待遇改善を進めることが求められます。
厳しい労働環境のイメージ
「きつい・汚い・危険」といった、いわゆる3Kのイメージが根強く残っていることも、若手人材が整備士の仕事を敬遠する原因の1つです。
実際の労働環境は改善されていても、固定観念が払拭できていません。
厳しい労働環境の具体的なイメージ
- 夏は暑く冬は寒い空調のない作業環境
- オイルやグリスなどによる身体や衣服の汚れ
- 重い部品やタイヤの持ち運びによる身体的負担
- 長時間労働や休日出勤が多いという先入観
このようなイメージを払拭するためには、空調設備の導入や最新リフトの設置といった具体的な労働環境の改善と、その取り組みを写真や動画で積極的に発信し、クリーンで安全な職場であることをアピールする必要があります。
キャリアパスが描けないことへの将来性の不安
入社後のキャリアパスが不明確であるため、整備士として長く働き続ける将来像を描けず、応募をためらう求職者が少なくありません。
特に、マネジメント職への昇進ルート、あるいはEVやADAS(先進運転支援システム)といった最新技術のスペシャリストとして認定される制度などが不明瞭な場合、成長意欲の高い人材は魅力を感じにくいでしょう。
個人の成長と企業の将来性を感じられる、明確なキャリアプランの提示が採用成功には不可欠です。
自社の魅力が求職者に届いていない
働きやすい制度や独自の強みがあるにもかかわらず、その魅力が求職者に十分に伝わっていないケースが見られます。
採用活動において、給与や休日といった条件面以外の情報発信が不足していることが原因です。
発信が不足しがちな自社の魅力の例
- 最新の診断機器や特定整備ツールなどの設備投資状況
- 具体的な研修制度や資格取得支援の実績と取得後の待遇
- 社員同士の良好な関係性がわかる社内イベントや日常風景
- お客様からの感謝の声や、地域社会への貢献活動
求職者は、職場のリアルな雰囲気や働く社員の姿といった情報も重視しています。
採用サイトやSNSなどを活用し、自社の魅力を具体的に発信しなければ、多くの求人情報の中に埋もれてしまいます。
参考記事:採用SNS戦略を成功させる!利点を最大化する10のステップ徹底解説
採用競合の激化と求める人材像のミスマッチ
整備士不足を背景に採用競合が激化する中で、企業が求める人材像が高すぎたり、逆に曖昧だったりすることが、採用の機会損失につながっています。
同業他社だけでなく、労働条件の良い他業界とも人材の奪い合いになっているのが現状です。
| 企業の求める人材像(理想) | 採用市場に多い求職者の実態 |
|---|---|
| 即戦力となる経験豊富なベテラン | 未経験でも成長したい意欲ある若手 |
| 最新技術にも対応できるマルチプレイヤー | 特定の車種や分野での経験は豊富 |
このようなミスマッチを解消するためには、採用ターゲットを見直し、未経験者を受け入れて育成する体制を整えるなどの対策が考えられます。
採用市場を正しく理解し、自社に必要な人材要件を再定義することが、競争を勝ち抜く上で重要です。
理想の候補者を見つけるなら「HELLOBOSS」がおすすめ
採用競合が激しく、求める人材と出会えない場合は、AIを活用した「HELLOBOSS」がおすすめです。
10万人以上のユーザーの中から、貴社の求める経験やスキルに合った人材をAIがスピーディーに推薦します。
「HELLOBOSS」なら、求人サイトにはいない転職潜在層にもアプローチできるため、これまで出会えなかった優秀な整備士と出会える可能性があります。
無料から始められるので、まずは気軽にAI採用の効果を体験してみてください。
整備士不足が企業に与える3つのリスク
整備士不足は、単に「人が足りない」という採用の問題だけではありません。放置すると企業の経営基盤そのものを揺るがしかねない、深刻な経営リスクに直結します。
整備士不足が企業に与える3つのリスク
ここでは、企業が直面する具体的な3つのリスクについて解説します。
整備品質の低下による顧客信用の失墜
整備士不足は、現場への業務過多を招き、整備品質の低下に直結します。その結果、顧客からの信用を失ってしまうリスクが高まります。
人手が足りないと、一台の車にかけられる時間が物理的に短くなり、確認作業の省略やヒューマンエラーが発生しやすくなるでしょう。
一度の整備不良が顧客の安全を脅かす事態となれば、信用の回復は困難です。品質は事業の生命線であり、その低下は企業の存続を危うくする最大のリスクといえます。
従業員の負担増が引き起こす離職の連鎖
整備士が不足すると、残った従業員への業務負担が増加し、職場環境の悪化から離職の連鎖を引き起こすリスクがあります。一人が辞めると、その分の業務が他の従業員にのしかかり、さらなる長時間労働や休日出勤につながるためです。
| フェーズ | 内容 |
|---|---|
| 人手不足 | 一部の従業員が退職し、必要な人員が不足 |
| 業務過多 | 残った従業員の業務量が増加し、残業が常態化 |
| 環境悪化 | 有給取得が難しくなり、職場の雰囲気が悪化 |
| 新たな離職 | 心身の負担に耐えかねた従業員がさらに退職し、負のスパイラルが加速 |
この悪循環に陥ると、人材の確保はますます困難になります。新たな人材を採用するためにも、まずは既存従業員の負担を軽減し、定着を図る必要があるでしょう。
事業の縮小や工場の閉鎖に追い込まれる可能性
整備士不足が慢性化し、解決の見込みが立たない場合、最終的には事業の縮小や工場の閉鎖という経営判断を迫られるリスクがあります。仕事を受注したくても、対応できる整備士がいないため売上を確保できなくなるからです。
| 段階 | 企業への影響 |
|---|---|
| 第一段階 | 新規顧客の受付停止、車検の予約制限 |
| 第二段階 | 売上・利益の大幅な減少 |
| 第三段階 | 特定のサービスからの撤退、営業時間の短縮 |
| 最終段階 | 事業譲渡、工場の閉鎖、廃業 |
整備士不足は単なる現場の問題ではなく、企業の存続そのものを左右する経営課題であることを認識する必要があるでしょう。
整備士採用を成功させる10の対策
整備士不足の原因やリスクを踏まえ、ここからは採用を成功させるための具体的な解決策を解説します。
整備士採用を成功させる10の対策
できることから一つずつ着手していきましょう。
未経験・女性・シニアなど採用ターゲットを広げる
即戦力となる経験者だけにこだわらず、採用ターゲットを広げることが人材確保のポイントです。競争の激しい経験者採用だけでなく、多様な人材に目を向け、自社で育成する視点が求められます。
| ターゲット | アプローチのポイント |
|---|---|
| 未経験者 | 充実した研修制度とOJTで育成する体制をアピール |
| 女性 | 更衣室や力仕事の負担を軽減する設備、柔軟な勤務制度を整える |
| シニア | 長年の経験を活かせる業務分担や、体力に配慮した働き方を提案 |
これまで応募に至らなかった層へアプローチすることで、新たな採用の可能性が生まれます。自社の受け入れ体制を整え、それぞれのターゲットに響くメッセージを発信しましょう。
給与テーブルと評価制度の透明化を図る
「何を、どのように頑張れば評価され、昇給するのか」という明確な基準を示すことが重要です。評価基準が曖昧だと、従業員は将来の収入を見通せず、モチベーションの低下や会社への不信感につながります。
例えば、等級ごとの給与テーブルを公開したり、「〇〇の資格を取得すれば資格手当が月額〇円プラスされる」といった具体的なルールを設けたりします。
透明性の高い制度は、従業員の納得感を高め、定着率の向上にも貢献するでしょう。
年間休日数の増加と柔軟な働き方を導入する
ワークライフバランスを重視する求職者が増える中、休日数の確保と柔軟な働き方の導入は非常に有効な対策です。
柔軟な働き方の導入例
- 希望休制度や連休取得の推奨
- 週休3日制の検討
- 時間単位での有給休暇取得制度
- 育児や介護と両立できる時短勤務制度
すべての制度を一度に導入するのは難しくても、従業員の希望を聞きながら、できることから試すのが良いでしょう。多様な働き方を認めることで、これまで応募できなかった層にも門戸を開けます。
最新の整備設備・ツール導入で負担を軽減する
最新の設備やツールへの投資は、従業員の身体的負担を直接的に軽減し、生産性を向上させる効果があります。
「きつい・汚い」といったイメージを払拭し、「スマートで効率的に働ける職場」であることを示すことは、特に若手へのアピールになるでしょう。
例えば、フルフラットリフトや電動工具、最新の故障診断機などを導入すれば、作業効率は格段に上がります。安全で快適な作業環境の整備を行いましょう。
資格取得支援や研修制度でスキルアップを後押しする
社員の成長を会社が支援する姿勢を示すことは、成長意欲の高い人材を惹きつけ、定着させるうえで非常に効果的です。自身のスキルアップが会社の評価や待遇に直結することが分かれば、従業員の学習意欲も自然と高まります。
スキルアップ支援の具体例
- 整備士資格や検査員資格の取得費用の全額または一部補助
- 外部研修やメーカー研修への参加奨励(費用は会社負担)
- ハイブリッド車やEVに関する社内勉強会の定期開催
教育体制の充実は、従業員の満足度を高めるだけでなく、未経験者採用を可能にする基盤づくりにもつながります。会社の未来への投資として、積極的に取り組みましょう。
写真や動画で職場のリアルな雰囲気を伝える
求人票のテキスト情報だけでは伝わらない、職場のリアルな雰囲気を視覚的に伝えることが有効です。
求職者は、給与や休日といった条件面だけでなく、人間関係や職場の清潔さなど、実際に働く環境を強く意識しています。
採用サイトやSNSへの写真や動画の例
- 笑顔で働く社員の姿
- 整理整頓された工場の様子
- 若手やベテラン社員へのインタビュー動画
ありのままの姿を見せることで、求職者は入社後の自分をイメージしやすくなり、安心感につながります。
参考記事:【完全解説】オウンドメディア採用の成功事例|成功する10ステップ
自社採用サイトやSNSで継続的に情報発信する
求人媒体に広告を出すだけでなく、自社の採用サイトやSNSなどで継続的に情報発信を行い、企業のファンを育てる視点が求められます。
転職を考えていない潜在層に対しても、日頃から企業の魅力や文化に触れてもらうことが重要です。
情報発信のポイント
- ブログで整備の豆知識を発信
- Instagramで社員の日常を紹介
待っているだけの採用から、自ら情報を届ける攻めの採用へ転換する意識が必要です。
参考記事:採用SNS戦略を成功させる!利点を最大化する10のステップ徹底解説
国の助成金や給付金制度を活用する
労働環境の改善や人材育成に取り組む企業を支援するため、国は様々な助成金制度を用意しています。コストを抑えながら待遇改善や設備投資、教育訓練を実施できるため、これらを活用しない手はありません。
| 助成金の種類(例) | 活用できる場面 |
|---|---|
| キャリアアップ助成金 | 非正規雇用の従業員を正社員化・処遇改善する際など |
| 人材開発支援助成金 | 従業員に専門的な技能講習や訓練を受けさせる際など |
| 働き方改革推進支援助成金 | 時間外労働の削減や有給取得促進に取り組む際など |
参考:厚生労働省|キャリアアップ助成金、厚生労働省|人材開発支援助成金、厚生労働省|働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
自社で活用できる制度がないか、厚生労働省のホームページや、地域の労働局、ハローワークに一度相談してみることをおすすめします。
応募から面接までの選考プロセスを簡略化する
優秀な人材ほど複数の企業からアプローチを受けているため、選考プロセスが複雑だと途中で離脱されてしまいます。応募のハードルを下げ、スピーディーな選考を行うことが、他社に先んじて人材を確保するコツです。
選考プロセス簡略化の例
- 応募時の履歴書を不要にする
- Webフォームは簡単な入力のみにする
- 面接回数を原則1回に絞る
「すぐに応募でき、すぐに結果がわかる」というスムーズな選考体験は、企業への好印象にもつながります。
参考記事:【フロー図付き】採用フロー完全マニュアル|新卒・中途別に解説
効率よく採用するなら「HELLOBOSS」がおすすめ
選考プロセスを効率化し、採用担当者の負担を減らしたい場合も「HELLOBOSS」がおすすめです。AIが候補者の自動推薦だけでなく、求人票の自動生成もサポートするため、採用業務を大幅に効率化できます 。
候補者とはチャットで直接やり取りできるため、スピーディーな選考が可能です 。
月額4,000円から利用でき、採用が決まっても成功報酬は一切かかりません 。無料から始められるので、採用の効率化にぜひ活用してみてください。
カジュアル面談で入社後のギャップをなくす
正式な面接の前に、お互いをリラックスした状態で理解するためのカジュアルな面談の場を設けることが、入社後のミスマッチを防ぎます。
選考という堅い雰囲気ではないため、求職者は本音で質問しやすく、企業側も自社の素顔を伝えやすいからです。
現場の若手社員や工場長などが同席し、仕事のやりがいや大変な点を率直に話すことで、求職者の不安を解消します。相互理解を深めることが、内定承諾率の向上と早期離職の防止に直結します。
参考記事:カジュアル面談からスカウトを成功させる7つのコツ|進め方も解説
整備士採用におすすめの採用チャネル
採用を成功させるには、魅力的な職場づくりと並行して、適切な「採用チャネル」を選ぶことが重要です。それぞれのチャネルの特徴を理解し、自社の予算や求める人材像に合わせて、複数の方法を組み合わせることが効果的です。
整備士採用におすすめの採用チャネル
ここでは、7つの採用チャネルについて、その特徴と活用法を解説します。
整備士特化型求人サイト
整備士の仕事を探している意欲の高い求職者に、効率よくアプローチできるのが特化型求人サイトです。登録者の多くが整備士資格保有者や経験者であるため、求める人材と出会える確率が高まります。
特化型サイトの主なメリット
- 採用ターゲットが絞られているためミスマッチが少ない
- 整備士ならではのスキルや経験を記載できる
- 業界の給与相場や動向を把握しやすい
掲載にはコストがかかりますが、即戦力を求める場合には非常に有効な方法です。複数のサイトを比較し、自社のエリアや求める人材像に合ったサービスを選びましょう。
AIマッチング「HELLOBOSS」
採用のミスマッチを減らし、効率を上げたい場合に、AIを活用したマッチングサービスが有効です。膨大な求職者データの中から、AIが自社の求めるスキルや社風に合った人材を自動で探し出してくれます。
私たちが提供する採用アプリ「HELLOBOSS」では、自動で求人票を作成でき、AIが最適な候補者を提案します。
チャットで直接アプローチすることも可能なため、採用担当者の負担を軽減しつつ、これまで出会えなかった潜在的な候補者との接点を創出します。
求人検索エンジン
求人検索エンジンは、幅広い層の求職者に無料で求人情報を見てもらえる可能性がある点が魅力です。多くの求職者が仕事探しの入り口として利用しているため、掲載するだけで多くの人の目に触れる機会が生まれます。
ただし、多くの求人に埋もれやすいため、職種名や仕事内容を工夫してクリックされやすくする必要があります。
リファラル
リファラル採用は、自社の従業員からの紹介を通じて採用する方法で、定着率の高さと採用コストの低さが期待できます。
従業員が自社の文化や仕事内容を理解したうえで紹介するため、入社後のミスマッチが起こりにくいのが特徴です。
リファラル採用の特徴
- 採用コストを抑え、信頼できる人材を確保しやすい
- 人間関係が悪化するリスク、紹介がつねに出るとは限らない
- 紹介してくれた社員へのインセンティブ制度が必要
社員が「友人に自信をもって紹介したい」と思えるような魅力的な職場づくりが、リファラル採用成功の基盤となります。
参考記事:リファラル採用が難しい理由とは?注意点や失敗しないコツも解説
SNS・動画プラットフォーム
X(旧Twitter)やInstagram、TikTok・YouTubeなどを活用し、企業の魅力を発信することで、転職を今すぐには考えていない潜在層にアプローチできます。
求人サイトには登録していないものの、「良い会社があれば」と考えている層に、企業の文化や雰囲気を直接伝えられるのが強みです。
発信内容の例
- YouTubeで工場の1日を紹介
- TikTokで「整備士あるある」を紹介
- Instagramで社員のオフショットを公開
継続的な情報発信は企業のブランディングにつながり、将来の採用活動を楽にします。
参考記事:YouTubeを使った採用活動に成功する17のコツ|成功事例も紹介
専門学校・職業訓練校
専門学校・職業訓練校は、これから整備士としてキャリアをスタートする、意欲の高い若手人材を確保するために重要です。新卒採用は、長期的な視点で自社の文化に合った人材を育成できるメリットがあります。
| チャネル | 特徴 | アプローチ方法 |
|---|---|---|
| 専門学校 | 2年間専門知識を学んだ学生が中心 | 求人票の提出、合同企業説明会への参加、インターンシップの受け入れ |
| 職業訓練校 | 異業種からの転職を目指す多様な年齢層が在籍 | 求人票の提出、施設見学の実施 |
学校の就職担当者と日頃から良好な関係を築き、自社の魅力をこまめに伝えておくことが採用成功につながります。
ハローワーク
ハローワーク(公共職業安定所)は、無料で求人掲載ができる最も基本的な採用チャネルです。地域に密着した採用活動を行いたい場合や、採用コストをかけられない場合に特に有効です。
地元での就職を希望する求職者が多く登録しているため、近隣のエリアから人材を探したい場合に適しています。また、各種助成金の相談窓口にもなっています。
他のチャネルと併用しながら、地域の人材にアプローチする手段として活用しましょう。
整備士の採用が難しい状況を打破したAI活用の成功事例
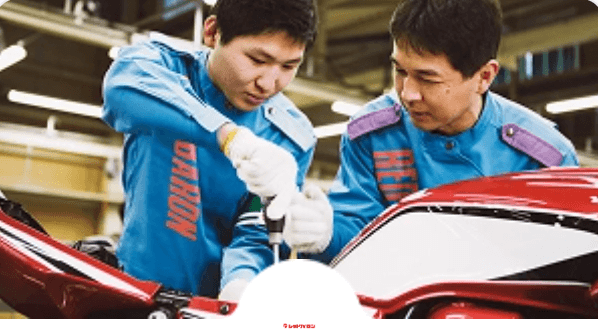
整備士の有効求人倍率は非常に高く、従来の求人媒体だけで募集を出しても応募が集まらないのが現状です。
ここでは、AI採用ツール「HELLOBOSS」を活用し、整備士を採用した企業の事例を紹介します。
レッドバロンでは、採用難易度の高い整備士の母集団形成に課題を感じていました。
そこでHELLOBOSSのSocial+プランを導入し、AI作成の動画広告を活用したSNSアプローチを展開。
その結果、開始1ヶ月で20代の整備士の採用に成功しています。
さらに、副次的な効果で自社ホームページからの応募も増えました。
AIを活用することで、整備士を採用できる可能性が高まります。
整備士の採用についてよくある質問
ここでは、整備士の採用についてよくある質問に回答していきます。
自動車整備士不足に対して国はどのような対策をしていますか?
国(主に国土交通省)は、整備士不足を重要な課題と捉え、業界団体と連携しながら多角的な対策を進めています。
国の主な対策例
- 若年層へのPR活動
- 「働きやすい職場ガイドライン」を策定
- 外国人材の活用
これらの施策は、整備士という職業のイメージを向上させ、将来の担い手を確保することを目的としています。
整備士の未経験者を採用する場合、どのような教育が必要ですか?
未経験者を採用する場合、社会人としての基本から専門知識・技術までを段階的に学べる、体系的な教育プログラムが不可欠です。
現場での実務訓練(OJT)と、座学などの研修(Off-JT)を組み合わせることが効果的とされています。
| 教育プログラム | 形式 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 導入研修(Off-JT) | 座学 | ・ビジネスマナー講座 ・安全衛生教育 ・工具の基本操作講習 ・自動車構造の基礎知識 |
| 現場研修(OJT) | 実地研修 | ・先輩社員によるマンツーマン指導(メンター制度) ・実務を通じた技能習得 |
| 資格取得支援 | セミナー・補助 | ・整備士資格取得の勉強会開催 ・受験費用の補助 |
国も事業主による教育訓練を支援しており、厚生労働省の「人材開発支援助成金」などを活用することで、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部について助成を受けられる場合があります。
外国人整備士の採用は有効な手段ですか?
はい、深刻な人材不足を補うために、外国人整備士の採用は非常に有効な手段の一つです。
2019年から始まった在留資格「特定技能」制度の活用により、一定の専門性と技能を持つ即戦力人材の確保が期待できます。
外国人整備士採用のポイント
- 意欲の高い若手人材を確保できる可能性がある
- 在留資格の申請手続き・日本語教育・住居の確保といった生活面でのサポート体制の構築が必要
外国人材の受け入れに関する手続きや支援については、国土交通省や関連団体が相談窓口を設けています。
出典:公益財団法人 国際人材協力機構|在留資格「特定技能」とは
まとめ
整備士の採用は難しい状況ですが、原因を理解し、一つずつ対策を講じることで、採用成功の可能性は高まります。まずは、できることから始めていきましょう。
整備士採用を成功させる10の対策
- 未経験・女性・シニアなど採用ターゲットを広げる
- 給与テーブルと評価制度の透明化を図る
- 年間休日数の増加と柔軟な働き方を導入する
- 最新の整備設備・ツール導入で負担を軽減する
- 資格取得支援や研修制度でスキルアップを後押しする
- 写真や動画で職場のリアルな雰囲気を伝える
- 自社採用サイトやSNSで継続的に情報発信する
- 国の助成金や給付金制度を活用する
- 応募から面接までの選考プロセスを簡略化する
- カジュアル面談で入社後のギャップをなくす
様々な対策の中でも、すぐに即戦力となりうる人材へアプローチしたい場合は、ダイレクトリクルーティングが有効です。
AIを活用したダイレクトリクルーティングツール
「HELLOBOSS」は、10万人以上のユーザーの中から、AIが貴社に合う整備士候補を推薦するダイレクトリクルーティングツールです。AIが候補者を探してくれるため、採用担当者の負担を軽減できます。
月額4,000円からスタートでき、成功報酬は一切かかりません。
無料から始められるので、ぜひ一度、AIによるマッチングを体験してみてください。











