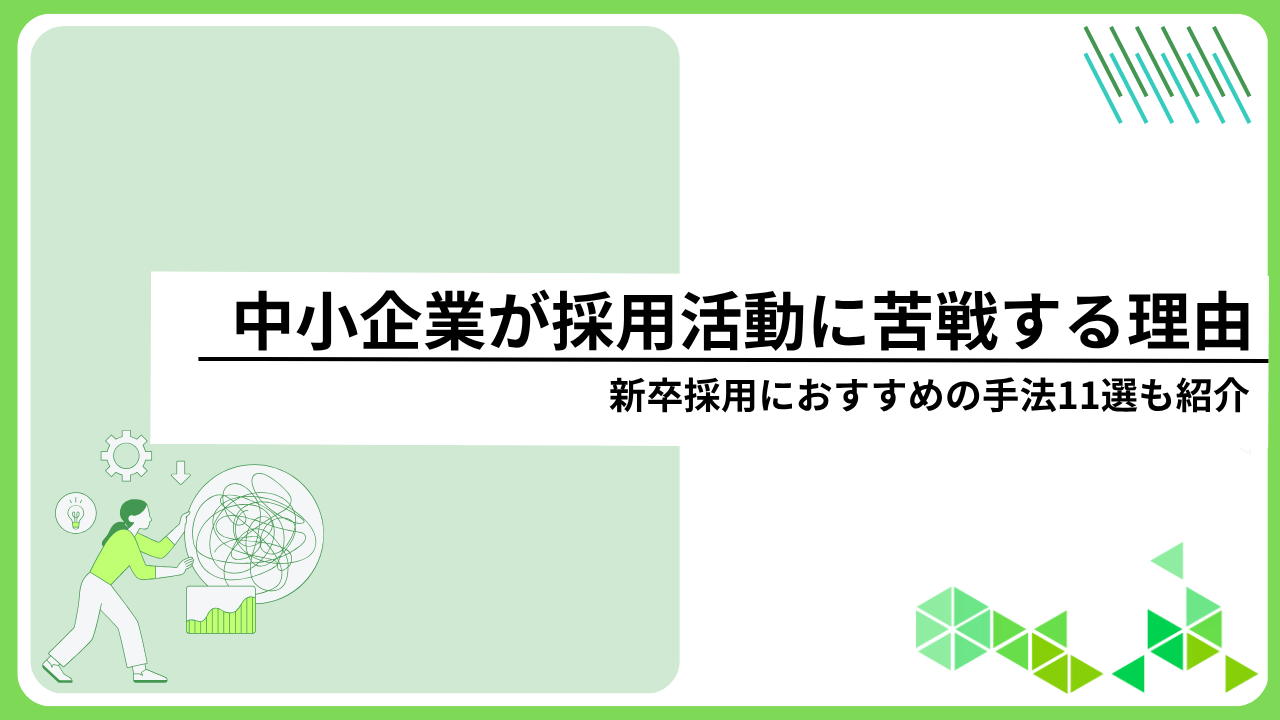「中小企業で人材を採用するのは難しい…」
「どうすれば採用活動に苦戦せずに済むの?」
とお悩みの中小企業の人事担当者様に向けた記事です。
この記事でわかること
- 中小企業が人材採用に苦戦する理由
- 中小企業が採用活動に成功する戦略11ステップ
- 中小企業の採用におすすめのチャネル10選
知名度や人材不足の影響などから、中小企業では人材採用が難しいケースがあるでしょう。
しかし、中小企業でも正しい戦略と採用チャネルを組み合わせれば、人材を採用できる可能性は高まります。
この記事では、中小企業で成果が出やすい採用ノウハウを網羅的に解説しています。
もう「人材を採用できなかったらどうしよう…」と悩みたくないですよね?
この記事を読むことで、自社が抱える採用のボトルネックを把握し、限られた予算やリソースの中でも採用の効果を高める具体策がわかります。
採用の目標を達成できる可能性が上がるので、最後まで読んでみてください。
コストを抑えて人材にアプローチできます
「前置きはいいから、早く人材を採用するコツを知りたい!」という方は、中小企業が採用活動に成功する戦略11ステップへジャンプしてみて下さい。

Contents
中小企業が採用難で苦戦する5つの内的課題
まずは、中小企業が採用で苦戦する内的な課題を解説します。
中小企業が採用難で苦戦する内的課題
- 企業の知名度が低いから
- 採用コストが限られるから
- 採用ノウハウが足りないから
- 採用にかけられるリソースが足りないから
- 待遇面で大手企業に勝てないから
状況を好転させるためにも、内的な課題を知るところから始めていきましょう。
企業の知名度が低いから
企業名があまり知られていない状況は、新卒・中途を問わず応募意欲が下がるケースがあります。有名企業と比較された際に「聞いたことがない」と感じられるだけで興味を抱かれにくく、応募数が伸びにくいかもしれません。
例えば
地方の中小企業で製造業を営んでいる場合、地元では認知度があっても他地域の候補者には伝わりづらいでしょう。
企業の知名度の低さは人材採用における障壁となり、優秀な人材の獲得を難しくする要因となる可能性があります。
採用コストが限られるから
潤沢な広告費やシステム導入費を用意しにくい中小企業は、採用活動に苦戦することがあります。予算の問題で求人サイトの目立たない枠しか選べない場合もあり、必要な母集団を得られないケースもあるでしょう。
以下は費用が限られた際に起こりやすい影響です。
| 要因 | 考えられる影響 |
|---|---|
| 広告掲載費の不足 | 集客力の弱い枠しか選べず閲覧数が少ない |
| 専門ツールの未導入 | 応募受付の自動化が進まず対応が遅れる |
| 研修費の不足 | 面接官や担当者のスキル習得が進まず向上しにくい |
予算の優先順位を見直し、最小限の投資で最大の効果を狙う必要があります。詳しい方法は、中小企業が採用活動に成功する戦略11ステップから解説しているので、このまま読み進めてみてください。
採用ノウハウが足りないから
採用ノウハウが足りていない場合も、人材の採用が難しくなります。選考基準や面接手法が統一されていないと、優秀な候補者を見逃しやすいでしょう。
例
求める人物像を明確にせず、質問が場当たり的になると短い面談時間では本質を把握しにくいです。その結果、ミスマッチを引き起こすリスクもあります。
採用の成功パターンを記録できず、長い期間に渡って採用に苦戦するかもしれません。具体的な採用ノウハウもこの後から解説していきますが、PDCAサイクルを回してうまくいった事例を蓄積していきましょう。
採用にかけられるリソースが足りないから
人事担当が経理や総務を兼任している中小企業は珍しくありません。応募者からの問い合わせ対応や求人情報の更新が後回しになると、他社に人材を獲得されてしまう危険性もあります。
注意
他の業務があると、応募があっても面接の時間を取りにくいでしょう。結果として人材獲得の機会損失を生み続けるかもしれません。
リソースが足りない場合は、後述する各種ツールで対応できる可能性があるので、有効活用してみてください。
待遇面で大手企業に勝てないから
給料や福利厚生を比較して、大手企業を選ぶ応募者もいます。厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査」によると、企業規模別の平均年収は以下のとおりです。
| 企業規模(従業員数) | 平均年収 |
|---|---|
| 1,000人以上 | 578万円 |
| 100〜999人 | 496万円 |
| 10〜99人 | 437万円 |
従業員数1,000人以上の大手企業と、10〜99人の中小企業では、平均年収に140万円以上の違いがあります。
複数の内定を獲得した人は待遇の良さを優先する場合があり、待遇に魅力を感じられないと内定を辞退することも珍しくありません。
待遇面を引き上げられない場合は、成長機会やキャリアアップの早さを具体的に示すなど対策が必要です。
「前置きはいいから、早く人材を採用するコツを知りたい!」という方は、中小企業が採用活動に成功する戦略11ステップへジャンプしてみて下さい。
中小企業が採用難で苦戦する2つの外的課題
続いて、中小企業の採用活動を難しくしている外的課題も解説します。
中小企業が採用難で苦戦する外的課題
- 働き手が不足しているから
- 中小企業の将来性を不安視する方がいるから
外的課題は自社で解決することは難しいですが、業況を知らないと正しい対策を打てません。念のため外的課題も知っておきましょう。
働き手が不足しているから
少子高齢化が加速し、人材市場では売り手が優位な傾向があります。厚生労働省が発表した令和6年11月の有効求人倍率は「1.25倍」で、求職者より求人の方が多い状況が続いています。
参考:厚生労働省|一般職業紹介状況(令和6年11月分)について
以下は働き手が少ない背景の一例です。
働き手が少ない背景の例
- 少子高齢化が進み、若手人材の母数が減少している
- 都市部の大企業に人が集まり、地方へ流れにくい
- 景気に左右されやすく、採用時期を逃すと応募者ゼロになるケースがある
地域や業種によっては説明会を開催してもわずかな人数しか集まらず、採用の進行が遅れる場合があります。
働き手が不足している中では、戦略的な採用活動が求められます。具体的な戦略は、中小企業が採用活動に成功する戦略11ステップから解説していくので、このまま読み進めてみてください。
中小企業の将来性を不安視する方がいるから
「安定第一」と考える求職者は、大手や老舗企業を選ぶ傾向が根強いです。家族に相談したときに「聞いた経験がない会社は先行きが不安…」と言われ、内定辞退に至る場合もあるでしょう。
ポイント
特に新卒であれば「中小企業は不況下で持ちこたえられるのか?」と疑問をもたれることがあります。
もちろん経営がうまくいっている中小企業はたくさんありますが、中小企業全体のイメージで判断されてしまうリスクが存在します。
中小企業が採用活動に成功する戦略11ステップ
では、中小企業が採用活動に成功しやすくなる戦略を11ステップで解説していきます。
中小企業が採用活動に成功する戦略11ステップ
- 採用ペルソナを決める
- 採用エリアを拡大する
- 待遇を改善できないか検討する
- 採用フローを最適化する
- 自社に入社するメリットを言語化する
- 候補者の興味を引く求人票を書く
- 採用時期を前倒しする
- 経営層や現場のメンバーも採用活動に参加する
- カジュアル面談を実施する
- 内定者フォローを徹底する
- 採用担当者の研修を強化する
この順に対策していくと、人材を採用できる確率が高まります。できるところからでも良いので、始めていきましょう。
採用ペルソナを決める
採用で求める人物像をはっきりさせると、募集要項や面接で重視したい点がブレにくいです。例えば「営業経験2年以上のチャレンジ精神がある人」「チームワークを尊重しながら効率化を進められる人」のように、社風と職務内容を想定しながら条件を絞っていきます。
ポイント
細かいスキルをリスト化するだけでなく、会社の目指す将来像に共感しそうな性格や志向性を加味すると良いでしょう。
具体的なペルソナの設定手順は以下のとおりです。
採用ペルソナを設計するステップ
- 採用したい人材像を社長や現場に聞く
- 人材を採用する目的を定義する
- 採用したい人材像を書き出す
- 採用市場に合わせたペルソナにする
- ペルソナを経営層や現場のメンバーに確認してもらう
詳しいペルソナの設定方法は、採用ペルソナの作り方完全ガイド|テンプレートと7ステップのフレームワークを参考にしてみてください。
また、ペルソナは「必須条件」と「歓迎条件」も設定すると、採用時の判断材料になります。
たとえばWebマーケティング職なら、以下のように「必須条件」と「歓迎条件」を整理します。
| 必須条件の例 | 歓迎条件の例 |
|---|---|
| ・Web広告の運用経験1年以上 ・顧客データを分析し数字で改善点を示せる ・GoogleスプレッドシートやExcelなどを用いた集計が苦にならない | ・HTML/CSSへの基礎的な理解 ・広告運用に関する資格を保有している ・過去にチームリーダーとして実績を残した経験がある |
作成後は人事と現場で認識を合わせ、面接基準が共有される状態を目指しましょう。
採用エリアを拡大する
求人を出すエリアを限定していると、応募が集まりにくいです。特に都市部で競合が多い場合、地方や遠方在住の人へ視野を広げると、母集団を増やせる可能性があります。
ポイント
オンライン面接を取り入れると、遠隔地の候補者も交通費や移動時間を気にせず参加しやすいです。
地域で人材が不足している会社は、遠方からのUターン・Iターン希望者の採用も視野に入れましょう。自治体の移住支援策や補助金の有無も調べ、候補者に具体的な利点を示すのがコツです。
待遇を改善できないか検討する
条件面が良い企業に応募する人が多いため、待遇を改善できないか検討してみてください。大幅な給与アップが難しくても、以下のような制度の見直しで魅力を感じてもらえる可能性があります。
待遇改善の例
- 時短勤務
- 定時退社の徹底
- 年間休日数を増やす
- 休暇制度の整備
- 育児や介護と両立しやすい働き方
社員の意見をヒアリングし、現実的に実装できるものから導入すると効果的です。見直しの結果を採用ページでわかりやすく発信し「給与以外の魅力がある」とアピールすると応募増が期待できます。
選考フローを最適化する
無駄な工程や不透明な評価基準が多いと、候補者は他社に流れやすくなります。
悪い例
書類選考に1週間、面接日程の調整にさらに1週間かかるような状況では、離脱される恐れがあるでしょう。
意思決定を素早くするために、一次面接・二次面接をまとめてオンラインで実施する企業もあります。
以下は見直す項目の例です。
| 選考フロー | 改善案 |
|---|---|
| 面接回数 | 一度で済ませる |
| 日程調整 | 候補者が希望する時間帯をあらかじめ選択してもらう |
| 書類選考 | 必須の要件と歓迎要件に分けて、早く判断できる基準を作る |
スムーズなフローは「この会社は動きが早くて安心できる」という印象を与え、ライバルに先を越されるリスクを下げます。見直した流れは社内に周知し、同じ基準で評価・連絡できるように統一するのがおすすめです。
自社に入社するメリットを言語化する
応募前に社名を知らない人が多い中小企業こそ、入社の利点を強調する工夫が必要です。
入社するメリットの例
- 新人でも企画を考案しやすい
- 外部に頼らず製品やサービスを開発できる
- 顧客の要望をスピーディーに形にしやすい
例えば、以下の要素を言語化してみましょう。
| 要素 | 言語化の例 |
|---|---|
| 成長機会 | ・勉強会や資格取得補助 ・社内外の研修に参加できる ・未経験でも先輩からマンツーマンで学べる |
| 働きやすさ | ・一部リモートワークOK ・有給消化率が高く残業少なめ ・育児や介護を支援する制度を導入 |
| 社風 | ・少人数で意見を出し合いやすい ・上下関係がフラット ・活発なアイデア交換を歓迎する文化 |
| 評価制度 | ・半期ごとに目標を設定し昇給や昇格に反映 ・チーム成果だけでなく個人の貢献度も評価 ・社内表彰などモチベーションを高める仕組み |
具体的な事例を加えればさらに信頼感が高まり、中小企業でも大手にはない魅力を印象づけやすくなります。
候補者の興味を引く求人票を書く
掲載枠や文字数に制約があっても、魅力をきちんと伝えれば応募への誘導率は高まります。まずは短いフレーズを冒頭に据えて「続きを読みたい」と感じてもらう工夫がおすすめです。
キャッチコピーの具体例
- 毎週アイデア提案会を実施。月1回は新人の発案が採用されやすい
- 残業は月10時間以内。土日休み+リモート導入で家庭と両立
- 業界未経験でもOK。研修や資格補助ありでゼロから学べる
こうした表現は「自社だからこそ得られるメリット」を凝縮し、一目で伝わる形を意識します。数字や具体的エピソードを混ぜると真実味が増し、自社に興味を抱く人を増やしやすいです。
求人のキャッチコピーの書き方は、求人キャッチコピーの例文集50選一覧|6つの面白い心理効果も紹介を参考にしてみてください。
職種名・仕事内容を具体的に書く
職種の呼び方が漠然としていると、応募を検討する前にスルーされがちです。例えば「企画営業」より「化粧品ブランドの企画営業(既存顧客対応8割)」といったように、取り扱い製品や顧客層、業務配分を入れると判断材料が増えます。
仕事内容はなるべく詳細に示すと、具体的なイメージがわきやすくなります。具体例は以下のとおりです。
| 記載する項目 | 内容 |
|---|---|
| 一日の流れ | 午前は電話対応と顧客訪問を計画。 午後に商談や提案資料作成。 |
| 取引先の業界 | ITサービス、コンサル企業がメイン。 訪問は1日2〜3社ほど。 |
| 入社後の流れ | 座学研修(2週間)→上司との同行→独り立ちまでは最短2ヶ月 |
数字や時系列を交えると「どんな場面で力を発揮できるか」を想像しやすくなり、応募への後押しにつながります。
休日・福利厚生をわかりやすく提示する
応募者は給与だけでなく労働条件にも敏感です。休日や福利厚生を積極的に訴求すると、「働くうえでの安心感」を得てもらいやすいです。
例えば、以下のように要点を整理します。
休日
- 完全週休2日制(土日)+祝日休み
- 年間休日120日以上(2024年は125日)
- 有給取得率8割、平均消化日数10日
福利厚生
- 住宅手当:3万円/月を一律支給
- 交通費:上限2万円/月
- 産休・育休制度:復帰後の時短勤務OK
- 社内表彰や社員旅行あり
数字を入れるほどイメージが固まりやすく、同等の給与水準であれば「休みを取りやすい会社」を選ぶ傾向も高まります。社内規定がまだ整っていない箇所があるなら、改善策を検討しながら求人の段階で工夫を示すのも良いでしょう。
さらに詳しい求人情報の書き方は、求人票の書き方のコツを徹底解説|求人票の作り方5ステップにまとめています。
採用時期を前倒しする
採用活動のスタートが遅れると、優秀な人材が大手企業や他社で内定を得てしまいがちです。新卒採用なら大学3年生の夏頃に準備を始め、中途採用でも季節問わず通年で募集するようにしましょう。
例えば、以下のように先手を打つのがポイントです。
ポイント
- インターンシップを早めに実施し、興味を高める
- SNSやWebで募集枠を常時公開し、空きが出たらすぐ面接
- 内定承諾までのフローをシンプルに設計
早めのアプローチが、知名度が低い中小企業でも候補者とじっくり話す時間を確保するチャンスになります。
経営層や現場のメンバーも採用活動に参加する
人事担当だけが採用活動していると、会社の全容を伝えにくい可能性があります。経営者が面接に出席すればビジョンを伝えられます。さらに、配属先のリーダーが会社説明会に出ると仕事のリアルを話せるため、候補者の納得度が上がるでしょう。
以下のような組み合わせもおすすめです。
経営層や現場のメンバーが採用活動に参加する例
- 役員が面接を担当し、事業計画の将来像を示す
- 実際の業務リーダーが質疑応答し、不安を解消する
- 他部署の社員が社内を案内して雰囲気を伝える
連携を深めると応募者は「職場での連帯感」をイメージしやすくなり、入社意欲を高めるきっかけになります。
カジュアル面談を実施する
早期のすり合わせを重視するなら、応募前でも気軽に話し合えるカジュアル面談を実施すると良いでしょう。応募者も採用担当者と気軽に話せるので、親近感を持ってもらいやすいです。
会議室に候補者を呼ぶだけでなく、オンラインで「知識テストやスキルは不問なので、まず話してみたい」と案内する方法もあります。
具体的には、以下のような流れでカジュアル面談を実施してみましょう。
カジュアル面談の流れ
- SNSやサイト上で「カジュアル面談募集中」と明示
- 経歴や希望条件を簡単に共有してもらう
- リラックスした雰囲気で企業紹介や雑談を通じて相性を探る
堅苦しくないやりとりで相性を確かめられるため、企業側が求める人物像と候補者の希望を確認しやすくなります。採用担当者の手間は増えますが、1人でも多く採用したい場合はカジュアル面談が有効です。
内定者フォローを徹底する
内定を出しても、候補者が承諾するとは限りません。近年の求職者は複数の企業から内定をもらうケースが多く、内定を出した後も関係を切らさない努力が求められます。
懇親会や個別面談で「何か不安はないですか?」と声をかけたり、現場見学を追加で企画したりすると辞退率を抑えられます。
具体的には、以下の取り組みを検討してみてください。
内定者フォローの例
- オンライン座談会:内定者同士や先輩社員と意見交換
- メールマガジン:業務トピックや社内行事を定期的に案内
- 入社前研修:短期間の実務体験やスキル勉強会
こうした交流が、会社で働く姿を自然に想像できる効果を生み、内定承諾率を高めます。内定を出した後も気を引き締めて、候補者との関係を良くしていきましょう。
採用担当者の研修を強化する
面接ノウハウやマーケティング手法を知らないまま採用活動を進めると、せっかく応募があっても魅力を十分に伝えられません。外部セミナーや勉強会などを活用して、採用ノウハウを学ぶ姿勢が必要です。
具体的な学習方法は以下のとおりです。
| 学習方法 | 概要 |
|---|---|
| 外部セミナーや勉強会への参加 | 人材会社や業界団体が主催する採用セミナーに参加し、最新トレンドを取り込む |
| 書籍やオンライン講座を活用する | 「採用の教科書」や「面接官トレーニング」のような専門書を購入し、社内で共有しながら読み進める |
| ロールプレイやフィードバック | 面接官同士で模擬面接を行い、質問や回答例をブラッシュアップする |
| オンラインコミュニティへの参加 | SNS上の採用担当者コミュニティで悩みを相談し合い、成功事例を教わる |
| コンサルタントや顧問を一時的に招く | 採用コンサルタントをスポットで雇い、課題分析や対策案を出してもらう |
研修を受けただけで終わると個人のスキル習得にとどまり、組織全体の採用力向上にはつながりにくいです。以下のような方法で、社内全体の採用ノウハウを底上げしましょう。
ノウハウを共有する方法
- 研修レポートをまとめ、面接官や現場社員に配布
- 次回の募集や面接に新しい質問項目や評価表を反映
- スカウトメールの文面テンプレートを社内フォルダで共有
研修と実務を往復しながらPDCAを回すことで、採用担当者が蓄えたノウハウが社内に定着し、長期的に活用されやすくなります。学んだ知識をすぐ実践に移し、効果を確認して次の改善につなげるサイクルを根づかせましょう。
中小企業の採用におすすめのチャネル10選|コストも紹介
続いて、中小企業の採用活動におすすめのチャネルを紹介していきます。まだ使っていないものがあれば、実践してみてください。
中小企業の採用におすすめのチャネル
- ダイレクトリクルーティング
- リファラル採用
- SNSリクルーティング
- 採用ページ
- 地方のコミュニティ
- インターンシップ
- 求人サイト
- ハローワーク
- 合同説明会
- エージェント
各チャネルにかかるコストの相場も紹介するので、検討してみましょう。
ダイレクトリクルーティング
ダイレクトリクルーティングは、人材データベースを参照して、企業が直接候補者へアプローチする方法です。必要なスキルを持つ人を自社から探せるため、知名度に左右されにくく、即戦力層を短期間で確保しやすいです。
ただし、一人ずつ連絡する手間があるため、短期間に大人数を集めたい場合は向かないでしょう。
| メリット | ・知名度が低くても興味を持つ人を狙い打ちしやすい ・コミュニケーションが早く、面談に進みやすい ・受け身で待つ採用よりも早期に行動しやすい |
| デメリット | ・スカウトメールの文章を工夫しないと返信率が下がる ・担当者がこまめにフォローする必要がある |
| コスト相場 | 月額数万円~数十万円の定額利用サービスや、成果報酬型プランがある |
ダイレクトリクルーティングは「HELLOBOSS」がおすすめ
ダイレクトリクルーティングは、私たちが提供する「HELLOBOSS」がおすすめです。
月額4,000円〜でスカウトメール送り放題なので、貴社にフィットしそうな人材に積極的にアプローチしてみましょう。
さらに、10万人を超えるユーザーの中から、AIが貴社に合う人材をマッチングしてくれるため、採用担当者の負担を軽減します。
候補者と直接チャットができるため、返信率も高く、信頼関係を築きやすいのもメリットです。
無料版から始めることも可能です。テストとして使ってみてください。
わずか3ステップで始められるため、さっそくHELLOBOSSを試してみましょう。
リファラル採用
リファラル採用は、社員の知人・友人を紹介してもらう採用方法です。社内文化を知る社員が候補者を選ぶため、入社後のミスマッチを防ぎやすいです。また、外部のサービスを使わないため、費用対効果が高いメリットもあります。
自社の求める人物像やスキルを社員に正しく共有するのがコツです。
| メリット | ・社風や業務内容を理解している社員が候補者を選ぶ ・採用コストが少なく、早期離職も起きにくい ・社員のモチベーション向上につながる可能性がある |
| デメリット | ・求める人物像を社内で共有しないと紹介の精度が下がる ・似た人材ばかりが集まり、多様性が欠けるリスクがある |
| コスト相場 | 紹介時の報奨金(数万円~数十万円)を社内規定で設定する例が多い |
ただし、高額な紹介料を社員に支払うと、職業安定法や労働基準法に抵触する恐れがあるので注意しましょう。以下のように紹介料を支払うのが一般的です。
リファラル採用の紹介料の取り扱い
- 賃金や給与として支払う
- 就業規則や雇用契約に明記する
- 支給条件を明確化する(◯ヶ月以上在籍していることなど)
SNSリクルーティング
X(旧Twitter)やInstagramなどのSNSで、会社の活動や社員の様子を定期的に発信し、興味を持った人に応募をうながす方法です。ビジュアルを活かしやすく、あまり費用がかからない点が魅力です。
また、SNS上の人材に直接アプローチすることも可能です。
注意
一方、使い方を誤ると炎上リスクがあるため、投稿内容や返信ルールを整える必要があります。
| メリット | ・軽い予算で社内の雰囲気を視覚的に伝えやすい ・リアルタイムなコミュニケーションが可能 ・若年層へのリーチが期待しやすい |
| デメリット | ・炎上や誤解を防ぐため、運用ルールが必須 ・反応が得られるまで時間がかかる |
| コスト相場 | SNS自体は無料だが、有料広告を使うなら月数万円~10万円程度 |
採用ページ
自社ホームページや特設サイトに、求人情報と企業の魅力をまとめた採用ページを用意しましょう。企業理念や具体的な業務写真、社員インタビューなどを掲載して、候補者にアプローチします。
求人サイトに掲載できない細かい情報も伝えられるので、積極的に自社の情報を発信するのがコツです。
注意
更新を怠ると古い情報で印象が悪くなるため、定期的なメンテナンスが欠かせません。また、デザインが悪いと第一印象を損なう恐れがあるため、デザイナーへの外注も検討してください。
| メリット | ・自社ブランディングを一貫して表現できる ・動画や写真を活用し、わかりやすく魅力を発信できる ・他のチャネル(求人サイトなど)からリンクしやすい |
| デメリット | ・放置すると鮮度が落ち、逆効果になる ・制作や運用にはデザインやライティングの知識が必要 |
| コスト相場 | 制作費数万円~数十万円(外注による) |
地方のコミュニティ
地域の就職フェアや自治体の採用支援制度など、ローカルに根ざしたチャネルを活用する方法です。特に地方では競合他社との比較が少ない場合があり、人材を確保しやすい面があります。
地元の商工会議所やNPO法人と連携して、地域コミュニティで会社説明会を開催する企業もあります。
| メリット | ・中小企業が目立ちやすい ・地域の絆や支援制度で、定着率が高い人材を呼びこめる |
| デメリット | ・地域イベントだけだと母集団が少ない恐れがある ・Uターン・Iターン希望者に情報を届ける工夫が必要 |
| コスト相場 | ・自治体のイベント参加費:無料~数万円 ・ポスターやパンフレット作成費は数万円程度 |
インターンシップ
学生や未経験者を短期間で受け入れ、業務を体験してもらう方法です。実際に仕事をしてもらうため、入社後のミスマッチが低減し、内定後の辞退率も下がりやすいです。
短期(1~2週間)で業務の一部を任せたり、長期(1〜2ヶ月)で特定のプロジェクトを担当してもらったりする方法があります。
| メリット | ・会社と候補者が相互理解を深められる ・就職先の候補を絞る場になり、内定率を高めやすい ・職場を見せることで将来像をイメージしやすくなる |
| デメリット | ・受け入れ態勢の整備が必要 ・報酬や保険など制度面の検討が必要 |
| コスト相場 | 1人あたり数万円~数十万円(研修費・保険料・社員のフォロー時間による) |
求人サイト
求人サイトには総合型や特化型など種類があり、掲載すると多くの候補者に見てもらえます。社名を知ってもらう機会にはなりますが、職種や待遇が平均的だと他社に埋もれがちです。
求人サイトを利用する際は、候補者に発見してもらえるように、キャッチコピーや求人票の書き方にこだわりましょう。キャッチコピーや求人票のコツは、以下の記事にまとめています。
関連記事
- 求人キャッチコピーの例文集50選一覧|6つの面白い心理効果も紹介
- 求人票の書き方のコツを徹底解説|求人票の作り方5ステップ
| メリット | ・幅広い層からの応募が見込める ・知名度が低くてもサイト流入を通じて認知される ・募集職種や業界に合ったサイトがある |
| デメリット | ・多くの企業が募集するため差別化が必要 ・原稿や写真のクオリティが求められる |
| コスト相場 | 1枠数万円~50万円程度(掲載期間やランクにより幅がある) |
ハローワーク
公共の求人サービスで、費用がかからない点が最大の魅力です。特に、地元志向が強い候補者とのマッチングが期待できます。
求人票を登録するだけでは応募者が集まりにくい場合もあるため、記載内容をよく練りましょう。近年は求人票のオンライン受付やセミナーの活用など、使いやすさが向上しています。
| メリット | ・コストを抑えられる ・地元の人材を集めるのに有効 |
| デメリット | ・他社と同じ仕組みで掲載されるため差別化が必要 ・求人票をわかりやすく書かないと埋もれやすい |
| コスト相場 | 無料(求人票作成などの手間は発生する) |
合同説明会
多くの企業が一堂に集まるイベントに出展し、対面でPRする手段です。主に新卒向けや業界別の転職フェアなどがあり、短時間で多くの求職者と接点を持ちやすいメリットがあります。
ブースの設営や資料作成が必要なため準備のコストはかかりますが、候補者が多く集まるため、自社の魅力を直接アピールできます。
| メリット | ・1日で複数の候補者と面談できる ・候補者の反応を見ながら説明を調整できる ・候補者への訴求力が高い |
| デメリット | ・ブース設営や社員の人員確保など準備が必要 ・イベント後の即フォローが重要 |
| コスト相場 | 数万円~数百万円(会場規模や出展料による) |
エージェント
人材紹介会社に依頼し、自社に合う候補者を紹介してもらうサービスです。担当コンサルタントが企業情報を理解した上で、条件に合う人を紹介するため、精度の高い面談を組みやすいです。
ただし、採用が決まった段階で成果報酬を支払うケースが多く、採用人数や想定年収によってコストが大きくなる場合があります。
| メリット | ・応募者との各種調整を代行してくれる ・短期間でプロが候補者を絞り込む ・専門人材の採用に強い |
| デメリット | ・採用決定者の年収が高いほど費用が増える ・企業の魅力をエージェントへ細かく伝える必要がある |
| コスト相場 | 採用が決まった人の想定年収の20%~35%程度 |
採用の苦戦から脱却した中小企業の成功事例

ここでは、採用難易度が高い状況でも、AI採用ツール「HELLOBOSS」を活用して「採用の苦戦」から脱却した中小企業などの事例を紹介します。
AIを活用して人材を採用した中小企業の成功事例
- 専門職を採用できた情報通信業の事例
- 2週間で経理経験者を採用したサービス業の事例
- 地方でドライバー採用に成功した運輸業の事例
- ターゲットからの応募を獲得した飲食業の事例
自社に近い課題をもつ企業の事例を参考にしてみてください。
専門職を採用できた情報通信業の事例
情報通信業の株式会社Yoii(従業員数1〜49名)では、採用難易度の高い「審査」と「経理・財務ポジション」の母集団形成に課題を抱えていました。
そこでHELLOBOSSのAgentプランを導入し、AIマッチングとコンサルタントによる推薦を活用。
その結果、半年間で3名の推薦から3名の採用決定という高精度なマッチングを実現しました。
知名度が課題となる中小企業でも、ピンポイントなアプローチで専門人材を採用できる可能性があります。
2週間で経理経験者を採用したサービス業の事例
サービス業のフィナンシャルフィールパートナーズ(従業員数1〜49名)では、経理経験者の採用において母集団形成とコスト削減を目指していました。
HELLOBOSSのProプランを導入し、AIマッチングとスカウト機能を活用してアプローチを実施。
結果として、導入からわずか2週間で2名の採用に成功しています。
リソースが限られる小規模組織でも、AIを活用すればスピーディーな採用活動が実現できます。
地方でドライバー採用に成功した運輸業の事例
ある運輸業では、母集団形成に苦戦しやすい地方のドライバー採用において、HELLOBOSSを活用しました。
AIを活用してターゲットへ的確にアプローチしたことで、有効応募率は90%以上を達成しています。
さらに、既存の求人媒体と比較して一人当たりの採用単価を30%削減することにも成功。
採用難易度が高い地域や職種であっても、AI採用ツールを活用すれば、コストを抑えた採用成功が見込めます。
ターゲットからの応募を獲得した飲食業の事例
ある飲食業では、求人検索エンジンの応募単価が高騰しており、店長候補ポジションの採用に苦戦していました。
HELLOBOSSを活用し、動画による訴求とAIアプローチを組み合わせた運用を開始。
その結果、ターゲット層からの応募を多数獲得し、獲得効率の良い採用ツールとして定着しています。
競合が多い業界でも、AIと動画で自社の魅力を正しく伝えれば、求職者を振り向かせることができます。
中小企業の採用活動でやってはいけないこと
採用活動において「やってはいけないこと」も解説していきます。
中小企業の採用活動でやってはいけないこと
- 虚偽の求人を出す
- レスポンスが遅い
- 候補者にしつこく連絡する
これらの行動は人材を採用できないだけでなく、評判を落としてしまうためNGです。失敗を防ぐためにも、念のため知っておきましょう。
虚偽の求人を出す
仕事内容や給与など、実態とかけ離れた情報を求人票に記載するのはNGです。職業安定法に抵触するのはもちろん、早期離職に繫がります。
また、SNSなどで不満を拡散される恐れがあるでしょう。企業に対するネガティブな評判が広まると、次の募集がさらに苦戦する状況になりかねません。
虚偽求人の例
- 実際より高い給与を記載する
- 残業が多いにも関わらず「残業なし」と書く
- 研修・教育環境が整っていないのに「充実」と強調する
いずれも信頼を失い、応募者から見放される原因になりやすいです。
レスポンスが遅い
面接後の合否連絡に時間をかけすぎると、別の企業へ流れてしまうリスクが高まります。例えば、書類選考が終わっているのに「業務が忙しく後回しにしていた」という状態だと、応募者は不安を覚えて他社の内定を受けるかもしれません。
注意
合否の連絡が遅い企業は選考フロー全体に統一感がなく「組織体制が不安定」という印象を与えやすいです。
面接終了から1週間以内には結果を伝える体制を整えましょう。社内で誰が担当するかを明確にしながら、迅速に対応すると応募者の意欲を保ちやすくなります。
候補者にしつこく連絡する
内定を出した後、短い回答期限を押し付けたり、1日に何度も連絡する行為は逆効果です。候補者は人生の大きな選択を前に、他社との比較や家族・知人に相談するため、強制的なプレッシャーに嫌悪感を抱くことがあります。
忙しい合間を縫って選考に臨んでいる場合もあり、過剰な連絡がストレスになり、内定を辞退されるリスクもあるでしょう。
| しつこく連絡するリスク | 具体例 |
|---|---|
| 内定辞退 | 「強引な会社」とのイメージが残り、応募者が去る |
| 悪評拡散 | SNSやクチコミサイトでマイナス評価を広められる |
| 企業ブランド低下 | 他の候補者や社員にも悪影響を与え、採用難が続く |
最初に内定通知を出す際に「1週間程度を目処にご検討ください」と伝え、丁寧なフォローにとどめる姿勢が理想的です。
中小企業が定着率を上げる3つのコツ
採用した人材がすぐに辞めてしまわないように、定着率を上げる施策も実施しましょう。
中小企業が定着率を上げるコツ
- メンター制度の導入
- 研修制度の整備
- キャリアパスの整備
採用コストをロスしないためにも、これらを実施していくのがおすすめです。
メンター制度の導入
経験を積んだ先輩が新入社員を個別にフォローするメンター制度は、初期の離職を防ぐうえで有効です。例えば週1回の面談を設定し、業務の進め方や社内ルールを丁寧に伝え、つまずきを早期に解決する流れを作ります。
ポイント
メンターは技術指導だけでなく、悩みごとの相談役も兼ねるため、新入社員の孤立感を減らせます。それが離職防止に繋がります。
メンター制度の導入にあたり、担当者の選び方やサポート範囲を具体的に決めておくのがおすすめです。メンターが抱える負担を考慮し、月ごとの負担や目標を共有しておけば、両者にとって無理なく運用しやすくなります。
研修制度の整備
入社後の研修や勉強会が少ない中小企業は、業務を独学で学ぶしかなく、社員によって成長速度に差が出がちです。仕事に対する不安が大きくなると、離職者が出るリスクが高まります。
例
週1回の勉強会やオンライン講座を導入し、全員が計画的にスキルアップできる仕組みが望ましいです。
社内連携も自然に深まり「学べる会社」という雰囲気が醸成されると、定着率アップにつながります。
研修制度を整えるうえで、以下を考慮すると良いでしょう。
研修制度の整備で考慮すること
- 開催頻度と所要時間(週1回30分、月1回2時間など)
- 内容のレベル(初級・中級・上級に分けて段階的に学ぶ)
- 講師(社内で賄うか外部を招くか)
こうした学習機会を定期的に提供すると、新入社員だけでなくベテラン社員にも刺激になり、全社的なスキル向上が期待できます。
キャリアパスの整備
将来の昇給や役職の進み方が不明確な組織では、社員が不安を覚えて離職を考えやすいです。例えば「入社3年で主任、5年で課長補佐を目指す」といった具体像を示すと、モチベーションを保ちやすくなります。
定期的に個別面談を実施して、本人の適性や希望を踏まえた次のステップを共有しておくのがコツです。
| キャリアパスの例 | 主な内容 | 期間の目安 |
|---|---|---|
| 新人~若手期 | 基本的な業務習得と社内ルールへの適応 | 入社から3年目頃 |
| 中堅期(リーダー候補) | 部下や後輩への指導、部門目標への貢献 | 3~5年目 |
| 管理職(課長・部長など) | 部門の人材育成や予算管理、経営層との連携 | 5年目以降 |
このような道筋を事前に確認できれば、社員は未来の姿を想像しながら人生の計画を立てやすくなります。成果を出した社員に対して具体的なポジションを用意する動きがあれば、働く意欲が高まり離職率も下がります。
中小企業の採用活動でよくある質問
最後に、中小企業の採用活動でよくある質問に答えていきます。
中小企業の採用活動でミスマッチを防ぐコツは?
入社後の実態と候補者のイメージが大きく違うと、早期離職の原因になります。そこで「求める人物像」「職場環境」「仕事の流れ」などを事前にきちんと説明しましょう。
業務内容を具体的に語り、1日のスケジュールや社内の意思決定スピードを共有すれば、入社後のギャップが減ります。
また、面接に現場リーダーや先輩を交えて、業務のリアルを直接話してもらう方法も効果的です。
ミスマッチ防止に有効な手順
- 職務内容と応募条件を明確化(裁量権や必要スキルなど)
- 選考中に具体的な業務事例を示し、候補者の質問を歓迎
- 入社前オリエンテーションや職場見学を実施
こうした手順を踏めば、会社が期待している役割と応募者の得意分野が合致するか、早い段階で見極めやすくなります。
もし人材を採用できないままだとどうなる?
長期的な視点で見ると、既存メンバーに負荷が集中し、離職を誘発する恐れがあります。
例
受注案件が増えても人手が足りずに納期が厳しくなり、結果としてクレームや社員の疲労が増大するかもしれません。余裕がない状況が続くと新規事業の立ち上げや、製品改良に取りかかるリソースも限られ、組織の成長が滞りがちです。
対外的な評価が下がっていくと、評判の影響で採用がさらに難しくなるリスクがあります。人材確保と社内環境の改善を同時に進める姿勢が必要です。
面接ではどんな質問をしたらいい?
求職者の本音を探るうえで、過去の経験や具体的なエピソードに着目する質問が有効です。
具体例
「前職でどんな課題に直面し、どう解決したか」「自分が成長を感じた瞬間はいつか」と質問すると、実務力や思考パターンを把握しやすくなります。
短い時間で多くを聞くよりも、深掘りして話してもらう方が、候補者の人物像をイメージしやすいです。
| よくある質問例 | 得られる情報 |
|---|---|
| 成功体験で苦労したポイントは? | 問題解決力やストレス耐性 |
| チームで協力が必要だった場面は? | コミュニケーションの取りかた |
| 目標に向かう過程で工夫したことは? | 行動力や継続力、責任感 |
こうした質問を組み合わせると、候補者がどんな考え方で働いてきたのか見えてきます。面接官ばかり話す時間が長くならないように注意しましょう。
採用に関する助成金や補助金はある?
雇用や研修に関係する助成制度は複数あり、条件を満たせば費用面でメリットがあります。
ポイント
研修を行う企業に給付される「人材開発支援助成金」や、非正規社員を正社員に転換した企業を支援する「キャリアアップ助成金」などが挙げられます。
ただし、提出書類や対象期間などが細かく指定されているため、準備の時間を想定しておきましょう。
助成金活用のステップ
- 厚生労働省のサイトや自治体窓口で該当する制度を調べる
- 受給条件や必要書類、申請の期限をリストアップ
- 申請書類の作成を始める前に社会保険労務士や商工会議所へ相談
- 期限や提出様式を守り、不備なく書類を送付する
助成金を活用して研修費用や人件費の一部をまかなえる可能性があるため、早めのリサーチと準備を進めてみてください。
中小企業が新卒を採用するコツは?
早めの説明会やインターンシップで学生との接点を増やすと、興味を持ってもらえるチャンスがあります。例えば、3年生の夏頃からオンライン説明会を始め、職場の雰囲気や実際の業務を具体的に紹介するのが効果的です。
ポイント
新卒は大手企業を優先する人もいますが、裁量が大きい環境や成長スピードの速さなどの利点を示せば、魅力を感じて応募する学生が出てきます。
内定を出した後は学生の不安を解消するため、内定者懇親会や少人数の面談を組み、社内の空気を共有しながら入社意欲を高めていきましょう。
新卒の人材を採用するコツは、新卒採用が難しい7つの理由|新卒採用におすすめの手法11選も紹介も参考にしてみてください。
まとめ|中小企業向けの採用方法を実践しましょう
知名度の不足や人手不足の影響で、中小企業の採用活動が難しい側面はあります。しかし、採用活動を見直していけば、人材採用の目標を達成できる可能性が上がります。
さっそく以下のようなチャネルを組み合わせながら、採用活動を進めていきましょう。
中小企業の採用におすすめのチャネル
- ダイレクトリクルーティング
- リファラル採用
- SNSリクルーティング
- 採用ページ
- 地方のコミュニティ
- インターンシップ
- 求人サイト
- ハローワーク
- 合同説明会
- エージェント
くりかえしですが、ダイレクトリクルーティングでは、私たちが提供する「HELLOBOSS」がおすすめです。
月額4,000円〜でスカウトメール送り放題なので、コストを抑えて貴社にフィットしそうな人材にアプローチできます。
候補者と直接チャットができるため、返信率も高く、信頼関係を築きやすいメリットがあります。
無料版から利用できるので、テストとして使ってみてください。
わずか3ステップで始められるため、さっそくHELLOBOSSを試してみましょう。
貴社の人材採用の参考になれば幸いです。