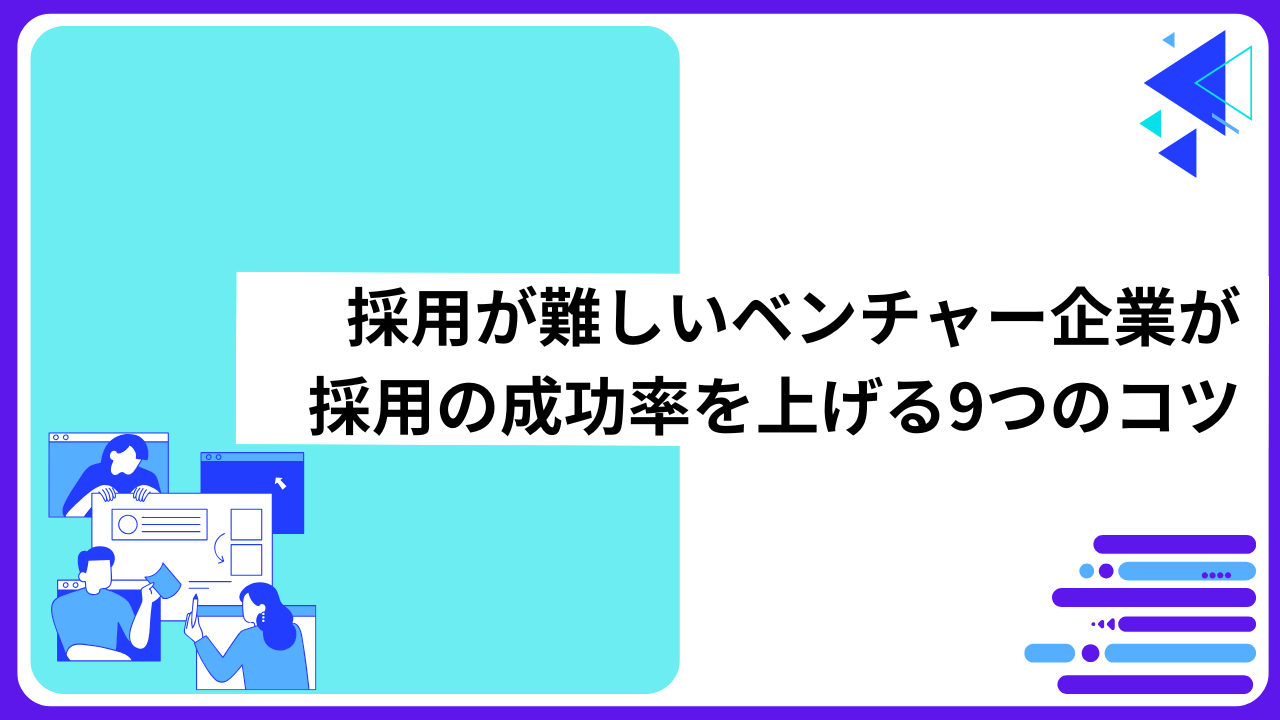「ベンチャー企業の採用活動は難しい…」
「どうすれば良い人材を採用できる?」
とお悩みのベンチャー企業の人事担当者様に向けた記事です。
この記事でわかること
- ベンチャー企業の採用が難しい理由
- ベンチャー企業で人材採用の成功率を上げる9つのコツ
- ベンチャー企業におすすめの採用手法10選
市場の人材不足や、大手企業に人材が集まりやすいことなどから、ベンチャー企業の採用活動が難しくなっています。
「ベンチャー企業の仕事は大変そう…」というネガティブなイメージを持つ求職者もいるため、採用活動が難航するケースもあるでしょう。
この記事では、ベンチャー企業が人材採用に成功するコツを完全解説しています。
自社に合う人材を採用できる可能性が上がるため、人材採用の目標を達成したい人事担当者様は最後まで読んでみてください。
人材にダイレクトアプローチできます
「前置きはいいから、早く人材を採用するコツを知りたい!」という方は、ベンチャー企業で人材採用の成功率を上げる9つのコツへジャンプしてみて下さい。

Contents
ベンチャー企業で人材採用が難しい内的要因5選
まずは、ベンチャー企業で人材採用が難しい内的要因を紹介します。
採用が難しい要因を知らないと対策を打てないため、知っておきましょう。
ベンチャー企業で人材採用が難しい内的要因
- 企業の知名度が足りないから
- ベンチャー企業にネガティブな印象があるから
- 採用担当者のリソースが足りないから
- 採用にかけられるコストが不足しているから
- 待遇面で大手企業に見劣りするから
1つずつ解説していきます。
企業の知名度が足りないから
認知度の低さは、そもそも求人情報に気づいてもらえず応募が集まりにくい一番の理由です。大手企業も存在する求人市場では、ベンチャー企業の名前を見ても「何をしている会社かわからない…」と思われることがあります。
注意
外部からの評価や実績が少ない場合、求職者が業務内容や将来性をイメージしにくく、信頼性の裏付けを得にくいかもしれません。その結果、書類選考以前に検討外とされる可能性があります。
入口の時点で候補者と接点を作れないと、優秀な人材を確保する難易度が上がり、採用の軌道にのるまでに時間を要するでしょう。
ベンチャー企業にネガティブな印象があるから
ベンチャー企業は、大企業と比べて雇用が不安定だと思われたり、長時間労働が常態化していると連想されたりする場合があります。特に安定志向の方にとっては、将来像がはっきり見えない環境だと不安になるかもしれません。
注意
実際には研修制度や働き方を整えていても、既存のイメージに引きずられることがあります。そうした固定観念が根強いと、応募の入り口が狭まります。
イメージが先行すると実際の魅力が正しく伝わりにくく、人材獲得に苦戦する要因になります。誤解を解こうと説明しても、先入観を変えるのに時間がかかるのも懸念点です。
採用担当者のリソースが足りないから
ベンチャー企業では、社長や役員、現場のリーダーが採用を兼任している状況が多いです。営業や企画の仕事で手いっぱいになり、応募者への連絡や選考スケジュール調整が後回しになることもあるでしょう。
下表にあるように、作業が詰まると応募者のフォローが遅れ、人材を採用できない可能性が高まります。
| 見られる現象 | 起こりやすい結果 |
|---|---|
| 応募者への返信が遅れる | 興味が冷めて、別企業の面接に流れてしまう |
| 面接枠を十分に確保できない | 候補者の予定と合わず、すれ違いが増える |
| 書類選考の基準が曖昧 | 選考に時間がかかることで、他社で先に内定を出されてしまい、採用の機会を逃す |
| 採用広報や宣伝が後回しになる | 母集団が増えず、安定的な人材確保が難しい |
さらに、採用活動の量が少ないとノウハウが乏しくなりがちで、求人情報の発信内容も改善しにくいでしょう。こうした点が重なると、せっかく興味を持ってくれた候補者をスムーズに迎えられず、採用の成果にムラが出やすいです。
採用にかけられるコストが不足しているから
求人サイトやエージェント、求人広告など、どの手段にも予算が必要です。ベンチャー企業は研究開発やサービス拡大に資金を投下するため、人材確保の予算が少ない場合があります。
注意
無理に高額な広告を利用しても継続性を担保しづらく、思うほど成果が上がらないまま終了することもあるでしょう。コストをかけて広範囲に情報を拡散できないと、母集団形成が滞り、有望な候補者に情報が届きにくいです。
さらに、面接に投入する人件費なども限られると、フォローアップや選考プロセスの改善に着手しづらく、採用難が長引くリスクがあります。
待遇面で大手企業に見劣りするから
給与や福利厚生、休暇制度などで差が出ると、求職者の目には魅力が薄く映ります。大手企業のように高い初任給や手厚い手当を用意しにくいため、同じ業界で比較されたときに不利になりがちです。
ポイント
実際には成長機会が豊富なベンチャー企業でも、待遇欄に大きな魅力を示せないと敬遠されるかもしれません。さらに、新しい制度を整えようにも運営コストが増えるため、導入そのものを後回しにする企業もあります。
結果として候補者が働く環境への安心感が得られず、早い段階で応募をあきらめる可能性もあるでしょう。
「前置きはいいから、早く人材を採用するコツを知りたい!」という方は、ベンチャー企業で人材採用の成功率を上げる9つのコツへジャンプしてみて下さい。
ベンチャー企業で人材採用が難しい外的要因3選
続いて、ベンチャー企業の人材採用が難しい外的要因を解説します。
ベンチャー企業の人材採用が難しい外的要因
- 人材不足で採用競争が激化しているから
- 採用チャネルが複雑化しているから
- 安定思考の求職者もいるから
外的要因は自社では対策できないものですが、どういう業況なのか知っておかないと効果的な対策を立てられません。念のため外的要因も理解しておきましょう。
人材不足で採用競争が激化しているから
労働人口は減少傾向にあり、特にITやエンジニアなど専門性を要する分野では応募者数が伸びにくいです。厚生労働省が発表した令和6年11月の有効求人倍率は1.25倍で、売り手市場が続いているとわかります。
出典:厚生労働省|一般職業紹介状況(令和6年11月分)について
また、大手企業や外資系企業も同じ人材を求めて積極的に採用活動を進めるため、倍率が高い状態です。求職者がスキルを武器に複数の企業を比較する中、ベンチャー企業はブランド力で見劣りすることもあります。
その結果、他社と比較されて採用に至らないケースもあるでしょう。
採用チャネルが複雑化しているから
採用手段は多様化しており、複数の方法を活用しないと有力な候補者に届きにくい状況です。以下のようにチャネルごとに得意分野が異なるため、全方位的に取り組まないと狙った層に接触し損ねるかもしれません。
| 代表的な採用チャネル | 特徴 |
|---|---|
| 求人サイト | 幅広い層へ一括で知らせる方法 |
| SNS採用 | クリエイティブ職や若手層に直接アピールしやすい |
| ダイレクトリクルーティング | 即戦力人材にピンポイントでアプローチしやすい |
| コミュニティ参加 | 業界イベントで近い専門分野の人にアプローチしやすい |
複数チャネルを扱うにはノウハウや人的資源が必要です。そうした体制が整っていない場合は、せっかく注目を集めてもフォローが遅れて離脱を招く恐れがあります。
安定志向の求職者もいるから
近年は働き方が多様化しているものの、経済情勢の影響などから安定や福利厚生を重視する人もいます。大手企業なら給与水準や待遇が明確で、長期的に働きたい層には魅力的に映りやすいでしょう。
ポイント
一方、ベンチャー企業は「事業が軌道にのるまで読めない」「長時間労働が続くのでは…?」と警戒される場合があります。家族を支えている方や安定収入を求める方の中には、未知のリスクを負うよりも既存の安心材料を優先する方もいます。
そうした傾向が強い層とは最初から接点を持ちにくく、候補者の母集団拡大が難しくなることがあります。
ベンチャー企業で人材採用の成功率を上げる9つのコツ
それでは、ベンチャー企業が人材を採用していくコツを解説していきます。
ベンチャー企業が人材を採用していくコツ
- ミッションやビジョンを明確にする
- 採用ペルソナを明確にする
- 自社の強みを整理する
- 採用プロセスを最適化する
- 採用基準を決めておく
- 現場社員や経営者も採用活動に参加する
- ストックオプションを提示する
- 採用担当者のスキルアップを図る
- 未経験者の採用を検討する
採用が厳しい状況でも、これらを実施していけば採用に成功する確率が上がります。1つずつ解説していくので、できそうなものから始めてみてください。
ミッションやビジョンを明確にする
自社のミッションやビジョンを具体的に打ち出すと、候補者が「なぜそこで働きたいか」を想像しやすいです。単に「社会貢献したい」ではなく、どの課題を解決しようと考えているのかを数字や実例で示すのが有効です。
以下のようにポイントを押さえると、一貫したメッセージを伝えやすくなります。
| ミッションやビジョンを考える要素 | 詳細 |
|---|---|
| 今後目指す事業規模や顧客層 | 何年後にどの市場で勝負するか |
| どんな価値を提供するか | 既存サービスとの違いや革新点 |
| 実行プロセスのエピソード | 開発中の苦労やチームの取り組みなど |
組織内でミッションやビジョンを共有しておけば、面接や広報でも自然に語れるようになり、熱意のある人材を引き寄せるでしょう。候補者の熱意を引き出しやすくなり、入社後のモチベーション維持にも役立ちます。
採用ペルソナを明確にする
自社が求める「採用ペルソナ」を明確にしましょう。採用ペルソナとは、自社で採用したい人物像の詳細のことです。
必要とするスキルや経験だけでなく、どんな職場環境にフィットするかまで設定すると、採用ミスマッチを抑えられます。
以下のように項目別に整理すると、採用ペルソナが定まりやすいです。
| 項目 | 例 |
|---|---|
| スキル | Web開発3年以上、リーダー経験など |
| 志向性 | 新しい手法を積極的に試す |
| 価値観 | チャレンジ精神を楽しめる |
| 人柄 | オープンマインドで相談しやすい |
現場のリーダーやチームの声を踏まえながらペルソナを考えると、実務の期待と応募者の特性が合致しやすくなります。募集要項にも反映させやすくなり、早期離職を防ぎながら長期的に活躍する人材の確保につながるでしょう。
ちなみに、ペルソナを設定する具体的な手順は以下のとおりです。
採用ペルソナを設計するステップ
- 採用したい人材像を社長や現場に聞く
- 人材を採用する目的を定義する
- 採用したい人材像を書き出す
- 採用市場に合わせたペルソナにする
- ペルソナを経営層や現場のメンバーに確認してもらう
ペルソナ設定の詳細は、採用ペルソナの作り方完全ガイド|テンプレートと7ステップのフレームワークを参考にしてみてください。
自社の強みを整理する
大企業と比べて給与や福利厚生で劣るなら「若手のうちから裁量を持てる」などの強みを明示すると良いでしょう。単に「やりがいがある」という表現ではなく、具体的な成功体験や社内ルールの自由度を示すと、候補者が入社後の姿を想像しやすいです。
以下のような視点から洗い出すと、自社の魅力を理解しやすいでしょう。
ベンチャー企業の強みの例
- キャリアアップの早さ:昇格事例や平均年齢を数値化
- 裁量の大きさ:新しいアイデアを実践しやすいフロー
- 現場の風通し:少人数だからこそ直接声を届けられる
ベンチャー企業の強みの具体例
- 入社半年でプロジェクトリーダーへ登用するケースあり
- 平均年齢26歳で意思決定を担うポジションに進んだ例あり
- SNS広告の予算管理やクリエイティブ制作にも裁量を発揮できる
こうした強みをSNSや採用ページで発信しておくと、認知度が低い場合でも「ここでなら成長できそう」と思ってもらいやすいです。結果として応募意欲を高めやすくなります。
採用プロセスを最適化する
現在の採用プロセスを最適化できないか検討してみてください。採用プロセスが煩雑で採用まで時間がかかると、優秀な候補者から離脱される可能性があるためです。
書類選考や面接日程の調整を迅速に進め、面接回数も必要最小限に絞ると良いでしょう。オンライン面接を活用すれば候補者の時間を取りすぎず、遠方からの応募を促せます。
スピーディーに選考を進めると、候補者は「対応が早く信頼できる」と感じやすくなります。ベンチャー企業の強みであるスピード感を活かし、早く魅力をアピールすると採用の勝率が上がります。
ポイント
各フローの移行率を計算して、選考の妨げになっている部分を特定・改善しましょう。もしかすると、余計な工程が含まれているかもしれません。
採用のKPIを設定して、各フローの移行率を改善していくと、採用の成果が変わります。採用KPIについては、採用KPIを設定する5ステップ|4つの運用のコツと注意点も解説を参考にしてみてください。
採用基準を決めておく
選考のたびに評価が変わると、ミスマッチや工数の増加を招きやすいです。そのため、最初に役割や業務範囲を整理して、どのスキルや人柄を優先したいか明文化しておくのがおすすめです。
以下のように共有すれば、担当者が交代しても統一的に候補者を評価しやすくなります。
採用基準の例
- 求めるスキル:経験年数や専門領域
- カルチャー適合:社内で尊重される考え方との一致度
- 実績や志向:成果を出す流れや自己啓発への姿勢
また、価値観や得意分野を分類し「必須条件」と「歓迎条件」に分けると判断しやすくなります。以下は「必須条件」と「歓迎条件」の具体例です。
| タイプ | 具体例 |
|---|---|
| 必須条件 | ・サーバーサイド開発経験3年以上 ・チームリーダーとして5名以上をまとめた実績 ・週5日の常駐勤務が可能 |
| 歓迎条件 | ・ReactやVue.jsなどの知識 ・上流工程での要件定義経験 ・英語のリーディングに抵抗がない |
まずは必須条件を満たしているかを見極め、可能な限り歓迎条件を備えているなら評価を高める形をとると、入社後に想定外のギャップが発生しにくくなります。こうした基準があれば、書類選考から面接までスムーズに進行できて、求める人材像とのズレを軽減できるでしょう。
現場社員や経営者も採用活動に参加する
現場のメンバーやトップが面接に関わることで魅力を伝えられます。
経営者の想いに触れると、応募者は方向性や事業ビジョンを理解できるでしょう。そして、現場メンバーが業務のリアルを伝えれば、やりがいを感じ、不明点の解消もしやすくなります。
以下のように工夫してみましょう。
具体的な方法
- 経営者との対話:価値観や将来像を直接共有
- 現場社員との懇談:具体的な業務や雰囲気を説明
- オフィス見学:職場の空気を体感してもらう
こうした参加型の採用活動を実施すれば、候補者は会社全体の空気を感じ取り、ベンチャーらしいスピード感や柔軟さに魅力を抱きやすくなります。
ストックオプションを提示する
大企業と比べて給与や福利厚生で劣る場合でも、将来の成長に伴う利益を分配するストックオプションを用意すると、候補者に対して別の魅力を与えやすいです。
ストックオプションとは
ストックオプションは、あらかじめ決めた価格で株式を取得できる権利のことです。自社が拡大すれば経済的リターンが増し、ベンチャー特有のリスクを上回るやりがいにつながることがあります。
例えば、事業が黒字化すれば保有株の価値が跳ね上がるなど、夢を感じる要素になるでしょう。さらに、経営に近い立場で働く意識が高まり、当事者意識を備えた人材が活躍する可能性もあります。
採用担当者のスキルアップを図る
ベンチャー企業は採用や広報などの役割を兼任しやすいため、採用の知識や経験が不足しがちです。そこで限られたリソースでも優秀な人材を確保するため、以下のようなスキルを養うと採用活動を前進させやすくなります。
さらに、学び方を工夫すると実務への活用が加速します。
| スキル | 内容 | 学習方法 |
|---|---|---|
| 洞察力 | 候補者の強みを見抜き、企業との相性を判断 | ・模擬面接の録画を分析 ・心理学の入門書を読む |
| 調整力 | 現場社員や経営者を巻き込んで、採用活動を進める | ・プロジェクト管理ソフトの活用 ・ロールプレイ |
| マーケティングスキル | 自社の魅力を発信し、興味を引くスキル | ・セミナー参加 ・ケーススタディ |
| コミュニケーション力 | 候補者の本音を聞き出したり、社内メンバーと情報を共有したりする会話術 | 社内外の面談をこなし、フィードバック |
外部セミナーやSNS上のコミュニティに参加して、事例を学ぶのもおすすめです。また、面接の録画やフィードバック会など社内で試行錯誤すると、成長速度が上がりやすくなります。
習得したスキルを実務に活かし、ベンチャー特有のスピード感に合わせた採用活動を実現しましょう。
未経験者の採用を検討する
即戦力だけでなく、ポテンシャル枠として意欲の高い未経験者を迎えることも検討してみてください。ベンチャーは社内ルールが固定的ではないため、未経験の人材によって新しい風を入れやすく、早期に成長してくれる可能性があります。
特にチームワークや学習意欲を重んじる社風なら、スキルより意欲を優先する方が成果につながる可能性もあるでしょう。
具体的には、以下のような工夫で成果が出やすくなります。
未経験者を採用するための準備
- 教育体制の準備:マニュアルや先輩社員のサポート
- キャリアサポート:本人の目標と業務が合致するか確認
- 業務サポート:困っている部分を早めに把握して修正する
こうした仕組みを整えると、モチベーションが高い人材を育てられて、組織全体の力を底上げする効果が期待できます。社内で未経験者を受け入れる状態を作れそうであれば、実践してみましょう。
ベンチャー企業におすすめの採用手法10選
続いて、ベンチャー企業におすすめの採用手法を解説していきます。
ベンチャー企業におすすめの採用手法
- ダイレクトリクルーティング
- リファラル採用
- SNSリクルーティング
- 求人サイト
- エージェント
- 採用代行
- イベントに参加する
- オウンドメディア
- フリーランス人材への業務委託
- 複数の採用手法を組み合わせる
以下の観点も併せて解説するので、自社に合いそうな手法を試してみてください。
この章でわかること
- どのように使うか
- どんなターゲットに有効か
- どんなベンチャー企業に向いているか
- 費用相場
ダイレクトリクルーティング
| どのように使うか | スカウト型のサイトで候補者を検索し、直接メッセージを送る。面談前にスキルや経歴を細かく確認し、ターゲットを絞り込む。 |
| どんなターゲットに有効か | 特定のスキルや実績を持つ即戦力の候補者 |
| どんなベンチャー企業に向いているか | 応募が集まりにくいケースや、早期に中核人材が必要な場面が多い企業 |
| 費用相場 | 月額3〜20万円程度の利用料(スカウト配信やデータベース検索など) ※プランによって差がある |
ダイレクトリクルーティングは、自社が求める人材へ直接アプローチすることで、短期間で即戦力を確保しやすい方法です。応募が集まりにくいベンチャー企業にとって、認知度の低さを補える手段です。
ポイント
例えば、スキル検索機能があるスカウト型のサイトでは、実績や経歴を閲覧しながら特定の経験を持つ候補者に連絡できます。
応募者が受け身でない分、早期に面談へ進みやすく、競合が激化する前に意思確認できるのもメリットです。さらに、アプローチの際に現場の仕事内容を具体的に伝えると、マッチ度合いを高めやすいです。
ただし、多数の候補者へ連絡する手間があるため、効率化のためにスカウト文面のテンプレートや検索条件を明確に設定しておきましょう。
候補者に刺さるスカウトメールのテンプレートと例文
ダイレクトリクルーティングのスカウトメールは、以下のテンプレートがおすすめです。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| 呼びかけ | 「◯◯様」「◯◯さん」など相手の名前を丁寧に入れる |
| 挨拶と自己紹介 | ・突然のご連絡で失礼いたします。 ・はじめまして、△△株式会社の◯◯です。 |
| 相手への興味を示す部分 | ・ポートフォリオ、SNS投稿、発表資料など具体的にどこで知ったか記載 ・技術分野や得意領域など「何に注目したか」を明記 |
| 自社の特徴や募集背景 | ・自社の事業内容、現在取り組んでいるプロジェクト ・募集しているポジションの具体的な役割 |
| コールトゥアクション | ・少しでも興味があればお話してみませんか? ・オンラインでカジュアルにお話ししましょう。 |
| 結び | ・連絡先や担当者名を忘れずに記載 ・次のアクションが取りやすいよう、面談候補日を挙げる |
例文は以下のとおりです。
例文
◯◯さん
はじめまして。△△株式会社で採用を担当している佐藤と申します。
X(旧Twitter)での投稿や作品を拝見し、UIデザインのコンセプトがとてもユニークだと感じました。
弊社は、スマートフォン向けの学習アプリを開発しているベンチャー企業です。利用者が飽きずに学び続けられるUIを追求しており、その領域で経験豊富な方を探していました。
◯◯さんがブログで紹介していた「学習者が操作しやすいデザイン」の考え方に共感し、ぜひお話を伺いたいと思っています。
今後、新しい学習コンテンツの企画とUI改善プロジェクトを同時に進める計画があります。その中心でアイデアを形にし、使いやすさの検証まで関わっていただける方を積極的に探している状況です。◯◯さんがこだわっているUXリサーチ手法などのお話もぜひ聞いてみたいです。
もし少しでもご興味があれば、オンラインで30分ほどカジュアルな面談をしませんか?具体的な日程のご希望があれば教えてください。私も柔軟に対応しますので、気軽にご返信いただけると嬉しいです。
◯◯さんのクリエイティブな視点を事業に活かせる機会があれば最高だと考えています。ご連絡をお待ちしています。―――――――
△△株式会社 採用担当
佐藤 太郎(さとう たろう)
Mail:recruit@△△.co.jp
―――――――
相手の強みや実績に直接ふれつつ、自社の課題やプロジェクト内容を具体的に示すと好印象です。最初の接触段階では「企業の紹介」よりも「候補者に興味を抱いた点」を重視すると返信率が高まります。
ダイレクトリクルーティングはHELLOBOSSがおすすめ
ダイレクトリクルーティングでは、私たちが提供する「HELLOBOSS」がおすすめです。10万人を超えるユーザーの中から、AIが貴社に合う人材をマッチングしてくれるため、採用担当者の負担を軽減します。
候補者と直接チャットができるため、返信率も高く、信頼関係を築きやすいのもメリットです。
月額4,000円〜でスカウトメール送り放題なので、貴社にフィットしそうな人材をAIに推薦してもらったら、積極的にアプローチしてみましょう。
無料版から始めることも可能です。テストとして使ってみてください。
わずか3ステップで始められるため、さっそくHELLOBOSSを試してみましょう。
リファラル採用
| どのように使うか | 社内メンバーの人脈を活用し、知り合いを紹介してもらう。必要なスキルや社風を共有しやすく、事前に候補者の人柄や働き方を把握できる。 |
| どんなターゲットに有効か | 社風を理解してくれる適応力の高い人材 |
| どんなベンチャー企業に向いているか | 社員同士のつながりが強く、コストをかけずに採用ルートを広げたい企業 |
| 費用相場 | 0円〜30万円程度(紹介成功時の報奨金) |
リファラル採用は社員の人脈や紹介を活かす採用手法です。社内での相性が高く、採用コストを抑えやすい点がメリットです。紹介者が企業文化やスキル要件をよく理解しているため、ミスマッチのリスクを下げられます。
ポイント
一方、候補者の人数が限られやすいので、急成長を目指す場合は他の手法と併用しましょう。
社員へのインセンティブとして成功報酬型を採用したり、紹介実績を評価制度に反映する仕組みがあります。例えば、内定成立時に一定額を支給する形や、月給の1ヶ月分をボーナスとして付与する形などが代表的です。
ただし、職業安定法第40条で、労働者の募集に従事する者に賃金以外の報酬を支払うことは原則として禁止されています。そのため、報酬は賃金として位置づけるようにしましょう。
| インセンティブの仕組み | 金額例 | 留意点 |
|---|---|---|
| 一時金(成果報酬型) | 内定確定で10万円、3ヶ月在籍後に追加5万円など | 契約成立時のモチベーションは高いが、一過性になりやすい |
| 給与連動型 | 紹介成功者に月給の1ヶ月分を上乗せ | 紹介件数が増えるほど金額が大きくなるため、年間予算を管理する必要がある |
| 福利厚生型 | 社員旅行の参加費を全額負担、食事券の配布など | 金銭以外の報酬を重視する社員には好評だが、即効性は低め |
インセンティブは一時金に限らず、社内評価の一部として昇給や表彰を取り入れる方法もあります。複数の仕組みを組み合わせながら、紹介者のやる気を高めてみましょう。
また、紹介を促進するには定期的に募集状況を共有し、目指す人材像を具体化して社員に伝えるのがコツです。
SNSリクルーティング
| どのように使うか | X(旧Twitter)やInstagramで企業アカウントを運用し、仕事内容やカルチャーを発信。ハッシュタグなどで対象スキル保有者へ直接訴求。 |
| どんなターゲットに有効か | デジタルリテラシーが高く、ネット上で積極的に情報収集する候補者 |
| どんなベンチャー企業に向いているか | 認知度が低くても積極的に発信し、新しい層へアピールしたい企業。更新を継続できる体制を整えられる企業 |
| 費用相場 | 0円〜10万円程度/月(SNS運用や広告費など) |
SNSを活用して候補者とつながることで、無料かつ手軽に採用活動を進められます。X(旧Twitter)やInstagram、LinkedInなどを使い、企業のカルチャーや取り組みを発信すると認知拡大につながるでしょう。
例
新商品のデザイン過程を画像や動画で紹介すれば、求職者は仕事のリアルを感じ取りやすいです。
加えてハッシュタグを使って特定のスキルを持つユーザーへ届くようにすれば、狙った人材ともつながりやすくなります。
ベンチャー企業の場合、スピーディーに情報を更新できるSNSは相性が良いでしょう。発信頻度を維持するために担当者を決めたり、投稿の方向性を定期的に見直してPDCAを回したりすると成果が出やすいです。
求人サイト
| どのように使うか | 広く認知を得る目的でサイトに掲載する。募集要件を具体的に書き、画像などで職場の雰囲気を伝える。 |
| どんなターゲットに有効か | 広いターゲットに対応 |
| どんなベンチャー企業に向いているか | ある程度の出稿費用をかけられ、短期的に応募数を増やしたい企業 |
| 費用相場 | 10〜50万円程度/1掲載(4〜6週間) または月額料金制 |
求人サイトは最も広く利用される募集経路で、知名度に左右されずに一定数の応募を見込みやすいです。
例えば
総合型の大手サイトでは母集団を大きくしやすく、業種特化型なら必要な職種の候補者に深くアプローチできます。
掲載料金や期間などは媒体によって違うため、募集人員やスキル要件を検討して合ったプランを選びましょう。
また、求人票の書き方は応募数を左右するので、職務概要や評価制度などを具体的に書くと興味を引きやすいです。社名を知らない人が多いケースでも、写真や動画を掲載しながら自社の特徴をわかりやすく示すと応募率が高まるでしょう。
ちなみに、魅力的な求人票を書くコツは以下のとおりです。
応募が集まりやすい求人票の作り方5ステップ
- 求めるペルソナを明確にする
- ペルソナが興味を持つ自社の強みをまとめる
- 求人内容を具体的に記載する
- 写真や動画を入れる
- 社内で求人票の内容をチェックする
求人票の書き方は、求人票の書き方のコツを徹底解説|求人票の作り方5ステップにまとめているので、参考にしてみてください。
エージェント
| どのように使うか | 条件に合う候補者を人材コンサルタントが紹介する。成功報酬型が主流で費用は採用後に発生。 |
| どんなターゲットに有効か | スキルや経験値がある即戦力人材 |
| どんなベンチャー企業に向いているか | 社内リソースが限られており、募集職種をピンポイントで埋めたい企業 |
| 費用相場 | 採用決定者の想定年収の20〜35%程度 |
エージェントを使うと、人材のプロが候補者の経歴と志向を把握したうえで紹介してくれるので、早期戦力を探したいときに頼もしい存在です。例えば、エンジニアやセールス経験者など、必要なスキルを持つ人材を素早く候補に挙げてもらいやすいでしょう。
ポイント
報酬形態は成功報酬が中心なので、採用決定後に費用が発生する仕組みになっています。紹介手数料が高額になりやすい点は、予算とのバランスに注意が必要です。
自社の社風や業務内容をエージェントにしっかり伝えておくと、候補者への紹介がスムーズに進みやすくなります。限られた採用リソースを補う策として検討しましょう。
採用代行
| どのように使うか | 専門業者に募集や面接調整などを任せる。書類選考からスカウトまで代行してもらえる。 |
| どんなターゲットに有効か | 広いターゲットに対応 |
| どんなベンチャー企業に向いているか | 自社で採用ノウハウを蓄積しつつも、当面は外部の力を借りたい企業 |
| 費用相場 | 20〜50万円程度/月(固定費または契約形態による) |
採用代行は企業の募集や面接の日程調整などを専門業者に委託する方法で、人事担当者が少ない組織にとって負担を減らしやすいです。
メリット
求人要件のすり合わせやスカウトメールの送付を外部に依頼し、社内担当者は面接や最終決定などに集中できます。
ノウハウが豊富な代行会社から、書類選考の評価ポイントや効果的な採用フローの設計を学べるメリットもあるでしょう。月額固定型や成功報酬型など費用プランはいくつかあり、予算に合わせて選択できます。
ただし、すべてを外部に任せると社内に採用スキルが蓄積しにくいです。必要な部分だけを委託し、自社で運用できる範囲を徐々に広げるのも良いでしょう。
イベントに参加する
| どのように使うか | 合同企業説明会や個別セミナーに出展して、対面で事業内容や魅力を伝える。 |
| どんなターゲットに有効か | 広いターゲットに対応 |
| どんなベンチャー企業に向いているか | オフラインまたはオンラインの場を活用して、短期間で多くの候補者と接触したい企業 |
| 費用相場 | 数万〜数百円/回(出展料や資料作成費用など) |
イベントへの参加は候補者と直接話し合う機会を確保しやすく、事業内容や職場の雰囲気を生の声で伝えやすいです。
例
合同企業説明会では多くの求職者が一度に集まるため、その場で興味を深めてもらえる可能性があります。個別セミナーやオフィス訪問イベントを開催し、代表者が新規プロジェクトを紹介したり、現場メンバーの生の意見を聞かせたりするのも良いでしょう。
出展や運営に手間とコストはかかりますが、オンラインでは伝わりにくい熱意やチームの空気感を体感してもらえる点が魅力です。参加後のフォロー体制を整え、興味を持った方と継続的な関係を作っていきましょう。
オウンドメディア
| どのように使うか | 自社サイトやブログに社風やプロジェクト事例を掲載。SNSとの連携で継続的に情報を発信。 |
| どんなターゲットに有効か | 企業文化や働き方に共感しそうな層 |
| どんなベンチャー企業に向いているか | 長期的にコンテンツを運用できる体制がある企業 |
| 費用相場 | 0〜100万円程度/月(運用コスト+記事制作費用など) |
オウンドメディアは自社サイト・SNS・YouTubeなどで、自由に情報を発信する方法です。視聴者がファン化しやすく、応募につながる可能性があります。
オウンドメディアで発信する内容の例
- インタビュー記事
- 社内行事の写真・動画
- 仕事の流れを具体的に紹介する動画
SNSのフォロワー・YouTubeのチャンネル登録者などが蓄積していくと、安定して人材を採用できるタレントプールになる可能性もあるでしょう。また、オウンドメディア→オフラインの交流会を企画すれば、候補者と直接話せる機会を作れます。
オウンドメディア運営は、更新の頻度を保つ仕組みを用意し、SNSや検索エンジンと連動させると認知拡大に役立ちます。社内スタッフがコンテンツを定期的に執筆するのは負担がかかるため、ライターを外注するなど、長期的に運営できる体制が必要です。
フリーランス人材への業務委託
| どのように使うか | 専門的な領域を短期契約で依頼する。UI制作やマーケティングなど、プロの力を必要な時期に活用。 |
| どんなターゲットに有効か | 特定スキルを持つ個人事業主や、副業を検討している優秀層 |
| どんなベンチャー企業に向いているか | 正社員を増やす余裕が少ないが、案件ベースで即戦力を加えたい企業 |
| 費用相場 | 10〜100万円程度/案件(専門性や作業範囲で大きく変動) |
フリーランス人材に業務を依頼すると、短期間だけプロの力を借りて専門分野を補強しやすいです。例えば、WebデザインやSNSマーケティングの案件で、実績豊富なフリーランスにスポット的に参画してもらえます。
正社員の人材を採用できなくても、案件規模に合わせて契約できるのが強みです。
ただし、フリーランス人材への業務委託には、以下のデメリットもあるため知っておきましょう。
フリーランスに外注するときの注意点
- 情報漏洩リスクがある
- 社内ノウハウが蓄積しにくい
- 長期的に依頼できるとは限らない
オンラインを活用して進行管理するスタイルを取り入れれば、物理的な距離を問わず優秀な人材と連携しやすいです。プロセスに関与しながらノウハウを学び、将来的な正社員採用の可能性を探る機会にもなります。
複数の採用手法を組み合わせる
| どのように使うか | 複数のチャネルを併用して応募者を増やし、採用成功率を高める。運用後はデータを分析して効果的な手段に注力。 |
| どんなターゲットに有効か | 広いターゲットに対応 |
| どんなベンチャー企業に向いているか | 短期間で体制を拡大したいが、1つの方法に依存するとリスクが大きいと考える企業 |
多面的に候補者へアプローチするには、ダイレクトリクルーティングや求人サイト、SNS活用など複数の方法を併用するのがおすすめです。知名度が低いベンチャー企業は、1つの手法に頼ると応募が伸び悩むリスクがあるためです。
具体例
母集団を確保するために求人サイトを使い、特定スキルの人材にはダイレクトリクルーティングを並行すると良いでしょう。
採用が落ち着いた段階で各手法の応募数や選考通過率を分析し、効果の高い手段にリソースを振り分ければ、成長速度に合った採用体制を築きやすくなります。
AIを活用して人材を採用できたベンチャー企業の成功事例

AIツールを活用して人材の採用に成功したベンチャー企業の事例を紹介します。
ここでは、AI採用ツール「HELLOBOSS」を使って採用難を突破した事例を紹介します。
人材採用に成功したベンチャー企業の事例
具体的な成功の秘訣を見ていきましょう。
専門職を採用できた情報通信業のAI活用事例
情報通信業の株式会社Yoii(従業員数1〜49名)では、難易度の高い「審査」と「経理・財務ポジション」の採用に苦戦していました。
そこで「HELLOBOSS」のAgentプランを導入し、AIマッチングとコンサルタントの企業理解を活かしたピンポイントなアプローチを実施。
その結果、半年間で3名の推薦に対し3名の採用決定という成果を創出しました。
自社にマッチする人材を見極めるAI技術が有効です。
2週間で2名を採用したサービス業のAI活用事例
サービス業のフィナンシャルフィールパートナーズ(従業員数1〜49名)では、経理経験者の採用を目指して「HELLOBOSS」のProプランを導入しました。
AIマッチングとチャットスカウト機能を活用し、ターゲットとなる層へ直接アプローチを展開。
導入からわずか2週間で2名の採用に成功しています。
スピード感が求められるベンチャー企業でも、AIを活用すると即戦力人材と速く出会える可能性があります。
採用単価を30%削減した運輸業のAI活用事例
ある運輸業では、地方での母集団形成に苦戦しやすい「ドライバー採用」において、HELLOBOSSのエンタープライズプランを活用しました。
AIがターゲットへ的確にアプローチしたことで、有効応募率は90%以上を記録。
既存媒体より採用単価を30%削減することにも成功しました。
採用難易度が高い職種やエリアでも、AIによる最適化でコストを抑えた採用が可能です。
ベンチャー企業に向いている人材の特徴7選
ベンチャー企業で人材を採用するときは、前述のとおり「採用ペルソナ」を明確化するのがおすすめです。
関連記事:採用ペルソナの作り方完全ガイド|テンプレートと7ステップのフレームワーク
とはいえ、ある程度の指標があった方がペルソナを設定しやすいと思うので、一般的に「ベンチャー企業に向いている」とされる人材の特徴を解説していきます。
ベンチャー企業に向いている人材の特徴
- 主体性がある
- 柔軟性がある
- 好奇心が強い
- スピード感がある
- コミット力がある
- ビジネスを作るのが好き
- チームワークを活かせる
こうした人材を見分ける面接の質問も紹介するので、参考にしてみてください。
主体性がある
チーム内で指示を待たず、自ら課題を探しにいく姿勢の人は、ベンチャー企業の環境で成長しやすいです。未経験の領域でも、まずは動いてから学ぶスタイルを持つ人材は、組織に良い影響を与えるでしょう。
ポイント
社内で課題が山積みの場面でも、自分が担える範囲を即座に定義し、その対策を打ち出せるため業務効率が上がりやすいです。
前例が少ない場面で活躍しやすいため、新しいプロダクトの立ち上げや新規事業のテスト運用などで力を発揮します。
主体性がある人材を見極めるには、面接で以下のように質問すると良いでしょう。
面接の質問例
- 自ら提案して実施した業務改善案を聞かせてください。
- 主体的に動いた具体的なエピソードを教えてください。
柔軟性がある
変化が早いベンチャー企業では、柔軟な対応が役立ちます。突然の方向転換や、新しい手段を試す必要に迫られた場合でも、前向きに切り替えて次のアクションを考えられる人は頼りになります。
ポイント
チーム全体の目標が急に変わっても、代替案を提案して試行錯誤を進められるので、トラブルに強い組織文化を育みやすいです。
視点を変えたり追加でリサーチしたりと、状況に応じて最適な方法を取り入れる能力が重宝されます。
柔軟性がある人材を見極めるには、面接で以下のように質問してみてください。
面接の質問例
- 想定外の課題が発生した際、どのように対処しましたか?
- 変化への対応を求められた際、どのように情報収集していますか?
好奇心が強い
未知の領域でも臆せず飛び込み、新たな知識や技術を吸収する姿勢の人は、成長フェーズのベンチャー企業で活躍しやすいです。
例
新しいマーケティング手法やツールに触れる機会があれば、自発的に学び成果に結びつけようと試行錯誤を繰り返すでしょう。
好奇心が強い人は周囲のアイデアにも積極的で、社内勉強会を開いたり、他部署とのコラボ企画を提案したりする行動があります。加速する情報社会の中で、変化や発見を楽しんで取り組む様子が周囲への刺激にもなります。
面接では以下のように質問すると、好奇心があるかチェックできるでしょう。
面接の質問例
- 最近興味をもった技術や分野は何ですか?
- 新しいアイデアを試すとき、どのようなプロセスで進めますか?
スピード感がある
ベンチャー企業では、限られたリソースを有効に使い、短期間でアウトプットが求められます。細部まで詰めすぎてタイミングを逃すよりも、まずは最低限の形を提示してフィードバックを得る方が成果につながりやすい環境でしょう。
ポイント
すぐに行動し、小さな検証を積み重ねながら、段階的にレベルアップを図る姿勢の人材は、企業にとって有益です。
チーム内で確認作業が増える前に、初期段階の検証結果を共有して修正案を素早く提示できれば、競合に先んじたサービス展開も狙いやすいです。
スピード感がある人材を見極めるには、面接で以下のように質問すると良いでしょう。
面接の質問例
- 納期が厳しい案件で、どう間に合わせたか聞かせてください。
- リリースが限られているとき、最初に取り組むことは何ですか?
コミット力がある
決めたゴールまで粘り強く走り抜く人材は、ベンチャー企業に必要不可欠です。困難があっても、目指すビジョンを見失わず食らいつく人材は心強いです。
ポイント
進捗が芳しくない局面でも、上司や同僚と積極的に対話して戦略を修正するなど、最後まで諦めない気概が求められます。結果として、プロダクトの完成度や売上に貢献できるだけでなく、チームの士気向上にもつながるでしょう。
高いコミット力がある人はリソース不足や予期しない障害にもめげず、前向きに行動を続ける傾向があります。
コミット力がある人材を見極めるには、面接で以下のように質問してみてください。
面接の質問例
- 目標を達成したときの過程を詳しく教えてください。
- 障害に直面した際、ゴールを変えずに突破した経験を教えてください。
ビジネスを作るのが好き
ゼロから何かを立ち上げる取り組みが好きな人は、イノベーションを推進しやすいです。新規事業や既存サービスの拡張アイデアを提案し、自分で収益構造まで考えて試してみようとする積極性が強みです。
例
新しい顧客層へアプローチする方法を自ら企画して、検証を重ねながらプロトタイプを作り上げる流れが理想的です。経営視点を持つ人材ほど、将来的なスケールを意識して小さな成功と失敗を繰り返し改善を図ります。
スタートアップ期の組織で課題を解決し、ビジネスを成長させる推進力が生まれやすいです。
面接では以下のように質問してみましょう。
面接の質問例
- 過去に自分で立ち上げた企画やプロジェクトはありますか?
- ビジネスチャンスを探すとき、最初に何を調べますか?
チームワークを活かせる
少人数で複数の業務を同時にこなすベンチャー企業では、チームワークを意識できる人材が欠かせません。成功体験だけを重視せず、他メンバーの得意分野や苦手部分を把握して、うまく役割分担すると生産性が高まります。
ポイント
社内のコミュニケーションを活発にして、協力し合える空気を生み出す力が必要です。
共同でアイデアを形にした経験がある人は、全体の目標と個人のモチベーションを両立させる工夫を持っていることが多いです。
チームワークを活かせる人は、面接で以下のように質問すると見分けやすいでしょう。
面接の質問例
- チームのメンバーの得意分野をどう把握しますか?
- チームプロジェクトで困難な状況になったとき、どう修正しましたか?
【新卒・中途採用別】人材を見極めるコツ
ここからは、新卒・中途採用別に人材を見極めるコツを解説していきます。
ベンチャー企業に合う新卒・中途人材を採用するためにも参考にしてみてください。
新卒人材を見極めるコツ
新卒人材の採用では、学業やサークル活動など、学生時代に自ら行動した経験から成長意欲を探る方法がよく使われます。例えば、大規模なイベント運営に携わったか、ゼミで新しいプロジェクトを立ち上げたかなどを詳しく聞くと、自主性や柔軟性を確かめやすいです。
ポイント
カルチャーフィットを判断するためには、面接や座談会の場で会社の価値観や働き方を共有し、学生のビジョンとどれだけ重なるかを確認するのが効果的です。
例えば、グループディスカッションでチーム内の意見をまとめる場面を観察すると、協調性やリーダーシップの度合いを測りやすいです。
面接では以下のように質問して、自社とフィットするか確かめてみましょう。
| 着眼点 | 質問の例 |
|---|---|
| 自主性と主体性 | 学生時代に自発的に進めた活動の内容を教えてください。 |
| 困難への取り組み方 | 予想外の課題に直面したとき、どのように対応しましたか? |
| 会社への共感度合い | 企業のビジョンやカルチャーに対して、どんな感想を持ちましたか? |
新卒の人材を採用するコツは、新卒採用が難しい7つの理由|新卒採用におすすめの手法11選も紹介で詳しく解説しているので、参考にしてみてください。
中途人材を見極めるコツ
前職で成果を挙げた実績がある人なら、即戦力の中途人材として期待できます。担当範囲がどれほど広かったかや、どれくらい売上を伸ばしたかなど深掘りすると、専門スキルのレベルを把握しやすいです。
例
開発職なら使用言語やフレームワークの活用事例、営業職ならどんな顧客層にアプローチしていたかを聞いてみましょう。ベンチャー企業は方向転換が多い環境なので、適応力もチェックするのがおすすめです。
また、大幅な組織変更や新規プロジェクト立ち上げの際、どのように業務を乗り切ったかを尋ねると、柔軟に対応できる人物かどうか判断しやすいです。オンボーディング後の具体的な役割を想定し、入社後すぐ活躍できるかを総合的に検討しましょう。
中途採用の面接の質問例①
過去に活用した技術スタックやフレームワークを、学習のプロセスや導入理由とあわせて詳しく教えてください。どのような問題を解決し、成果につながったかも聞かせてください。
中途採用の面接の質問例②
組織体制や方針が大きく変わったとき、どのように優先順位を組み直し、周囲と協力して乗り越えましたか?具体的なプロセスや失敗事例があれば知りたいです。
中途採用の面接の質問例③
自分の担当外の領域に飛び込む必要があった場面はありましたか?進め方に迷ったとき、どんな工夫やリサーチを行い、結果を導いたかを詳しく聞かせてください。
中途人材を採用するコツは、中途採用が難しい7つの理由と解決策|成功に必要な9ステップで詳しく解説しています。
ベンチャー企業で人材に定着してもらう対策
せっかく採用した人材がすぐに辞めてしまっては、採用コストが無駄になってしまいます。ベンチャー企業で人材に定着してもらう対策も進めていきましょう。
ベンチャー企業で人材に定着してもらう対策
- メンター制度の導入
- ビジョンの共有
- キャリアパスの提示
- スキルアップ支援
- 1on1ミーティングの実施
こちらも1つずつ解説していくので、参考にしてみてください。
メンター制度の導入
「メンター制度」とは、新入社員や経験が浅いメンバーに相談役をアサインし、サポートする方法です。例えば、営業職に配属された社員に、先輩が商談へ同行して相手との交渉を解説する場面を設けると成果につなげやすいでしょう。
配置するメンターは職種が近く、コミュニケーション力がある人を選ぶのがおすすめです。振り返りを毎月実施して、メンター側と本人の課題をすり合わせると定着しやすいです。
メンター制度のポイント
- 相性が良い先輩を選ぶ
- 定期的に進捗を共有
- 不明点や不安を解消しやすい環境づくり
ビジョンの共有
会社がどの分野を攻めているかや長期的な方針を伝え、全員が同じ方向を向くようにしましょう。四半期ごとに社内キックオフを行い、経営陣が次の戦略や進行中のプロジェクトを説明すると納得感を得られやすいです。
ポイント
新しく入社したメンバーも、組織の動きや競合の存在を知ると自分の役割を意識しやすくなります。短期的な成果だけでなく、将来的に社会へ与えたいインパクトなども共有するとモチベーションが維持されやすいです。
キャリアパスの提示
将来の展望を示すと、社員が長い目で社内に腰を据えてくれます。入社後、1年目にはプロジェクトの補佐、2年目には小規模チームのリードなど段階的な成長ルートを明示しましょう。
| キャリアパスの示し方 | 例 |
|---|---|
| 具体的なステップ | 入社2年で新規サービスのPM補佐 → 3年で独立したチームを管理など |
| モデルケース | 社内で成果を出した先輩の成長過程を紹介し、働き方のイメージを伝える |
| 定期的な見直し | 四半期に1回の面談などで状況を更新し、新しい目標を設定する |
実際の社内事例を交えるとイメージが強まり、自分も同じように活躍できる感覚を得やすいです。
月次面談でスキルや希望役割の変化を確認し、そのうえでキャリアプランを再調整するのも効果的です。
大枠を作りつつ、本人の興味や適性に合わせると離職リスクが減るでしょう。
スキルアップ支援
技術研修や社内勉強会を用意し、学び続けられる環境を整えると社員が意欲を保ちやすいです。以下は職種別のスキルアップ支援の例です。
| 職種 | スキルアップ支援の例 |
|---|---|
| エンジニア | 週1回のハンズオンセミナーでReactやVueなどを使った小規模アプリを共同開発。発表後にメンターからコードレビューし、改善案をチームで議論する流れを取り入れる。 |
| 営業 | 週に1度、先輩やマネージャーが顧客役を担当するロールプレイを実施。録音を振り返ってトークの成功例や改善点を洗い出し、次回の商談に活かせるよう共有する。 |
| マーケティング | プラットフォームの新機能を検証するミニプロジェクトを1ヶ月単位で進め、ABテストの結果を数値レポート化してチーム全体に共有。費用対効果をリアルタイムで把握して次の施策に反映する。 |
外部セミナーの費用を補助する制度を導入するケースもあります。学んだ内容をプロジェクトで試す機会も用意し、成果を発揮したメンバーをきちんと評価すると社内に学ぶ姿勢が根づきやすいです。
1on1ミーティングの実施
上司と部下が定期的に1対1で対話すると、小さな不満や方向性のズレを早めに解消できて、離職を防ぎやすくなります。週1や隔週で30分から1時間ほどの枠を決め、業務の進み具合だけでなく将来のキャリアやスキル習得の希望も共有しましょう。
例
「今、チームで困っていることがあるか」「次のプロジェクトで挑戦してみたいことは何か」などを聞くと、社員が安心して本音を打ち明けやすいです。
雑談ベースで距離を縮める時間も大事にしながら、適宜アドバイスや環境改善を行うと長期定着につながります。
ベンチャー企業の採用活動でよくある質問
最後に、ベンチャー企業の採用でよくある質問に答えていきます。
ベンチャー企業に向いていない人材の特徴は?
ベンチャー企業では予測不能な変化が起きやすいため、自発的に動けない人や挑戦を嫌うタイプは苦労しやすいでしょう。さらに、責任範囲が明確に区切られていない場面で「自分の仕事じゃない」と考える人は、チーム全体の進捗を阻みやすいです。
他にも、ベンチャー企業に向いていない人材の特徴は、以下のようなものがあります。
ベンチャー企業に向いていない人材の特徴
- 新しい領域に踏み出す意欲が薄い
- 変化を嫌い、既存のやり方に固執する
- 指示がないと何もしない
- 責任範囲外に手を出したがらない
- 他部署との連携に消極的
一度設定した手順にとらわれすぎる傾向や、リスクを回避しすぎて動きが鈍る姿勢も問題です。
自ら学習しながら試行錯誤する作業を避けると、ベンチャー特有のスピード感に乗り遅れやすいです。
求職者から人気がないベンチャー企業の特徴は?
採用段階で事業ビジョンが明確に伝わらないと、応募者が働くイメージを描きにくいです。また、経営方針が曖昧なだけでなく、待遇面や評価制度の仕組みを公開しない場合も候補者に敬遠されやすいです。
求職者から人気がないベンチャー企業の特徴
- 経営や目標設定が不透明
- 労働環境が過酷で長時間労働が常態化
- 昇給や評価のルールがあいまい
- 募集要項に書かれた仕事内容と実際が大幅に異なる
- 社外への情報発信が少なく知名度が低い
入社後のミスマッチが想定される企業ほど、敬遠される傾向があります。組織が拡大期にあるなら、最低限の情報公開や現場の声を発信して、人材が安心して応募できる土台を整えましょう。
スタートアップ企業の採用は難しい?
限られた知名度と採用予算で優秀な人材を集めるには工夫が必要です。大手と比べて待遇面で見劣りしやすく、無名のスタートアップ企業は求人情報が見落とされやすいかもしれません。
ポイント
しかし、先ほど紹介したダイレクトリクルーティングやリファラル採用を併用すれば、転職潜在層へ接点を広げやすいです。やりがいを重視する人材もいるため、魅力的なプロジェクトの内容や経営理念を継続的に発信しましょう。
迅速な選考フローとカジュアル面談を組み合わせれば、大手にはないスピード感をアピールしやすいです。
まとめ
ベンチャー企業の採用が難しい業況ではありますが、以下のような手法を組み合わせて人材を獲得していきましょう。
ベンチャー企業におすすめの採用手法
- ダイレクトリクルーティング
- リファラル採用
- SNSリクルーティング
- 求人サイト
- エージェント
- 採用代行
- イベントに参加する
- オウンドメディア
- フリーランス人材への業務委託
- 複数の採用手法を組み合わせる
くりかえしですが、ダイレクトリクルーティングは私たちが提供する「HELLOBOSS」がおすすめです。10万人を超えるユーザーの中から、AIが貴社に合う人材をマッチングしてくれるため、採用担当者の負担を軽減します。
候補者と直接チャットができるため、返信率も高く、信頼関係を築きやすいのもメリットです。
月額4,000円〜でスカウトメール送り放題なので、貴社にフィットしそうな人材をAIに推薦してもらったら、積極的にアプローチしてみましょう。
無料版から始めることも可能です。テストとして使ってみてください。
わずか3ステップで始められるため、さっそくHELLOBOSSを試してみましょう。
貴社の人材採用の参考になれば幸いです。